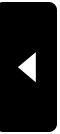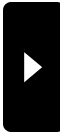2014年04月07日
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第38回総会及び第2作業部会第10回会合(平成26年3月25日~29日、於 横浜市)において、IPCC第5次評価報告書第2作業部会報告書の政策決定者向け要約(SPM)が承認・公表されるとともに、第2作業部会報告書の本体が受諾されました。
第2作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)の概要
A. 複雑かつ変化しつつある世界において観測されている影響、脆弱性、適応観測されている影響
ここ数十年、気候変動の影響が全大陸と海洋において、自然生態系及び人間社会に以下のような影響を与えている。気候変動の影響の証拠は、自然生態系に最も強くかつ包括的に現れている。
i)水文システムの変化による、水量や水質の観点からの水資源への影響
ii)陸域、淡水、海洋生物の生息域の変化等
iii)農作物への負の影響が正の影響よりもより一般的
熱波や干ばつ、洪水、台風、山火事等、近年の気象と気候の極端現象による影響は、現在の気候の変動性に対するいくつかの生態系や多くの人間システムの著しい脆弱性や曝露を明らかにしている。
適応経験
・適応は一部の計画に組み込まれつつあり、限定的であるが実施されている適応策がある。例として、アジアにおいては、一部の地域で、適応が、早期警戒システムや統合的水資源管理、アグロフォレストリー、マングローブの植林を通じて促進されている。
・気候変動に関連したリスクへの対応は、気候変動の影響の深刻さや起こる時期の不確かさ、また適応の有効性の制限という不確実性がある中で、変わりつつある世界において意思を決定していくということを含意している。
B. 将来のリスクと適応の機会
複数の分野地域に及ぶ主要リスク
主要なリスクは国連気候変動枠組条約第2 条に記載されるような、「気候システムに対する危険な人為的干渉」による深刻な影響の可能性である。確信度の高い複数の分野や地域に及ぶ主
要なリスクとして、以下の8 つがあげられている。それぞれが1つあるいはそれ以上の「懸念の理由」に寄与している。なお、該当する「懸念の理由」の番号は、本文末尾のボックスの記載に対応している。
i)海面上昇、沿岸での高潮被害などによるリスク[懸念の理由1~5]
高潮、沿岸洪水、海面上昇により、沿岸の低地や小島嶼国において死亡、負傷、健康被害、または生計崩壊が起きるリスクがある。
ii)大都市部への洪水による被害のリスク[懸念の理由2, 3]
いくつかの地域において、洪水によって、大都市部の人々が深刻な健康被害や生計崩壊にあうリスクがある。
iii)極端な気象現象によるインフラ等の機能停止のリスク[懸念の理由2~4]
極端な気象現象が、電気、水供給、医療・緊急サービスなどの、インフラネットワークと重要なサービスの機能停止をもたらすといった、社会システム全体に影響を及ぼすリスクがある。
iv)熱波による、特に都市部の脆弱な層における死亡や疾病のリスク[懸念の理由2, 3]
極端に暑い期間においては、特に脆弱な都市住民や屋外労働者に対する、死亡や健康障害のリスクがある。
v)気温上昇、干ばつ等による食料安全保障が脅かされるリスク[懸念の理由2~4]
気温上昇、干ばつ、洪水、降水量の変動や極端な降水により、特に貧しい人々の食料安全保障が脅かされるとともに、食料システムが崩壊するリスクがある。
vi)水資源不足と農業生産減少による農村部の生計及び所得損失のリスク[懸念の理由2, 3]
飲料水や灌漑用水への不十分なアクセスと農業の生産性の低下により、半乾燥地域において、特に最小限の資本しか持たない農民や牧畜民の生計や収入が失われる可能性がある。
vii)沿岸海域における生計に重要な海洋生態系の損失リスク[懸念の理由1, 2, 4]
特に熱帯と北極圏の漁業コミュニティにおいて、沿岸部の人々の生計を支える海洋・沿岸の生態系と生物多様性、生態系便益・機能・サービスが失われる可能性がある。
viii)陸域及び内水生態系がもたらすサービスの損失リスク[懸念の理由 1, 3, 4]
人々の生計を支える陸域及び内水の生態系と生物多様性、生態系便益・機能・サービスが失われる可能性がある。
・気候変動の速さと大きさを制限することにより、その影響による全般的なリスクを低減できる。
一方、温暖化が大規模になれば、深刻かつ広範で、不可逆的な影響が起る可能性が高まる。
C. 将来のリスクの管理とレジリエンスの構築
効果的な適応のための原則
・適応は、地域や背景が特有であるため、すべての状況にわたって適切なリスク低減のアプローチは存在しない。
・限られた証拠によると、世界全体の適応ニーズと適応のための資金には隔たりがある。世界全体の適応に要する費用を算定する研究には、データや手法、適用範囲が不十分という特徴があり、更なる研究の向上が必要である。
・重要なコベネフィット、相乗効果、トレードオフは緩和と適応の間や異なる適応の反応の中に存在する。相互作用は地域内及び地域をまたいで起こる(確信度は非常に高い)。
気候に対してレジリエントな経路と変革
・経済的、社会的、技術的、政治的決定や行動の変革が、気候に対してレジリエント(強靭)な経路を可能とする。
懸念の理由
人による気候システムへの影響は明らかである。しかし、その影響が国連気候変動枠組条約第2 条にある“危険な人類的干渉”に当たるどうかは、リスク評価と価値判断の両方が必要である。以下の包括的な「懸念の理由(Reasons For Concern)」は、あらゆる分野及び地域にわたる主要なリスクをまとめる枠組みを提供する。懸念の理由は、温暖化や人々、経済、及び生態系にとっての適応の限界の意味するところを解説している。それらは、気候システムに対する危険な人為的干渉を評価するための1 つの出発点を提供する。気温変化については、1986~2005 年平均からの相対的な値として示されている。
(1) 脅威に曝されている独特な生態系や文化等のシステム
深刻な影響のリスクに直面するシステムの数は1℃の気温上昇で増加し、北極海氷システムやサンゴ礁など適応能力が限られている多くの種やシステムは2℃の気温上昇で非常に高いリスクにさらされる。
(2) 極端な気象現象による気候変動関連リスク
熱波、極端な降水、沿岸洪水のような極端現象による気候変動関連リスクは中程度であり(確信度が高い)、1℃の気温上昇で高い状態になる(確信度は中程度)。
(3) 影響の分布
リスクは均一に分布しているわけではなく、どのような発展段階の国であれ、一般的に不利な条件におかれた人々やコミュニティほど多くのリスクを抱えている。特に作物生産への気候変動の影響が地域によって異なるため、リスクは中程度である(確信度は中程度から高い)。地域の作物生産と水の利用性の低下の予測をもとに、不均一な分布による影響から生じるリスクは2℃以上の気温上昇により増大する。(確信度は中程度)
(4) 世界総合的な影響
温暖化の全世界への総合的な影響のリスクは、地球の生物多様性及び世界経済全体への影響についてみると、1~2 ℃の気温上昇ではリスクは中程度である(確信度は中程度)。約3℃またはそれ以上の気温上昇では、生態系由来の財・サービスの損失を伴う広範囲に及ぶ生物多様性の損失が起こり、リスクが高くなる(確信度が高い)。
(5) 大規模な特異現象
温暖化の進行に伴い、いくつかの物理システムあるいは生態系が急激かつ不可逆的な変化のリスクにさらされる可能性がある。リスクは、1~2℃の気温上昇に伴い不均衡に増加し、3℃以上の気温上昇で氷床の消失による大規模で不可逆的な海面上昇の可能性があることから、高くなる。
第5 次評価報告書における可能性と確信度の表現について
IPCC では、評価結果の「可能性」と「確信度」を表す用語を、一貫した基準に基づいて使用し
ている。以下に、第5 次評価報告書で用いる用語を示す。
「可能性」とは、はっきり定義できる事象が起こった、あるいは将来起こることについての確率
的評価である。また、「確信度」とは、モデル、解析あるいはある意見の正しさに関する不確実性
の程度を表す用語であり、証拠(例えばメカニズムの理解、理論、データ、モデル、専門家の判断)
の種類や量、品質及び整合性と、特定の知見に関する文献間の競合の程度等に基づく見解の一致度
に基づいて定性的に表現される。
<可能性の表現>
用語 発生する可能性
ほぼ確実 99%~100%
可能性が極めて高い 95%~100%
可能性が非常に高い 90%~100%
可能性が高い 66%~100%
どちらかと言えば 50%~100%
どちらも同程度 33%~66%
可能性が低い 0%~33%
可能性が非常に低い 0%~10%
可能性が極めて低い 0%~5%
ほぼありえない 0%~1%
<
第2作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)の概要
A. 複雑かつ変化しつつある世界において観測されている影響、脆弱性、適応観測されている影響
ここ数十年、気候変動の影響が全大陸と海洋において、自然生態系及び人間社会に以下のような影響を与えている。気候変動の影響の証拠は、自然生態系に最も強くかつ包括的に現れている。
i)水文システムの変化による、水量や水質の観点からの水資源への影響
ii)陸域、淡水、海洋生物の生息域の変化等
iii)農作物への負の影響が正の影響よりもより一般的
熱波や干ばつ、洪水、台風、山火事等、近年の気象と気候の極端現象による影響は、現在の気候の変動性に対するいくつかの生態系や多くの人間システムの著しい脆弱性や曝露を明らかにしている。
適応経験
・適応は一部の計画に組み込まれつつあり、限定的であるが実施されている適応策がある。例として、アジアにおいては、一部の地域で、適応が、早期警戒システムや統合的水資源管理、アグロフォレストリー、マングローブの植林を通じて促進されている。
・気候変動に関連したリスクへの対応は、気候変動の影響の深刻さや起こる時期の不確かさ、また適応の有効性の制限という不確実性がある中で、変わりつつある世界において意思を決定していくということを含意している。
B. 将来のリスクと適応の機会
複数の分野地域に及ぶ主要リスク
主要なリスクは国連気候変動枠組条約第2 条に記載されるような、「気候システムに対する危険な人為的干渉」による深刻な影響の可能性である。確信度の高い複数の分野や地域に及ぶ主
要なリスクとして、以下の8 つがあげられている。それぞれが1つあるいはそれ以上の「懸念の理由」に寄与している。なお、該当する「懸念の理由」の番号は、本文末尾のボックスの記載に対応している。
i)海面上昇、沿岸での高潮被害などによるリスク[懸念の理由1~5]
高潮、沿岸洪水、海面上昇により、沿岸の低地や小島嶼国において死亡、負傷、健康被害、または生計崩壊が起きるリスクがある。
ii)大都市部への洪水による被害のリスク[懸念の理由2, 3]
いくつかの地域において、洪水によって、大都市部の人々が深刻な健康被害や生計崩壊にあうリスクがある。
iii)極端な気象現象によるインフラ等の機能停止のリスク[懸念の理由2~4]
極端な気象現象が、電気、水供給、医療・緊急サービスなどの、インフラネットワークと重要なサービスの機能停止をもたらすといった、社会システム全体に影響を及ぼすリスクがある。
iv)熱波による、特に都市部の脆弱な層における死亡や疾病のリスク[懸念の理由2, 3]
極端に暑い期間においては、特に脆弱な都市住民や屋外労働者に対する、死亡や健康障害のリスクがある。
v)気温上昇、干ばつ等による食料安全保障が脅かされるリスク[懸念の理由2~4]
気温上昇、干ばつ、洪水、降水量の変動や極端な降水により、特に貧しい人々の食料安全保障が脅かされるとともに、食料システムが崩壊するリスクがある。
vi)水資源不足と農業生産減少による農村部の生計及び所得損失のリスク[懸念の理由2, 3]
飲料水や灌漑用水への不十分なアクセスと農業の生産性の低下により、半乾燥地域において、特に最小限の資本しか持たない農民や牧畜民の生計や収入が失われる可能性がある。
vii)沿岸海域における生計に重要な海洋生態系の損失リスク[懸念の理由1, 2, 4]
特に熱帯と北極圏の漁業コミュニティにおいて、沿岸部の人々の生計を支える海洋・沿岸の生態系と生物多様性、生態系便益・機能・サービスが失われる可能性がある。
viii)陸域及び内水生態系がもたらすサービスの損失リスク[懸念の理由 1, 3, 4]
人々の生計を支える陸域及び内水の生態系と生物多様性、生態系便益・機能・サービスが失われる可能性がある。
・気候変動の速さと大きさを制限することにより、その影響による全般的なリスクを低減できる。
一方、温暖化が大規模になれば、深刻かつ広範で、不可逆的な影響が起る可能性が高まる。
C. 将来のリスクの管理とレジリエンスの構築
効果的な適応のための原則
・適応は、地域や背景が特有であるため、すべての状況にわたって適切なリスク低減のアプローチは存在しない。
・限られた証拠によると、世界全体の適応ニーズと適応のための資金には隔たりがある。世界全体の適応に要する費用を算定する研究には、データや手法、適用範囲が不十分という特徴があり、更なる研究の向上が必要である。
・重要なコベネフィット、相乗効果、トレードオフは緩和と適応の間や異なる適応の反応の中に存在する。相互作用は地域内及び地域をまたいで起こる(確信度は非常に高い)。
気候に対してレジリエントな経路と変革
・経済的、社会的、技術的、政治的決定や行動の変革が、気候に対してレジリエント(強靭)な経路を可能とする。
懸念の理由
人による気候システムへの影響は明らかである。しかし、その影響が国連気候変動枠組条約第2 条にある“危険な人類的干渉”に当たるどうかは、リスク評価と価値判断の両方が必要である。以下の包括的な「懸念の理由(Reasons For Concern)」は、あらゆる分野及び地域にわたる主要なリスクをまとめる枠組みを提供する。懸念の理由は、温暖化や人々、経済、及び生態系にとっての適応の限界の意味するところを解説している。それらは、気候システムに対する危険な人為的干渉を評価するための1 つの出発点を提供する。気温変化については、1986~2005 年平均からの相対的な値として示されている。
(1) 脅威に曝されている独特な生態系や文化等のシステム
深刻な影響のリスクに直面するシステムの数は1℃の気温上昇で増加し、北極海氷システムやサンゴ礁など適応能力が限られている多くの種やシステムは2℃の気温上昇で非常に高いリスクにさらされる。
(2) 極端な気象現象による気候変動関連リスク
熱波、極端な降水、沿岸洪水のような極端現象による気候変動関連リスクは中程度であり(確信度が高い)、1℃の気温上昇で高い状態になる(確信度は中程度)。
(3) 影響の分布
リスクは均一に分布しているわけではなく、どのような発展段階の国であれ、一般的に不利な条件におかれた人々やコミュニティほど多くのリスクを抱えている。特に作物生産への気候変動の影響が地域によって異なるため、リスクは中程度である(確信度は中程度から高い)。地域の作物生産と水の利用性の低下の予測をもとに、不均一な分布による影響から生じるリスクは2℃以上の気温上昇により増大する。(確信度は中程度)
(4) 世界総合的な影響
温暖化の全世界への総合的な影響のリスクは、地球の生物多様性及び世界経済全体への影響についてみると、1~2 ℃の気温上昇ではリスクは中程度である(確信度は中程度)。約3℃またはそれ以上の気温上昇では、生態系由来の財・サービスの損失を伴う広範囲に及ぶ生物多様性の損失が起こり、リスクが高くなる(確信度が高い)。
(5) 大規模な特異現象
温暖化の進行に伴い、いくつかの物理システムあるいは生態系が急激かつ不可逆的な変化のリスクにさらされる可能性がある。リスクは、1~2℃の気温上昇に伴い不均衡に増加し、3℃以上の気温上昇で氷床の消失による大規模で不可逆的な海面上昇の可能性があることから、高くなる。
第5 次評価報告書における可能性と確信度の表現について
IPCC では、評価結果の「可能性」と「確信度」を表す用語を、一貫した基準に基づいて使用し
ている。以下に、第5 次評価報告書で用いる用語を示す。
「可能性」とは、はっきり定義できる事象が起こった、あるいは将来起こることについての確率
的評価である。また、「確信度」とは、モデル、解析あるいはある意見の正しさに関する不確実性
の程度を表す用語であり、証拠(例えばメカニズムの理解、理論、データ、モデル、専門家の判断)
の種類や量、品質及び整合性と、特定の知見に関する文献間の競合の程度等に基づく見解の一致度
に基づいて定性的に表現される。
<可能性の表現>
用語 発生する可能性
ほぼ確実 99%~100%
可能性が極めて高い 95%~100%
可能性が非常に高い 90%~100%
可能性が高い 66%~100%
どちらかと言えば 50%~100%
どちらも同程度 33%~66%
可能性が低い 0%~33%
可能性が非常に低い 0%~10%
可能性が極めて低い 0%~5%
ほぼありえない 0%~1%
<
Posted by 春 ヲ 呼 プ at 09:10│Comments(0)
│地球環境・国際環境協力