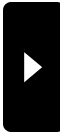2019年04月03日
林業及び木材産業における「働き方改革」
・ 「働き方改革」の最初のステップとして、経営理念とは何か、どのように取組を進めていけばよいのか等を専門家に指導してもらう必要がある。経営理念を持たない会社もある中で、基本的な手ほどきを示すことが必要である。
・ まずは手引きを読んでもらい、誰に相談すればよいのかが分かるというのが取組の出発点ではないか。
④ 解決すべき主な課題
・ 賃金データから「生産性の向上」という課題が導き出されるわけではない。「能力に応じた賃金制度の構築」といった課題に修正すべき。
・ 「雇用の安定化」は「雇用の改善」と修正すべき。
⑤ 課題解決のヒント
【従業員の募集・採用方法の見直し】
・ ハローワークで求人票を見て感じることであるが、自社の魅力をアピールする欄に何も記載していない企業が多い。そのために応募がなく、採用難から抜け出せていないのではないか。
・ マッチングの機会が与えられることが重要。UIターン移住セミナーや行政のウェブサイト等がマッチングの機会として考えられる。
【年間カレンダーを作成する必要性】
・ 月給制を導入するためには、年間労働日数を示すカレンダーを作成する必要がある。各月の労働日数がはっきりしないのが林業の問題点。カレンダーを作成し、年間最大労働時間2,000時間を「見える化」する必要がある。
・ 2019年4月から年5日間の有給休暇の確実な取得が義務化されるが、他の業界では年間労働日数に基づくカレンダーの作成を始めている。有給休暇を考慮した上で導き出される最大稼働日数をどのように運用していくかについて、カレンダーを見ながら考える必要がある。
・ 天候や季節に左右される林業では、年間労働日数を定めておき、あとの休暇の調整や取得は各人に任せる方法しかないのではないか。
・ 今後働き手の多様性は増していくため、必ずしも全員を月給制で正社員にしなくてもよい可能性がある。多様な人々にそれぞれが望ましい形で参画してもらい、結果として事業が成立し持続可能な形となることが重要である。
【林業における長時間労働】
・ 林業では日中しか働くことができないため、1日あたりの労働時間は限られる。一方で、月給制導入に向けて業務量が増加すると、休暇日数が減って年間労働時間が長くなるという課題がある。
・ 一般企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から、残業時間の上限規制が適用される。休日労働を含め月間100時間を超えてはいけないことがルール化されることに留意しなければならない。1日あたりの労働時間は限られても、休日労働等の関係で残業規制の上限に触れる場合もあり、長時間労働と無関係ではないのではないか。
2019年04月02日
農文協の主張:森林経営管理法・森林環境税で日本の森林を破壊するな
http://www.ruralnet.or.jp/syutyo/2018/201807.htm
農文協トップ>主張> 2018年7月号
「私の森が消えた」
6月6日、前年の食料や農林水産業にかかわる優れた報道に贈られる「農業ジャーナリスト賞」を、MRT宮崎放送制作のドキュメンタリー番組「私の森が消えた――森林盗伐問題を追う」が受賞した。宮崎県内での放送は昨年5月だが、10月にTBS系列の「報道特集」で全国放送されて反響を呼び、今年1月には東京新聞「こちら特報部」が、そして3月にはNHK「おはよう日本」が全国的にも頻発している森林盗伐問題を追跡報道した。
番組によると、宮崎県では、放送までの過去5年間に県警に寄せられた森林伐採に関する相談件数は84件。うち被害届が受理されたのはわずか6件に過ぎない。
昨年9月に「宮崎県盗伐被害者の会」を結成し、会長となった海老原裕美さん(60歳)は宮崎市出身で現在は千葉市在住。海老原さんが生まれた年に両親が20aの山林を購入し、スギの苗木を植えた。2016年8月に帰省した際、母親と墓参りした帰りにスギ林があったはずの場所に行くと、スギの木は1本もなくなっており、盗伐被害に遭ったことがわかった。森林所有者や立木を買い受けた者などが立木を伐採する場合には、地元の市町村長に対して事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務づけられている。海老原さんが宮崎市に情報公開請求をしてみると、そこには2000年に死亡した父親の名前が署名され、押印されていた。明らかに文書偽造による無断伐採だったのだ。
それだけではない。海老原さんが被害を受けた面積はわずか20a。業者にとって大きな利益を得られる広さではない。番組ではドローンを飛ばし、空撮を試みた。その結果はナレーションによるとこうだ。
「すると、そこには、驚きの光景が。海老原さんの土地から伸びる作業道の先で、大規模な伐採が行なわれていたのだ。海老原さんの被害現場は、道路に面した平坦な場所にあるため、丸太を持ち出すための作業場として利用されたにすぎなかったのだ」
番組には、海老原さん以外にも、両親と祖父が植林した32aのスギの木で家を建てることを計画し、地盤調査までしていたのに無断伐採され、家の建設を中止せざるを得なくなった男性や、1200~1700本、580万~800万円相当のスギやヒノキを無断伐採された女性が登場する。この女性は、伐採現場の真下に九州電力の水力発電所があり、大雨や洪水で放置された残材が流出し発電所に損害を与えた場合、損害賠償の責任が及ぶことを恐れていた。
このように宮崎県で森林の盗伐(伐採業者の多くは「誤伐」と主張)が頻発している理由について番組は、一時期1m3当たり7000円を下回っていた木材価格が、バイオマス発電向けの低質材の単価の上昇と、輸出の拡大などで1万500円前後で取り引きされるようになったことを挙げている。
森林面積が県全体の76%を占める宮崎県。林業は県の代表的な産業の一つでスギの素材生産量は26年間全国1位を誇っている(バイオマスと輸出向けは素材生産量に含まれない)。しかし、盗伐・誤伐でなくとも「乱伐」「切り過ぎ」を指摘する声も多く、再造林のための苗木生産が追いつかなかったり、畜産県でもある同県で、C材以下の材がバイオマス発電に回るため、畜舎の敷料にするオガクズが不足するなどの影響も現れてきているという。
こうした森林の盗伐や誤伐について調査した林野庁は、昨年4月から今年1月の間に所有者に無断で木が伐採されたという自治体などへの相談が全国で62件あったと発表した。故意に伐採した疑いがあるものが11件、認識違いによって伐採された誤伐が37件、状況不明なものが14件。警察に相談した例も28件あったという。
原木の安価な大量安定供給が目的!?
「森林経営管理法案」
一方で現在開会中の国会では、「森林経営管理法案」が審議されている。その趣旨は、「林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図るためには、市町村を介して林業経営の意欲の低い小規模零細な森林所有者の経営を意欲と能力のある林業経営者につなぐことで林業経営の集積・集約化を図るとともに、経済的に成り立たない森林については、市町村が自ら経営管理を行なう仕組みを構築する必要がある」というもの。
そのために以下の措置を基本とする新たな仕組みを講ずるとしている。
(1)森林所有者に適切な経営管理を促すため、経営管理の責務を明確化するとともに
(2)森林所有者自らが経営管理を実行できない場合に、市町村が経営管理の委託を受け意欲と能力のある林業経営者に再委託する
(3)再委託できない森林および再委託に至るまでの間の森林においては、市町村が経営管理を行なう
要するにこの法案による新たな森林管理制度では、所有者が管理できない森林について、管理する権利を市町村に設定し、市町村は採算ベースに乗りそうな森林は「意欲と能力のある林業経営者」に管理を委託し、採算ベースに乗らない森林は市町村自らが管理するというもので、4月19日の衆議院本会議で可決された(本法を市町村が運用するに当たって、「森林の多面的機能の発揮」「公益的機能の発揮」「生物多様性の保全」について、十分に配慮するよう助言等の支援を行なうこと、自伐林家等が実施する森林管理や森林資源の利用の取り組み等に対し、さらなる支援を行なうことなど、異例の14項目の付帯決議つき)。本稿執筆時の5月末段階では参議院でも可決される見込みだ。
この法案の問題点はいくつもあるが、衆議院農林水産委員会の参考人質疑で泉英二・愛媛大学農学部名誉教授(森林学/森林・林業政策)は、「この法案は、究極的には、川下の大型化した木材産業およびバイオマス発電施設への原木の安価な大量安定供給が目的としか思いようがない」と断言し、「この法案はいったん廃案とするのが望ましい」と反対意見を述べた。
また法案が「経営管理権」としているのは「立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育等を行うための権利」であり、伐採については50年生程度での主伐(皆伐)であることは以下の沖修司林野庁長官の発言からも明らかだ。
「個人が所有する私有林の林家数は83万戸あると言われていますが、その9割が10ha未満の小規模所有が占めています。残念ながら今の時代、木材価格が安い。零細な所有者ほど自分たちで伐採、植林しようという意欲が湧きにくいのが現実です。人工林の半分が数年すると『51年生』以上になります。成長した木は、主伐が必要となります。今までは間伐で森を育てる段階でしたが、主伐は大量に切って利用していく段階。小規模な所有が多いと、切った後造林が必要となる主伐が採算性の問題などから行われず、林業が回っていかなくなります」(2018年1月13日日刊工業新聞・ニュースイッチ)
「違憲」の疑いすらある「森林経営管理法案」
さらに法案の国会提出の際の背景説明資料には、(1)「我が国の森林の所有形態は零細であり、8割の森林所有者は森林経営の意欲が低い」(2)「意欲の低い森林所有者のうち7割の森林所有者は主伐の意向すらない」との文言があり、まるで「主伐」が森林経営の意欲の高さを表すかのような表現となっている。また、「8割」「7割」の根拠となった2015年の林野庁「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査」で、72%の林業者が経営規模について「現状を維持したい」、7%が「規模を縮小したい」と回答していたのを「意欲が低い」と丸めて表記していたため、「データねつ造ではないか」「恣意的表現だ」との批判が広がり、林野庁は法案が衆議院を通過した後に(1)「我が国の森林の所有形態は零細であるが、85%の森林所有者は経営規模の拡大への意欲は低い」(2)「60%の森林所有者は、伐期に達した山林はあるが今後5年間は主伐の予定がないとしている」と修正した。
このことについて、泉名誉教授は次のように述べている。
「この法案の根本には、森林所有者は、林業経営をする意欲がない人たちと規定していることがある。一方で、森林所有者には伐採と、その後の造林の実施に責任を持つよう定めている。できない場合は市町村に委託させる内容になっているが、委託に同意しない所有者に対しては、市町村が勧告や意見書提出などのプロセスを経れば『同意したもの』とみなし、木を伐採してもいいことになっている。非常に強権的な内容で、憲法が保障する財産権を侵害している可能性が高い」(4月23日AERAdot.)
法案では、所有者不明の森林については、計画を公告して6カ月以内に異議がなければ、計画に同意したとみなし、市町村が管理できる規定もある。一度市町村に渡された管理権は、最大50年続く。また、「災害等防止措置命令」の制度を新設し、市町村は森林所有者に伐採などを命じることもできる。他の法律には見られない強大な権限を地方自治体に持たせる法案であり、違憲の可能性も高いのだ。
小規模森林所有者は「意欲がない」のか
それでは本当に「零細な森林所有者」は森林への関心を失っているのだろうか。冒頭で紹介した海老原さんはじめ「宮崎県盗伐被害者の会」の人びとは、たとえ森林の近くに住んでいなくても、木の成長を楽しみにしていた人ばかりである。また『季刊地域』33号でNPO法人自伐型林業推進協会(自伐協)の上垣喜寛事務局長は、上記林野庁の2015年調査から次のように指摘する。
「アンケートよると、森林の手入れ状況について『十分に手入れをしている』(13.9%)と『十分ではないものの、必要最低限の手入れはしていると思う』(47.5%)と、合わせて約6割が各自で手入れをしている。『森林に対して興味がない』という選択肢を選んだのは、わずか数人であり、『意欲がない』といえるデータとはいえない」
国から「意欲がない」と切り捨てられた小規模森林所有者が集まり、2014年に結成されたのが自伐協だ。
「『自伐型林業』とは、短期的な生産量を追い求める大規模林業と違い、間伐を何度も重ねて森林資源の蓄積量(在庫)を増やし、長期視点で持続的森林経営を目指す。いつでも山に入れるような壊れない道を高密に張り巡らせることで、木材の搬出コストを抑え、低投資・低コストの林業を実現。現状の材価でも手元に収入が残る林業として注目されるようになってきた」(同右)
2015年林野庁調査でも伐期に達した山林はあるが今後5年間に主伐を実施する予定はないと回答した人(60%)に、主伐を実施しない理由について尋ねたところ、「主伐を行なわず、間伐を繰り返す予定であるため」という回答の割合が58.0%ともっとも高くなっている。
また自伐協の中嶋健造代表理事は、自身のフェイスブックで「林業には適正規模があり、規模拡大のみを経営意欲の表れとみる林野庁の認識はおかしい」と批判する。
「森林経営には適正規模があるのです。とくに長期的な多間伐施業を実施する自伐型林業者では、1人あたり50ha前後が適正規模です。親子2世帯や2人単位で実施する場合が多いですが、この場合は100ha前後が適正規模となります。この経営規模を維持しながら、ha(面積)あたりの蓄積量と材質を上げていく、生産しながら蓄積量と質を上げていくということが森林経営の極意で、経営レベル向上が重要となります。規模を拡大することはかえって経営レベルを落としてしまうことになりかねません」
では「森林経営管理法案」における「意欲と能力のある林業経営者」とはどういうものか。じつは法案では、ほぼ木材の伐採・搬出のみを行なってきた「素材生産業者」をはじめて「林業経営者」と位置づけ、あらゆる施策と資金を集中して林業の担い手として育成しようとしている。林野庁は法案成立に先立つ今年2月に「林業経営体の育成について」という長官通知を各都道府県知事あてに出し、「意欲と能力のある林業経営体」の選定を求めたが、宮崎県で選定された25の経営体の中には、盗伐・誤伐の疑いをかけられている二つの経営体が含まれているという。
「小さい林業」の「意欲と能力」こそ評価せよ
昨年末、この「森林経営管理法案」とセットになる「税制改革大綱」が閣議決定された。2014年度から個人住民税に1人一律1000円を上乗せする「森林環境税」だ。約6200万人の納税者が対象となり、その総額約620億円(1割を都道府県、9割を市町村に按分)。沖長官は「毎年、森林整備に約1200億円を補助していますが、それでも年500~600億円足りず、補正予算で数百億円を追加している状況です。新税の税収600億円で、毎年の不足分を補える計算です。補助金は今まで通り、収支トントンとなる森林の整備に使い、新税は採算ベースにのらない森林の手入れから使います」(前掲日刊工業新聞・ニュースイッチ)と述べているが、「森林経営管理法案」がめざす森林行政のもとでは、補助金と新税で全国の山がはげ山と化してしまうのではないか。「森林環境税」が「森林破壊税」になってしまっては大問題だ。
じつはこの森林環境税、「森づくり県民税」などの名前ですでに37の府県で導入されており(国の新税は二重課税との指摘もある)、『季刊地域』33号には「地方版・森林環境税の活かし方」緊急アンケートの結果が掲載されている(33府県が回答)。たとえば2003年に全国でもっとも早く1人500円の森林環境税を導入した高知県では、徴収した税金を単年度で使い切ることによる無駄遣いを防ぎ、県民参加と透明性の向上を図るため「森林環境保全基金」を創設。税収の約1億7000万円は基金として積み立てられ、第三者機関の「基金運営委員会」での議論を経て、森林環境を保全する事業に充てられている。また、「小さい林業」の支援では、森林環境税とは別に、2013年度から「自伐林家等支援事業費補助金交付」を県単事業で導入。搬出間伐18万3000円/ha、2.5m 幅の作業道敷設1000円/mなどを助成している。
同県小規模林業推進協議会の副会長で、四万十市で自伐型林業を始めて6年目の宮﨑聖さん(39歳)は、「短期的な木材増産のための皆伐や過間伐、再造林に多くの補助金を使うよりも、高知県のように個人の小さな森林所有者に平等に支援をすれば、林業従事者も増え、長期的な木材増産も可能になります」と話している。
農文協が昨年9月に発行した『小さい林業で稼ぐコツ』は版を重ね、「山で稼ぐ 小さい林業ここにあり」を特集した『季刊地域』32号も売れ行き好調だ。林野庁は主伐と経営規模の拡大だけで「意欲と能力」を評価するのではなく、持続可能でかつ環境保全型の「小さい林業」の「意欲と能力」をこそ評価すべきではないか。
(農文協論説委員会)
2018年12月20日
浜松市農業振興ビジョン(案)解説編
浜松市農業振興ビジョン(案)解説編
9 用語解説
AI
Artificial Intelligence の略。日本語では「人工知能」という。
人間にしかできなかったような高度に知的な作業や判断をコンピュータを中心とする人工的なシステムにより行えるようにしたもの。
GAP
Good Aguricultural Practice の略。
農業生産工程管理。農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容に則って定められる点検項目に沿って、農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活動のこと。
GI(地理的表示保護制度)
伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特性が、品質等の特性に結びついている産品の名称(地理的表示)を知的財産として登録し、保護する制度。
ICT
Information and Communication Technology の略。
日本ではすでに一般的となったIT の概念をさらに一歩進め、IT=情報技術に通信コミュニケーションの重要性を加味した言葉。
NPO
Non-Profit Organization の略。
一般的には民間非営利組織と訳される。営利を目的とする株式会社などと異なり、収入から費用を差し引いた利益を関係者に分配しないことを基本に、社会的使命の追求を目的として、自発的な活動を継続して行う団体のこと。
SNS
Social Networking Service(ソーシャルネットワーキングサービス)の略
人と人とのつながりを促進・支援する、コミュニティ型のWeb サイト及びネットワークサービスのこと。コメントやトラックバックなどのコミュニケーション機能を有しているブログや、電子掲示板、あるいはそういったサービスを提供するウェブサイトも含まれる。
2 次産業
製造業、鉱業及び建設業からなる産業部門。
【参考】1 次産業:農業、林業、水産業など直接自然に働きかける産業の総称。
3 次産業
運輸、通信、商業、金融、公務及び自由職業、その他のサービス業を含む産業部門。
5S 活動
職場の環境改善で用いられるスローガンのこと。「整理」・「整頓」・「清掃」・「清潔」・「しつけ」の頭の文字S をとったもの。生産物の品質・コストなどを管理するための基礎的な条件となる。
6 次産業化
生産(1 次)のみにとどまらず、農産物加工や食品製造(2 次)、卸・小売、情報サービス、観光(3 次)分野にまで経営を発展させる農業経営の展開方法。
「1 次産業×2 次産業×3 次産業=6 次産業」という考え方による。
1次産業(農林水産物生産)×2次産業(加工)×3次産業(販売)のことで、それぞれの産業が一体となって、総合産業(6次産業)として発展することを目指し、その際、どれかが欠けると0になってしまうため、いずれも欠かないという、産業間連携の在り方を示すもの。
インバウンド
外国人が日本を訪れ観光すること。
オール浜松
農業者をはじめ、地域づくりの主役である市民や企業、農業協同組合、教育機関、NPO、各種団体、行政機関など、多様な主体が自らの特徴を生かし、浜松市全体で連携して取り組むこと。
観光資源
観光やレジャーに使われる施設や、あるいは風光明媚で目を楽しませる名勝などや舌を楽しませる郷土料理から伝統に基づく地域の文化など、観光産業の興すときの元となる地域にある資産や資源。
グリーン・ツーリズム
自然豊かな農山漁村地域に滞在し、その自然、文化、人々との交流を楽しむ余暇活動。
経営感覚
企業等を経営する上での能力や才能のこと。経営者が持っている仕事に対する考え方や姿勢。
経営耕地面積
農業経営体*が経営している耕地をいい、自家で所有している耕地(自作地)と、よそから借りて耕作している耕地(借入耕地)の合計。
※土地台帳の地目や面積に関係なく、実際の地目別の面積。(農林水産省)
経営耕地=所有耕地-貸付耕地-耕作放棄地+借入耕地
後継者(農業後継者)
15 歳以上の者で次の代で農業経営を継承することが確認されている者(予定者を含む。)。
耕作放棄地
農林水産省の統計調査における区分であり、過去1 年間作物の作付けがなく、今後数年の間に再び耕作する明確な意思のない農地。耕作放棄地は多少手を加えれば耕地になる可能性のあるもので、長期間にわたり放置し、現在、原野化しているような土地は含まない。
コーディネーター
物事が円滑に行われるように、全体の調整や進行を担当する人。
事業者
営利などの目的をもって事業を営む者。
市場競争力
企業等が、財やサービスを供給する市場へ自由に参入し、消費者を獲得するため、価格や品質面などで他の企業と競い合うこと。
静岡県経済産業ビジョン2018 ~2021 ( 農業・農村編)
静岡県の農業・農村の今後の方向を示す基本指針となる計画。
第1章 ビジョン策定の基本的な考え方、第2章 本県の農業・農村の現状と課題、第3章 ビジョンの基本方針、第4章 施策の推進方策、第5章 地域農業の振興方向(地域計画)の5章により構成されている。
実証実験
新開発の製品・技術などを、実際の場面で使用し、実用化に向けての問題点を検証すること。
市民協働
市民、市民活動団体、事業者及び市が、それぞれの特性を生かしながら、共通の課題や目的を達成するため、さまざまな観点や形態で取り組むこと。
市民農園
都市の住民がレクリエーション、自家消費用野菜・花の生産、高齢者の生きがいづくり等の多様な目的で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園。
ジェトロ(日本貿易振興機構)
日本貿易振興会を引き継いで設立された独立行政法人。対日投資の促進、農林水産物・食品の輸出や中堅・中小企業等の海外展開支援に機動的かつ効率的に取り組むとともに、調査や研究を通じ日本の企業活動や通商政策に貢献している。
ジビエ
キジ、ヤマウズラ、野ウサギ、シカ、イノシシなど、狩猟によって食材として捕獲される野生鳥獣やその肉。
消費者ニーズ
生活を送るうえでの消費者の基本的な欲求のこと。これに応えることが、商品を購入してもらうための必要条件となる。
食農教育
食のもつ多彩な役割の重要性を伝える「食育」に加えて、食を支えている農業についての知識や体験などを含む教育のこと。
食料・農業・農村基本計画(2015 年)
食料・農業・農村基本法に基づき、食料・農業・農村に関し、政府が中長期的に取り組むべき方針を定めたもの。
新規就農者
次のいずれかに該当するもの
(1) 新規自営農業就農者
農家世帯員で過去1年間の生活の主な状態が、「学生」又は「他に雇われた勤務が主」から「自営農業への従事が主」になった者。
(2) 新規雇用就農者
過去1年以内に新たに法人等に常雇い(年間7ヶ月以上)として雇用されることとなった者。
(3) 新規参入者
過去1年以内に土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者。
○新規学卒就農者
自営農業就農者で「学生」から「自営農業への従事が主」になった者及び雇用就農者で雇用される直前に学生であった者。
○認定新規就農者
認定新規就農者の欄に記載
水利組合
治水、水利、土工などの事業を営むため、地方公共団体または一定地域内の土地、家屋所有者を構成員として組織される公法人。
水利施設
農地へのかんがい用水の供給を目的とするかんがい施設や、農地における過剰な地表水及び土壌水の排除を目的とする排水施設。
戦略計画
浜松市未来ビジョンの基本構想で定めた都市の将来像「市民協働で築く『未来へかがやく創造都市・浜松』」及び「1 ダースの未来(理想の姿)」の実現を目指し、市の重点施策やその目標を掲げ、政策や事業とともに、行財政改革や資源配分などの考え方を含めた市政全般にわたる方向性を示し、毎年度の環境の変化を踏まえて策定する計画。
総農家数
販売農家(経営耕地面積30 アール以上、又は年間農産物販売金額50 万円以上)と自給的農家(経営耕地面積30 アール未満かつ年間農産物販売金額50 万円未満)の計。
第3 次浜松市食育推進計画
食を大切にし、生きる力を育むことを食育ととらえ、市民一人ひとりが食に対して関心を持ち、自ら食に関する正しい知識を身に付け、生涯にわたり健康的な食生活を実践していけるよう策定した浜松市の計画(2018~2022 年度)。
多面的機能
農業・農村が、食料を供給する役割だけでなく、その生産活動を通じ、国土の保全、水源のかん養、生物多様性の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等、さまざまな機能を有していること。
地域資源
地域内で産するさまざまな素材、自然景観や史跡、固有の技術・情報、地域に住む人材等をいう。
地域団体商標
協同組合等が、協同組合等の構成員に使用させる商標であり、地域名と、商品・役務の普通名称等を組み合わせた文字のみで構成されていて、一定以上有名になっている商標。
地域農業
その地域ならではの特色ある地域性豊かな農業。
地産地消
地域生産地域消費の略語で、地域で生産された農産物等をその地域で消費すること。
地方計画
都市問題のように特定地域へ集積した社会問題を解決するため,その計画の範域を拡大し、広域的に処理する計画、または国土計画の下位計画としての性格をもつ計画。
鳥獣被害
クマ、ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、ハクビシン、カラスなどの鳥獣により、農林水産物及び家畜等が被害を受けること。
直売所
その直売所が立地する周辺の農家あるいは農業協同組合(農協、JA)などが設置した、地元の農産物を販売する施設。
都市農業振興基本法
都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の多様な機能の発揮を通じ、良好な都市環境の形成に資することを目的として制定。
土地改良区
一定地域の土地改良事業*を実施することを目的に、土地改良法に基づき都道府県知事の認可を得て設立される公共団体。
土地改良事業
農用地、農業施設の改良・開発・保全・集団化に関する事業。
トレーサビリティ
食品等の生産や流通に関する履歴情報を追跡・遡及することができるしくみ。農業者や流通業者は、媒体(バーコード、IC タグ等)に食品情報を集積するなどし、それを消費者等が必要に応じて検索できるシステム。これにより、食品事故発生時の早期原因究明や農業者と消費者の「顔の見える関係」の構築が期待される。
担い手
制度や事業によってそれぞれ定義付けられるが、一般的には今後の農業を担う人をいう。
認定農業者
農業経営基盤強化促進法(昭和55 年法律第65 号)の規定に基づき、効率的で安定した農業経営を目指すために作成する「農業経営改善計画」を市町村に提出し、認定を受けた農業者(法人を含む。)。
認定新規就農者
農業経営基盤強化促進法(昭和55 年法律第65 号)の規定に基づき、「青年等就農計画」を市町村に提出し認定を受けた、経営開始前又は就農5 年以内でおおむね45 才未満の農業者(法人を含む。)。
農家
経営耕地面積が10 アール以上の農業を営む世帯又は農産物販売額が年間15 万円以上ある世帯。
農業基盤の強化の促進に関する基本的な構想
農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村で策定される計画のこと。浜松市の農業の持続的発展を図るため、将来(おおむね10 年後)の育成すべき農業経営の目標の設定と、その実現に向けての措置などを明らかにしている。
農業経営体
次のいずれかに該当する事業を行う者。
(1)経営耕地面積が30a 以上の規模の農業
(2)農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数、その他の事業
の規模が次の外形基準以上の農業
① 露地野菜作付面積15a
②施設野菜栽培面積350 ㎡
③果樹栽培面積10a
④露地花き栽培面積10a
⑤施設花き栽培面積250 ㎡
⑥搾乳牛飼養頭数1頭
⑦肥育牛飼養頭数1頭
⑧豚飼養頭数15 頭
⑨採卵鶏飼養羽数150 羽
⑩ブロイラー年間出荷羽数1,000 羽
⑪その他調査期日前1年間における農産物の総販売額50 万円に相当する事業の規模
(3)農作業の受託の事業
農業産出額
農業生産活動による最終生産物の総産出額であり、農産物の品目別生産量から、二重計上を避けるために、種子、飼料等の中間生産物を控除した数量に、当該品目別農家庭先価格を乗じて得た額を合計したものである。
農業就業人口
15 歳以上の農家世帯員のうち,過去1 年間に従事した仕事が自家農業だけの者、及び他産業に従事していても年間従事日数において自家農業従事日数のほうが多い者をいう。
農業者
農業に従事している人。
農産物
農業によって生産される物。穀類・野菜・果物・茶・畜産物・花きなど。
農村環境
経済生活の基礎を農業におく村落の環境。
農地銀行
農地の貸し借りや売買の促進(農地利用の流動化)を目的に、農業委員会に申込みのあった「売りたい・貸したい農地」や「農地を買いたい・借りたい農業者」の情報を公開するもの。
農地中間管理事業
農地を貸付けたい人から「公社」(機構)が農地を借り入れ、農業経営の規模拡大や効率化などを進める担い手に集約的に貸付ける制度。
農泊食文化海外発信地域(SAVOR JAPAN)
地域の食と、それを生み出す農林水産業を核として訪日外国人を中心とした観光客の誘致を図る地域として農林水産大臣が認定するもの。
浜松市農業振興協議会
浜松市の農業振興を図るため、農業関連団体が有機的に連携し、構成員相互の連絡調整を行うとともに、市の農業政策の形成に寄与することを目的とした組織。
浜松市農業振興地域整備計画
農用地区域の設定と農用地区域内の土地の農業上の用途の指定を定めた「農用地利用計画」と農業生産基盤の整備・開発、農用地等の保全、農業経営の規模の拡大等を定めた「農業振興のマスタープラン」を併せた計画。
浜松市農村環境計画
市が、農業振興地域において、農業総合整備事業の計画段階において、地域住民の多種多様な意向を踏まえ、農業の有する多面的機能の適切かつ十分な発揮や環境との調和への配慮に応じるため、環境に関する総合的な調査を行い、環境保全の基本方針を明確にした上で策定する地域の計画のこと。
ビジネス経営体
家族経営から脱皮し、企業的な経営感覚で、地域の農業を引っ張っていけるような経営体。目指すビジネス経営体の要件は、次の4 つである。
①経営が継承されていく永続的な経営体。
②雇用による労働力を確保している。
③企業として一定以上(概ね5,000 万円以上)の販売規模を持ち、成長を志向している。
④マーケティング戦略に基づくサービスや商品を提供している。
ビジネスマッチング
商品やサービスの提供側とその利用者側との間に入って結びつけてビジネスにつなげること。
人・農地プラン
集落・地域の徹底的な話し合いを通じて、人と農地の問題を一体的に解決し、持続可能な力強い農業を実現するため、今後の中心となる経営体や将来の農地利用のあり方などを定めたプラン。
法人化
個人事業主として事業を行っている者が、法人を設立して、その法人組織の中で事業を引き継いで行っていくこと。
マーケティング
買い手のニーズに基づき、生産物の仕様・価格・提供方法などを統合的に企画・実行する活動。
マーケティング戦略
マーケティング*活動をより効果的に行うために、自社の力を見極めたうえで、成長の方向性や事業展開の範囲・方法などを総合的に考えること。
見える化
物事の現状、進捗状況、実績、課題などを常に見えるようにしておくこと。
無菌苗(ウイルスフリー苗)
バイオテクノロジー(培養技術)を利用して、病原性ウイルスを取り除いた苗。病徴がなく、生育が旺盛で健全に生長する苗。
やらまいか精神【本編】
「やろうじゃないか」や「しましょうか」という遠州地方の方言だが、単なる方言ではなく、遠州人の「あれこれ考え悩むより、まず行動しよう」という進取の精神を表すもの。
ユニバーサル農業
農業や園芸作業を行うことによる生きがいづくりや高齢者・障がい者の社会参画などの効用を農業経営の改善や多様な担い手の育成などに生かしていく取組。
ワンストップサービス
ひとつの場所でさまざまなサービスが受けられる環境、場所のこと。
2018年12月18日
第2 次浜松市国際戦略プラン 用語解説
第2次浜松市国際戦略プラン(案)
国際通貨基金(IMF)(P.4)
国際貿易の促進、加盟国の高水準の雇用と国民所得の増大、為替の安定などに寄与する目的で業務を行う世界189 か国が加盟する国際機関。
アジア開発銀行(ADB)(P.4)
世界最大の貧困人口を抱えるアジア太平洋地域の貧困削減を図り、平等な経済成長を実現することを最重要課題として取り組む1996 年に設立された国際開発金融機関。
持続可能な開発目標(SDGs)(P.4)
2015 年9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030 アジェンダ」にて記載された2016 年から2030 年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っている。
ICT(P.5)
情報通信技術。主に情報処理や情報通信に関連する技術、産業、サービスなどの総称。ICT(Information and Communication echnology)
人工知能(AI)(P.5)
人間の知的ふるまいの一部をソフトウェアを用いて人工的に再現すること。AI(Artificial Intelligence)
IоT(P.5)
モノのインターネットの略。家電家具、住宅、道路、建築物、衣服などにセンサーが付随してインターネットと繋がることで相互作用を行い、生活を便利にする概念。IoT(Internet of Things)
ユネスコ創造都市ネットワーク(P.6)
ユネスコにより創設された都市のネットワークで、文化の多様性を保持するとともに、世界各地の文化産業が潜在的に有している可能性を都市間の連携により最大限に発揮させることを目的としている。音楽やデザインなど、7 つの分野から構成され。本市は、2014 年12 月に音楽分野に加盟した。
浜松国際ピアノコンクール(P.6)
1991 年(平成3 年)に市制80 周年を記念して、楽器と音楽のまちとしての歴史と伝統を誇るにふさわしい国際文化事業としてスタートし、以後3 年毎に開催されている。世界を目指している多くの若いピアニストに日ごろの研鑽の成果を披露する場の提供と若手ピアニストの育成、世界の音楽文化の振興、国際交流の推進を目的としている。また、1998 年(平成10 年)には、国際音楽コンクール世界連盟に加盟している。
アジア・太平洋吹奏楽指導者協会大会(P.6)
アジア・太平洋吹奏楽指導者協会(APBDA)が主催する大会で、吹奏楽に関する研究発表、講演、コンサート等が行われる。1994 年(平成6 年)に第8 回大会が浜松市で開催され、2018年(平成30 年)には、第20 回大会を再び浜松市で開催した。
外国人集住都市会議(P.6)
2001 年(平成13 年)に浜松市の提唱により設立された、外国人住民が多数居住する都市をもって構成される都市間ネットワーク。会員都市間で多文化共生に関する情報交換を行い、より良い施策の推進に繋げるとともに、法律や制度に起因する課題の解決を目指し、首長会議の
開催等を通じ国への政策提言を継続的に行っている。
インターカルチュラル・シティ(ICC)・ネットワーク(P.6)
国際機関である欧州評議会の主導により、世界120 都市以上が参加し、多様性を生かしたまちづくりを進める多文化共生分野の都市間ネットワーク。2017 年10 月、本市はアジアの都市として初めて同ネットワークに加盟した。
水と暮らしを豊かにする浜松技術プラットフォーム(HARP♪)(P.6)
蓄積された水道技術の維持向上を目的に、国際的な技術支援及び市内企業の海外展開を進めるため、本市上下水道部と市内企業・関係団体により構成された官民連携による技術支援活動や技術普及方策について意見交換等を行うプラットフォーム。2016 年9 月設置。
フェアトレードタウン(P.6)
市民団体や商店・企業、行政などが連携し、「まちぐるみ」でフェアトレード(適正な価格で継続的に購入する貿易の仕組み)の輪を広げていく自治体。
FSC森林認証(P.6)
ドイツのボンに本部を置く第三者機関が、森林の管理が環境や地域社会の利益に配慮して適切に行われているかどうか、経済的にも持続可能かどうかなどの視点から全世界統一の基準に基づいて審査・認証する森林の国際認証制度。
浜松地域FSC・CLT利活用推進協議会(P.6)
天竜材の地産地消による地域産業の活性化や地方創生、さらには都市の木質化による地球温暖化防止等を目的として設立された浜松地域の企業・団体が参画する官民連携組織。
SAVOR JAPAN(農泊 食文化海外発信地域)(P.6)
地域の食と、それを生み出す農林水産業を核として訪日外国人を中心とした観光客の誘致を図る地域として農林水産省が認定する制度。本市は2017 年度に認定を受けた。
公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー(P.6)
国内外のコンベンション及び観光客の誘致及び支援を行うことにより、コンベンション及び観光の振興を図るとともに、国際相互理解の増進並びに地域経済の活性化と文化の向上を目的とした公益財団法人で地域連携DMO。
地域連携DMO(P.6)
複数の地方公共団体に跨る区域を一体とした観光地域として、観光マネジメントとマーケティングを行うことにより観光地域づくりを行う組織。
ホストタウン(P.6)
2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向け、スポーツ王国、グローバル化の推進、地域の活性化、観光振興等に資する観点から、参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流を図る地方公共団体。
SDGs未来都市(P.6)
SDGs の理念に沿った基本的・総合的取組を推進しようとする都市・地域の中から、特に経済・社会・環境の三側面における新しい価値創出を通して持続可能な開発を実現するポテンシャルが高い都市・地域として選定されること。(SDGs:Sustainable Development Goals)
はままつ響きの創造プロジェクト(P.7)
本市の創造的文化活動や共生社会への取組等を国内外へ発信するため、「響き」をキーワードに地域が一体となった取組を推進する3 ヶ年にわたり実施する2020 文化プログラム。
デスティネーションキャンペーン(DC)(P.7)
JR グループと指定された自治体、地元の観光事業者等が共同で実施する国内最大の観光キャンペーン。期間は四半期ごとに年間4 回行われる。静岡県では2019 年4~6 月に19 年ぶりに開催される。
浜松国際交流協会(HICE)(P.8)
市民レベルでの国際交流及び多文化共生の推進母体として情報提供、相談業務、各種講座等を実施するとともに、NPO やボランティアの活動支援等を行う公益財団法人。
都市・自治体連合(UCLG)(P.8)
世界最大の自治体の連合組織。世界136 の国と地域の1,000 以上の都市と112 の自治体の全国組織が加盟。浜松市長は、現在、アジア太平洋支部(ASPAC)及び世界組織の執行理事及び評議員を務めている。
健康都市連合(AFHC)(P.8)
都市に暮らす人々の健康増進と生活向上を目指すネットワーク。アジア太平洋地域を中心に10 か国から178 都市44 団体が加盟。うち、日本からは38 都市4 団体が加盟。
欧州評議会(P.8)
人権、民主主義、法の支配の分野で国際社会の基準策定を主導する汎欧州の国際機関でフランス・ストラスブールに本部を置く。日本は1996 年からオブザーバー国として参加。
新たな産業(P.11)
本市の産業分野における計画として2011 年(平成23 年)に策定した「はままつ産業イノベーション構想(2017 年(平成29 年)改訂)」の中で、重点的に支援する成長分野として次の6つの分野を位置づけている。「次世代輸送用機器」「健康・医療」「新農業」「光・電子」「環境・エネルギー」「デジタルネットワーク・コンテンツ」。
国家戦略特区(P.12)
国家戦略特別区域。経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点の形成を促進する観点から国が定める区域のこと。
コンベンション(P.18)
各種大会や会議、見本市、イベントなどの催しのこと。開催によって、都市のイメージアップ、経済の活性化、集客、交流などが期待される。
浜松市未来を拓く農林漁業育成事業(P.18)
浜松市の農林水産物及び農山漁村の価値及び認知度向上に繋がる事業について、1 次産業である農林漁業と2 次産業の工業、3 次産業の商業や観光業等を組み合わせた6 次産業化・ブランド化を促し、農林漁業そして食料関連事業を活性化して次世代へと繋げることを目的とした補助事業。
「出世の街・浜松」ブランド(P.20)
「出世大名家康くん」「出世法師直虎ちゃん」、2017 年大河ドラマ「おんな城主直虎」でも注目を集めた浜松ゆかりの徳川家康公、井伊直虎・直政等の歴史資源の総称。
国際協力機構(JICA)(P.20)
国際協力の促進並びに日本及び国際社会の発展に資することを目的として、開発途上地域等の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に資する活動を行う独立行政法人。
浜松地域イノベーション推進機構(P.21)
産学官の交流及び連携のもとに各種事業を通じて地域企業の経営基盤強化を図ることにより、浜松地域はもとより静岡県の産業経済の発展に寄与することを目的として設立された公益財団法人。
静岡県国際経済振興会(SIBA)(P.21)
静岡県の貿易振興に関する事業を行うとともに、県内中小企業の国際化を推進することを目的に設立された公益社団法人。海外取引や国際規格に関するセミナーの開催や、展示会・商談会の実施、国際経済情報の収集提供、国際ビジネスに関する相談等の事業を行っている。
日本貿易振興機構(JETRO)(P.21)
アジア等地域との貿易の拡大及び経済協力の促進に寄与することを目的として、日本企業の海外展開支援、外国企業の日本への誘致、日本の通商政策への貢献等を行う独立行政法人。
グローバル人材(P.21)
グローバル化する社会の中で活躍できる人材。一般的には外国語でのコミュニケーション能力や異文化理解・活用力等が求められるとされる。
海外展開事業化可能性調査(P.21)
海外展開の実現可能性や採算性などを多角的に調査すること。浜松市では、市内に本社機能を有する中小企業者が、海外ビジネス展開(進出・販路開拓)を目指して実施する海外展開事業化可能性調査に要する経費の一部を補助している。
インバウンド(P.22)
外国人が訪れてくる旅行のこと。政府は、2020 年の訪日外国人旅行者数の目標値を4,000 万人に設定している。
MICE(P.22)
企業等の会議(Meeting)、報奨・研修旅行(Incentive Travel)、国際会議(Convention)、展示会(Exhibition/Event)の頭文字で、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベント等の総称。
FIT(P.22)
FIT(Foreign Independent Travel)は、旅行を計画する際に、交通機関のチケットの手配からホテル選び等に至るまでの行程を旅行会社等に頼まず個人で手配する旅行。
フィルムコミッション(P.22)
地方活性化、文化振興、観光振興を図るため、映画等の撮影場所誘致や撮影支援を行う機関。
デジタルプロモーション(P.22)
インターネットのウェブサイトやSNS 等のデジタル技術を活用した情報発信。
SNS(P.22)
SNS(Social Networking Service)は、趣味、職業、居住地域などを同じくする個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援するインターネットを利用したサービス。
スポーツツーリズム(P.22)
スポーツを見に行くための旅行およびそれに伴う周辺観光や、スポーツを支える人々との交流などスポーツに係るさまざまな旅行。
アウトドアツーリズム(P.22)
屋外で行うスポーツやレジャーの総称。海岸や山間部など自然豊かな場所で行うスポーツやレジャーを表すアウトドアを目的とする旅行。
グリーンツーリズム(P.22)
農林漁村に滞在または訪問し、その土地ならではのさまざまな体験を楽しむとともに、地域の人々との交流を通じて自然や文化、生活等の魅力に触れる旅行。
クリエイティブ人材(P.24)
デザイナー、作家、アーティスト等、商品の開発や音楽活動等を通じて新たな価値を創造する人材。
国際観光振興機構(JNTO)(P.26)
自治体、旅行業界関連企業・団体等と連携しながら訪日外国人旅行者の誘致活動を行う独立行政法人。通称、日本政府観光局。日本の観光の魅力を海外に広報・宣伝するとともに、外国人旅行者が快く日本を旅行できるよう受入環境の改善に取り組んでいる。
自治体国際化協会(CLAIR)(P.26)
地域の国際化を推進する地方自治体の協同組織として1988 年(昭和63 年)に設立された一般財団法人。主に地方自治体の海外における活動の支援や地域の国際化、海外における地域活性化の方策等について情報の収集・提供等を行っている。
自治体職員協力交流事業(LGOTP)(P.28)
日本の自治体が海外の自治体職員を研修員として受け入れ、自治体が有するノウハウや技術習得を図るとともに、研修員が国際化施策に協力することで地域の国際化を推進するため、総務省と自治体国際化協会(CLAIR)が支援している事業。
国際通貨基金(IMF)(P.4)
国際貿易の促進、加盟国の高水準の雇用と国民所得の増大、為替の安定などに寄与する目的で業務を行う世界189 か国が加盟する国際機関。
アジア開発銀行(ADB)(P.4)
世界最大の貧困人口を抱えるアジア太平洋地域の貧困削減を図り、平等な経済成長を実現することを最重要課題として取り組む1996 年に設立された国際開発金融機関。
持続可能な開発目標(SDGs)(P.4)
2015 年9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030 アジェンダ」にて記載された2016 年から2030 年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っている。
ICT(P.5)
情報通信技術。主に情報処理や情報通信に関連する技術、産業、サービスなどの総称。ICT(Information and Communication echnology)
人工知能(AI)(P.5)
人間の知的ふるまいの一部をソフトウェアを用いて人工的に再現すること。AI(Artificial Intelligence)
IоT(P.5)
モノのインターネットの略。家電家具、住宅、道路、建築物、衣服などにセンサーが付随してインターネットと繋がることで相互作用を行い、生活を便利にする概念。IoT(Internet of Things)
ユネスコ創造都市ネットワーク(P.6)
ユネスコにより創設された都市のネットワークで、文化の多様性を保持するとともに、世界各地の文化産業が潜在的に有している可能性を都市間の連携により最大限に発揮させることを目的としている。音楽やデザインなど、7 つの分野から構成され。本市は、2014 年12 月に音楽分野に加盟した。
浜松国際ピアノコンクール(P.6)
1991 年(平成3 年)に市制80 周年を記念して、楽器と音楽のまちとしての歴史と伝統を誇るにふさわしい国際文化事業としてスタートし、以後3 年毎に開催されている。世界を目指している多くの若いピアニストに日ごろの研鑽の成果を披露する場の提供と若手ピアニストの育成、世界の音楽文化の振興、国際交流の推進を目的としている。また、1998 年(平成10 年)には、国際音楽コンクール世界連盟に加盟している。
アジア・太平洋吹奏楽指導者協会大会(P.6)
アジア・太平洋吹奏楽指導者協会(APBDA)が主催する大会で、吹奏楽に関する研究発表、講演、コンサート等が行われる。1994 年(平成6 年)に第8 回大会が浜松市で開催され、2018年(平成30 年)には、第20 回大会を再び浜松市で開催した。
外国人集住都市会議(P.6)
2001 年(平成13 年)に浜松市の提唱により設立された、外国人住民が多数居住する都市をもって構成される都市間ネットワーク。会員都市間で多文化共生に関する情報交換を行い、より良い施策の推進に繋げるとともに、法律や制度に起因する課題の解決を目指し、首長会議の
開催等を通じ国への政策提言を継続的に行っている。
インターカルチュラル・シティ(ICC)・ネットワーク(P.6)
国際機関である欧州評議会の主導により、世界120 都市以上が参加し、多様性を生かしたまちづくりを進める多文化共生分野の都市間ネットワーク。2017 年10 月、本市はアジアの都市として初めて同ネットワークに加盟した。
水と暮らしを豊かにする浜松技術プラットフォーム(HARP♪)(P.6)
蓄積された水道技術の維持向上を目的に、国際的な技術支援及び市内企業の海外展開を進めるため、本市上下水道部と市内企業・関係団体により構成された官民連携による技術支援活動や技術普及方策について意見交換等を行うプラットフォーム。2016 年9 月設置。
フェアトレードタウン(P.6)
市民団体や商店・企業、行政などが連携し、「まちぐるみ」でフェアトレード(適正な価格で継続的に購入する貿易の仕組み)の輪を広げていく自治体。
FSC森林認証(P.6)
ドイツのボンに本部を置く第三者機関が、森林の管理が環境や地域社会の利益に配慮して適切に行われているかどうか、経済的にも持続可能かどうかなどの視点から全世界統一の基準に基づいて審査・認証する森林の国際認証制度。
浜松地域FSC・CLT利活用推進協議会(P.6)
天竜材の地産地消による地域産業の活性化や地方創生、さらには都市の木質化による地球温暖化防止等を目的として設立された浜松地域の企業・団体が参画する官民連携組織。
SAVOR JAPAN(農泊 食文化海外発信地域)(P.6)
地域の食と、それを生み出す農林水産業を核として訪日外国人を中心とした観光客の誘致を図る地域として農林水産省が認定する制度。本市は2017 年度に認定を受けた。
公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー(P.6)
国内外のコンベンション及び観光客の誘致及び支援を行うことにより、コンベンション及び観光の振興を図るとともに、国際相互理解の増進並びに地域経済の活性化と文化の向上を目的とした公益財団法人で地域連携DMO。
地域連携DMO(P.6)
複数の地方公共団体に跨る区域を一体とした観光地域として、観光マネジメントとマーケティングを行うことにより観光地域づくりを行う組織。
ホストタウン(P.6)
2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向け、スポーツ王国、グローバル化の推進、地域の活性化、観光振興等に資する観点から、参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流を図る地方公共団体。
SDGs未来都市(P.6)
SDGs の理念に沿った基本的・総合的取組を推進しようとする都市・地域の中から、特に経済・社会・環境の三側面における新しい価値創出を通して持続可能な開発を実現するポテンシャルが高い都市・地域として選定されること。(SDGs:Sustainable Development Goals)
はままつ響きの創造プロジェクト(P.7)
本市の創造的文化活動や共生社会への取組等を国内外へ発信するため、「響き」をキーワードに地域が一体となった取組を推進する3 ヶ年にわたり実施する2020 文化プログラム。
デスティネーションキャンペーン(DC)(P.7)
JR グループと指定された自治体、地元の観光事業者等が共同で実施する国内最大の観光キャンペーン。期間は四半期ごとに年間4 回行われる。静岡県では2019 年4~6 月に19 年ぶりに開催される。
浜松国際交流協会(HICE)(P.8)
市民レベルでの国際交流及び多文化共生の推進母体として情報提供、相談業務、各種講座等を実施するとともに、NPO やボランティアの活動支援等を行う公益財団法人。
都市・自治体連合(UCLG)(P.8)
世界最大の自治体の連合組織。世界136 の国と地域の1,000 以上の都市と112 の自治体の全国組織が加盟。浜松市長は、現在、アジア太平洋支部(ASPAC)及び世界組織の執行理事及び評議員を務めている。
健康都市連合(AFHC)(P.8)
都市に暮らす人々の健康増進と生活向上を目指すネットワーク。アジア太平洋地域を中心に10 か国から178 都市44 団体が加盟。うち、日本からは38 都市4 団体が加盟。
欧州評議会(P.8)
人権、民主主義、法の支配の分野で国際社会の基準策定を主導する汎欧州の国際機関でフランス・ストラスブールに本部を置く。日本は1996 年からオブザーバー国として参加。
新たな産業(P.11)
本市の産業分野における計画として2011 年(平成23 年)に策定した「はままつ産業イノベーション構想(2017 年(平成29 年)改訂)」の中で、重点的に支援する成長分野として次の6つの分野を位置づけている。「次世代輸送用機器」「健康・医療」「新農業」「光・電子」「環境・エネルギー」「デジタルネットワーク・コンテンツ」。
国家戦略特区(P.12)
国家戦略特別区域。経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点の形成を促進する観点から国が定める区域のこと。
コンベンション(P.18)
各種大会や会議、見本市、イベントなどの催しのこと。開催によって、都市のイメージアップ、経済の活性化、集客、交流などが期待される。
浜松市未来を拓く農林漁業育成事業(P.18)
浜松市の農林水産物及び農山漁村の価値及び認知度向上に繋がる事業について、1 次産業である農林漁業と2 次産業の工業、3 次産業の商業や観光業等を組み合わせた6 次産業化・ブランド化を促し、農林漁業そして食料関連事業を活性化して次世代へと繋げることを目的とした補助事業。
「出世の街・浜松」ブランド(P.20)
「出世大名家康くん」「出世法師直虎ちゃん」、2017 年大河ドラマ「おんな城主直虎」でも注目を集めた浜松ゆかりの徳川家康公、井伊直虎・直政等の歴史資源の総称。
国際協力機構(JICA)(P.20)
国際協力の促進並びに日本及び国際社会の発展に資することを目的として、開発途上地域等の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に資する活動を行う独立行政法人。
浜松地域イノベーション推進機構(P.21)
産学官の交流及び連携のもとに各種事業を通じて地域企業の経営基盤強化を図ることにより、浜松地域はもとより静岡県の産業経済の発展に寄与することを目的として設立された公益財団法人。
静岡県国際経済振興会(SIBA)(P.21)
静岡県の貿易振興に関する事業を行うとともに、県内中小企業の国際化を推進することを目的に設立された公益社団法人。海外取引や国際規格に関するセミナーの開催や、展示会・商談会の実施、国際経済情報の収集提供、国際ビジネスに関する相談等の事業を行っている。
日本貿易振興機構(JETRO)(P.21)
アジア等地域との貿易の拡大及び経済協力の促進に寄与することを目的として、日本企業の海外展開支援、外国企業の日本への誘致、日本の通商政策への貢献等を行う独立行政法人。
グローバル人材(P.21)
グローバル化する社会の中で活躍できる人材。一般的には外国語でのコミュニケーション能力や異文化理解・活用力等が求められるとされる。
海外展開事業化可能性調査(P.21)
海外展開の実現可能性や採算性などを多角的に調査すること。浜松市では、市内に本社機能を有する中小企業者が、海外ビジネス展開(進出・販路開拓)を目指して実施する海外展開事業化可能性調査に要する経費の一部を補助している。
インバウンド(P.22)
外国人が訪れてくる旅行のこと。政府は、2020 年の訪日外国人旅行者数の目標値を4,000 万人に設定している。
MICE(P.22)
企業等の会議(Meeting)、報奨・研修旅行(Incentive Travel)、国際会議(Convention)、展示会(Exhibition/Event)の頭文字で、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベント等の総称。
FIT(P.22)
FIT(Foreign Independent Travel)は、旅行を計画する際に、交通機関のチケットの手配からホテル選び等に至るまでの行程を旅行会社等に頼まず個人で手配する旅行。
フィルムコミッション(P.22)
地方活性化、文化振興、観光振興を図るため、映画等の撮影場所誘致や撮影支援を行う機関。
デジタルプロモーション(P.22)
インターネットのウェブサイトやSNS 等のデジタル技術を活用した情報発信。
SNS(P.22)
SNS(Social Networking Service)は、趣味、職業、居住地域などを同じくする個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援するインターネットを利用したサービス。
スポーツツーリズム(P.22)
スポーツを見に行くための旅行およびそれに伴う周辺観光や、スポーツを支える人々との交流などスポーツに係るさまざまな旅行。
アウトドアツーリズム(P.22)
屋外で行うスポーツやレジャーの総称。海岸や山間部など自然豊かな場所で行うスポーツやレジャーを表すアウトドアを目的とする旅行。
グリーンツーリズム(P.22)
農林漁村に滞在または訪問し、その土地ならではのさまざまな体験を楽しむとともに、地域の人々との交流を通じて自然や文化、生活等の魅力に触れる旅行。
クリエイティブ人材(P.24)
デザイナー、作家、アーティスト等、商品の開発や音楽活動等を通じて新たな価値を創造する人材。
国際観光振興機構(JNTO)(P.26)
自治体、旅行業界関連企業・団体等と連携しながら訪日外国人旅行者の誘致活動を行う独立行政法人。通称、日本政府観光局。日本の観光の魅力を海外に広報・宣伝するとともに、外国人旅行者が快く日本を旅行できるよう受入環境の改善に取り組んでいる。
自治体国際化協会(CLAIR)(P.26)
地域の国際化を推進する地方自治体の協同組織として1988 年(昭和63 年)に設立された一般財団法人。主に地方自治体の海外における活動の支援や地域の国際化、海外における地域活性化の方策等について情報の収集・提供等を行っている。
自治体職員協力交流事業(LGOTP)(P.28)
日本の自治体が海外の自治体職員を研修員として受け入れ、自治体が有するノウハウや技術習得を図るとともに、研修員が国際化施策に協力することで地域の国際化を推進するため、総務省と自治体国際化協会(CLAIR)が支援している事業。
2018年12月14日
2018年12月14日
2017年04月13日
「奄美群島国立公園」
34カ所目となる国立公園「奄美群島国立公園」
平成28年12月26日付けで中央環境審議会より答申を受けた「奄美群島国立公園の新規指定について」は、以下のとおり官報に告示されることとなりました。
今回の告示により、奄美大島、加計呂麻島、請島、与路島、喜界島、徳之島、沖永良部島及び与論島で構成される奄美群島に新たに国立公園が指定されることになります。
奄美群島は、国内最大規模の亜熱帯照葉樹林が広がり、大陸や日本本土との分離・結合を繰り返した島々の地史を背景に、アマミノクロウサギをはじめとする多種多様な固有で希少な動植物が生息・生育するとともに、世界有数の速度で今も隆起するサンゴ礁段丘、琉球石灰岩の海食崖やカルスト地形、世界的北限に位置するサンゴ礁のほか、マングローブや干潟など多様な自然環境を有する地域です。
また、奄美群島国立公園に含まれる奄美大島及び徳之島は、昨年4月に公園区域の大規模拡張を行った西表石垣国立公園の西表島、昨年9月に新たにやんばる国立公園として指定した沖縄島北部とともに、世界自然遺産候補地にもなっています。
奄美群島 国立 公園 の指定 及び公園計画決定 の概要
1.背景
奄美群島は、 特徴の異なる8つ々で構成されており奄美群島は、 特徴の異なる8つ々で構成されており世界的にも数少なく国内では最 大規模の亜熱帯照葉樹林、アマミノクロウサギなど固有又は希少動植物 大規模の亜熱帯照葉樹林、アマミノクロウサギなど固有又は希少動植物 、琉球石灰岩の 、琉球石灰岩の 海食崖や世界的北限に位置する サンゴ礁 、マングローブや干潟 、マングローブや干潟 など多様自然環境を有して います。
平成 22 年度に実施された国立公園総点検事業おいては、当該地域の 年度に実施された国立公園総点検事業おいては、当該地域の これらの 自然環境 が我国を代表する傑出された地域であと高く評価、新規に立公園の指定行う候 が我国を代表する傑出された地域であと高く評価、新規に立公園の指定行う候 補地として選定され ました 。
このよ うな評価を受け 、奄美群島について、自然環境関する情報をさら収集・分析し 奄美群島について、自然環境関する情報をさら収集・分析し 奄美群島について、自然環境関する情報をさら収集・分析し 奄美群島について、自然環境関する情報をさら収集・分析し た結果、 我が国を代表する傑出した景観有地域とて、新に奄美群島立公園指 我が国を代表する傑出した景観有地域とて、新に奄美群島立公園指 定する ことしまた 。また 、当該指定に併せて、 既に指定されている奄美群島国公園の 一部地域を 本国立公園に 編入し、 国定公園の指を解除します 。
2.指定理由 ・公園計画の 基本方針等
奄美群島 は、 次の風景形式中で、我が国を代表する傑出した自然有地域 次の風景形式中で、我が国を代表する傑出した自然有地域 であるため、国立公園に指定すもの。 であるため、国立公園に指定すもの。 また、 景観要素と本国立公園の特徴を簡潔 に表したテーマは次のとおりです。
風景 形式 :多くの固有種が集中して分布する国内最大規模亜熱帯照葉樹林生態 多くの固有種が集中して分布する国内最大規模亜熱帯照葉樹林生態 系、 自然性の高い河川景観、干潟・マングローブ生態 系サゴ礁自然性の高い河川景観、干潟・マングローブ生態 系サゴ礁自然性の高い河川景観、干潟・マングローブ生態 系サゴ礁自然性の高い河川景観、干潟・マングローブ生態 系サゴ礁系といった多様な生態が複合的に一体景観
主な 景観要素: 景観要素: 亜熱帯照葉樹林、 砂浜、 干潟海食崖砂浜、 干潟海食崖砂浜、 干潟海食崖リアス海岸、 海鳥やウミガメ の繁殖地、 の繁殖地、 の繁殖地、 の繁殖地、 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 、人と 、人と 自然の 関わりを示す文化景観
テ ー マ :「生命いのち にぎわう亜熱帯のシマ ~森と 海島人 しまっちゅ の暮らし~ 」
公園計画については、 自然環境と景観の多様性及びそこで体験きる質を 維 持向上できるよう、また利用者が自然環境の多様性・固有や伝統的な人と 向上できるよう、また利用者が自然環境の多様性・固有や伝統的な人と 向上できるよう、また利用者が自然環境の多様性・固有や伝統的な人と 向上できるよう、また利用者が自然環境の多様性・固有や伝統的な人と 向上できるよう、また利用者が自然環境の多様性・固有や伝統的な人と 向上できるよう、また利用者が自然環境の多様性・固有や伝統的な人と 向上できるよう、また利用者が自然環境の多様性・固有や伝統的な人と 向上できるよう、また利用者が自然環境の多様性・固有や伝統的な人と 向上できるよう、また利用者が自然環境の多様性・固有や伝統的な人と の関わりを感じること ができるよう 、適正な 保護規制計画、 保護施設 計画及び利用計画を設定します。
3.公園区域
スタジイ等を主とする奄美大島及び 徳之島 の亜熱帯照葉樹林 、砂浜、干潟海食崖リ 砂浜、干潟海食崖リ 砂浜、干潟海食崖リ 砂浜、干潟海食崖リ 砂浜、干潟海食崖リ アス海岸等 多様な自然景観 を有する奄美群島の海岸、 サンゴ礁 や魚類等の 生息 地となっ ている海域、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形などの自然景観人と関わりを ている海域、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形などの自然景観人と関わりを ている海域、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形などの自然景観人と関わりを 示す文化景観や集落を 公園区域とします。
4.保護規制計画
陸域については、 アマミノクロウサギをは じめとする固有又希少な 動植物の生息地 ・ 生育地 である 亜熱帯照葉樹林 、特異な景観を有するマングローブ重点的に保護しま。 また、海域 については良好なサンゴの生息区また、海域 については良好なサンゴの生息区また、海域 については良好なサンゴの生息区や与論島の沖合1 km に及ぶ広大な礁湖 の景観 を海域公園地区とし、 海域 景観を保護します。
5.保護 施設 計画
○自然再生施設
若齢照葉樹林等について、高への 再生・誘導 を図 ります 。
与論島における礁池内ついて衰退した サンゴ 群集等の再生を図ります 。
6.利用施設計画
利用者が 奄美群島の地形や生物等自然 環境多様性・固有、伝統的な人と奄美群島の地形や生物等自然 環境多様性・固有、伝統的な人と奄美群島の地形や生物等自然 環境多様性・固有、伝統的な人と奄美群島の地形や生物等自然 環境多様性・固有、伝統的な人ととの関わりを感じるこができよう 次の利用施設を計画します。
(1 )集団施設計画
奄美市住用町に「集団施設地区」を計画し、川及び役勝の河口発達する 奄美市住用町に「集団施設地区」を計画し、川及び役勝の河口発達する 奄美市住用町に「集団施設地区」を計画し、川及び役勝の河口発達する 奄美市住用町に「集団施設地区」を計画し、川及び役勝の河口発達する マングローブや 亜熱帯照葉樹林等における自然探勝をはじめとす適正利用推進 亜熱帯照葉樹林等における自然探勝をはじめとす適正利用推進 します。
(2) 単独施設
各市町 村において、以下の通り計画する。
奄美市 :園地( 園地( 6箇所 )、 宿舎(1箇所)、 野営場水泳宿舎(1箇所)、 野営場水泳宿舎(1箇所)、 野営場水泳宿舎(1箇所)、 野営場水泳宿舎(1箇所)、 野営場水泳宿舎(1箇所)、 野営場水泳宿舎(1箇所)、 野営場水泳宿舎(1箇所)、 野営場水泳宿舎(1箇所)、 野営場水泳宿舎(1箇所)、 野営場水泳宿舎(1箇所)、 野営場水泳博物 展示施設( 1箇所 )
大島郡和村 :園地(2箇所)、 園地(2箇所)、 野営場(1箇所)
大島 郡宇検村 :園地(1箇所)
大島 郡瀬戸内町 :園地(5箇所) 、宿舎1水泳場園地(5箇所) 、宿舎1水泳場園地(5箇所)
、宿舎1水泳場大島 郡龍郷町 :園地(1箇所)、博物 園地(1箇所)、博物 展示施設(1箇所)
大島 郡喜界町 :園地( 4箇所 )
大島郡徳之町:園地(2箇所) 、野営場1大島郡徳之町:園地(2箇所)
、野営場1大島郡天城町:園地( 2箇所 )
大島郡伊仙町:園地(4箇所) 、野営場(1箇所)
大島郡和泊町:園地(1箇所)
大島郡 知名町:園地(3箇所) 、野営場1
大島郡与論町:園地(1箇所) 、野営場大島郡与論町:園地(1箇所)
、野営場合計:園地( 合計:園地( 合計:園地( 合計:園地( 32 箇所)、野営場( 箇所)、野営場( 箇所)、野営場( 箇所)、野営場( 6箇所)、水泳場(2宿舎博物展 箇所)、水泳場(2宿舎博物展 箇所)、水泳場(2宿舎博物展 箇所)、水泳場(2宿舎博物展 箇所)、水泳場(2宿舎博物展 箇所)、水泳場(2宿舎博物展 箇所)、水泳場(2宿舎博物展 箇所)、水泳場(2宿舎博物展 箇所)、水泳場(2宿舎博物展 箇所)、水泳場(2宿舎博物展 箇所)、水泳場(2宿舎博物展 示施設( 2箇所)
(3)道路
(ア)車道
奄美市、 大島郡瀬戸内町、同和村 大島郡瀬戸内町、同和村 大島郡瀬戸内町、同和村 大島郡瀬戸内町、同和村 大島郡瀬戸内町、同和村 大島郡瀬戸内町、同和村 大島郡瀬戸内町、同和村 大島郡瀬戸内町、同和村 大島郡瀬戸内町、同和村 、同 郡宇検村 郡宇検村 郡宇検村 及び 同郡 龍郷町 龍郷町 (奄美大島)にお (奄美大島)にお (奄美大島)にお (奄美大島)にお (奄美大島)にお (奄美大島)にお (奄美大島)にお いて、車道( 10 路線)を、同郡喜界町( 喜界島)において 、車道(1路線) を計画 し ます 。
(イ)歩道
奄美市、大島郡宇検村及び同和( )において歩道奄美市、大島郡宇検村及び同和( )において歩道奄美市、大島郡宇検村及び同和( )において歩道奄美市、大島郡宇検村及び同和( )において歩道奄美市、大島郡宇検村及び同和( )において歩道奄美市、大島郡宇検村及び同和( )において歩道奄美市、大島郡宇検村及び同和( )において歩道奄美市、大島郡宇検村及び同和( )において歩道奄美市、大島郡宇検村及び同和( )において歩道奄美市、大島郡宇検村及び同和( )において歩道3路線)を、同 路線)を、同 路線)を、同 郡喜界町 ( 喜界島)において、歩道( 喜界島)において、歩道( 喜界島)において、歩道( 喜界島)において、歩道( 喜界島)において、歩道( 喜界島)において、歩道1路線)を 路線)を 路線)を 、同郡 徳之島町及び同郡 徳之島町及び同郡 徳之島町及び同郡 徳之島町及び同郡 徳之島町及び天城町 天城町 (徳 之島) において、歩道( 2路線)を計画します。
(参考: 公園面積 公園面積 )
陸 域
海 域
特別保護地区 5,248 ha
第一種特別地域 9,125 ha
第二種特別地域 25, 25,004 ha
第三種特別地域 1, 234 ha
普通地域 1,570 ha
陸域合計 42,181 42,18142,181 ha
海 域
海域公園地区 1,12 4 ha
普通地域 31,9 58 ha
海域合計 33,082 33,082 ha
平成28年12月26日付けで中央環境審議会より答申を受けた「奄美群島国立公園の新規指定について」は、以下のとおり官報に告示されることとなりました。
今回の告示により、奄美大島、加計呂麻島、請島、与路島、喜界島、徳之島、沖永良部島及び与論島で構成される奄美群島に新たに国立公園が指定されることになります。
奄美群島は、国内最大規模の亜熱帯照葉樹林が広がり、大陸や日本本土との分離・結合を繰り返した島々の地史を背景に、アマミノクロウサギをはじめとする多種多様な固有で希少な動植物が生息・生育するとともに、世界有数の速度で今も隆起するサンゴ礁段丘、琉球石灰岩の海食崖やカルスト地形、世界的北限に位置するサンゴ礁のほか、マングローブや干潟など多様な自然環境を有する地域です。
また、奄美群島国立公園に含まれる奄美大島及び徳之島は、昨年4月に公園区域の大規模拡張を行った西表石垣国立公園の西表島、昨年9月に新たにやんばる国立公園として指定した沖縄島北部とともに、世界自然遺産候補地にもなっています。
奄美群島 国立 公園 の指定 及び公園計画決定 の概要
1.背景
奄美群島は、 特徴の異なる8つ々で構成されており奄美群島は、 特徴の異なる8つ々で構成されており世界的にも数少なく国内では最 大規模の亜熱帯照葉樹林、アマミノクロウサギなど固有又は希少動植物 大規模の亜熱帯照葉樹林、アマミノクロウサギなど固有又は希少動植物 、琉球石灰岩の 、琉球石灰岩の 海食崖や世界的北限に位置する サンゴ礁 、マングローブや干潟 、マングローブや干潟 など多様自然環境を有して います。
平成 22 年度に実施された国立公園総点検事業おいては、当該地域の 年度に実施された国立公園総点検事業おいては、当該地域の これらの 自然環境 が我国を代表する傑出された地域であと高く評価、新規に立公園の指定行う候 が我国を代表する傑出された地域であと高く評価、新規に立公園の指定行う候 補地として選定され ました 。
このよ うな評価を受け 、奄美群島について、自然環境関する情報をさら収集・分析し 奄美群島について、自然環境関する情報をさら収集・分析し 奄美群島について、自然環境関する情報をさら収集・分析し 奄美群島について、自然環境関する情報をさら収集・分析し た結果、 我が国を代表する傑出した景観有地域とて、新に奄美群島立公園指 我が国を代表する傑出した景観有地域とて、新に奄美群島立公園指 定する ことしまた 。また 、当該指定に併せて、 既に指定されている奄美群島国公園の 一部地域を 本国立公園に 編入し、 国定公園の指を解除します 。
2.指定理由 ・公園計画の 基本方針等
奄美群島 は、 次の風景形式中で、我が国を代表する傑出した自然有地域 次の風景形式中で、我が国を代表する傑出した自然有地域 であるため、国立公園に指定すもの。 であるため、国立公園に指定すもの。 また、 景観要素と本国立公園の特徴を簡潔 に表したテーマは次のとおりです。
風景 形式 :多くの固有種が集中して分布する国内最大規模亜熱帯照葉樹林生態 多くの固有種が集中して分布する国内最大規模亜熱帯照葉樹林生態 系、 自然性の高い河川景観、干潟・マングローブ生態 系サゴ礁自然性の高い河川景観、干潟・マングローブ生態 系サゴ礁自然性の高い河川景観、干潟・マングローブ生態 系サゴ礁自然性の高い河川景観、干潟・マングローブ生態 系サゴ礁系といった多様な生態が複合的に一体景観
主な 景観要素: 景観要素: 亜熱帯照葉樹林、 砂浜、 干潟海食崖砂浜、 干潟海食崖砂浜、 干潟海食崖リアス海岸、 海鳥やウミガメ の繁殖地、 の繁殖地、 の繁殖地、 の繁殖地、 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 サンゴ礁、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形 、人と 、人と 自然の 関わりを示す文化景観
テ ー マ :「生命いのち にぎわう亜熱帯のシマ ~森と 海島人 しまっちゅ の暮らし~ 」
公園計画については、 自然環境と景観の多様性及びそこで体験きる質を 維 持向上できるよう、また利用者が自然環境の多様性・固有や伝統的な人と 向上できるよう、また利用者が自然環境の多様性・固有や伝統的な人と 向上できるよう、また利用者が自然環境の多様性・固有や伝統的な人と 向上できるよう、また利用者が自然環境の多様性・固有や伝統的な人と 向上できるよう、また利用者が自然環境の多様性・固有や伝統的な人と 向上できるよう、また利用者が自然環境の多様性・固有や伝統的な人と 向上できるよう、また利用者が自然環境の多様性・固有や伝統的な人と 向上できるよう、また利用者が自然環境の多様性・固有や伝統的な人と 向上できるよう、また利用者が自然環境の多様性・固有や伝統的な人と の関わりを感じること ができるよう 、適正な 保護規制計画、 保護施設 計画及び利用計画を設定します。
3.公園区域
スタジイ等を主とする奄美大島及び 徳之島 の亜熱帯照葉樹林 、砂浜、干潟海食崖リ 砂浜、干潟海食崖リ 砂浜、干潟海食崖リ 砂浜、干潟海食崖リ 砂浜、干潟海食崖リ アス海岸等 多様な自然景観 を有する奄美群島の海岸、 サンゴ礁 や魚類等の 生息 地となっ ている海域、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形などの自然景観人と関わりを ている海域、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形などの自然景観人と関わりを ている海域、隆起段丘鍾乳洞やカルスト地形などの自然景観人と関わりを 示す文化景観や集落を 公園区域とします。
4.保護規制計画
陸域については、 アマミノクロウサギをは じめとする固有又希少な 動植物の生息地 ・ 生育地 である 亜熱帯照葉樹林 、特異な景観を有するマングローブ重点的に保護しま。 また、海域 については良好なサンゴの生息区また、海域 については良好なサンゴの生息区また、海域 については良好なサンゴの生息区や与論島の沖合1 km に及ぶ広大な礁湖 の景観 を海域公園地区とし、 海域 景観を保護します。
5.保護 施設 計画
○自然再生施設
若齢照葉樹林等について、高への 再生・誘導 を図 ります 。
与論島における礁池内ついて衰退した サンゴ 群集等の再生を図ります 。
6.利用施設計画
利用者が 奄美群島の地形や生物等自然 環境多様性・固有、伝統的な人と奄美群島の地形や生物等自然 環境多様性・固有、伝統的な人と奄美群島の地形や生物等自然 環境多様性・固有、伝統的な人と奄美群島の地形や生物等自然 環境多様性・固有、伝統的な人ととの関わりを感じるこができよう 次の利用施設を計画します。
(1 )集団施設計画
奄美市住用町に「集団施設地区」を計画し、川及び役勝の河口発達する 奄美市住用町に「集団施設地区」を計画し、川及び役勝の河口発達する 奄美市住用町に「集団施設地区」を計画し、川及び役勝の河口発達する 奄美市住用町に「集団施設地区」を計画し、川及び役勝の河口発達する マングローブや 亜熱帯照葉樹林等における自然探勝をはじめとす適正利用推進 亜熱帯照葉樹林等における自然探勝をはじめとす適正利用推進 します。
(2) 単独施設
各市町 村において、以下の通り計画する。
奄美市 :園地( 園地( 6箇所 )、 宿舎(1箇所)、 野営場水泳宿舎(1箇所)、 野営場水泳宿舎(1箇所)、 野営場水泳宿舎(1箇所)、 野営場水泳宿舎(1箇所)、 野営場水泳宿舎(1箇所)、 野営場水泳宿舎(1箇所)、 野営場水泳宿舎(1箇所)、 野営場水泳宿舎(1箇所)、 野営場水泳宿舎(1箇所)、 野営場水泳宿舎(1箇所)、 野営場水泳博物 展示施設( 1箇所 )
大島郡和村 :園地(2箇所)、 園地(2箇所)、 野営場(1箇所)
大島 郡宇検村 :園地(1箇所)
大島 郡瀬戸内町 :園地(5箇所) 、宿舎1水泳場園地(5箇所) 、宿舎1水泳場園地(5箇所)
、宿舎1水泳場大島 郡龍郷町 :園地(1箇所)、博物 園地(1箇所)、博物 展示施設(1箇所)
大島 郡喜界町 :園地( 4箇所 )
大島郡徳之町:園地(2箇所) 、野営場1大島郡徳之町:園地(2箇所)
、野営場1大島郡天城町:園地( 2箇所 )
大島郡伊仙町:園地(4箇所) 、野営場(1箇所)
大島郡和泊町:園地(1箇所)
大島郡 知名町:園地(3箇所) 、野営場1
大島郡与論町:園地(1箇所) 、野営場大島郡与論町:園地(1箇所)
、野営場合計:園地( 合計:園地( 合計:園地( 合計:園地( 32 箇所)、野営場( 箇所)、野営場( 箇所)、野営場( 箇所)、野営場( 6箇所)、水泳場(2宿舎博物展 箇所)、水泳場(2宿舎博物展 箇所)、水泳場(2宿舎博物展 箇所)、水泳場(2宿舎博物展 箇所)、水泳場(2宿舎博物展 箇所)、水泳場(2宿舎博物展 箇所)、水泳場(2宿舎博物展 箇所)、水泳場(2宿舎博物展 箇所)、水泳場(2宿舎博物展 箇所)、水泳場(2宿舎博物展 箇所)、水泳場(2宿舎博物展 示施設( 2箇所)
(3)道路
(ア)車道
奄美市、 大島郡瀬戸内町、同和村 大島郡瀬戸内町、同和村 大島郡瀬戸内町、同和村 大島郡瀬戸内町、同和村 大島郡瀬戸内町、同和村 大島郡瀬戸内町、同和村 大島郡瀬戸内町、同和村 大島郡瀬戸内町、同和村 大島郡瀬戸内町、同和村 、同 郡宇検村 郡宇検村 郡宇検村 及び 同郡 龍郷町 龍郷町 (奄美大島)にお (奄美大島)にお (奄美大島)にお (奄美大島)にお (奄美大島)にお (奄美大島)にお (奄美大島)にお いて、車道( 10 路線)を、同郡喜界町( 喜界島)において 、車道(1路線) を計画 し ます 。
(イ)歩道
奄美市、大島郡宇検村及び同和( )において歩道奄美市、大島郡宇検村及び同和( )において歩道奄美市、大島郡宇検村及び同和( )において歩道奄美市、大島郡宇検村及び同和( )において歩道奄美市、大島郡宇検村及び同和( )において歩道奄美市、大島郡宇検村及び同和( )において歩道奄美市、大島郡宇検村及び同和( )において歩道奄美市、大島郡宇検村及び同和( )において歩道奄美市、大島郡宇検村及び同和( )において歩道奄美市、大島郡宇検村及び同和( )において歩道3路線)を、同 路線)を、同 路線)を、同 郡喜界町 ( 喜界島)において、歩道( 喜界島)において、歩道( 喜界島)において、歩道( 喜界島)において、歩道( 喜界島)において、歩道( 喜界島)において、歩道1路線)を 路線)を 路線)を 、同郡 徳之島町及び同郡 徳之島町及び同郡 徳之島町及び同郡 徳之島町及び同郡 徳之島町及び天城町 天城町 (徳 之島) において、歩道( 2路線)を計画します。
(参考: 公園面積 公園面積 )
陸 域
海 域
特別保護地区 5,248 ha
第一種特別地域 9,125 ha
第二種特別地域 25, 25,004 ha
第三種特別地域 1, 234 ha
普通地域 1,570 ha
陸域合計 42,181 42,18142,181 ha
海 域
海域公園地区 1,12 4 ha
普通地域 31,9 58 ha
海域合計 33,082 33,082 ha
2015年05月29日
群馬など4湿地をラムサール登録 国内50カ所に
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015052901001060.html
2015年5月29日 09時30分
環境省は29日、国際的に重要な湿地の保全を目指すラムサール条約に、群馬、茨城、佐賀の4カ所が新たに登録されたと発表した。国内の登録湿地は50カ所になった。
6月1日からウルグアイで締約国会議が開かれ、期間中の3日に認定証が授与される。環境省によると、授与式には佐賀市の秀島敏行市長ら関係自治体の代表が出席する予定。
4カ所は群馬県の芳ケ平湿地群、茨城県の涸沼、佐賀県の東よか干潟と肥前鹿島干潟。
ほかに、既に登録されている慶良間諸島海域(沖縄)について、昨年3月に同諸島などが国立公園に指定されたことを受け、登録面積を8290ヘクタールに拡張した。
(共同)

日本の登録湿地
北海道
釧路湿原(1980年6月17日登録)
クッチャロ湖(1989年7月6日登録)
ウトナイ湖(1991年12月12日登録)
霧多布湿原(1993年6月10日登録)
厚岸湖・別寒辺牛湿原(1993年6月10日登録、2005年11月8日区域拡張)
宮島沼(2002年11月18日登録)
雨竜沼湿原(2005年11月8日登録)
サロベツ原野(2005年11月8日登録)
濤沸湖(2005年11月8日登録)
阿寒湖(2005年11月8日登録)
野付半島・野付湾(2005年11月8日登録)
風蓮湖・春国岱(2005年11月8日登録)
大沼 (七飯町)(2012年7月3日登録)
東北地方・関東地方・中部地方
青森県
仏沼(2005年11月8日登録)
宮城県
伊豆沼・内沼(1985年 9月13日登録)
蕪栗沼・周辺水田(2005年11月8日登録)
化女沼(2008年10月30日登録)
山形県
大山上池・下池(2008年10月30日登録)
福島県・群馬県・新潟県
尾瀬(2005年11月8日登録)
新潟県
佐潟(1996年3月23日登録)
瓢湖(2008年10月30日登録)
栃木県
奥日光の湿原(2005年11月8日登録)
栃木県・群馬県・埼玉県・茨城県(面積のほとんどが栃木県)
渡良瀬遊水地(2012年7月3日登録)
群馬県
芳ケ平湿地群(2015年5月29日登録)
茨城県
涸沼(2015年5月29日登録)
千葉県
谷津干潟(1993年6月10日登録)
石川県
片野鴨池(1993年6月10日登録)
富山県
弥陀ヶ原 (立山)(2012年7月3日登録)
大日平(2012年7月3日登録)
福井県
三方五湖(2005年11月8日登録)
中池見湿地(2012年7月3日登録)
愛知県
藤前干潟(2002年11月18日登録)
東海丘陵湧水湿地群(2012年7月3日登録)
近畿地方
滋賀県
琵琶湖(1993年6月10日登録、2008年10月30日区域拡張)
兵庫県
円山川下流域・周辺水田(2012年7月3日登録)
和歌山県
串本沿岸海域(串本海中公園周辺)(2005年11月8日登録)
中国地方
広島県
宮島の海岸部の一部(2012年7月3日登録)
鳥取県・島根県
中海(2005年11月8日登録)
島根県
宍道湖(2005年11月8日登録)
山口県
秋吉台地下水系(2005年11月8日登録)
九州・沖縄地方
熊本県
荒尾干潟(2012年7月3日登録)
大分県
くじゅう坊ガツル・タデ原湿原(2005年11月8日登録)
佐賀県
東よか干潟(2015年5月29日登録)
肥前鹿島干潟(2015年5月29日登録)
鹿児島県
藺牟田池(2005年11月8日登録)
屋久島永田浜(2005年11月8日登録)
沖縄県
漫湖(1999年5月15日登録)
慶良間諸島海域(2005年11月8日登録)
名蔵アンパル(2005年11月8日登録)
久米島の渓流・湿地(2008年10月30日登録)
与那覇湾(2012年7月3日登録)
2015年5月29日 09時30分
環境省は29日、国際的に重要な湿地の保全を目指すラムサール条約に、群馬、茨城、佐賀の4カ所が新たに登録されたと発表した。国内の登録湿地は50カ所になった。
6月1日からウルグアイで締約国会議が開かれ、期間中の3日に認定証が授与される。環境省によると、授与式には佐賀市の秀島敏行市長ら関係自治体の代表が出席する予定。
4カ所は群馬県の芳ケ平湿地群、茨城県の涸沼、佐賀県の東よか干潟と肥前鹿島干潟。
ほかに、既に登録されている慶良間諸島海域(沖縄)について、昨年3月に同諸島などが国立公園に指定されたことを受け、登録面積を8290ヘクタールに拡張した。
(共同)
日本の登録湿地
北海道
釧路湿原(1980年6月17日登録)
クッチャロ湖(1989年7月6日登録)
ウトナイ湖(1991年12月12日登録)
霧多布湿原(1993年6月10日登録)
厚岸湖・別寒辺牛湿原(1993年6月10日登録、2005年11月8日区域拡張)
宮島沼(2002年11月18日登録)
雨竜沼湿原(2005年11月8日登録)
サロベツ原野(2005年11月8日登録)
濤沸湖(2005年11月8日登録)
阿寒湖(2005年11月8日登録)
野付半島・野付湾(2005年11月8日登録)
風蓮湖・春国岱(2005年11月8日登録)
大沼 (七飯町)(2012年7月3日登録)
東北地方・関東地方・中部地方
青森県
仏沼(2005年11月8日登録)
宮城県
伊豆沼・内沼(1985年 9月13日登録)
蕪栗沼・周辺水田(2005年11月8日登録)
化女沼(2008年10月30日登録)
山形県
大山上池・下池(2008年10月30日登録)
福島県・群馬県・新潟県
尾瀬(2005年11月8日登録)
新潟県
佐潟(1996年3月23日登録)
瓢湖(2008年10月30日登録)
栃木県
奥日光の湿原(2005年11月8日登録)
栃木県・群馬県・埼玉県・茨城県(面積のほとんどが栃木県)
渡良瀬遊水地(2012年7月3日登録)
群馬県
芳ケ平湿地群(2015年5月29日登録)
茨城県
涸沼(2015年5月29日登録)
千葉県
谷津干潟(1993年6月10日登録)
石川県
片野鴨池(1993年6月10日登録)
富山県
弥陀ヶ原 (立山)(2012年7月3日登録)
大日平(2012年7月3日登録)
福井県
三方五湖(2005年11月8日登録)
中池見湿地(2012年7月3日登録)
愛知県
藤前干潟(2002年11月18日登録)
東海丘陵湧水湿地群(2012年7月3日登録)
近畿地方
滋賀県
琵琶湖(1993年6月10日登録、2008年10月30日区域拡張)
兵庫県
円山川下流域・周辺水田(2012年7月3日登録)
和歌山県
串本沿岸海域(串本海中公園周辺)(2005年11月8日登録)
中国地方
広島県
宮島の海岸部の一部(2012年7月3日登録)
鳥取県・島根県
中海(2005年11月8日登録)
島根県
宍道湖(2005年11月8日登録)
山口県
秋吉台地下水系(2005年11月8日登録)
九州・沖縄地方
熊本県
荒尾干潟(2012年7月3日登録)
大分県
くじゅう坊ガツル・タデ原湿原(2005年11月8日登録)
佐賀県
東よか干潟(2015年5月29日登録)
肥前鹿島干潟(2015年5月29日登録)
鹿児島県
藺牟田池(2005年11月8日登録)
屋久島永田浜(2005年11月8日登録)
沖縄県
漫湖(1999年5月15日登録)
慶良間諸島海域(2005年11月8日登録)
名蔵アンパル(2005年11月8日登録)
久米島の渓流・湿地(2008年10月30日登録)
与那覇湾(2012年7月3日登録)
2015年02月25日
ツマアカスズメバチ
1.特定外来生物に指定されたツマアカスズメバチの規制の開始
ヴェスパ・ヴェルティナ(ツマアカスズメバチ。以下「ツマアカスズメバチ」という。)については、平成27年3月1日(日)から、その飼養、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いについて、外来生物法に基づく規制が開始されます。
これにより、ツマアカスズメバチの飼養等は原則として禁止されますが、学術研究等の特定の目的に限り、下記3.の基準に適合する施設を有する等、飼養等の許可の基準を満たす場合には、許可を得ることができます。
なお、既に飼養等している場合は、平成27年8月31日(月)までに飼養等許可申請が必要となります。申請手続きは、全国の地方環境事務所等にて受け付けています。(全国の地方環境事務所等連絡先 http://www.env.go.jp/nature/intro/3breed/reo.html)
2.外来生物法
ツマアカスズメバチが特定外来生物に指定されたことから、輸入時に種類名証明書の添付が必要な生物として、「スズメバチ属全種」が指定されました。
3.特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の一部改正
ツマアカスズメバチについて、当該種の特徴等を踏まえ、特定飼養等施設の基準の細目等を定めました。
4.特定外来生物の防除の告示の一部改正
「セイヨウオオマルハナバチ等の防除に関する件」を一部改正し、新たに特定外来生物に指定されたツマアカスズメバチについて、防除の公示を行いました。
※3及び4の詳細は、環境省報道発表HP(http://www.env.go.jp/press/index.php)の添付資料をご参照ください。
ヴェスパ・ヴェルティナ(ツマアカスズメバチ。以下「ツマアカスズメバチ」という。)については、平成27年3月1日(日)から、その飼養、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いについて、外来生物法に基づく規制が開始されます。
これにより、ツマアカスズメバチの飼養等は原則として禁止されますが、学術研究等の特定の目的に限り、下記3.の基準に適合する施設を有する等、飼養等の許可の基準を満たす場合には、許可を得ることができます。
なお、既に飼養等している場合は、平成27年8月31日(月)までに飼養等許可申請が必要となります。申請手続きは、全国の地方環境事務所等にて受け付けています。(全国の地方環境事務所等連絡先 http://www.env.go.jp/nature/intro/3breed/reo.html)
2.外来生物法
ツマアカスズメバチが特定外来生物に指定されたことから、輸入時に種類名証明書の添付が必要な生物として、「スズメバチ属全種」が指定されました。
3.特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の一部改正
ツマアカスズメバチについて、当該種の特徴等を踏まえ、特定飼養等施設の基準の細目等を定めました。
4.特定外来生物の防除の告示の一部改正
「セイヨウオオマルハナバチ等の防除に関する件」を一部改正し、新たに特定外来生物に指定されたツマアカスズメバチについて、防除の公示を行いました。
※3及び4の詳細は、環境省報道発表HP(http://www.env.go.jp/press/index.php)の添付資料をご参照ください。
2015年02月17日
国立公園は32箇所
平成27年2月16日
(お知らせ)甑島(こしきしま)国定公園、妙高戸隠連山国立公園及び三陸復興国立公園の指定日等について
平成27年3月16日には、「甑島(こしきしま)国定公園」が新たに指定され、国定公園は57箇所となります。
また、平成27年3月27日には、「妙高戸隠連山国立公園」が新たに指定され、国立公園は32箇所となります。
さらに、平成27年3月31日に南三陸金華山国定公園が三陸復興国立公園に編入され、三陸復興国立公園が拡張されます。
平成27年1月20日付けで中央環境審議会より答申を受けた甑島国定公園及び妙高戸隠連山国立公園の指定並びに三陸復興国立公園の拡張による変更等については、下記の通り官報に告示されることとなりました。
○甑島国定公園の指定及び公園計画の決定 平成27年3月16日
○妙高戸隠連山国立公園の指定及び公園計画の決定 平成27年3月27日
○三陸復興国立公園の公園区域及び公園計画の変更 平成27年3月31日
※南三陸金華山国定公園は三陸復興国立公園に編入されることにより、3月31日に指定が解除されますので、 平成27年3月31日時点の国定公園の箇所数は、56となります。
妙高戸隠連山国立公園
甑島国定公園
(お知らせ)甑島(こしきしま)国定公園、妙高戸隠連山国立公園及び三陸復興国立公園の指定日等について
平成27年3月16日には、「甑島(こしきしま)国定公園」が新たに指定され、国定公園は57箇所となります。
また、平成27年3月27日には、「妙高戸隠連山国立公園」が新たに指定され、国立公園は32箇所となります。
さらに、平成27年3月31日に南三陸金華山国定公園が三陸復興国立公園に編入され、三陸復興国立公園が拡張されます。
平成27年1月20日付けで中央環境審議会より答申を受けた甑島国定公園及び妙高戸隠連山国立公園の指定並びに三陸復興国立公園の拡張による変更等については、下記の通り官報に告示されることとなりました。
○甑島国定公園の指定及び公園計画の決定 平成27年3月16日
○妙高戸隠連山国立公園の指定及び公園計画の決定 平成27年3月27日
○三陸復興国立公園の公園区域及び公園計画の変更 平成27年3月31日
※南三陸金華山国定公園は三陸復興国立公園に編入されることにより、3月31日に指定が解除されますので、 平成27年3月31日時点の国定公園の箇所数は、56となります。
妙高戸隠連山国立公園
甑島国定公園
2015年02月17日
ダーバン・プラットフォーム(ADP2-8)
http://www.env.go.jp/press/100337.html
平成27年2月16日
強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会第2回会合第8セッション(ADP2-8)の結果について(お知らせ)
2月8日~13日、スイス・ジュネーブにおいて、国連気候変動枠組条約の下の「強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会(ADP)」第2回会合第8セッションが行われたところ、概要は以下のとおり。我が国から、外務・経済産業・環境・農林水産・国土交通各省関係者が出席した。
(注)ADPは、2011年末に南アフリカ・ダーバンで開催された第17回気候変動枠組条約締約国会議(COP17)での決定を受け設置されたもの。(1)2015年に採択される予定の、全ての国に適用される2020年以降の新しい法的枠組み(以下「2015年合意」という。)(ワークストリーム1)及び(2)2020年までの緩和の野心の向上(ワークストリーム2)について議論を行う。
1.2015年合意についての議論(ワークストリーム1)
昨年12月にペルー・リマで開催されたCOP20の決定において、同決定の添付文書である「交渉テキスト案の要素」をCOP20の成果として認識し、本年5月前に「交渉テキスト」を作成することを目指し、作業を加速化させることが決定された。今次会合は、5月前に開催される最後のADPセッションであり、会合の最終日(13日)に交渉テキスト案を作成する予定とされていた。
(1)2015年合意に関する交渉
(ア)今次会合では、まず、「交渉テキスト案の要素」を踏まえ、セクション(A:前文、B:定義、C:総則/目的、D:緩和、E:適応及び損失と損害(ロス・アンド・ダメージ)、G:資金、H:技術開発・移転、I:キャパシティ・ビルディング、J:行動と支援の透明性、K:目標の周期及びプロセス、L:実施の促進及び遵守、M:手続・組織事項)ごとに、交渉テキスト案の要素に盛り込まれていない事項のみについて、各国からの追加提案が受け付けられた。その後、当該文書をどのように簡素化するかについて各国が意見を述べ、これに基づき実際に簡素化のための作業を行うのは次回会合とされた。
(イ)さらに、2015年合意の「構造」や、各国から様々な提案がなされている目標の周期、市場メカニズムといった個別テーマに焦点を当てた議論も行われた。「構造」については、多くの国が現在の文書の構造は最終的な合意の構造を予断しないと述べた。また、多くの先進国が、2015年合意はすべての国に適用され、気候変動枠組条約の附属書に基づく先進国・途上国の差異化を含めないものとなるべき、2015年合意の核となるのは緩和に向けた各国の取組であり、緩和に関する目標の周期が必要であること等を主張した。一方、一部の途上国は、気候変動枠組条約の附属書に基づく差異化が2020年以降も継続する、先進国が一定の周期に基づいて緩和に関する目標の提出、資金提供の義務を負うべきと主張した。
2015年合意の中核となる法的合意とそれに関連するCOP決定にそれぞれどのような内容を含めるべきかについても議論された。この中で、先進国は永続的なものは法的合意に、時間の経過とともに柔軟に発展させるべきものはCOP決定に含めるべきであり、重要性の違いではないと主張した。一方、多くの途上国は、本件を議論するのは時期尚早として意見を示さなかった。
(ウ)目標を提出する周期については、10年を主張する国と5年を主張する国とで分かれ、加えて、5年ごとのレビューを行う案や目標年を5年後とし10年後の参照目標も提出する案等が提示された。また、多くの途上国が、緩和に限らず、適応や資金も同様に目標に関する周期を設定するべきと主張した。
(エ)市場メカニズムについては、先進国と途上国を含む多くの国が、経験から学びつつ今後も目標の達成に市場メカニズムを活用することは有益であると主張したが、一方でその活用に反対する国もあった。また、2015年合意の下で定めるべきルールの内容、国連の関与のあり方、対象とするセクター、既存の京都メカニズムの取扱い等について議論が行われた。
(オ)こうした議論を踏まえ、12日の夜に交渉テキスト案(「ジュネーブテキスト」)がホームページ上に掲載され、翌13日の閉会会合において、今後、当該文書を交渉テキストとして事務局が編集し、国連公用語に翻訳の上、3月中に締約国に配布されることが決定した。
(2)我が国の立場
(ア)我が国は、新たな枠組みは全ての国が参加する公平かつ実効的なものであるべき、2015年合意において、各国は①定量化可能な目標の提出、②目標達成に向けた対策措置の実施、③実施状況のレビューを受けること、の3点について義務を負うべき、と主張した。
(イ)適応については、緩和とは性質の異なるものであることに鑑み、各国が適応を国家開発計画等に統合し、適応計画プロセスに着手し、適応行動をとるべき、資金については、先進国のみならず全ての責任と能力のある国による資金支援を奨励すべき、といった点を法的合意に含めることが考えられると主張した。
(ウ)市場メカニズム(我が国の進めている二国間クレジット制度(JCM)を含む)については、各国が目標の達成において、様々な市場メカニズムを適切に活用するよう、クレジットの二重計上防止を含む各国共通の計上ルールを構築していくべきと主張した。また、土地セクターについては、各国の国内事情を踏まえ行動にインセンティブを与えることや、既存のアプローチの活用が望ましいことを主張した。
(エ)目標の周期については、目標の終了年を2030年とする10年間の周期が好ましいと考える一方、5年毎の中間レビューを設けるという折衷案も検討しうるため、周期を中間レビューとともに10年毎に設定することを支持する、このレビューは各締約国の目標に対する明確性、透明性、理解、比較可能性を促進することが目的である旨主張した。
2.2020年までの緩和の野心向上(ワークストリーム2:WS2)
10日及び12日に2020年までの野心向上、及びそのためにCOP20決定においてADPに要請された、「技術的検討プロセス」の推進に関する議論が行われた。
先進国及び途上国の両方からWS2の取組の重要性が述べられた。途上国からは、改正京都議定書の批准が進んでいないこと、支援の提供についてギャップがあること、先進国の削減目標の野心が不足していることなどの主張があった。先進国からは、WS2における昨年からの成果を強調するとともに、先進国及び途上国の双方が着実に2020年までの取組を進めつつ、技術的検討プロセスを着実に実施していくことが重要であること、野心向上に向けては既存の仕組みを活用が重要であること、資金に関しては民間資金の活用が重要であるとの主張がなされた。
また、「技術的検討プロセス」については、主に、①削減効果の高い取組を実施に移すために「技術的検討プロセス」はどう貢献できるか、②これまでの経験に基づき、2015 年の「技術的検討プロセス」の活動をどう強化するか、③国以外のアクターの活動に関する情報共有をどう促進すべきかについて、国際機関からの発表と締約国との議論が行われた。
さらに、今後の技術専門家会合(TEM)の具体的なテーマ等について議論が行われた。会合の最終日に事務局から本会合の概要が発表され、今回の会合を受けて今後の計画が4月までに発表される予定。
3.他国やステークホルダー等との対話
様々な交渉グループに属する国々と緊密な意見交換を行うとともに、国内外のNGOとの意見交換、邦人記者に対するブリーフを行った。
4.今後のADP交渉予定
次回会合は6月1日~11日にドイツ・ボンにおいて開催される予定。また、通常の6月、12月に加えて、8月31日~9月4日及び10月19日~10月23日の2回のADP追加会合の開催が決定した。
平成27年2月16日
強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会第2回会合第8セッション(ADP2-8)の結果について(お知らせ)
2月8日~13日、スイス・ジュネーブにおいて、国連気候変動枠組条約の下の「強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会(ADP)」第2回会合第8セッションが行われたところ、概要は以下のとおり。我が国から、外務・経済産業・環境・農林水産・国土交通各省関係者が出席した。
(注)ADPは、2011年末に南アフリカ・ダーバンで開催された第17回気候変動枠組条約締約国会議(COP17)での決定を受け設置されたもの。(1)2015年に採択される予定の、全ての国に適用される2020年以降の新しい法的枠組み(以下「2015年合意」という。)(ワークストリーム1)及び(2)2020年までの緩和の野心の向上(ワークストリーム2)について議論を行う。
1.2015年合意についての議論(ワークストリーム1)
昨年12月にペルー・リマで開催されたCOP20の決定において、同決定の添付文書である「交渉テキスト案の要素」をCOP20の成果として認識し、本年5月前に「交渉テキスト」を作成することを目指し、作業を加速化させることが決定された。今次会合は、5月前に開催される最後のADPセッションであり、会合の最終日(13日)に交渉テキスト案を作成する予定とされていた。
(1)2015年合意に関する交渉
(ア)今次会合では、まず、「交渉テキスト案の要素」を踏まえ、セクション(A:前文、B:定義、C:総則/目的、D:緩和、E:適応及び損失と損害(ロス・アンド・ダメージ)、G:資金、H:技術開発・移転、I:キャパシティ・ビルディング、J:行動と支援の透明性、K:目標の周期及びプロセス、L:実施の促進及び遵守、M:手続・組織事項)ごとに、交渉テキスト案の要素に盛り込まれていない事項のみについて、各国からの追加提案が受け付けられた。その後、当該文書をどのように簡素化するかについて各国が意見を述べ、これに基づき実際に簡素化のための作業を行うのは次回会合とされた。
(イ)さらに、2015年合意の「構造」や、各国から様々な提案がなされている目標の周期、市場メカニズムといった個別テーマに焦点を当てた議論も行われた。「構造」については、多くの国が現在の文書の構造は最終的な合意の構造を予断しないと述べた。また、多くの先進国が、2015年合意はすべての国に適用され、気候変動枠組条約の附属書に基づく先進国・途上国の差異化を含めないものとなるべき、2015年合意の核となるのは緩和に向けた各国の取組であり、緩和に関する目標の周期が必要であること等を主張した。一方、一部の途上国は、気候変動枠組条約の附属書に基づく差異化が2020年以降も継続する、先進国が一定の周期に基づいて緩和に関する目標の提出、資金提供の義務を負うべきと主張した。
2015年合意の中核となる法的合意とそれに関連するCOP決定にそれぞれどのような内容を含めるべきかについても議論された。この中で、先進国は永続的なものは法的合意に、時間の経過とともに柔軟に発展させるべきものはCOP決定に含めるべきであり、重要性の違いではないと主張した。一方、多くの途上国は、本件を議論するのは時期尚早として意見を示さなかった。
(ウ)目標を提出する周期については、10年を主張する国と5年を主張する国とで分かれ、加えて、5年ごとのレビューを行う案や目標年を5年後とし10年後の参照目標も提出する案等が提示された。また、多くの途上国が、緩和に限らず、適応や資金も同様に目標に関する周期を設定するべきと主張した。
(エ)市場メカニズムについては、先進国と途上国を含む多くの国が、経験から学びつつ今後も目標の達成に市場メカニズムを活用することは有益であると主張したが、一方でその活用に反対する国もあった。また、2015年合意の下で定めるべきルールの内容、国連の関与のあり方、対象とするセクター、既存の京都メカニズムの取扱い等について議論が行われた。
(オ)こうした議論を踏まえ、12日の夜に交渉テキスト案(「ジュネーブテキスト」)がホームページ上に掲載され、翌13日の閉会会合において、今後、当該文書を交渉テキストとして事務局が編集し、国連公用語に翻訳の上、3月中に締約国に配布されることが決定した。
(2)我が国の立場
(ア)我が国は、新たな枠組みは全ての国が参加する公平かつ実効的なものであるべき、2015年合意において、各国は①定量化可能な目標の提出、②目標達成に向けた対策措置の実施、③実施状況のレビューを受けること、の3点について義務を負うべき、と主張した。
(イ)適応については、緩和とは性質の異なるものであることに鑑み、各国が適応を国家開発計画等に統合し、適応計画プロセスに着手し、適応行動をとるべき、資金については、先進国のみならず全ての責任と能力のある国による資金支援を奨励すべき、といった点を法的合意に含めることが考えられると主張した。
(ウ)市場メカニズム(我が国の進めている二国間クレジット制度(JCM)を含む)については、各国が目標の達成において、様々な市場メカニズムを適切に活用するよう、クレジットの二重計上防止を含む各国共通の計上ルールを構築していくべきと主張した。また、土地セクターについては、各国の国内事情を踏まえ行動にインセンティブを与えることや、既存のアプローチの活用が望ましいことを主張した。
(エ)目標の周期については、目標の終了年を2030年とする10年間の周期が好ましいと考える一方、5年毎の中間レビューを設けるという折衷案も検討しうるため、周期を中間レビューとともに10年毎に設定することを支持する、このレビューは各締約国の目標に対する明確性、透明性、理解、比較可能性を促進することが目的である旨主張した。
2.2020年までの緩和の野心向上(ワークストリーム2:WS2)
10日及び12日に2020年までの野心向上、及びそのためにCOP20決定においてADPに要請された、「技術的検討プロセス」の推進に関する議論が行われた。
先進国及び途上国の両方からWS2の取組の重要性が述べられた。途上国からは、改正京都議定書の批准が進んでいないこと、支援の提供についてギャップがあること、先進国の削減目標の野心が不足していることなどの主張があった。先進国からは、WS2における昨年からの成果を強調するとともに、先進国及び途上国の双方が着実に2020年までの取組を進めつつ、技術的検討プロセスを着実に実施していくことが重要であること、野心向上に向けては既存の仕組みを活用が重要であること、資金に関しては民間資金の活用が重要であるとの主張がなされた。
また、「技術的検討プロセス」については、主に、①削減効果の高い取組を実施に移すために「技術的検討プロセス」はどう貢献できるか、②これまでの経験に基づき、2015 年の「技術的検討プロセス」の活動をどう強化するか、③国以外のアクターの活動に関する情報共有をどう促進すべきかについて、国際機関からの発表と締約国との議論が行われた。
さらに、今後の技術専門家会合(TEM)の具体的なテーマ等について議論が行われた。会合の最終日に事務局から本会合の概要が発表され、今回の会合を受けて今後の計画が4月までに発表される予定。
3.他国やステークホルダー等との対話
様々な交渉グループに属する国々と緊密な意見交換を行うとともに、国内外のNGOとの意見交換、邦人記者に対するブリーフを行った。
4.今後のADP交渉予定
次回会合は6月1日~11日にドイツ・ボンにおいて開催される予定。また、通常の6月、12月に加えて、8月31日~9月4日及び10月19日~10月23日の2回のADP追加会合の開催が決定した。
2015年01月01日
RCPシナリオについて
RCP(代表的濃度経路)シナリオ
政策的な温室効果ガスの緩和策を前提として、将来の温室効果ガス安定化レベルとそこに至るまでの経路のうち代表的なもの(代表的濃度経路)を選び作成したシナリオ
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書から、このシナリオ区分に基づいた気候の予測や影響評価が行われるようになった
従来のSRESシナリオに基づいた予測と違い、目標主導型の社会経済シナリオを複数作成して検討することが可能
RCPに続く数値は、2100 年における1750 年に対するおおよその合計放射強制力(単位:W/m2)を示し、大きいほど2100 年における放射強制力が大きい
※SRESシナリオ:IPCCが2000 年に発表した「排出シナリオに関する特別報告書(SRES : SpecialReport on Emission Scenarios) 」の中で定めたシナリオ。様々な将来の社会変化を想定し、それぞれの想定(シナリオ)に応じた将来の温室効果ガス排出量を推計した。
※放射強制力:ある因子が持つ、地球-大気システムに出入りするエネルギーのバランスを変化させる影響力の尺度であり、潜在的な気候変動メカニズムとしてのその因子の重要性の指標である。正の放射強制力には地表面を昇温させる傾向が、負の放射強制力には地表面を降温させる傾向がある。
(IPCC第4次報告書第一作業部会政策決定者向け要約より)
文部科学省・経済産業省・気象庁・環境省2013年9月27日報道発表資料をもとに作成


政策的な温室効果ガスの緩和策を前提として、将来の温室効果ガス安定化レベルとそこに至るまでの経路のうち代表的なもの(代表的濃度経路)を選び作成したシナリオ
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書から、このシナリオ区分に基づいた気候の予測や影響評価が行われるようになった
従来のSRESシナリオに基づいた予測と違い、目標主導型の社会経済シナリオを複数作成して検討することが可能
RCPに続く数値は、2100 年における1750 年に対するおおよその合計放射強制力(単位:W/m2)を示し、大きいほど2100 年における放射強制力が大きい
※SRESシナリオ:IPCCが2000 年に発表した「排出シナリオに関する特別報告書(SRES : SpecialReport on Emission Scenarios) 」の中で定めたシナリオ。様々な将来の社会変化を想定し、それぞれの想定(シナリオ)に応じた将来の温室効果ガス排出量を推計した。
※放射強制力:ある因子が持つ、地球-大気システムに出入りするエネルギーのバランスを変化させる影響力の尺度であり、潜在的な気候変動メカニズムとしてのその因子の重要性の指標である。正の放射強制力には地表面を昇温させる傾向が、負の放射強制力には地表面を降温させる傾向がある。
(IPCC第4次報告書第一作業部会政策決定者向け要約より)
文部科学省・経済産業省・気象庁・環境省2013年9月27日報道発表資料をもとに作成


2014年12月25日
PM2.5に関する「注意喚起のための暫定的な指針」(第2次)
微小粒子状物質(PM2.5)に関する「注意喚起のための暫定的な指針」に係る判断方法の改善について(第2次)平成26年11 月28 日
(1)午前中の早めの時間での判断について
午前中の早めの時間での判断については、「日平均値70μg/m3 に対応する1時間値は85μg/m3 として、複数の測定局を対象とした複数時間の平均値について同一区域内の中央値を求めて判断することが適当」
(2)午後からの活動に備えた判断について
午後からの活動に備えた判断については、「当日午前5時から12 時までの1時間値の平均値が80μg/m3 を超えた場合に注意喚起を実施する。」、「同一区域内の測定局データの中央値で判断するのではなく、最大値を用いて判断することとする。」
(3)注意喚起の解除について
「注意喚起を実施した区域内にある
判断基準値を超過した全ての一般環境大気測定局において、PM2.5 濃度の1時間値が2時間連続して50μg/m3 以下に改善した場合は、当該局及び近隣局の濃度推移傾向も考慮しつつ注意喚起の解除を判断する」ことが適当である。
(1)午前中の早めの時間での判断について
午前中の早めの時間での判断については、「日平均値70μg/m3 に対応する1時間値は85μg/m3 として、複数の測定局を対象とした複数時間の平均値について同一区域内の中央値を求めて判断することが適当」
(2)午後からの活動に備えた判断について
午後からの活動に備えた判断については、「当日午前5時から12 時までの1時間値の平均値が80μg/m3 を超えた場合に注意喚起を実施する。」、「同一区域内の測定局データの中央値で判断するのではなく、最大値を用いて判断することとする。」
(3)注意喚起の解除について
「注意喚起を実施した区域内にある
判断基準値を超過した全ての一般環境大気測定局において、PM2.5 濃度の1時間値が2時間連続して50μg/m3 以下に改善した場合は、当該局及び近隣局の濃度推移傾向も考慮しつつ注意喚起の解除を判断する」ことが適当である。
2014年12月12日
温暖化対策会議 再生エネで削減しよう
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014121202000175.html
東京新聞 2014年12月12日
ペルーで開催中の気候変動枠組み条約第二十回締約国会議(COP20)も大詰めだ。米中が存在感を示す中、日本は「原発を動かせないから」と温室効果ガス削減目標を示せないままなのか。
COP20は地球の未来にとって重要な節目になる。京都議定書第二約束期間の後、二〇二〇年以降の新たな温室効果ガス削減ルールづくりの成否を占う会議である。
そのCOP20の序盤早々、日本は国際NGOが、交渉に後ろ向きな国に対して皮肉を込めて贈呈する「化石賞」を贈られた。
昨年までの交渉で、以下のことが決まっている。
来年末、パリで開くCOP21で、新たな約束を結ぶ。先進国だけに義務を課してきた京都議定書とは違い、途上国も何らかの形で削減に参加する。国別に削減枠を割り当てず、それぞれの国が実現可能な自主目標を国連に登録し、達成状況を確認し合う。可能なら来年三月(無理なら五月)までに自主目標を提示する-。
各国が示すべき自主目標をできるだけ底上げするのが、COP20の最も大きな使命である。
ポスト京都の約束は、本来〇九年のコペンハーゲン会議(COP15)で決めることになっていた。欧州連合(EU)として、パリ会議の失敗は許されない。
EUは三〇年に一九九〇年比40%減という目標をすでに掲げて、会議をリードする。温室効果ガス排出世界一位の中国と二位の米国も、開幕直前に自主目標を世界に示し、九日からの閣僚級会合でも、積極姿勢をアピールするのに余念がない。
日本はといえば、原発の稼働状況が見えないうちは、自主目標は決められないというばかり。すでに“周回遅れ”の感がある。日本は排出量世界五位だが、国民一人当たりでは中国より多くなる。
EUなどは、風力など再生可能エネルギーの拡充を、削減の柱に据えている。原発頼みは言い訳として通らない。
閣僚級会合には、望月義夫環境相が、選挙を押して参加した。
日本には、途上国が温暖化の悪影響に対応する資金の提供と引き換えのように、削減目標提示の猶予を請うのではなく、再生エネルギーを活用した前向きな提案を最後まで望みたい。
せめて目標提示の時期ぐらい表明しておかないと、化石賞の返上どころか、“世界”から、ますます置いてきぼりにされていく。日本に不利なルールができていく。
2014年07月16日
WGRI5及びSBSTTA18
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18344
平成26年7月3日
生物多様性条約の実施に関する第5回作業部会(WGRI5)及び第18回科学技術助言補助機関会合(SBSTTA18)の開催結果について(お知らせ)
生物多様性条約第12回締約国会議(COP12)の各議題について検討を行う条約実施に関する第5回作業部会(WGRI5)及び第18回科学技術助言補助機関会合(SBSTTA18)が、それぞれ6月16日(月)~20日(金)及び6月23日(月)~28日(土)に、モントリオール(カナダ)で開催されました。会合では、資源動員戦略、条約プロセスの効率性、地球規模生物多様性概況第4版、海洋・沿岸の生物多様性、侵略的外来種、合成生物学等、広範な議題について議論され、合計23本の勧告が採択されました。これらの勧告は、COP12で検討される予定です。
1.第5回条約実施に関する作業部会(WGRI5)の概要
会議名称
日本語:第5回条約実施に関する作業部会(WGRI5)
英 語:The fifth meeting of the Ad-Hoc Open-ended Working Group on Review of Implementation of the Convention
開催期間:平成26年6月16日(月)~20日(金)
場所:モントリオール(カナダ)
会議の概要:
本会合では、締約国代表の他、国際機関、NGO等約300名の参加により、合計12本の勧告案が政策的観点から検討され、採択されました(一部留保が付いたものも含む)。主要な議題の概要は下記の通りです。
(1)生物多様性国家戦略の改訂・実施状況レビュー
生物多様性日本基金を通じた我が国の生物多様性国家戦略改定等への支援に対し、多くの国から謝意や賛辞が表明されました。生物多様性国家戦略の改訂や国別報告書を提出していない国に対して早期提出を強く促し、全ての締約国に対して国家戦略の実施を強化することを求めるCOP12への勧告が採択されました。
(2)条約及び戦略計画2011-2020の実施に関する実施状況評価
能力養成、科学技術協力及びクリアリングハウスメカニズムについて、それぞれ進捗状況が評価され、今後の展開について議論されました。科学技術協力、能力養成及び技術移転を含む戦略計画の実施及び愛知目標の達成に向けた主要なCOP12の決定については、「ピョンチャンロードマップ2020」としてとりまとめられることとなっています。このうち科学技術協力については、韓国政府のイニシアティブにより新たな枠組みの立ち上げが検討されており、科学技術協力の強化に向けた締約国間の情報共有や協力の実施等を求めるCOP12への勧告が採択されました。
(3)資源動員戦略
COP11で採択された暫定報告枠組みを使った各国の資源動員状況報告等に基づき、資源動員目標等について議論されました。資源動員に関する最終目標については、生物多様性に関する国際的な資金フローを2015年までに倍にして2020年まで維持する目標、COP13における目標の見直し、条約実施のニーズと必要な資金に関するギャップを著しく減少させるための国内の資源動員目標等が議論され、COP12への勧告の主要部分は合意に至らないまま留保付きで採択され、COP12に議論が持ち越されました。
(4)貧困削減及び持続可能な開発のための生物多様性
貧困削減や開発への生物多様性の統合に関して締約国に行動を求めるとともに、持続可能な開発目標及びポスト2015年国連開発アジェンダについて締約国が戦略計画2011-2020及び愛知目標を適切に反映する必要性を強調し、事務局長に対して関係機関や締約国等と協力してその適切な反映を支援し、結果をCOP13で報告するよう求めるCOPへの勧告が採択された。また、同議題に関連するイニシアティブとして、SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップが勧告に盛り込まれました。
(5)条約プロセスの効率性
条約の効率的な運用方法について議論が行われ、WGRIを補助機関会合とすること、COPとカルタヘナ及び名古屋議定書の締約国会議を同時開催すること、生物多様性国家戦略の査読を試行的に実施することについて決定することや、締約国会議の度に各締約国が国家戦略の実施状況等について報告することを求めるCOP12への勧告が決定されました。
【本会合の公式ウェブサイト】 http://www.cbd.int/wgri5/
2.第18回科学技術助言補助機関会合(SBSTTA18)の概要
会議名称
日本語:第18回科学技術助言補助機関会合(SBSTTA18)
英 語:The eighteenth meeting of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice
開催期間:平成26年6月23日(月)~28日(土)
開催地:モントリオール(カナダ)
会議の概要:
本会合では、締約国代表の他、国際機関、NGO等約500名の参加により、合計11本の勧告案が科学技術的観点から検討され、採択されました(一部留保が付いたものも含む)。主要な議題の概要は下記の通りです。
(1)地球規模生物多様性概況第4版
地球規模生物多様性概況第4版は、各愛知目標の達成状況に関する科学的分析や、各締約国からの国別報告書や生物多様性国家戦略等に基づき、戦略計画2011-2020及び愛知目標の達成状況及び今後の達成見込みついてとりまとめるものです。本会合では、報告書案について議論が行われ、今後の査読過程を踏まえてCOP12までに報告書及び関連文書を完成させること、戦略計画実施及び愛知目標達成に向けて必要な主要な行動リストを作成することを事務局に求め、COP12に対して、同報告書を歓迎し、事務局及び各締約国が主流化に努め、主要な行動リストの活用を奨励する勧告が採択されました。なお、同勧告に含まれた本報告書の主要な結論は下記の通りです。
○ほとんどの愛知目標について施策の進展があった一方、現状では目標達成には不十分で、目標達成のためには緊急かつ追加的な対策が必要。
○愛知目標の達成は貧困削減や持続可能な開発に大きく貢献する。
○愛知目標達成に向けた行動としては、生物多様性損失の根本原因に対処する主流化施策の実施、生物多様性国家戦略の策定・実施、情報共有や資源動員等が効果的。
○生物多様性と生態系サービスの価値について社会全体のステークホルダーや政府機関に周知することを通じ、戦略計画実施及び愛知目標達成に向けた支援を拡大することが必要。民間参画や主流化にはパートナーシップが必要。
○科学技術協力、能力養成及び技術移転の推進が必要。
○あらゆるセクターからの資金の著しい増加が求められる。
(2)海洋・沿岸の生物多様性
生態学的及び生物学的に重要な海域の基準に合致する海域の抽出結果について共有され、各国での海域抽出や、関係する科学的知見の活用を各締約国に求め、更なる地域ワークショップの開催を事務局に求めること等を内容とするCOP12への勧告が採択されました。また、水中騒音の生物多様性への影響軽減に向けた措置の実施を各締約国に促すことや、海ゴミの影響や海洋酸性化への対応を求めること等も同勧告に含まれました。
(3)侵略的外来種
ペット・展示生物・生き餌・生食料として導入される侵略的外来種に関係するリスクへの対策に関する自主的ガイダンスの採択とその規制措置等への活用を求めることを内容とするCOP12への勧告が採択されました。同ガイダンスでは、関係機関の役割、リスク評価の実施、リスク軽減に向けた施策の実施、リスク評価や侵略的外来種リストの情報共有等についてとりまとめられています。
(4)合成生物学
合成生物学から生じる構成要素,生物及び産品によって引き起こされる生物多様性等への影響について議論されました。同分野は条約実施に関係する一方、新規事項として優先的な対応をすべきかどうかを決定するためには分析に必要な情報が現在は十分にないと結論づけました。また、事務局による更なる情報収集や専門家会合の開催について要請された一方、生物多様性へのリスク評価や、商業利用時の野外実験や配慮事項等のCOP12への勧告の主要部分については合意に至らないまま留保付きで採択され、多くの事項についてCOP12に議論が持ち越されました。
(5)気候変動と生物多様性
気候変動と生物多様性については、我が国からの提案により、防災・減災に関する国際目標である兵庫行動枠組みに関連し、締約国に対して気候変動への適応及び防災・減災に関する国内施策の実施時に生態系の活用を求めること等を内容とするCOP12への勧告が採択されました。
【本会合の公式ウェブサイト】 http://www.cbd.int/doc/?meeting=SBSTTA-18
平成26年7月3日
生物多様性条約の実施に関する第5回作業部会(WGRI5)及び第18回科学技術助言補助機関会合(SBSTTA18)の開催結果について(お知らせ)
生物多様性条約第12回締約国会議(COP12)の各議題について検討を行う条約実施に関する第5回作業部会(WGRI5)及び第18回科学技術助言補助機関会合(SBSTTA18)が、それぞれ6月16日(月)~20日(金)及び6月23日(月)~28日(土)に、モントリオール(カナダ)で開催されました。会合では、資源動員戦略、条約プロセスの効率性、地球規模生物多様性概況第4版、海洋・沿岸の生物多様性、侵略的外来種、合成生物学等、広範な議題について議論され、合計23本の勧告が採択されました。これらの勧告は、COP12で検討される予定です。
1.第5回条約実施に関する作業部会(WGRI5)の概要
会議名称
日本語:第5回条約実施に関する作業部会(WGRI5)
英 語:The fifth meeting of the Ad-Hoc Open-ended Working Group on Review of Implementation of the Convention
開催期間:平成26年6月16日(月)~20日(金)
場所:モントリオール(カナダ)
会議の概要:
本会合では、締約国代表の他、国際機関、NGO等約300名の参加により、合計12本の勧告案が政策的観点から検討され、採択されました(一部留保が付いたものも含む)。主要な議題の概要は下記の通りです。
(1)生物多様性国家戦略の改訂・実施状況レビュー
生物多様性日本基金を通じた我が国の生物多様性国家戦略改定等への支援に対し、多くの国から謝意や賛辞が表明されました。生物多様性国家戦略の改訂や国別報告書を提出していない国に対して早期提出を強く促し、全ての締約国に対して国家戦略の実施を強化することを求めるCOP12への勧告が採択されました。
(2)条約及び戦略計画2011-2020の実施に関する実施状況評価
能力養成、科学技術協力及びクリアリングハウスメカニズムについて、それぞれ進捗状況が評価され、今後の展開について議論されました。科学技術協力、能力養成及び技術移転を含む戦略計画の実施及び愛知目標の達成に向けた主要なCOP12の決定については、「ピョンチャンロードマップ2020」としてとりまとめられることとなっています。このうち科学技術協力については、韓国政府のイニシアティブにより新たな枠組みの立ち上げが検討されており、科学技術協力の強化に向けた締約国間の情報共有や協力の実施等を求めるCOP12への勧告が採択されました。
(3)資源動員戦略
COP11で採択された暫定報告枠組みを使った各国の資源動員状況報告等に基づき、資源動員目標等について議論されました。資源動員に関する最終目標については、生物多様性に関する国際的な資金フローを2015年までに倍にして2020年まで維持する目標、COP13における目標の見直し、条約実施のニーズと必要な資金に関するギャップを著しく減少させるための国内の資源動員目標等が議論され、COP12への勧告の主要部分は合意に至らないまま留保付きで採択され、COP12に議論が持ち越されました。
(4)貧困削減及び持続可能な開発のための生物多様性
貧困削減や開発への生物多様性の統合に関して締約国に行動を求めるとともに、持続可能な開発目標及びポスト2015年国連開発アジェンダについて締約国が戦略計画2011-2020及び愛知目標を適切に反映する必要性を強調し、事務局長に対して関係機関や締約国等と協力してその適切な反映を支援し、結果をCOP13で報告するよう求めるCOPへの勧告が採択された。また、同議題に関連するイニシアティブとして、SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップが勧告に盛り込まれました。
(5)条約プロセスの効率性
条約の効率的な運用方法について議論が行われ、WGRIを補助機関会合とすること、COPとカルタヘナ及び名古屋議定書の締約国会議を同時開催すること、生物多様性国家戦略の査読を試行的に実施することについて決定することや、締約国会議の度に各締約国が国家戦略の実施状況等について報告することを求めるCOP12への勧告が決定されました。
【本会合の公式ウェブサイト】 http://www.cbd.int/wgri5/
2.第18回科学技術助言補助機関会合(SBSTTA18)の概要
会議名称
日本語:第18回科学技術助言補助機関会合(SBSTTA18)
英 語:The eighteenth meeting of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice
開催期間:平成26年6月23日(月)~28日(土)
開催地:モントリオール(カナダ)
会議の概要:
本会合では、締約国代表の他、国際機関、NGO等約500名の参加により、合計11本の勧告案が科学技術的観点から検討され、採択されました(一部留保が付いたものも含む)。主要な議題の概要は下記の通りです。
(1)地球規模生物多様性概況第4版
地球規模生物多様性概況第4版は、各愛知目標の達成状況に関する科学的分析や、各締約国からの国別報告書や生物多様性国家戦略等に基づき、戦略計画2011-2020及び愛知目標の達成状況及び今後の達成見込みついてとりまとめるものです。本会合では、報告書案について議論が行われ、今後の査読過程を踏まえてCOP12までに報告書及び関連文書を完成させること、戦略計画実施及び愛知目標達成に向けて必要な主要な行動リストを作成することを事務局に求め、COP12に対して、同報告書を歓迎し、事務局及び各締約国が主流化に努め、主要な行動リストの活用を奨励する勧告が採択されました。なお、同勧告に含まれた本報告書の主要な結論は下記の通りです。
○ほとんどの愛知目標について施策の進展があった一方、現状では目標達成には不十分で、目標達成のためには緊急かつ追加的な対策が必要。
○愛知目標の達成は貧困削減や持続可能な開発に大きく貢献する。
○愛知目標達成に向けた行動としては、生物多様性損失の根本原因に対処する主流化施策の実施、生物多様性国家戦略の策定・実施、情報共有や資源動員等が効果的。
○生物多様性と生態系サービスの価値について社会全体のステークホルダーや政府機関に周知することを通じ、戦略計画実施及び愛知目標達成に向けた支援を拡大することが必要。民間参画や主流化にはパートナーシップが必要。
○科学技術協力、能力養成及び技術移転の推進が必要。
○あらゆるセクターからの資金の著しい増加が求められる。
(2)海洋・沿岸の生物多様性
生態学的及び生物学的に重要な海域の基準に合致する海域の抽出結果について共有され、各国での海域抽出や、関係する科学的知見の活用を各締約国に求め、更なる地域ワークショップの開催を事務局に求めること等を内容とするCOP12への勧告が採択されました。また、水中騒音の生物多様性への影響軽減に向けた措置の実施を各締約国に促すことや、海ゴミの影響や海洋酸性化への対応を求めること等も同勧告に含まれました。
(3)侵略的外来種
ペット・展示生物・生き餌・生食料として導入される侵略的外来種に関係するリスクへの対策に関する自主的ガイダンスの採択とその規制措置等への活用を求めることを内容とするCOP12への勧告が採択されました。同ガイダンスでは、関係機関の役割、リスク評価の実施、リスク軽減に向けた施策の実施、リスク評価や侵略的外来種リストの情報共有等についてとりまとめられています。
(4)合成生物学
合成生物学から生じる構成要素,生物及び産品によって引き起こされる生物多様性等への影響について議論されました。同分野は条約実施に関係する一方、新規事項として優先的な対応をすべきかどうかを決定するためには分析に必要な情報が現在は十分にないと結論づけました。また、事務局による更なる情報収集や専門家会合の開催について要請された一方、生物多様性へのリスク評価や、商業利用時の野外実験や配慮事項等のCOP12への勧告の主要部分については合意に至らないまま留保付きで採択され、多くの事項についてCOP12に議論が持ち越されました。
(5)気候変動と生物多様性
気候変動と生物多様性については、我が国からの提案により、防災・減災に関する国際目標である兵庫行動枠組みに関連し、締約国に対して気候変動への適応及び防災・減災に関する国内施策の実施時に生態系の活用を求めること等を内容とするCOP12への勧告が採択されました。
【本会合の公式ウェブサイト】 http://www.cbd.int/doc/?meeting=SBSTTA-18
2014年07月16日
京都議定書目標達成計画の進捗状況について(お知らせ)
平成26年7月3日
京都議定書目標達成計画の進捗状況について(お知らせ)
7月1日に、「地球温暖化対策推進本部」を持ち回りにより開催し、「京都議定書目標達成計画の進捗状況」の点検を行いました。
1.今回の点検について
「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)に基づく「京都議定書目標達成計画」(平成20年3月28日閣議決定)については、「地球温暖化対策推進本部」(本部長:内閣総理大臣)において、同計画に盛り込まれた個々の対策について政府が講じた施策の進捗状況等の点検を行うこととされています。
これを受けて、7月1日に、地球温暖化対策推進本部を持ち回りにより開催し、「京都議定書目標達成計画の進捗状況」の点検を行いました。
今回の点検に当たっては、目標達成計画に掲げられた各対策・施策の排出削減量及び対策評価指標について、原則として2000年度から2012年度までの実績の把握を行うとともに、計画策定時の見込みに照らした実績のトレンド等を評価し、対策・施策の追加・強化等の状況を把握しました。
2.対策の進捗状況
188件の対策のうち、見込みに照らした実績のトレンド等は以下のとおりでした。
[1] 目標達成又は実績のトレンドが見込みを上回っている 108件
[2] 実績のトレンドが概ね見込みどおり 11件
[3] 実績のトレンドが計画策定時の見込みと比べて低い 51件
[4] その他(定量的なデータが得られないものなど) 18件
3.京都議定書第一約束期間の達成状況
2008年度から2012年度の京都議定書第一約束期間中の5カ年平均の総排出量は、12億7,800万トンであり、基準年度比で1.4%の増加となりましたが、これに森林等吸収源及び京都メカニズムクレジットを加味すると、5カ年平均で基準年比8.4%減となり、我が国は京都議定書の目標(基準年比6%減)を達成することとなります。
4.今後について
今回の点検において、見込みと実績のトレンドに大きな乖離が生じている対策や実績が見込みを下回っている対策については、計画策定時からの状況変化も影響を与えていると考えられるものの、今後の地球温暖化対策を考える際には、京都議定書目標達成計画の実施及び進捗点検を通じて得られた知見を十分に活用しながら、対策自体の在り方や、活動量の変化が対策量や削減量に与える影響の精査、削減をより確実なものとする施策の在り方についても検討が必要です。また、各対策・施策で、実績データが入手できていないものや、実績値の把握が遅いものについては実績データの入手ができた段階で、公表を行うこととします。
新たな地球温暖化対策計画の策定に至るまでの間については、平成25年3月15日に決定した「当面の地球温暖化対策に関する方針」に基づき、地方公共団体、事業者及び国民には、それぞれの取組状況を踏まえ、京都議定書目標達成計画に掲げられたものと同等以上の取組を推進することを求めることとし、政府は、地方公共団体、事業者及び国民による取組を引き続き支援することで取組の加速を図ることとしています。また、政府は、新たな地球温暖化対策計画に即した新たな政府実行計画の策定に至るまでの間においても、従前の政府実行計画に掲げられたものと同等以上の取組を推進することとしています。
(参考)地球温暖化対策推進本部の構成
本部長 :内閣総理大臣
副本部長:内閣官房長官、環境大臣、経済産業大臣
本部員 :他のすべての国務大臣
※対策・施策ごとの個票については、地球温暖化対策推進本部のウェブサイトを参照ください。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ondanka/index.html
添付資料
京都議定書目標達成計画の進捗状況[PDF 422.2 KB]
京都議定書目標達成計画の進捗状況について(お知らせ)
7月1日に、「地球温暖化対策推進本部」を持ち回りにより開催し、「京都議定書目標達成計画の進捗状況」の点検を行いました。
1.今回の点検について
「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)に基づく「京都議定書目標達成計画」(平成20年3月28日閣議決定)については、「地球温暖化対策推進本部」(本部長:内閣総理大臣)において、同計画に盛り込まれた個々の対策について政府が講じた施策の進捗状況等の点検を行うこととされています。
これを受けて、7月1日に、地球温暖化対策推進本部を持ち回りにより開催し、「京都議定書目標達成計画の進捗状況」の点検を行いました。
今回の点検に当たっては、目標達成計画に掲げられた各対策・施策の排出削減量及び対策評価指標について、原則として2000年度から2012年度までの実績の把握を行うとともに、計画策定時の見込みに照らした実績のトレンド等を評価し、対策・施策の追加・強化等の状況を把握しました。
2.対策の進捗状況
188件の対策のうち、見込みに照らした実績のトレンド等は以下のとおりでした。
[1] 目標達成又は実績のトレンドが見込みを上回っている 108件
[2] 実績のトレンドが概ね見込みどおり 11件
[3] 実績のトレンドが計画策定時の見込みと比べて低い 51件
[4] その他(定量的なデータが得られないものなど) 18件
3.京都議定書第一約束期間の達成状況
2008年度から2012年度の京都議定書第一約束期間中の5カ年平均の総排出量は、12億7,800万トンであり、基準年度比で1.4%の増加となりましたが、これに森林等吸収源及び京都メカニズムクレジットを加味すると、5カ年平均で基準年比8.4%減となり、我が国は京都議定書の目標(基準年比6%減)を達成することとなります。
4.今後について
今回の点検において、見込みと実績のトレンドに大きな乖離が生じている対策や実績が見込みを下回っている対策については、計画策定時からの状況変化も影響を与えていると考えられるものの、今後の地球温暖化対策を考える際には、京都議定書目標達成計画の実施及び進捗点検を通じて得られた知見を十分に活用しながら、対策自体の在り方や、活動量の変化が対策量や削減量に与える影響の精査、削減をより確実なものとする施策の在り方についても検討が必要です。また、各対策・施策で、実績データが入手できていないものや、実績値の把握が遅いものについては実績データの入手ができた段階で、公表を行うこととします。
新たな地球温暖化対策計画の策定に至るまでの間については、平成25年3月15日に決定した「当面の地球温暖化対策に関する方針」に基づき、地方公共団体、事業者及び国民には、それぞれの取組状況を踏まえ、京都議定書目標達成計画に掲げられたものと同等以上の取組を推進することを求めることとし、政府は、地方公共団体、事業者及び国民による取組を引き続き支援することで取組の加速を図ることとしています。また、政府は、新たな地球温暖化対策計画に即した新たな政府実行計画の策定に至るまでの間においても、従前の政府実行計画に掲げられたものと同等以上の取組を推進することとしています。
(参考)地球温暖化対策推進本部の構成
本部長 :内閣総理大臣
副本部長:内閣官房長官、環境大臣、経済産業大臣
本部員 :他のすべての国務大臣
※対策・施策ごとの個票については、地球温暖化対策推進本部のウェブサイトを参照ください。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ondanka/index.html
添付資料
京都議定書目標達成計画の進捗状況[PDF 422.2 KB]
2014年05月26日
湿地が有する経済的な価値の評価結果について
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18162
平成26年5月23日
1.背景・経緯
・2010年に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で、TEEB(生態系と生物多様性の経済学)の最終報告書が公表されるなど、生物多様性や生態系サービスの価値を経済的に評価することの重要性が注目されている。
・様々な主体が生物多様性及び生態系サービスの価値を認識し、その保全や利用に際して適切な意思決定が行われることを促進するため、環境省においても経済価値評価の検討を進めている。
・平成25年度には、我が国の生態系の中でも特に近年の損失が大きい生態系である湿地について、経済的な価値の評価を実施した。
2.評価の対象
湿地タイプ 面積
湿原:110,325ha
干潟:49,165ha
※湿原及び干潟の定義、面積は環境省自然環境保全基礎調査による。
3.評価方法
・湿原及び干潟が有する生態系サービスを整理し、既存の調査研究事例等を用いて経済価値評価が可能な生態系サービスのみを評価した。
・これまでに全国レベルで定量的な評価が行われている生態系サービスについては、適切な代替財(ダム、水質浄化施設にかかる費用等)を用いて貨幣換算を行った。
・定量的な評価が一部地域でしか行われていない場合には、その値を全国に適用して評価額を計算した。
・評価額は湿原及び干潟が年間に生み出す生態系サービス(フロー)の価値として算出した。
・経済価値の評価が困難な生態系サービスについては、生態系サービスの内容と経済評価にあたっての課題を整理した。
4.評価結果
・湿原及び干潟が有する生態系サービスのうち、今回、経済価値の評価を行ったものは以下のとおり。
■湿原の生態系サービスの経済価値評価結果
◎生態系サービス 評価額(/年) 原単位(/ha/年)
●調整サービス
・気候調整 (二酸化炭素の吸収) 約31億円 〔高層湿原〕約1.4万円 〔中間湿原〕約2.2万円 〔低層湿原〕約3.1万円
・気候調整 (炭素蓄積) 約986億円―約1,418億円 〔高層湿原〕約250万円 〔中間湿原〕約154万円―約177万円 〔低層湿原〕約58万円―約105万円
・水量調整 約645億円 約59万円
・水質浄化 (窒素の吸収) 約3,779億円 約343万円
●生息・生育地サービス
・生息・生育環境の提供 約1,800億円 約163万円
●文化的サービス
・自然景観の保全 約1,044億円 約95万円
・レクリエーションや環境教育 約106億円―約994億円 約9.6万円― 約90万円
■干潟の生態系サービスの経済価値試算結果
◎生態系サービス 評価額(/年) 原単位(/ha/年)
●供給サービス
・食料 約907億円 約185万円
●調整サービス
・水質浄化 約2,963億円 約603万円
●生息・生育地サービス
・生息・生育環境の提供 約2,188億円 約445万円
●文化的サービス
・レクリエーションや環境教育 約45億円 約9.1万円
平成26年5月23日
1.背景・経緯
・2010年に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で、TEEB(生態系と生物多様性の経済学)の最終報告書が公表されるなど、生物多様性や生態系サービスの価値を経済的に評価することの重要性が注目されている。
・様々な主体が生物多様性及び生態系サービスの価値を認識し、その保全や利用に際して適切な意思決定が行われることを促進するため、環境省においても経済価値評価の検討を進めている。
・平成25年度には、我が国の生態系の中でも特に近年の損失が大きい生態系である湿地について、経済的な価値の評価を実施した。
2.評価の対象
湿地タイプ 面積
湿原:110,325ha
干潟:49,165ha
※湿原及び干潟の定義、面積は環境省自然環境保全基礎調査による。
3.評価方法
・湿原及び干潟が有する生態系サービスを整理し、既存の調査研究事例等を用いて経済価値評価が可能な生態系サービスのみを評価した。
・これまでに全国レベルで定量的な評価が行われている生態系サービスについては、適切な代替財(ダム、水質浄化施設にかかる費用等)を用いて貨幣換算を行った。
・定量的な評価が一部地域でしか行われていない場合には、その値を全国に適用して評価額を計算した。
・評価額は湿原及び干潟が年間に生み出す生態系サービス(フロー)の価値として算出した。
・経済価値の評価が困難な生態系サービスについては、生態系サービスの内容と経済評価にあたっての課題を整理した。
4.評価結果
・湿原及び干潟が有する生態系サービスのうち、今回、経済価値の評価を行ったものは以下のとおり。
■湿原の生態系サービスの経済価値評価結果
◎生態系サービス 評価額(/年) 原単位(/ha/年)
●調整サービス
・気候調整 (二酸化炭素の吸収) 約31億円 〔高層湿原〕約1.4万円 〔中間湿原〕約2.2万円 〔低層湿原〕約3.1万円
・気候調整 (炭素蓄積) 約986億円―約1,418億円 〔高層湿原〕約250万円 〔中間湿原〕約154万円―約177万円 〔低層湿原〕約58万円―約105万円
・水量調整 約645億円 約59万円
・水質浄化 (窒素の吸収) 約3,779億円 約343万円
●生息・生育地サービス
・生息・生育環境の提供 約1,800億円 約163万円
●文化的サービス
・自然景観の保全 約1,044億円 約95万円
・レクリエーションや環境教育 約106億円―約994億円 約9.6万円― 約90万円
■干潟の生態系サービスの経済価値試算結果
◎生態系サービス 評価額(/年) 原単位(/ha/年)
●供給サービス
・食料 約907億円 約185万円
●調整サービス
・水質浄化 約2,963億円 約603万円
●生息・生育地サービス
・生息・生育環境の提供 約2,188億円 約445万円
●文化的サービス
・レクリエーションや環境教育 約45億円 約9.1万円
2014年05月19日
生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)推薦地域への勧告について (お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18188
平成26年5月16日
生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)推薦地域への勧告について (お知らせ)
ユネスコが実施する生物圏保存地域*(国内呼称:ユネスコエコパーク)について、我が国から昨年9月に申請を行った「只見」及び「南アルプス」の2件の新規登録案件、並びに既に登録されている「志賀高原」の拡張登録案件に対する、生物圏保存地域国際諮問委員会(ユネスコ事務局長の諮問機関)の勧告内容が今般ユネスコにより公開されましたのでお知らせいたします。
*英名:Biosphere Reserves(BR)
1.勧告の内容
(1) 新規登録案件
○「只見」(福島県) : 「条件付き承認」**
○「南アルプス」(山梨県、長野県、静岡県) : 「承認」
** 条件は、「核心地域」、「緩衝地域」及び「移行地域」の3つの地域のうち「緩衝地域」のゾーニングに関する修正。
(2) 拡張登録案件
○「志賀高原」(群馬県、長野県) : 「承認」
【参考】勧告の区分
・承認(approved) : エコパークとして承認。
・条件付き承認(approved pending) : 追加情報の提出が必要。
・延期(deferred) : 申請書の改定が必要。次回の諮問委員会で審議。
・却下(rejected):エコパークとして相応しくないもの。
(3) ユネスコ加盟国全体での勧告状況
○新規登録
申請件数29件(承認9件、条件付き承認7件、延期12件、却下1件)
○拡張登録
申請件数5件(承認4件、条件付き承認1件)
○詳細は下記のユネスコMAB計画ウェブサイトに掲載
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/SC-14-CONF-226-10_new_BRs_extensions-modifications_en.pdf
2.今後の予定
今後、この勧告を受けて、2014(平成26)年6月10~13日にスウェーデンにて開催されるユネスコMAB計画国際調整理事会において、登録・拡張の可否が審議・決定される予定。
平成26年5月16日
生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)推薦地域への勧告について (お知らせ)
ユネスコが実施する生物圏保存地域*(国内呼称:ユネスコエコパーク)について、我が国から昨年9月に申請を行った「只見」及び「南アルプス」の2件の新規登録案件、並びに既に登録されている「志賀高原」の拡張登録案件に対する、生物圏保存地域国際諮問委員会(ユネスコ事務局長の諮問機関)の勧告内容が今般ユネスコにより公開されましたのでお知らせいたします。
*英名:Biosphere Reserves(BR)
1.勧告の内容
(1) 新規登録案件
○「只見」(福島県) : 「条件付き承認」**
○「南アルプス」(山梨県、長野県、静岡県) : 「承認」
** 条件は、「核心地域」、「緩衝地域」及び「移行地域」の3つの地域のうち「緩衝地域」のゾーニングに関する修正。
(2) 拡張登録案件
○「志賀高原」(群馬県、長野県) : 「承認」
【参考】勧告の区分
・承認(approved) : エコパークとして承認。
・条件付き承認(approved pending) : 追加情報の提出が必要。
・延期(deferred) : 申請書の改定が必要。次回の諮問委員会で審議。
・却下(rejected):エコパークとして相応しくないもの。
(3) ユネスコ加盟国全体での勧告状況
○新規登録
申請件数29件(承認9件、条件付き承認7件、延期12件、却下1件)
○拡張登録
申請件数5件(承認4件、条件付き承認1件)
○詳細は下記のユネスコMAB計画ウェブサイトに掲載
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/SC-14-CONF-226-10_new_BRs_extensions-modifications_en.pdf
2.今後の予定
今後、この勧告を受けて、2014(平成26)年6月10~13日にスウェーデンにて開催されるユネスコMAB計画国際調整理事会において、登録・拡張の可否が審議・決定される予定。
2014年05月09日
2012年度(平成24年度)の温室効果ガス排出量(確定値)
平成26年4月15日
2012年度(平成24年度)の温室効果ガス排出量(確定値)について(お知らせ)
今般、地球温暖化対策の推進に関する法律等に基づき、2012年度(平成24年度)の温室効果ガス排出量(確定値(注1))をとりまとめました。
2012年度の我が国の総排出量(確定値)は、13億4,300万トンで、これは京都議定書の規定による基準年比6.5%増(注2)、前年度比2.8%増となっています。
また、京都議定書第一約束期間(2008~2012年度)の総排出量は5カ年平均で12億7,800万トン(基準年比1.4%増)、目標達成に向けて算入可能な森林等吸収源による吸収量は5カ年平均で4,870万トン(基準年比3.9%)となりました。
この結果、京都メカニズムクレジット(注3)を加味すると、5カ年平均で基準年比8.4%減(注4)となり、京都議定書の目標(基準年比6%減)を達成することとなります。
我が国を含む先進国は、気候変動に関する国際連合枠組条約(以下「条約」という。)第4条及び同京都議定書(以下「京都議定書」という。)第7条に基づき、温室効果ガスの排出量等の目録を作成し、条約事務局に提出することとされています。また、条約の国内措置を定めた地球温暖化対策の推進に関する法律第7条において、政府は、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し、公表することとされています。
これらの規定に基づき、2012年度(平成24年度)の温室効果ガス排出量等を算定した結果、別添のとおりとなりました。
2012年度の我が国の温室効果ガスの総排出量(確定値(注1))は、13億4,300万トンでした。これは、京都議定書の規定による基準年(CO2、CH4、N2Oは1990年度、HFCs、PFCs、SF6は1995年。以下「基準年」という。)の総排出量と比べると、6.5%(8,180万トン)の増加となっています(注2)。
2011年度の総排出量(13億700万トン)と比べると、発電に伴う二酸化炭素排出量が増加したことなどにより、2.8%(3,660万トン)増加しています。その要因としては、製造業の生産量が減少するとともに、家庭部門で節電が更に進む一方で、東日本大震災以降の火力発電の増加によって化石燃料消費量が増加したことなどが挙げられます。
京都議定書第一約束期間(2008~2012年度)の5カ年平均の総排出量は12億7,800万トンで、基準年比1.4%の増加となっています。
また、2012年度の京都議定書に基づく吸収源活動の排出・吸収量は、5,280万トン(森林吸収源対策による吸収量は5,170万トン、都市緑化等による吸収量は110万トン)の吸収となりました。これは、基準年総排出量の4.2%に相当します(うち森林吸収源対策による吸収量は4.1%に相当)。
これにより、第一約束期間の目標達成に向けて算入可能な森林等吸収源による吸収量は、5カ年平均で4,870万トン(森林吸収源対策による吸収量は4,770万トン(注5)、都市緑化等による吸収量は100万トン)となりました。これは基準年総排出量の3.9%に相当します(うち森林吸収源対策による吸収量は3.8%に相当)。
(注1)
確定値の算定について……「確定値」とは、我が国の温室効果ガスの排出量等の目録として条約事務局に正式に提出した値という意味です。今後、各種統計データの年報値の修正、算定方法の見直し等により、今般とりまとめた「確定値」が変更される場合があります。
(注2)
実際の総排出量の基準年比増分について……6.5%増という数値は森林等吸収源や京都メカニズムからのクレジットを含むものではありません。
(注3)
京都メカニズムクレジット……政府取得分(平成25年度末時点での京都メカニズムクレジット取得事業によるクレジットの総取得量(9,749.3万トン))及び民間取得分(電気事業連合会のクレジット量「電気事業における環境行動計画(2013年度版)」)。
(注4)
京都議定書の目標達成に係る最終的な排出量等の確定……最終的な排出量・吸収量は、2014年度に実施される国連気候変動枠組条約及び京都議定書下での審査の結果を踏まえ確定されます。また、京都メカニズムクレジットも、第一約束期間の調整期間終了後に確定する予定です(2015年後半以降の見通し)。
(注5)
森林吸収源対策による吸収量は、5カ年の森林吸収量が我が国に設定されている算入上限値(5カ年で2億3,830万トン)を上回ったため、算入上限値の年平均値。
2012年度(平成24年度)の温室効果ガス排出量(確定値)について(お知らせ)
今般、地球温暖化対策の推進に関する法律等に基づき、2012年度(平成24年度)の温室効果ガス排出量(確定値(注1))をとりまとめました。
2012年度の我が国の総排出量(確定値)は、13億4,300万トンで、これは京都議定書の規定による基準年比6.5%増(注2)、前年度比2.8%増となっています。
また、京都議定書第一約束期間(2008~2012年度)の総排出量は5カ年平均で12億7,800万トン(基準年比1.4%増)、目標達成に向けて算入可能な森林等吸収源による吸収量は5カ年平均で4,870万トン(基準年比3.9%)となりました。
この結果、京都メカニズムクレジット(注3)を加味すると、5カ年平均で基準年比8.4%減(注4)となり、京都議定書の目標(基準年比6%減)を達成することとなります。
我が国を含む先進国は、気候変動に関する国際連合枠組条約(以下「条約」という。)第4条及び同京都議定書(以下「京都議定書」という。)第7条に基づき、温室効果ガスの排出量等の目録を作成し、条約事務局に提出することとされています。また、条約の国内措置を定めた地球温暖化対策の推進に関する法律第7条において、政府は、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し、公表することとされています。
これらの規定に基づき、2012年度(平成24年度)の温室効果ガス排出量等を算定した結果、別添のとおりとなりました。
2012年度の我が国の温室効果ガスの総排出量(確定値(注1))は、13億4,300万トンでした。これは、京都議定書の規定による基準年(CO2、CH4、N2Oは1990年度、HFCs、PFCs、SF6は1995年。以下「基準年」という。)の総排出量と比べると、6.5%(8,180万トン)の増加となっています(注2)。
2011年度の総排出量(13億700万トン)と比べると、発電に伴う二酸化炭素排出量が増加したことなどにより、2.8%(3,660万トン)増加しています。その要因としては、製造業の生産量が減少するとともに、家庭部門で節電が更に進む一方で、東日本大震災以降の火力発電の増加によって化石燃料消費量が増加したことなどが挙げられます。
京都議定書第一約束期間(2008~2012年度)の5カ年平均の総排出量は12億7,800万トンで、基準年比1.4%の増加となっています。
また、2012年度の京都議定書に基づく吸収源活動の排出・吸収量は、5,280万トン(森林吸収源対策による吸収量は5,170万トン、都市緑化等による吸収量は110万トン)の吸収となりました。これは、基準年総排出量の4.2%に相当します(うち森林吸収源対策による吸収量は4.1%に相当)。
これにより、第一約束期間の目標達成に向けて算入可能な森林等吸収源による吸収量は、5カ年平均で4,870万トン(森林吸収源対策による吸収量は4,770万トン(注5)、都市緑化等による吸収量は100万トン)となりました。これは基準年総排出量の3.9%に相当します(うち森林吸収源対策による吸収量は3.8%に相当)。
(注1)
確定値の算定について……「確定値」とは、我が国の温室効果ガスの排出量等の目録として条約事務局に正式に提出した値という意味です。今後、各種統計データの年報値の修正、算定方法の見直し等により、今般とりまとめた「確定値」が変更される場合があります。
(注2)
実際の総排出量の基準年比増分について……6.5%増という数値は森林等吸収源や京都メカニズムからのクレジットを含むものではありません。
(注3)
京都メカニズムクレジット……政府取得分(平成25年度末時点での京都メカニズムクレジット取得事業によるクレジットの総取得量(9,749.3万トン))及び民間取得分(電気事業連合会のクレジット量「電気事業における環境行動計画(2013年度版)」)。
(注4)
京都議定書の目標達成に係る最終的な排出量等の確定……最終的な排出量・吸収量は、2014年度に実施される国連気候変動枠組条約及び京都議定書下での審査の結果を踏まえ確定されます。また、京都メカニズムクレジットも、第一約束期間の調整期間終了後に確定する予定です(2015年後半以降の見通し)。
(注5)
森林吸収源対策による吸収量は、5カ年の森林吸収量が我が国に設定されている算入上限値(5カ年で2億3,830万トン)を上回ったため、算入上限値の年平均値。
2014年04月07日
名古屋議定書に係る国内措置のあり方
Ⅰ 名古屋議定書について
議定書は、遺伝資源の利用から生ずる利益を公正かつ衡平に配分すること(遺伝資源の取得の適当な機会の提供、関連のある技術の適当な移転及び適当な資金供与により配分することを含む。)並びにこれによって生物の多様性の保全及びその構成要素の持続可能な利用に貢献することを目的としている(第1条)。
ABS(遺伝資源の取得の機会の提供や利益の配分(Access and Benefit-Sharing。以下「ABS」という。))について規定している に関しては、条約において、①各国は自国の天然資源に対して主権的権利を有するものと認められ、遺伝資源の取得の機会につき定める権限は、その国の国内法令に従うこと(条約第15 条1)、②遺伝資源の取得の機会が与えられるためには、当該遺伝資源の提供国である締約国が別段の決定を行う場合を除き、当該締約国の事前の情報に基づく同意(以下「PIC」という。)を必要とすること(条約第15 条5)、③遺伝資源の利用から生ずる利益の配分は、相互に合意する条件(以下「MAT」という。)で行うこと(条約第15 条7)が規定されている。
Ⅱ 名古屋議定書の主要規定
1.遺伝資源の提供国としての措置に係る規定(第6条、第7条及び第8条)
① 遺伝資源の取得の機会の提供(第6条)
② 遺伝資源に関連する伝統的な知識の取得の機会の提供(第7条)
③ 特別の考慮事項(第8条)
2.遺伝資源の利用国としての措置に係る規定(第15 条、第16 条及び第17 条)
① ABS 法令等の遵守(第15 条)
② 遺伝資源に関連する伝統的な知識に係るABS 法令等の遵守(第16 条)
③ 遺伝資源の利用の監視(monitoring)(第17 条)
3.遺伝資源の提供国及び利用国の双方としての対応に係る規定
① ABS クリアリングハウス及び情報の共有(第14 条)
締約国は、秘密の情報の保護を妨げることなく、議定書によって必要とされている情報及び締約国会議の決定により必要とされる情報をABS クリアリングハウスに提供することが規定されている(第14 条2)。これらの情報には以下を含むとされている。
ア ABS に関する立法上、行政上及び政策上の措置
イ 国内の中央連絡先及び権限ある当局に関する情報
ウ PIC を与えるとの決定及びMAT の設定を証明するものとして発給された許可証等
② MAT の遵守(第18 条)
締約国は、遺伝資源等の提供者及び利用者に対して、紛争解決を対象とする規定をMATに含めることを奨励すること(第18条1)、MATから生ずる紛争の事案について、自国の法制度の下で訴訟を提起することができることを確保すること(第18条2)が規定されている。
4.用語の定義(第2条)
上記1、2及び3に記述した各条文に基づく措置の対象となる遺伝資源や遺伝資源の利用の定義は以下のように規定されている。
① 遺伝資源(条約第2条の用語の定義を適用)
「遺伝資源」とは、現実の又は潜在的な価値を有する遺伝素材をいう。
「遺伝素材」とは、遺伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物その他に由来する素材をいう。
② 遺伝資源の利用
「遺伝資源の利用」とは、遺伝資源の遺伝的又は生化学的な構成に関する研究及び開発を行うこと(条約第二条に定義するバイオテクノロジーを用いて行うものを含む。)をいう。
Ⅲ 名古屋議定書に対応する国内措置のあり方に係る意見のまとめ
(1)基本的な考え方
① 遺伝資源等の適正な利用の促進への貢献
遵守措置は、提供国のABS 法令等を遵守して取得された遺伝資源等が日本において利用されるようにするための機能をもち、利用者が安心して遺伝資源を利用できることとなり、利用の促進に貢献し、また、利用者による提供国のABS 法令等の遵守のための自主的な取組を後押しするものとなるべきである。
② 国内関係者からの支持及び国際社会への説明責任
遵守措置は、規制的なものとなった場合には国内の学術研究活動や産業活動に負の影響を及ぼす可能性があることを考慮し、日本の利用者が諸外国との競争上不利な立場に置かれる等学術研究活動や産業活動を妨げることのない、遺伝資源の利用を促進するためのものとすべきである。同時に、日本の利用者が提供国からの信頼を得られるものであって、国内にも海外にもその妥当性を説明できるものとなる必要がある。
③ 明確、簡素かつ実際的
遵守措置は、遺伝資源のすべての利用者が対応できるよう、明確かつ確実であって、実施にあたって過度な負担のない簡素なものであり、各々の学術研究分野や産業分野におけるこれまでの利用慣行から可能な限り乖離しない程度に実際的なものとなるべきである。また、施行後一定期間経過後に、運用の実態を踏まえて遵守措置の内容に係る必要な変更を行うことについて検討するべきである。
④ 遺伝資源の国際的な流通への配慮
日本とEU 等の主要先進国等の利用者間での遺伝資源の流通が今後も円滑に行われるよう、日本の遵守措置とそれらの国の遵守措置の可能かつ適切な範囲内でのルールの共通性について、問題点等も考慮した上で検討するべきである。
⑤ 普及啓発と支援措置の重要性
遵守措置を実施する前提として、その普及啓発を行う必要がある。また、学術機関や企業等の遺伝資源等の利用者が円滑に議定書を実施できるように、遵守措置と併せて車の両輪として、政府による利用者に対する支援措置をその周知の上で実施する必要がある。
2014年04月07日
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第38回総会及び第2作業部会第10回会合(平成26年3月25日~29日、於 横浜市)において、IPCC第5次評価報告書第2作業部会報告書の政策決定者向け要約(SPM)が承認・公表されるとともに、第2作業部会報告書の本体が受諾されました。
第2作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)の概要
A. 複雑かつ変化しつつある世界において観測されている影響、脆弱性、適応観測されている影響
ここ数十年、気候変動の影響が全大陸と海洋において、自然生態系及び人間社会に以下のような影響を与えている。気候変動の影響の証拠は、自然生態系に最も強くかつ包括的に現れている。
i)水文システムの変化による、水量や水質の観点からの水資源への影響
ii)陸域、淡水、海洋生物の生息域の変化等
iii)農作物への負の影響が正の影響よりもより一般的
熱波や干ばつ、洪水、台風、山火事等、近年の気象と気候の極端現象による影響は、現在の気候の変動性に対するいくつかの生態系や多くの人間システムの著しい脆弱性や曝露を明らかにしている。
適応経験
・適応は一部の計画に組み込まれつつあり、限定的であるが実施されている適応策がある。例として、アジアにおいては、一部の地域で、適応が、早期警戒システムや統合的水資源管理、アグロフォレストリー、マングローブの植林を通じて促進されている。
・気候変動に関連したリスクへの対応は、気候変動の影響の深刻さや起こる時期の不確かさ、また適応の有効性の制限という不確実性がある中で、変わりつつある世界において意思を決定していくということを含意している。
B. 将来のリスクと適応の機会
複数の分野地域に及ぶ主要リスク
主要なリスクは国連気候変動枠組条約第2 条に記載されるような、「気候システムに対する危険な人為的干渉」による深刻な影響の可能性である。確信度の高い複数の分野や地域に及ぶ主
要なリスクとして、以下の8 つがあげられている。それぞれが1つあるいはそれ以上の「懸念の理由」に寄与している。なお、該当する「懸念の理由」の番号は、本文末尾のボックスの記載に対応している。
i)海面上昇、沿岸での高潮被害などによるリスク[懸念の理由1~5]
高潮、沿岸洪水、海面上昇により、沿岸の低地や小島嶼国において死亡、負傷、健康被害、または生計崩壊が起きるリスクがある。
ii)大都市部への洪水による被害のリスク[懸念の理由2, 3]
いくつかの地域において、洪水によって、大都市部の人々が深刻な健康被害や生計崩壊にあうリスクがある。
iii)極端な気象現象によるインフラ等の機能停止のリスク[懸念の理由2~4]
極端な気象現象が、電気、水供給、医療・緊急サービスなどの、インフラネットワークと重要なサービスの機能停止をもたらすといった、社会システム全体に影響を及ぼすリスクがある。
iv)熱波による、特に都市部の脆弱な層における死亡や疾病のリスク[懸念の理由2, 3]
極端に暑い期間においては、特に脆弱な都市住民や屋外労働者に対する、死亡や健康障害のリスクがある。
v)気温上昇、干ばつ等による食料安全保障が脅かされるリスク[懸念の理由2~4]
気温上昇、干ばつ、洪水、降水量の変動や極端な降水により、特に貧しい人々の食料安全保障が脅かされるとともに、食料システムが崩壊するリスクがある。
vi)水資源不足と農業生産減少による農村部の生計及び所得損失のリスク[懸念の理由2, 3]
飲料水や灌漑用水への不十分なアクセスと農業の生産性の低下により、半乾燥地域において、特に最小限の資本しか持たない農民や牧畜民の生計や収入が失われる可能性がある。
vii)沿岸海域における生計に重要な海洋生態系の損失リスク[懸念の理由1, 2, 4]
特に熱帯と北極圏の漁業コミュニティにおいて、沿岸部の人々の生計を支える海洋・沿岸の生態系と生物多様性、生態系便益・機能・サービスが失われる可能性がある。
viii)陸域及び内水生態系がもたらすサービスの損失リスク[懸念の理由 1, 3, 4]
人々の生計を支える陸域及び内水の生態系と生物多様性、生態系便益・機能・サービスが失われる可能性がある。
・気候変動の速さと大きさを制限することにより、その影響による全般的なリスクを低減できる。
一方、温暖化が大規模になれば、深刻かつ広範で、不可逆的な影響が起る可能性が高まる。
C. 将来のリスクの管理とレジリエンスの構築
効果的な適応のための原則
・適応は、地域や背景が特有であるため、すべての状況にわたって適切なリスク低減のアプローチは存在しない。
・限られた証拠によると、世界全体の適応ニーズと適応のための資金には隔たりがある。世界全体の適応に要する費用を算定する研究には、データや手法、適用範囲が不十分という特徴があり、更なる研究の向上が必要である。
・重要なコベネフィット、相乗効果、トレードオフは緩和と適応の間や異なる適応の反応の中に存在する。相互作用は地域内及び地域をまたいで起こる(確信度は非常に高い)。
気候に対してレジリエントな経路と変革
・経済的、社会的、技術的、政治的決定や行動の変革が、気候に対してレジリエント(強靭)な経路を可能とする。
懸念の理由
人による気候システムへの影響は明らかである。しかし、その影響が国連気候変動枠組条約第2 条にある“危険な人類的干渉”に当たるどうかは、リスク評価と価値判断の両方が必要である。以下の包括的な「懸念の理由(Reasons For Concern)」は、あらゆる分野及び地域にわたる主要なリスクをまとめる枠組みを提供する。懸念の理由は、温暖化や人々、経済、及び生態系にとっての適応の限界の意味するところを解説している。それらは、気候システムに対する危険な人為的干渉を評価するための1 つの出発点を提供する。気温変化については、1986~2005 年平均からの相対的な値として示されている。
(1) 脅威に曝されている独特な生態系や文化等のシステム
深刻な影響のリスクに直面するシステムの数は1℃の気温上昇で増加し、北極海氷システムやサンゴ礁など適応能力が限られている多くの種やシステムは2℃の気温上昇で非常に高いリスクにさらされる。
(2) 極端な気象現象による気候変動関連リスク
熱波、極端な降水、沿岸洪水のような極端現象による気候変動関連リスクは中程度であり(確信度が高い)、1℃の気温上昇で高い状態になる(確信度は中程度)。
(3) 影響の分布
リスクは均一に分布しているわけではなく、どのような発展段階の国であれ、一般的に不利な条件におかれた人々やコミュニティほど多くのリスクを抱えている。特に作物生産への気候変動の影響が地域によって異なるため、リスクは中程度である(確信度は中程度から高い)。地域の作物生産と水の利用性の低下の予測をもとに、不均一な分布による影響から生じるリスクは2℃以上の気温上昇により増大する。(確信度は中程度)
(4) 世界総合的な影響
温暖化の全世界への総合的な影響のリスクは、地球の生物多様性及び世界経済全体への影響についてみると、1~2 ℃の気温上昇ではリスクは中程度である(確信度は中程度)。約3℃またはそれ以上の気温上昇では、生態系由来の財・サービスの損失を伴う広範囲に及ぶ生物多様性の損失が起こり、リスクが高くなる(確信度が高い)。
(5) 大規模な特異現象
温暖化の進行に伴い、いくつかの物理システムあるいは生態系が急激かつ不可逆的な変化のリスクにさらされる可能性がある。リスクは、1~2℃の気温上昇に伴い不均衡に増加し、3℃以上の気温上昇で氷床の消失による大規模で不可逆的な海面上昇の可能性があることから、高くなる。
第5 次評価報告書における可能性と確信度の表現について
IPCC では、評価結果の「可能性」と「確信度」を表す用語を、一貫した基準に基づいて使用し
ている。以下に、第5 次評価報告書で用いる用語を示す。
「可能性」とは、はっきり定義できる事象が起こった、あるいは将来起こることについての確率
的評価である。また、「確信度」とは、モデル、解析あるいはある意見の正しさに関する不確実性
の程度を表す用語であり、証拠(例えばメカニズムの理解、理論、データ、モデル、専門家の判断)
の種類や量、品質及び整合性と、特定の知見に関する文献間の競合の程度等に基づく見解の一致度
に基づいて定性的に表現される。
<可能性の表現>
用語 発生する可能性
ほぼ確実 99%~100%
可能性が極めて高い 95%~100%
可能性が非常に高い 90%~100%
可能性が高い 66%~100%
どちらかと言えば 50%~100%
どちらも同程度 33%~66%
可能性が低い 0%~33%
可能性が非常に低い 0%~10%
可能性が極めて低い 0%~5%
ほぼありえない 0%~1%
<
第2作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)の概要
A. 複雑かつ変化しつつある世界において観測されている影響、脆弱性、適応観測されている影響
ここ数十年、気候変動の影響が全大陸と海洋において、自然生態系及び人間社会に以下のような影響を与えている。気候変動の影響の証拠は、自然生態系に最も強くかつ包括的に現れている。
i)水文システムの変化による、水量や水質の観点からの水資源への影響
ii)陸域、淡水、海洋生物の生息域の変化等
iii)農作物への負の影響が正の影響よりもより一般的
熱波や干ばつ、洪水、台風、山火事等、近年の気象と気候の極端現象による影響は、現在の気候の変動性に対するいくつかの生態系や多くの人間システムの著しい脆弱性や曝露を明らかにしている。
適応経験
・適応は一部の計画に組み込まれつつあり、限定的であるが実施されている適応策がある。例として、アジアにおいては、一部の地域で、適応が、早期警戒システムや統合的水資源管理、アグロフォレストリー、マングローブの植林を通じて促進されている。
・気候変動に関連したリスクへの対応は、気候変動の影響の深刻さや起こる時期の不確かさ、また適応の有効性の制限という不確実性がある中で、変わりつつある世界において意思を決定していくということを含意している。
B. 将来のリスクと適応の機会
複数の分野地域に及ぶ主要リスク
主要なリスクは国連気候変動枠組条約第2 条に記載されるような、「気候システムに対する危険な人為的干渉」による深刻な影響の可能性である。確信度の高い複数の分野や地域に及ぶ主
要なリスクとして、以下の8 つがあげられている。それぞれが1つあるいはそれ以上の「懸念の理由」に寄与している。なお、該当する「懸念の理由」の番号は、本文末尾のボックスの記載に対応している。
i)海面上昇、沿岸での高潮被害などによるリスク[懸念の理由1~5]
高潮、沿岸洪水、海面上昇により、沿岸の低地や小島嶼国において死亡、負傷、健康被害、または生計崩壊が起きるリスクがある。
ii)大都市部への洪水による被害のリスク[懸念の理由2, 3]
いくつかの地域において、洪水によって、大都市部の人々が深刻な健康被害や生計崩壊にあうリスクがある。
iii)極端な気象現象によるインフラ等の機能停止のリスク[懸念の理由2~4]
極端な気象現象が、電気、水供給、医療・緊急サービスなどの、インフラネットワークと重要なサービスの機能停止をもたらすといった、社会システム全体に影響を及ぼすリスクがある。
iv)熱波による、特に都市部の脆弱な層における死亡や疾病のリスク[懸念の理由2, 3]
極端に暑い期間においては、特に脆弱な都市住民や屋外労働者に対する、死亡や健康障害のリスクがある。
v)気温上昇、干ばつ等による食料安全保障が脅かされるリスク[懸念の理由2~4]
気温上昇、干ばつ、洪水、降水量の変動や極端な降水により、特に貧しい人々の食料安全保障が脅かされるとともに、食料システムが崩壊するリスクがある。
vi)水資源不足と農業生産減少による農村部の生計及び所得損失のリスク[懸念の理由2, 3]
飲料水や灌漑用水への不十分なアクセスと農業の生産性の低下により、半乾燥地域において、特に最小限の資本しか持たない農民や牧畜民の生計や収入が失われる可能性がある。
vii)沿岸海域における生計に重要な海洋生態系の損失リスク[懸念の理由1, 2, 4]
特に熱帯と北極圏の漁業コミュニティにおいて、沿岸部の人々の生計を支える海洋・沿岸の生態系と生物多様性、生態系便益・機能・サービスが失われる可能性がある。
viii)陸域及び内水生態系がもたらすサービスの損失リスク[懸念の理由 1, 3, 4]
人々の生計を支える陸域及び内水の生態系と生物多様性、生態系便益・機能・サービスが失われる可能性がある。
・気候変動の速さと大きさを制限することにより、その影響による全般的なリスクを低減できる。
一方、温暖化が大規模になれば、深刻かつ広範で、不可逆的な影響が起る可能性が高まる。
C. 将来のリスクの管理とレジリエンスの構築
効果的な適応のための原則
・適応は、地域や背景が特有であるため、すべての状況にわたって適切なリスク低減のアプローチは存在しない。
・限られた証拠によると、世界全体の適応ニーズと適応のための資金には隔たりがある。世界全体の適応に要する費用を算定する研究には、データや手法、適用範囲が不十分という特徴があり、更なる研究の向上が必要である。
・重要なコベネフィット、相乗効果、トレードオフは緩和と適応の間や異なる適応の反応の中に存在する。相互作用は地域内及び地域をまたいで起こる(確信度は非常に高い)。
気候に対してレジリエントな経路と変革
・経済的、社会的、技術的、政治的決定や行動の変革が、気候に対してレジリエント(強靭)な経路を可能とする。
懸念の理由
人による気候システムへの影響は明らかである。しかし、その影響が国連気候変動枠組条約第2 条にある“危険な人類的干渉”に当たるどうかは、リスク評価と価値判断の両方が必要である。以下の包括的な「懸念の理由(Reasons For Concern)」は、あらゆる分野及び地域にわたる主要なリスクをまとめる枠組みを提供する。懸念の理由は、温暖化や人々、経済、及び生態系にとっての適応の限界の意味するところを解説している。それらは、気候システムに対する危険な人為的干渉を評価するための1 つの出発点を提供する。気温変化については、1986~2005 年平均からの相対的な値として示されている。
(1) 脅威に曝されている独特な生態系や文化等のシステム
深刻な影響のリスクに直面するシステムの数は1℃の気温上昇で増加し、北極海氷システムやサンゴ礁など適応能力が限られている多くの種やシステムは2℃の気温上昇で非常に高いリスクにさらされる。
(2) 極端な気象現象による気候変動関連リスク
熱波、極端な降水、沿岸洪水のような極端現象による気候変動関連リスクは中程度であり(確信度が高い)、1℃の気温上昇で高い状態になる(確信度は中程度)。
(3) 影響の分布
リスクは均一に分布しているわけではなく、どのような発展段階の国であれ、一般的に不利な条件におかれた人々やコミュニティほど多くのリスクを抱えている。特に作物生産への気候変動の影響が地域によって異なるため、リスクは中程度である(確信度は中程度から高い)。地域の作物生産と水の利用性の低下の予測をもとに、不均一な分布による影響から生じるリスクは2℃以上の気温上昇により増大する。(確信度は中程度)
(4) 世界総合的な影響
温暖化の全世界への総合的な影響のリスクは、地球の生物多様性及び世界経済全体への影響についてみると、1~2 ℃の気温上昇ではリスクは中程度である(確信度は中程度)。約3℃またはそれ以上の気温上昇では、生態系由来の財・サービスの損失を伴う広範囲に及ぶ生物多様性の損失が起こり、リスクが高くなる(確信度が高い)。
(5) 大規模な特異現象
温暖化の進行に伴い、いくつかの物理システムあるいは生態系が急激かつ不可逆的な変化のリスクにさらされる可能性がある。リスクは、1~2℃の気温上昇に伴い不均衡に増加し、3℃以上の気温上昇で氷床の消失による大規模で不可逆的な海面上昇の可能性があることから、高くなる。
第5 次評価報告書における可能性と確信度の表現について
IPCC では、評価結果の「可能性」と「確信度」を表す用語を、一貫した基準に基づいて使用し
ている。以下に、第5 次評価報告書で用いる用語を示す。
「可能性」とは、はっきり定義できる事象が起こった、あるいは将来起こることについての確率
的評価である。また、「確信度」とは、モデル、解析あるいはある意見の正しさに関する不確実性
の程度を表す用語であり、証拠(例えばメカニズムの理解、理論、データ、モデル、専門家の判断)
の種類や量、品質及び整合性と、特定の知見に関する文献間の競合の程度等に基づく見解の一致度
に基づいて定性的に表現される。
<可能性の表現>
用語 発生する可能性
ほぼ確実 99%~100%
可能性が極めて高い 95%~100%
可能性が非常に高い 90%~100%
可能性が高い 66%~100%
どちらかと言えば 50%~100%
どちらも同程度 33%~66%
可能性が低い 0%~33%
可能性が非常に低い 0%~10%
可能性が極めて低い 0%~5%
ほぼありえない 0%~1%
<
2014年04月07日
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第38回総会及び第2作業部会第10回会合(平成26年3月25日~29日、於 横浜市)において、IPCC第5次評価報告書第2作業部会報告書の政策決定者向け要約(SPM)が承認・公表されるとともに、第2作業部会報告書の本体が受諾されました。
第2作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)の概要
A. 複雑かつ変化しつつある世界において観測されている影響、脆弱性、適応観測されている影響
ここ数十年、気候変動の影響が全大陸と海洋において、自然生態系及び人間社会に以下のような影響を与えている。気候変動の影響の証拠は、自然生態系に最も強くかつ包括的に現れている。
i)水文システムの変化による、水量や水質の観点からの水資源への影響
ii)陸域、淡水、海洋生物の生息域の変化等
iii)農作物への負の影響が正の影響よりもより一般的
熱波や干ばつ、洪水、台風、山火事等、近年の気象と気候の極端現象による影響は、現在の気候の変動性に対するいくつかの生態系や多くの人間システムの著しい脆弱性や曝露を明らかにしている。
適応経験
・適応は一部の計画に組み込まれつつあり、限定的であるが実施されている適応策がある。例として、アジアにおいては、一部の地域で、適応が、早期警戒システムや統合的水資源管理、アグロフォレストリー、マングローブの植林を通じて促進されている。
・気候変動に関連したリスクへの対応は、気候変動の影響の深刻さや起こる時期の不確かさ、また適応の有効性の制限という不確実性がある中で、変わりつつある世界において意思を決定していくということを含意している。
B. 将来のリスクと適応の機会
複数の分野地域に及ぶ主要リスク
主要なリスクは国連気候変動枠組条約第2 条に記載されるような、「気候システムに対する危険な人為的干渉」による深刻な影響の可能性である。確信度の高い複数の分野や地域に及ぶ主
要なリスクとして、以下の8 つがあげられている。それぞれが1つあるいはそれ以上の「懸念の理由」に寄与している。なお、該当する「懸念の理由」の番号は、本文末尾のボックスの記載に対応している。
i)海面上昇、沿岸での高潮被害などによるリスク[懸念の理由1~5]
高潮、沿岸洪水、海面上昇により、沿岸の低地や小島嶼国において死亡、負傷、健康被害、または生計崩壊が起きるリスクがある。
ii)大都市部への洪水による被害のリスク[懸念の理由2, 3]
いくつかの地域において、洪水によって、大都市部の人々が深刻な健康被害や生計崩壊にあうリスクがある。
iii)極端な気象現象によるインフラ等の機能停止のリスク[懸念の理由2~4]
極端な気象現象が、電気、水供給、医療・緊急サービスなどの、インフラネットワークと重要なサービスの機能停止をもたらすといった、社会システム全体に影響を及ぼすリスクがある。
iv)熱波による、特に都市部の脆弱な層における死亡や疾病のリスク[懸念の理由2, 3]
極端に暑い期間においては、特に脆弱な都市住民や屋外労働者に対する、死亡や健康障害のリスクがある。
v)気温上昇、干ばつ等による食料安全保障が脅かされるリスク[懸念の理由2~4]
気温上昇、干ばつ、洪水、降水量の変動や極端な降水により、特に貧しい人々の食料安全保障が脅かされるとともに、食料システムが崩壊するリスクがある。
vi)水資源不足と農業生産減少による農村部の生計及び所得損失のリスク[懸念の理由2, 3]
飲料水や灌漑用水への不十分なアクセスと農業の生産性の低下により、半乾燥地域において、特に最小限の資本しか持たない農民や牧畜民の生計や収入が失われる可能性がある。
vii)沿岸海域における生計に重要な海洋生態系の損失リスク[懸念の理由1, 2, 4]
特に熱帯と北極圏の漁業コミュニティにおいて、沿岸部の人々の生計を支える海洋・沿岸の生態系と生物多様性、生態系便益・機能・サービスが失われる可能性がある。
viii)陸域及び内水生態系がもたらすサービスの損失リスク[懸念の理由 1, 3, 4]
人々の生計を支える陸域及び内水の生態系と生物多様性、生態系便益・機能・サービスが失われる可能性がある。
・気候変動の速さと大きさを制限することにより、その影響による全般的なリスクを低減できる。
一方、温暖化が大規模になれば、深刻かつ広範で、不可逆的な影響が起る可能性が高まる。
C. 将来のリスクの管理とレジリエンスの構築
効果的な適応のための原則
・適応は、地域や背景が特有であるため、すべての状況にわたって適切なリスク低減のアプローチは存在しない。
・限られた証拠によると、世界全体の適応ニーズと適応のための資金には隔たりがある。世界全体の適応に要する費用を算定する研究には、データや手法、適用範囲が不十分という特徴があり、更なる研究の向上が必要である。
・重要なコベネフィット、相乗効果、トレードオフは緩和と適応の間や異なる適応の反応の中に存在する。相互作用は地域内及び地域をまたいで起こる(確信度は非常に高い)。
気候に対してレジリエントな経路と変革
・経済的、社会的、技術的、政治的決定や行動の変革が、気候に対してレジリエント(強靭)な経路を可能とする。
懸念の理由
人による気候システムへの影響は明らかである。しかし、その影響が国連気候変動枠組条約第2 条にある“危険な人類的干渉”に当たるどうかは、リスク評価と価値判断の両方が必要である。以下の包括的な「懸念の理由(Reasons For Concern)」は、あらゆる分野及び地域にわたる主要なリスクをまとめる枠組みを提供する。懸念の理由は、温暖化や人々、経済、及び生態系にとっての適応の限界の意味するところを解説している。それらは、気候システムに対する危険な人為的干渉を評価するための1 つの出発点を提供する。気温変化については、1986~2005 年平均からの相対的な値として示されている。
(1) 脅威に曝されている独特な生態系や文化等のシステム
深刻な影響のリスクに直面するシステムの数は1℃の気温上昇で増加し、北極海氷システムやサンゴ礁など適応能力が限られている多くの種やシステムは2℃の気温上昇で非常に高いリスクにさらされる。
(2) 極端な気象現象による気候変動関連リスク
熱波、極端な降水、沿岸洪水のような極端現象による気候変動関連リスクは中程度であり(確信度が高い)、1℃の気温上昇で高い状態になる(確信度は中程度)。
(3) 影響の分布
リスクは均一に分布しているわけではなく、どのような発展段階の国であれ、一般的に不利な条件におかれた人々やコミュニティほど多くのリスクを抱えている。特に作物生産への気候変動の影響が地域によって異なるため、リスクは中程度である(確信度は中程度から高い)。地域の作物生産と水の利用性の低下の予測をもとに、不均一な分布による影響から生じるリスクは2℃以上の気温上昇により増大する。(確信度は中程度)
(4) 世界総合的な影響
温暖化の全世界への総合的な影響のリスクは、地球の生物多様性及び世界経済全体への影響についてみると、1~2 ℃の気温上昇ではリスクは中程度である(確信度は中程度)。約3℃またはそれ以上の気温上昇では、生態系由来の財・サービスの損失を伴う広範囲に及ぶ生物多様性の損失が起こり、リスクが高くなる(確信度が高い)。
(5) 大規模な特異現象
温暖化の進行に伴い、いくつかの物理システムあるいは生態系が急激かつ不可逆的な変化のリスクにさらされる可能性がある。リスクは、1~2℃の気温上昇に伴い不均衡に増加し、3℃以上の気温上昇で氷床の消失による大規模で不可逆的な海面上昇の可能性があることから、高くなる。
第5 次評価報告書における可能性と確信度の表現について
IPCC では、評価結果の「可能性」と「確信度」を表す用語を、一貫した基準に基づいて使用し
ている。以下に、第5 次評価報告書で用いる用語を示す。
「可能性」とは、はっきり定義できる事象が起こった、あるいは将来起こることについての確率
的評価である。また、「確信度」とは、モデル、解析あるいはある意見の正しさに関する不確実性
の程度を表す用語であり、証拠(例えばメカニズムの理解、理論、データ、モデル、専門家の判断)
の種類や量、品質及び整合性と、特定の知見に関する文献間の競合の程度等に基づく見解の一致度
に基づいて定性的に表現される。
<可能性の表現>
用語 発生する可能性
ほぼ確実 99%~100%
可能性が極めて高い 95%~100%
可能性が非常に高い 90%~100%
可能性が高い 66%~100%
どちらかと言えば 50%~100%
どちらも同程度 33%~66%
可能性が低い 0%~33%
可能性が非常に低い 0%~10%
可能性が極めて低い 0%~5%
ほぼありえない 0%~1%
<
第2作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)の概要
A. 複雑かつ変化しつつある世界において観測されている影響、脆弱性、適応観測されている影響
ここ数十年、気候変動の影響が全大陸と海洋において、自然生態系及び人間社会に以下のような影響を与えている。気候変動の影響の証拠は、自然生態系に最も強くかつ包括的に現れている。
i)水文システムの変化による、水量や水質の観点からの水資源への影響
ii)陸域、淡水、海洋生物の生息域の変化等
iii)農作物への負の影響が正の影響よりもより一般的
熱波や干ばつ、洪水、台風、山火事等、近年の気象と気候の極端現象による影響は、現在の気候の変動性に対するいくつかの生態系や多くの人間システムの著しい脆弱性や曝露を明らかにしている。
適応経験
・適応は一部の計画に組み込まれつつあり、限定的であるが実施されている適応策がある。例として、アジアにおいては、一部の地域で、適応が、早期警戒システムや統合的水資源管理、アグロフォレストリー、マングローブの植林を通じて促進されている。
・気候変動に関連したリスクへの対応は、気候変動の影響の深刻さや起こる時期の不確かさ、また適応の有効性の制限という不確実性がある中で、変わりつつある世界において意思を決定していくということを含意している。
B. 将来のリスクと適応の機会
複数の分野地域に及ぶ主要リスク
主要なリスクは国連気候変動枠組条約第2 条に記載されるような、「気候システムに対する危険な人為的干渉」による深刻な影響の可能性である。確信度の高い複数の分野や地域に及ぶ主
要なリスクとして、以下の8 つがあげられている。それぞれが1つあるいはそれ以上の「懸念の理由」に寄与している。なお、該当する「懸念の理由」の番号は、本文末尾のボックスの記載に対応している。
i)海面上昇、沿岸での高潮被害などによるリスク[懸念の理由1~5]
高潮、沿岸洪水、海面上昇により、沿岸の低地や小島嶼国において死亡、負傷、健康被害、または生計崩壊が起きるリスクがある。
ii)大都市部への洪水による被害のリスク[懸念の理由2, 3]
いくつかの地域において、洪水によって、大都市部の人々が深刻な健康被害や生計崩壊にあうリスクがある。
iii)極端な気象現象によるインフラ等の機能停止のリスク[懸念の理由2~4]
極端な気象現象が、電気、水供給、医療・緊急サービスなどの、インフラネットワークと重要なサービスの機能停止をもたらすといった、社会システム全体に影響を及ぼすリスクがある。
iv)熱波による、特に都市部の脆弱な層における死亡や疾病のリスク[懸念の理由2, 3]
極端に暑い期間においては、特に脆弱な都市住民や屋外労働者に対する、死亡や健康障害のリスクがある。
v)気温上昇、干ばつ等による食料安全保障が脅かされるリスク[懸念の理由2~4]
気温上昇、干ばつ、洪水、降水量の変動や極端な降水により、特に貧しい人々の食料安全保障が脅かされるとともに、食料システムが崩壊するリスクがある。
vi)水資源不足と農業生産減少による農村部の生計及び所得損失のリスク[懸念の理由2, 3]
飲料水や灌漑用水への不十分なアクセスと農業の生産性の低下により、半乾燥地域において、特に最小限の資本しか持たない農民や牧畜民の生計や収入が失われる可能性がある。
vii)沿岸海域における生計に重要な海洋生態系の損失リスク[懸念の理由1, 2, 4]
特に熱帯と北極圏の漁業コミュニティにおいて、沿岸部の人々の生計を支える海洋・沿岸の生態系と生物多様性、生態系便益・機能・サービスが失われる可能性がある。
viii)陸域及び内水生態系がもたらすサービスの損失リスク[懸念の理由 1, 3, 4]
人々の生計を支える陸域及び内水の生態系と生物多様性、生態系便益・機能・サービスが失われる可能性がある。
・気候変動の速さと大きさを制限することにより、その影響による全般的なリスクを低減できる。
一方、温暖化が大規模になれば、深刻かつ広範で、不可逆的な影響が起る可能性が高まる。
C. 将来のリスクの管理とレジリエンスの構築
効果的な適応のための原則
・適応は、地域や背景が特有であるため、すべての状況にわたって適切なリスク低減のアプローチは存在しない。
・限られた証拠によると、世界全体の適応ニーズと適応のための資金には隔たりがある。世界全体の適応に要する費用を算定する研究には、データや手法、適用範囲が不十分という特徴があり、更なる研究の向上が必要である。
・重要なコベネフィット、相乗効果、トレードオフは緩和と適応の間や異なる適応の反応の中に存在する。相互作用は地域内及び地域をまたいで起こる(確信度は非常に高い)。
気候に対してレジリエントな経路と変革
・経済的、社会的、技術的、政治的決定や行動の変革が、気候に対してレジリエント(強靭)な経路を可能とする。
懸念の理由
人による気候システムへの影響は明らかである。しかし、その影響が国連気候変動枠組条約第2 条にある“危険な人類的干渉”に当たるどうかは、リスク評価と価値判断の両方が必要である。以下の包括的な「懸念の理由(Reasons For Concern)」は、あらゆる分野及び地域にわたる主要なリスクをまとめる枠組みを提供する。懸念の理由は、温暖化や人々、経済、及び生態系にとっての適応の限界の意味するところを解説している。それらは、気候システムに対する危険な人為的干渉を評価するための1 つの出発点を提供する。気温変化については、1986~2005 年平均からの相対的な値として示されている。
(1) 脅威に曝されている独特な生態系や文化等のシステム
深刻な影響のリスクに直面するシステムの数は1℃の気温上昇で増加し、北極海氷システムやサンゴ礁など適応能力が限られている多くの種やシステムは2℃の気温上昇で非常に高いリスクにさらされる。
(2) 極端な気象現象による気候変動関連リスク
熱波、極端な降水、沿岸洪水のような極端現象による気候変動関連リスクは中程度であり(確信度が高い)、1℃の気温上昇で高い状態になる(確信度は中程度)。
(3) 影響の分布
リスクは均一に分布しているわけではなく、どのような発展段階の国であれ、一般的に不利な条件におかれた人々やコミュニティほど多くのリスクを抱えている。特に作物生産への気候変動の影響が地域によって異なるため、リスクは中程度である(確信度は中程度から高い)。地域の作物生産と水の利用性の低下の予測をもとに、不均一な分布による影響から生じるリスクは2℃以上の気温上昇により増大する。(確信度は中程度)
(4) 世界総合的な影響
温暖化の全世界への総合的な影響のリスクは、地球の生物多様性及び世界経済全体への影響についてみると、1~2 ℃の気温上昇ではリスクは中程度である(確信度は中程度)。約3℃またはそれ以上の気温上昇では、生態系由来の財・サービスの損失を伴う広範囲に及ぶ生物多様性の損失が起こり、リスクが高くなる(確信度が高い)。
(5) 大規模な特異現象
温暖化の進行に伴い、いくつかの物理システムあるいは生態系が急激かつ不可逆的な変化のリスクにさらされる可能性がある。リスクは、1~2℃の気温上昇に伴い不均衡に増加し、3℃以上の気温上昇で氷床の消失による大規模で不可逆的な海面上昇の可能性があることから、高くなる。
第5 次評価報告書における可能性と確信度の表現について
IPCC では、評価結果の「可能性」と「確信度」を表す用語を、一貫した基準に基づいて使用し
ている。以下に、第5 次評価報告書で用いる用語を示す。
「可能性」とは、はっきり定義できる事象が起こった、あるいは将来起こることについての確率
的評価である。また、「確信度」とは、モデル、解析あるいはある意見の正しさに関する不確実性
の程度を表す用語であり、証拠(例えばメカニズムの理解、理論、データ、モデル、専門家の判断)
の種類や量、品質及び整合性と、特定の知見に関する文献間の競合の程度等に基づく見解の一致度
に基づいて定性的に表現される。
<可能性の表現>
用語 発生する可能性
ほぼ確実 99%~100%
可能性が極めて高い 95%~100%
可能性が非常に高い 90%~100%
可能性が高い 66%~100%
どちらかと言えば 50%~100%
どちらも同程度 33%~66%
可能性が低い 0%~33%
可能性が非常に低い 0%~10%
可能性が極めて低い 0%~5%
ほぼありえない 0%~1%
<
2014年04月07日
2013年度京都メカニズムクレジット取得事業の結果
平成26年4月1日
「平成25年度京都メカニズムクレジット取得事業」の結果について(お知らせ)
京都議定書の削減約束を達成するため、環境省及び経済産業省は、平成18年度から独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)に委託し、京都メカニズムを活用してクレジットを取得する事業を実施しております。この度、NEDOが平成25年度におけるクレジット取得事業の結果について公表いたしましたので、お知らせいたします。
1.京都議定書目標達成計画(平成17年4月閣議決定。平成20年3月全部改定)において、国内対策に最大限努力してもなお京都議定書の約束達成に不足すると見込まれる差分(基準年総排出量比1.6%)については、「補足性の原則を踏まえつつ、京都メカニズムを活用したクレジットの取得によって確実に対応することが必要」とされております。このため、環境省及び経済産業省は、平成18年度からNEDOに政府のクレジット取得を委託し、京都メカニズムクレジット取得事業を開始いたしました。
2.本事業の実施に当たっては、京都議定書目標達成計画において、「クレジットを取得するに際しては、
[1]リスクの低減を図りつつ、費用対効果を考慮して取得すること、
[2]地球規模での温暖化防止、途上国の持続可能な開発への支援を図ること」
とされております。
同計画を踏まえて、平成25年度にはNEDOより383.9万トン(二酸化炭素換算)のクレジットが日本政府口座へ移転されました。また事業開始以降の日本政府口座への総移転量は、9,749.3万トン(二酸化炭素換算)となり、政府目標の約1億トン(二酸化炭素換算)をほぼ達成しました。
(参考)
○
「2013年度京都メカニズムクレジット取得事業の結果について」(NEDO発表資料)
<http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100048.html>
平成26年4月1日
NEDOは、政府からの委託により2006年度から2013年度にわたって京都メカニズムクレジット取得事業を実施しました。2013年度事業を以下のとおり実施しましたのでお知らせします。
1. 2013年度事業の結果について
(1) 2013年度の政府へのクレジット移転実績総量について
2013年度は、383.9万トン(二酸化炭素換算)を政府の管理口座へ移転し、総契約量の全量移転を完了しました。
この結果、事業期間の政府への移転実績総量は9749.3万トン(二酸化炭素換算)となり、政府目標の約1億トン(二酸化炭素換算)をほぼ達成しました。
(2) 2013年度契約結果について
2013年度は新たな契約締結は行いませんでした。
「平成25年度京都メカニズムクレジット取得事業」の結果について(お知らせ)
京都議定書の削減約束を達成するため、環境省及び経済産業省は、平成18年度から独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)に委託し、京都メカニズムを活用してクレジットを取得する事業を実施しております。この度、NEDOが平成25年度におけるクレジット取得事業の結果について公表いたしましたので、お知らせいたします。
1.京都議定書目標達成計画(平成17年4月閣議決定。平成20年3月全部改定)において、国内対策に最大限努力してもなお京都議定書の約束達成に不足すると見込まれる差分(基準年総排出量比1.6%)については、「補足性の原則を踏まえつつ、京都メカニズムを活用したクレジットの取得によって確実に対応することが必要」とされております。このため、環境省及び経済産業省は、平成18年度からNEDOに政府のクレジット取得を委託し、京都メカニズムクレジット取得事業を開始いたしました。
2.本事業の実施に当たっては、京都議定書目標達成計画において、「クレジットを取得するに際しては、
[1]リスクの低減を図りつつ、費用対効果を考慮して取得すること、
[2]地球規模での温暖化防止、途上国の持続可能な開発への支援を図ること」
とされております。
同計画を踏まえて、平成25年度にはNEDOより383.9万トン(二酸化炭素換算)のクレジットが日本政府口座へ移転されました。また事業開始以降の日本政府口座への総移転量は、9,749.3万トン(二酸化炭素換算)となり、政府目標の約1億トン(二酸化炭素換算)をほぼ達成しました。
(参考)
○
「2013年度京都メカニズムクレジット取得事業の結果について」(NEDO発表資料)
<http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100048.html>
平成26年4月1日
NEDOは、政府からの委託により2006年度から2013年度にわたって京都メカニズムクレジット取得事業を実施しました。2013年度事業を以下のとおり実施しましたのでお知らせします。
1. 2013年度事業の結果について
(1) 2013年度の政府へのクレジット移転実績総量について
2013年度は、383.9万トン(二酸化炭素換算)を政府の管理口座へ移転し、総契約量の全量移転を完了しました。
この結果、事業期間の政府への移転実績総量は9749.3万トン(二酸化炭素換算)となり、政府目標の約1億トン(二酸化炭素換算)をほぼ達成しました。
(2) 2013年度契約結果について
2013年度は新たな契約締結は行いませんでした。
2014年01月27日
新しい白神山地世界遺産地域管理計画の策定について
http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/press/kouhou/atarashiisirakamikanrikeikakusakutei.html
新しい白神山地世界遺産地域管理計画の策定について
平成25年10月15日
東北森林管理局
林野庁、環境省、文化庁、青森県及び秋田県は、本日、白神山地世界遺産地域について、最新の知見を踏まえた順応的管理を更に進めていくため、新しい白神山地世界遺産地域管理計画を策定しました。
本件は、林野庁、環境省、環境省 東北地方環境事務所、青森県及び秋田県においても、同時に発表しています。
1経緯
世界遺産については、その価値を将来にわたって保全していくため、適切な管理計画を策定することが求められています。
平成5年に世界遺産に登録された白神山地世界遺産地域については、平成7年11月に、林野庁、環境省及び文化庁が、管理計画を策定し、同計画に基づいた管理を行っています。
一方で、遺産地域の現状に合わせ、地域とのより密接な連携によって、最新の知見を踏まえた順応的管理を更に進めていくため、学識経験者等で構成する白神山地世界遺産地域科学委員会の助言を得つつ、国民の皆様からも意見をいただいて、新しい管理計画の検討を進めてきました。
その結果、本日、林野庁、環境省、文化庁、青森県及び秋田県は、新しい白神山地世界遺産地域管理計画を策定しました。
2新しい白神山地世界遺産地域管理計画のポイント
新しい白神山地世界遺産地域管理計画のポイントは以下のとおりです。
(1)遺産地域の管理主体の一員である青森県及び秋田県が、管理計画の策定者として新たに加わりました。
(2)新たに、以下のことを管理方針として位置づけました。
人手を加えず自然の推移に委ねることを基本に、各種制度に基づき厳正な保護を図ることに加え、必要に応じ、外来種対策等の能動的な管理を行うこと
遺産地域のモニタリングについて、地元市町村や大学・研究機関、その他の学識経験者等と連携して推進すること
気候変動、外来種・病害虫の侵入等について、関係者からの情報収集やモニタリング等を実施し、自然の価値を損ねる危機・予兆現象の早期発見に努めること
多種多様な生物種により構成された、複雑で将来予測が困難な生態系を保全するため、科学的知見やモニタリング結果等を踏まえ、白神山地世界遺産地域科学委員会の助言を得て順応的管理を行うこと
世界遺産としての価値を将来にわたって維持していくため、地域に暮らす人たちの知恵や技術を活かしながら、自然環境に配慮したエコツーリズムを推進すること
3新しい白神山地世界遺産地域管理計画及びその概要
白神山地世界遺産地域管理計画(PDF:319KB)
白神山地世界遺産地域管理計画巻末付表等(PDF:4,562KB)
白神山地世界遺産地域管理計画の概要(PDF:121KB)
2014年01月14日
世界自然遺産
・知床 北海道の北東部に位置し、火山活動などによって形成された標高1,500m 級の急峻な山々、切り立つ海岸断崖、湿原・湖沼群などにより構成されている。遺産地域はこの知床半島の中央部から先端の知床岬にかけての陸地と、その周辺の海を含む約71,100ha の地域
Ⅸ生態系:海氷の影響を受けた海と陸の生態系の豊かなつながり
Ⅹ生物多様性:動植物ともに北方系と南方系の種が混在することによって、多くの希少種や固有種を含む幅広い生物種が生息・生育するなど、生物の多様性を維持するために重要な地域
2014年01月07日
国内希少野生動植物種一覧
レッドデータブックやレッドリストで絶滅のおそれのある種(絶滅危惧I類、II類)とされたもののうち、人為の影響により生息・生育状況に支障を来す事情が生じているものの中から、国内希少野生動植物種に指定しています。
国内希少野生動植物種一覧表 平成25年6月現在(全89種)
* 鳥類(37種)
がんかも科 シジュウカラガン 平成5年
うみすずめ科 エトピリカ 〃
ウミガラス 〃
しぎ科 アマミヤマシギ 〃
カラフトアオアシシギ 〃
こうのとり科 コウノトリ 〃
とき科 トキ 〃
はと科 キンバト 〃
アカガシラカラスバト 〃
ヨナクニカラスバト 〃
わしたか科 オオタカ 〃
イヌワシ 〃
オガサワラノスリ 〃
オジロワシ 〃
オオワシ 〃
カンムリワシ 〃
クマタカ 〃
はやぶさ科 シマハヤブサ 〃
ハヤブサ 〃
きじ科 ライチョウ 〃
つる科 タンチョウ 〃
くいな科 ヤンバルクイナ 〃
あとり科 オガサワラカワラヒワ 〃
みつすい科 ハハジマメグロ 〃
ひたき科 アカヒゲ 〃
ホントウアカヒゲ 〃
ウスアカヒゲ 〃
オオトラツグミ 〃
オオセッカ 〃
やいろちょう科 ヤイロチョウ 〃
う科 チシマウガラス 〃
きつつき科 オーストンオオアカゲラ 〃
ミユビゲラ 〃
ノグチゲラ 〃
あほうどり科 アホウドリ 〃
ふくろう科 ワシミミズク 平成9年
シマフクロウ 平成5年
*哺乳類(5種)
ねこ科 ツシマヤマネコ 平成6年
イリオモテヤマネコ 〃)
おおこうもり科 ダイトウオオコウモリ 平成16年
オガサワラオオコウモリ平成21年
うさぎ科 アマミノクロウサギ 平成16年
*爬虫類(1種)
へび科 キクザトサワヘビ 平成7年
*両生類(1種)
さんしょううお科アベサンショウウオ 平成7年
*魚類(4種)
どじょう科 アユモドキ 平成16年
こい科 イタセンパラ 平成7年
スイゲンゼニタナゴ 平成14年
ミヤコタナゴ 平成6年
*昆虫類(15種)
はんみょう科 オガサワラハンミョウ 平成20年
げんごろう科 ヤシャゲンゴロウ 平成8年
マルコガタノゲンゴロウ平成23年
フチトリゲンゴロウ 〃
シャープゲンゴロウモドキ〃
くわがたむし科 ヨナグニマルバネクワガタ平成23年
こがねむし科 ヤンバルテナガコガネ 平成8年
せみ科イ シガキニイニイ 平成14年
しじみちょう科 オガサワラシジミ 平成20年
ゴイシツバメシジミ 平成8年
たてはちょう科 ヒョウモンモドキ 平成23年
えぞとんぼ科 オガサワラトンボ 平成20年
あおいととんぼ科 オガサワラアオイトトンボ 〃
はなだかとんぼ科 ハナダカトンボ 〃
とんぼ科 ベッコウトンボ 平成6年
*植物(26種、うち○特定国内希少野生動植物種7種)
ちゃせんしだ科 ヒメタニワタリ 平成20年
きく科 コヘラナレン 〃
おしだ科 アマミデンダ 平成11年 ○(平成11年)
つつじ科 ムニンツツジ 平成16年
ウラジロヒカゲツツジ 平成24年
ヤドリコケモモ 平成11年
しそ科 シマカコソウ 平成20年
のぼたん科 ムニンノボタン 平成16年
すいせん科 シモツケコウホネ 平成24年
らん科 アサヒエビネ 平成16年
ホシツルラン 〃
チョウセンキバナアツモリソウ平成14年
ホテイアツモリ 平成9年 ○(平成9年)
レブンアツモリソウ 平成6年 ○(平成6年)
アツモリソウ 平成9年 ○(平成9年)
オキナワセッコク 平成14年 ○(平成20年)
コゴメキノエラン 平成11年
シマホザキラン 平成16年
クニガミトンボソウ 平成14年
こしょう科 タイヨウフウトウカズラ 平成16年
とべら科 コバトベラ 〃
はなしのぶ科 ハナシノブ 平成7年 ○(平成7年)
さくらそう科 カッコソウ 平成24年
きんぽうげ科 キタダケソウ 平成6年 ○(平成6年)
はいのき科 ウチダシクロキ 平成20年
くまつづら科 ウラジロコムラサキ 平成16年_
国内希少野生動植物種一覧表 平成25年6月現在(全89種)
* 鳥類(37種)
がんかも科 シジュウカラガン 平成5年
うみすずめ科 エトピリカ 〃
ウミガラス 〃
しぎ科 アマミヤマシギ 〃
カラフトアオアシシギ 〃
こうのとり科 コウノトリ 〃
とき科 トキ 〃
はと科 キンバト 〃
アカガシラカラスバト 〃
ヨナクニカラスバト 〃
わしたか科 オオタカ 〃
イヌワシ 〃
オガサワラノスリ 〃
オジロワシ 〃
オオワシ 〃
カンムリワシ 〃
クマタカ 〃
はやぶさ科 シマハヤブサ 〃
ハヤブサ 〃
きじ科 ライチョウ 〃
つる科 タンチョウ 〃
くいな科 ヤンバルクイナ 〃
あとり科 オガサワラカワラヒワ 〃
みつすい科 ハハジマメグロ 〃
ひたき科 アカヒゲ 〃
ホントウアカヒゲ 〃
ウスアカヒゲ 〃
オオトラツグミ 〃
オオセッカ 〃
やいろちょう科 ヤイロチョウ 〃
う科 チシマウガラス 〃
きつつき科 オーストンオオアカゲラ 〃
ミユビゲラ 〃
ノグチゲラ 〃
あほうどり科 アホウドリ 〃
ふくろう科 ワシミミズク 平成9年
シマフクロウ 平成5年
*哺乳類(5種)
ねこ科 ツシマヤマネコ 平成6年
イリオモテヤマネコ 〃)
おおこうもり科 ダイトウオオコウモリ 平成16年
オガサワラオオコウモリ平成21年
うさぎ科 アマミノクロウサギ 平成16年
*爬虫類(1種)
へび科 キクザトサワヘビ 平成7年
*両生類(1種)
さんしょううお科アベサンショウウオ 平成7年
*魚類(4種)
どじょう科 アユモドキ 平成16年
こい科 イタセンパラ 平成7年
スイゲンゼニタナゴ 平成14年
ミヤコタナゴ 平成6年
*昆虫類(15種)
はんみょう科 オガサワラハンミョウ 平成20年
げんごろう科 ヤシャゲンゴロウ 平成8年
マルコガタノゲンゴロウ平成23年
フチトリゲンゴロウ 〃
シャープゲンゴロウモドキ〃
くわがたむし科 ヨナグニマルバネクワガタ平成23年
こがねむし科 ヤンバルテナガコガネ 平成8年
せみ科イ シガキニイニイ 平成14年
しじみちょう科 オガサワラシジミ 平成20年
ゴイシツバメシジミ 平成8年
たてはちょう科 ヒョウモンモドキ 平成23年
えぞとんぼ科 オガサワラトンボ 平成20年
あおいととんぼ科 オガサワラアオイトトンボ 〃
はなだかとんぼ科 ハナダカトンボ 〃
とんぼ科 ベッコウトンボ 平成6年
*植物(26種、うち○特定国内希少野生動植物種7種)
ちゃせんしだ科 ヒメタニワタリ 平成20年
きく科 コヘラナレン 〃
おしだ科 アマミデンダ 平成11年 ○(平成11年)
つつじ科 ムニンツツジ 平成16年
ウラジロヒカゲツツジ 平成24年
ヤドリコケモモ 平成11年
しそ科 シマカコソウ 平成20年
のぼたん科 ムニンノボタン 平成16年
すいせん科 シモツケコウホネ 平成24年
らん科 アサヒエビネ 平成16年
ホシツルラン 〃
チョウセンキバナアツモリソウ平成14年
ホテイアツモリ 平成9年 ○(平成9年)
レブンアツモリソウ 平成6年 ○(平成6年)
アツモリソウ 平成9年 ○(平成9年)
オキナワセッコク 平成14年 ○(平成20年)
コゴメキノエラン 平成11年
シマホザキラン 平成16年
クニガミトンボソウ 平成14年
こしょう科 タイヨウフウトウカズラ 平成16年
とべら科 コバトベラ 〃
はなしのぶ科 ハナシノブ 平成7年 ○(平成7年)
さくらそう科 カッコソウ 平成24年
きんぽうげ科 キタダケソウ 平成6年 ○(平成6年)
はいのき科 ウチダシクロキ 平成20年
くまつづら科 ウラジロコムラサキ 平成16年_
2013年11月28日
石原伸晃環境大臣 COP19ステートメント(平成25年11月20日)
議長、ありがとうございます。
日本政府を代表して、COP19議長を務めるポーランド政府及びマルチン・コロレツ環境大臣に心から感謝いたします。
また、この度フィリピンの方々を始め、先日の台風により被害を受けた方々に、心よりお悔やみを申し上げます。
議長、
世界全体での着実な排出削減を図るためには、2015年のCOP21において、すべての国が参加する公平かつ実効的な枠組みが採択されることが不可欠です。
このため、日本は、各国による自主的な約束と効果的で国際的な透明性メカニズムに基づく、2020年以降の枠組みの構築を強く支持します。
私は、このCOP19における成功に向け、努力してまいります。
議長、
2011年3月の東日本大震災及び原子力発電所事故は、我が国のエネルギー事情を一変させました。
こうした状況にも関わらず、我が国では官民挙げて気候変動への取組に最大限の努力をしてきました。
京都議定書第一約束期間の我が国の温室効果ガス排出量は、基準年比で8.2%削減の見込みとなりました。
その結果、京都議定書第一約束期間の6%削減目標を達成することができました。
次なるステップとして、我が国は2020年の削減目標について、2005年比で3.8%減とすることとしました。
この目標は一見すると低い値に映るかもしれません。
しかし、これは野心的な目標です。すでに世界最高水準にあるエネルギー効率を20%も改善するという野心的なものです。
この目標は、原発による排出削減効果を含めずに設定した、現時点でのものです。
エネルギー政策はまだ、検討中です。今後の検討の進展を踏まえて、さらなる見直しを行い、確定的な目標を設定します。
我が国は、あらゆるツールを活用し、低炭素社会を構築していきます。戦略的に気候変動対策を推進します。
洋上風力発電や地熱発電、蓄電池など再生可能エネルギー関連技術の開発と実証を促進します。
来年3月にIPCC総会が我が国で開催されます。これを機に、新たな国民運動を立ち上げ、さらなる低炭素なライフスタイルを奨励します。
議長、
我が国は、2050年までに世界全体で50%削減、先進国で80%という目標を改めて掲げます。今こそ、安倍総理が掲げた美しい星に向けた行動、「Actions for a Cool Earth」に取り組むべき時です。
まず、日本はさらなる技術革新に取り組みます。このため、今後5年間に官民合わせて1100億ドルの国内投資を行います。
次に、日本の低炭素技術の世界への応用を図ります。このため、二国間オフセット・クレジット制度を通じて、世界全体での排出削減に貢献していきます。
さらに、我が国は各国やステークホルダーとの連携を強化します。我が国は途上国に対し、2013年から2015年までの3年間に1兆6千億円、約160億ドルを支援します。気候変動の緩和と適応の分野において、ODA、OOF、民間資金など官民総動員で支援をします。
2020年の夏季オリンピック・パラリンピックは、東京で開催されることが決定しました。
オリンピックを通じて、低炭素社会、自然共生社会及び循環型社会を世界に示していきます。
ご清聴ありがとうございました。
日本政府を代表して、COP19議長を務めるポーランド政府及びマルチン・コロレツ環境大臣に心から感謝いたします。
また、この度フィリピンの方々を始め、先日の台風により被害を受けた方々に、心よりお悔やみを申し上げます。
議長、
世界全体での着実な排出削減を図るためには、2015年のCOP21において、すべての国が参加する公平かつ実効的な枠組みが採択されることが不可欠です。
このため、日本は、各国による自主的な約束と効果的で国際的な透明性メカニズムに基づく、2020年以降の枠組みの構築を強く支持します。
私は、このCOP19における成功に向け、努力してまいります。
議長、
2011年3月の東日本大震災及び原子力発電所事故は、我が国のエネルギー事情を一変させました。
こうした状況にも関わらず、我が国では官民挙げて気候変動への取組に最大限の努力をしてきました。
京都議定書第一約束期間の我が国の温室効果ガス排出量は、基準年比で8.2%削減の見込みとなりました。
その結果、京都議定書第一約束期間の6%削減目標を達成することができました。
次なるステップとして、我が国は2020年の削減目標について、2005年比で3.8%減とすることとしました。
この目標は一見すると低い値に映るかもしれません。
しかし、これは野心的な目標です。すでに世界最高水準にあるエネルギー効率を20%も改善するという野心的なものです。
この目標は、原発による排出削減効果を含めずに設定した、現時点でのものです。
エネルギー政策はまだ、検討中です。今後の検討の進展を踏まえて、さらなる見直しを行い、確定的な目標を設定します。
我が国は、あらゆるツールを活用し、低炭素社会を構築していきます。戦略的に気候変動対策を推進します。
洋上風力発電や地熱発電、蓄電池など再生可能エネルギー関連技術の開発と実証を促進します。
来年3月にIPCC総会が我が国で開催されます。これを機に、新たな国民運動を立ち上げ、さらなる低炭素なライフスタイルを奨励します。
議長、
我が国は、2050年までに世界全体で50%削減、先進国で80%という目標を改めて掲げます。今こそ、安倍総理が掲げた美しい星に向けた行動、「Actions for a Cool Earth」に取り組むべき時です。
まず、日本はさらなる技術革新に取り組みます。このため、今後5年間に官民合わせて1100億ドルの国内投資を行います。
次に、日本の低炭素技術の世界への応用を図ります。このため、二国間オフセット・クレジット制度を通じて、世界全体での排出削減に貢献していきます。
さらに、我が国は各国やステークホルダーとの連携を強化します。我が国は途上国に対し、2013年から2015年までの3年間に1兆6千億円、約160億ドルを支援します。気候変動の緩和と適応の分野において、ODA、OOF、民間資金など官民総動員で支援をします。
2020年の夏季オリンピック・パラリンピックは、東京で開催されることが決定しました。
オリンピックを通じて、低炭素社会、自然共生社会及び循環型社会を世界に示していきます。
ご清聴ありがとうございました。
2013年11月27日
COP19及びCOP/MOP9について(結果概要)
平成25年11月25日
国連気候変動枠組条約第19回締約国会議(COP19)及び京都議定書第9回締約国会合(COP/MOP9)について(結果概要) (お知らせ)
ポーランド・ワルシャワで11月11日(月)から11月23日(土)にかけて開催された国連気候変動枠組条約第19回締約国会議(COP19)及び京都議定書第9回締約国会合(COP/MOP9)の結果についてお知らせいたします。
1.日時:平成25年11月11日(月)~11月23日(土)
2.場所:ポーランド・ワルシャワ
3.結果概要:別紙参照
(別紙)
国連気候変動枠組条約第19回締約国会議(COP19)
京都議定書第9回締約国会合(CMP9)等の概要と評価
京都議定書第9回締約国会合(CMP9)等の概要と評価
平成25年11月23日
日本政府代表団
日本政府代表団
1 全体の概要と評価
(1)11月11日から23日まで、ポーランド・ワルシャワにおいて、国連気候変動枠組条約第19回締約国会議(COP19)、京都議定書第9回締約国会合(CMP9)等が行われた。我が国からは、石原環境大臣及び外務・経済産業・環境・財務・文部科学・農林水産・国土交通各省関係者が出席した。
(2)「強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会(ADP)」及び2つの補助機関会合における事務レベルの交渉を経て、11月19日以降のハイレベル・セグメントにおいて閣僚間でさらに協議を重ねた結果、最終的に以下の一連の決定を含むCOP及びCMPの決定等が採択された。
[1]ADPの作業計画を含むCOP決定
[2]気候資金に関する一連のCOP決定
[3]気候変動の悪影響に関する損失と被害(ロス&ダメージ)に関するCOP決定
(3) 2020年以降の枠組みについてすべての国が、自主的に決定する約束(contribution)のための国内準備を開始しCOP21に十分先立ち約束草案を示すことや、約束草案を示す際に提供する情報をCOP20で特定することなど、議論の前進につながる成果が得られ、COP21におけるすべての国が参加する将来枠組みの合意に向けた準備を整えるという我が国の目標を達成することができた。
2 日本政府の対応
(1)日本政府は、COP17のダーバン決定で決まった、2020年以降の新たな法的枠組みに関する2015年までの合意に向け、将来枠組みに含まれる要素の検討の作業と2015年までの作業計画の明確化を進めることを目指し、交渉に対応した。
(2)ハイレベル・セグメントでの石原環境大臣による演説等において、京都議定書第一約束期間の削減実績は8.2%であり、6%削減目標を達成する見込みであること、2020年の削減目標を2005年比3.8%減とすることを説明するとともに、安倍総理が掲げた美しい星に向けた行動「Actions for Cool Earth: ACE(エース)」に取り組むことを表明した。具体的には、さらなる技術革新、日本の低炭素技術の世界への応用、途上国に対する2013年から2015年までの3年間に1兆6千億円(約160億ドル)の支援を表明した。また、ADP閣僚対話に出席し、将来枠組みに関する我が国の考え方につき発言を行い、交渉の進展に貢献した。
(3)石原環境大臣は、会合期間中に各国と二国間会談を行い、日本の目標等に関して説明し理解を求めると共に、会合の成功に向けた連携を確認した。 また、二国間クレジット制度(JCM)に署名した8カ国が一堂に会する「JCM署名国会合」を開催し、JCMのプロジェクト形成を精力的に推進していくことを確認するとともに、経団連や日本政府主催のサイドイベントに出席し、日本の気候変動への取組をアピールした。
3 今次会合の成果
(1)ADPに関しては、ワークストリーム1(2020年枠組み)では、すべての国が、2020年以降の約束について、各国が自主的に決定する約束のための国内準備を開始してCOP21に十分先立ち(準備ができる国は2015年第1四半期までに)、約束草案を示すこと及び約束草案を示す際に提供する情報をCOP20で特定すること等の今後の段取りが決定した。ワークストリーム2(2020年以前の緩和の野心向上)では、高い排出削減可能性のある行動の機会に関する技術専門家会合の開催や、都市・地方の経験・ベストプラクティスの共有に関するフォーラムの開催等が決定された。来年は、3月10-14日に会合を開催すること、来年後半の追加会合の可能性を検討すること、6月及び12月(COP20)の会合においてハイレベル閣僚対話を開催すること等のスケジュールが決定した。
(2)資金については、COP18以降に先進国が行った資金プレッジの認知、2014年から2020年までの間の隔年の気候資金に関するハイレベル閣僚級対話の開催、気候資金拡大のための戦略・アプローチ等に関する会期中ワークショップの開催、COPと緑の気候基金(GCF)の間のアレンジメントへの合意等の決定が採択された。途上国は、2020年1,000億ドルに向けた中期目標の設定や、GCFへの拠出時期・金額を具体的数字を書き込むことを主張したが、最終的にはこれらの記述は決定に盛り込まれなかった。なお、先進国全体に対して短期資金期間(2010年から2012年)より高いレベルで公的気候資金の連続性を維持するよう求めた。また、先進国に対して、2014年から2020年までの間に気候資金を拡大するための更新した戦略・アプローチについて隔年のサブミッションを用意するよう求めた。
(3) 気候変動の悪影響に関する損失・被害(ロス&ダメージ)については、COP22で見直すことを条件とし、カンクン適応枠組みの下に「ワルシャワ国際メカニズム」を設立することに合意した。具体的には、条約下の既存組織の代表により構成される同メカニズムの執行委員会の設立(暫定措置)、同メカニズムの機能(データやベストプラクティス等の知見の共有、国連を含む条約内外の関係機関との連携、資金・技術・能力構築含む活動と支援の強化)、機能の実施のための2カ年作業計画の策定や執行委員会の構成や手続きの検討(2014年12月に検討)、COP22での同メカニズムについて見直し等を決定した。
(4)途上国における森林の減少・劣化による二酸化炭素の排出削減(REDD+)について、技術ガイダンス、資金、組織を含む支援の調整に関する枠組みを決定した。
(5)今回は日本政府として初めてイベントスペースを設置し、国、各種機関・組織、研究者等の取組の紹介や議論を行うイベントが多数開催され、盛況だった。
(6)なお、次回のCOP20はペルーが議長国を務め、リマで開催されることとなった。また、COP21はフランスが議長国を務めることが決まるとともに、セネガルがCOP22の議長国を務める意志があることを表明した。
(了)
2013年11月27日
「(愛称)みちのく潮風トレイル」
平成25年11月26日
東北太平洋岸自然歩道「(愛称)みちのく潮風トレイル」整備計画の決定について(お知らせ)
環境省では、三陸地域のグリーン復興プロジェクトの一つである「みちのく潮風トレイル」について、その一部となる青森県八戸市蕪島から岩手県久慈市小袖までの約100kmの区間で路線の設定及び整備計画の決定、ルートマップの作成を終えたので、11月29日に開通します。
○「三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興のビジョン」(平成24年5月環境省策定)のプロジェクトの一つである東北太平洋岸自然歩道「(愛称)みちのく潮風トレイル」については、わが国で10番目となる新たな長距離自然歩道として、地域におけるワークショップの開催を通じて詳細路線の検討を進めてきました。
○八戸市蕪島(かぶしま) (青森県)から相馬市松川浦(まつかわうら) (福島県)に至る全線約700kmのうち、八戸市蕪島から久慈市小袖(こそで)(岩手県)までの100.76kmの区間について路線の設定及び整備計画の決定、ルートマップの作成を終えましたので、その区間について11月29日をもって開通します。
○今回開通する区間については、開通記念イベントとして八戸市、久慈市での式典及び八戸市、久慈市、階上(はしかみ)町、洋野(ひろの)町でのウォークイベントを8月24日及び25日に開催したところです。このため、今回の開通にあたっては開通翌日の11月30日に八戸市蕪島で標識の除幕のみ行う予定です。(標識の除幕の詳細については、東北地方環境事務所国立公園・保全整備課(電話:022-722-2874)にお問合せください。)
○今回開通する区間における必要な標識類の整備を順次行うとともに、残る約600kmの区間の路線設定等の作業を引き続き進めていきます。
2013年11月20日
アジア保護地域憲章(仙台憲章)の概要
・アジアにおける保護地域の特質と方向性を示すため、アジア国立公園会議の合意文書として、会議最終日に会議参加者全員により合意したもの。
・法的拘束力は有しないが、会議参加者が協力して、本憲章に沿った取組を進めるとともに、アジア各国及び関係国際機関等に対し協力を呼びかけていく。
アジア保護地域憲章の主な内容
アジアの挑戦
• 保護地域は、自然と自然に関連する文化的資源を保全する最も有効な手段の一つ。
• アジアの広範で多様な保護地域体制は生物多様性条約の「愛知目標」を含む世界の生物多様性に関する諸目標の達成に、重要な役割を果たすものであることを認識。
• 人材や財源の強化とグローバルな最優良事例や手法の選択を通じ、アジアの保護地域の管理を強化することが喫緊の課題。
(注)「保護地域」は、陸域、海域、陸水域における政府が管理する保護地域だけでなく、私的な保護地域、自然の聖地、先住民や地域住民による保護地域を含む。
災害リスクの削減と復興のための保護地域
• アジアでは、人口増加や都市化、気候変動等により自然災害による被害が増加。
• 保護地域は、自然災害のリスクの高い場所における地域の回復能力(レジリエンス)を強化。
• 被災地における自然再生は地域社会の復興に貢献し、自然環境や生態系に対する人々の理解を促進。
地域開発と生物多様性保全の調和
• アジアには、高い生物多様性が開発等により脅かされている地域が多数存在。
• 保護地域は、自然環境を保護するためだけの措置ではなく、人と自然の間の調和を達成するための手法。
• 保護地域における良好な管理は、アジアにおける陸上景観や海洋景観の維持に寄与。
保護地域の協働管理
• アジアの社会は伝統的に土地および海に根ざしたものであることから、保護地域は地域の経済的利益や生計の向上にも資する必要。
• 地方政府、企業、先住民、NGOや青少年を含む多様な個人、地域社会、組織が参画し、すべての人々が裨益する保護地域の実現が必要。
• 保護地域の管理主体・体制は、地域固有の生態的、歴史的、政治的な背景に基づくことが必要。
文化・伝統と結びついた保護地域管理
• 保護地域、とくに自然の聖地や先住民や地域社会の保護地域は、地元の文化や伝統に深く根ざしており、人と自然が再びつながるには、これらを支援・奨励して発展させることが必要。
• 自然の聖地と言われるような場所は、人々や社会の精神的な豊かさや福利に資するだけでなく、生物多様性や生態系サービスの保全においても貴重な役割を発揮。
持続可能な観光および環境教育と持続可能な開発のための教育
• 保護地域は、レクリエーションや教育の機会を提供し、地域の人々に利益をもたらすエコツーリズムの資産として社会の福祉にも貢献。
• 環境教育と持続可能な開発のための教育は、保護地域の自然・文化の価値へ触れることに貢献。
保護地域の連携の強化
• 生物多様性にとって重要な地域の特定に向けた国際連携の促進が必要。
• アジアの保護地域の連携の強化は、保護地域の実効性が向上するほか、国同士の対話の増加や絆の強化にも寄与。
• 既存の国際的・地域的な協定や枠組みとの連携・協力の強化を図ることが必要。
○決意(コミットメント)
我々は、
• 保護地域が減災・防災、復興に果たす重要な役割に関する理解を広めることを確認。
• 参加型、持続可能、かつ地域住民へ利益を提供できる形で保護地域における責任ある観光や環境教育の機会を増やすことを確認。
• 政府、企業、先住民、NGOや青少年の更なる強力な関与を通じて保護地域のネットワークや連携を強化し、資金的・技術的支援を増加させることを確認。
• 保護地域の指定や管理に際し、地域の文化や伝統を尊重し、実践する人々の声に耳を傾けることを確認。
• 生物多様性と生態系サービスへの脅威を減らすことにより、愛知目標達成へ貢献することを確認。
• 保護地域の連携増進により、統治と管理能力を改善し、保護地域の価値を最大限に引き出すことを確認。
• 以上を通じ、保護地域が人類の進歩を促し、人と自然の共生を実現するような未来に向けて取り組む。