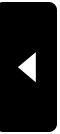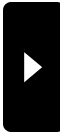2013年11月20日
アジア国立公園会議
2013 年11 月17 日
アジア国立公園会議 議長総括(仮訳)
星野 一昭
熊谷 嘉隆
熊谷 嘉隆
第1 回アジア国立公園会議は、国際自然保護連合(IUCN)及び日本の環境省の主催により、2013 年11 月13 日から17 日にかけて宮城県仙台市で開催された。会議にはアジア地域の22 ヶ国の保護地域所管機関の代表等を含む、政府、自治体、国際機関職員、NGO 職員、研究者、学生など世界の40 の国と地域から約800 名が参加した。
第6 回世界国立公園会議の1 年前に開催されたこの会議では、アジアにおける保護地域管理の現状・課題、そして優良事例などの経験を共有し、生物多様性条約の愛知目標の達成や保護地域作業計画の実施に向けた地域の協力体制の構築を推進するとともに、世界国立公園会議に向けてアジアからのメッセージを発信することを目的として開催された。
会議の概要
開会式では、石原伸晃環境大臣、Zhang Xinsheng IUCN 会長による開会挨拶、村井嘉浩宮城県知事、奥山恵美子仙台市長、Sally Barnes オーストラリア・ニューサウスウェールズ州環境遺産省事務次官による挨拶に続いて、田部井淳子氏(登山家)、武内和彦氏(国連大学上級副学長、中央環境審議会議長、東京大学教授)、Ernesto Enkerlin-Hoeflich 氏(IUCN 世界保護地域委員会委員長、モントレー工科大学教授)による基調講演が行われた。
全体会合では、アジア保護地域フィロソフィー、アジアにおける地域レベルの保護地域協力、IUCN 世界国立公園会議2014、愛知目標と韓国における生物多様性条約 COP12 の準備、IUCN 保護地域プログラム、世界保護地域データベース(WDPA)、グリーン復興プロジェクトと三陸復興国立公園、日本企業による生物多様性のための取組について情報共有が行われた。参加者は、UNEP/WCMC が作成中の「プロテクテッド・プラネット・アジア」レポートについて、各国の最新情報を提供するなどの協力を行うことを確認した。
参加者は次の6つのテーマのワーキング・グループに分かれて、保護地域に係る先進事例の発表や議論を行った。
WG1 自然災害と保護地域、
WG2 保護地域における観光・環境教育、
WG3 文化・伝統と保護地域、
WG4 保護地域の協働管理、
WG5 保護地域に関する国際連携、
WG6 生物多様性と保護地域。
会議に参加した若手研究者などによるユース・セッションも開催された。会議参加者は、フィールド・エクスカーションで、東日本大震災の被害を受けた地域に、日本の環境省がおいて創設した「三陸復興国立公園」を見学し、自然災害からの復興に向けて保護地域が果たす役割について認識を深めた。
会議の成果
会議参加者は、自然保護と地域の発展の両立に向けたアジアの経験に基づいた指針とも言うべき「アジア保護地域憲章」に合意した。
また、6つのワーキング・グループの議論を踏まえ、「第6回世界国立公園会議に向けたアジアからのメッセージ」が作成された。さらに、会議に参加した若手研究者などによ
り、「第1回アジア国立公園会議ユース宣言」がとりまとめられた。これらの成果は、最終日にIUCN、世界保護地域委員会、オーストラリア政府に対して手渡され、第6回世界国立公園会議の議論に十分反映されることとなった。
今後の展開
会議参加者は、世界国立公園会議において、アジア国立公園会議の成果が十分活用され、さらに議論が発展するよう、協力して取組を進めることに賛同した。会議参加者は、また、アジアにおける保護地域に係る協力体制の構築の必要性を認識した。その上で、IUCN アジア地域事務所、世界保護地域委員会、日本(環境省)に加え、関心のある国や国際機関を中心にしてパートナーシップ計画委員会(仮称)を設置し、準備・検討を進めることとなった。
2013年11月20日
化学物質政策ダイアローグ
平成25年11月18日
第7回日中韓における化学物質管理に関する政策ダイアローグの結果について(お知らせ)
11月13日(水)から15日(金)まで、「第7回日中韓における化学物質管理に関する政策ダイアローグ」(以下「化学物質政策ダイアローグ」という。)を京都市で開催しました。
11月14日に開催された日本、中国及び韓国の政府関係者による政府事務レベル会合では、3カ国の最新の化学物質管理政策、化学物質管理に関する国際動向への対応等に関する情報交換及び意見交換が行われました。今後、来年度の会合に向け、PRTRに関する技術的事項について会期間に情報交換を行うこと等について合意されました。
また、これに先立ち11月13日に開催された専門家会合では、日中韓3カ国の専門家による化学物質に係る生態毒性試験に関する共同研究や化学物質のリスク評価手法等について意見交換が行われました。そして、11月15日には、日中韓の化学物質管理政策に関する公開セミナーを開催しました。
次回の化学物質政策ダイアローグは、来年、韓国において開催される予定です。
1. これまでの経緯
平成18年12月に開催された第8回日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM8)において「化学物質管理に関する政策や規制に関する情報交換の推進」について合意されたことを受け、化学物質政策ダイアローグが、これまでに6回(平成19年(日本・東京)、平成20年(韓国・ソウル)、平成21年(中国・北京)、平成22年(日本・東京)、平成23年(韓国・済州島)、平成24年(中国・杭州))開催されました。
2. 概要
日時: 11月13日(水)~11月15日(金)
場所: 京都市
出席者:
中国: 環境保護部化学品登記中心Gao課長ほか
韓国: 環境部化学物質管理課Choung課長補佐ほか
日本: 環境省木村化学物質審査室長、国立環境研究所白石環境リスク研究センターフェロー、菅谷環境科学専門員ほか
3. 政策ダイアローグの結果
1日目) 中韓の化学物質管理に関する専門家会合
日時: 11月13日(水)
会場: 京都リサーチパーク
出席者: 18名(日中韓の政府関係者及び専門家等)
内容: 日中韓3カ国の専門家による化学物質に係る生態毒性試験に関する共同研究の進捗の報告、中国のGLP施設への現地調査の結果、定量的構造活性相関(QSAR)等の化学物質のリスク評価手法について意見交換が行なわれました。
今後、甲殻類及び魚類の生態毒性試験に関する共同研究を実施すること、韓国の試験施設への日本及び中国の専門家による訪問を来年上半期に実施するとともに、その際に3カ国の共同研究に関する会合を行うこと等について合意されました。
2日目) 日中韓政府事務レベル会合
日時: 11月14日(木)
会場: 京都リサーチパーク
出席者: 25名(日中韓の政府関係者及び専門家等)
内容: 日中韓の政府関係者により、3カ国の化学物質管理政策の最新動向として、化学物質管理に関する法律等の制定状況及び施行状況、環境リスクの評価方法等について活発な意見交換が行われるとともに、SAICM、POPs、水銀に関する水俣条約等の化学物質管理に関する国際動向への対応等について情報交換がなされました。
次回の会合では、化学物質管理に関する政策の最新の動向、特に、SAICM、水銀、リスク評価等に関する政策の状況について意見交換を行うこと、また、PRTRに関する技術的事項について会期間に情報交換を行い、必要に応じ、次回の専門家会合において議論すること等について合意されました。
3日目) 日中韓の化学物質管理政策に関するセミナー
日時: 11月15日(金)
会場: リーガロイヤルホテル京都
出席者: 約120名(日中韓の政府関係者、専門家及び一般参加者)
内容: 日中韓3カ国から、それぞれの国の化学物質管理制度の最新動向に関する発表がなされました。これらの発表について参加者からの質疑を受け、活発な情報・意見交換がなされました。
4. 次回開催予定
次回の本会合は、来年、韓国において開催される予定です。
第7回日中韓における化学物質管理に関する政策ダイアローグの結果について(お知らせ)
11月13日(水)から15日(金)まで、「第7回日中韓における化学物質管理に関する政策ダイアローグ」(以下「化学物質政策ダイアローグ」という。)を京都市で開催しました。
11月14日に開催された日本、中国及び韓国の政府関係者による政府事務レベル会合では、3カ国の最新の化学物質管理政策、化学物質管理に関する国際動向への対応等に関する情報交換及び意見交換が行われました。今後、来年度の会合に向け、PRTRに関する技術的事項について会期間に情報交換を行うこと等について合意されました。
また、これに先立ち11月13日に開催された専門家会合では、日中韓3カ国の専門家による化学物質に係る生態毒性試験に関する共同研究や化学物質のリスク評価手法等について意見交換が行われました。そして、11月15日には、日中韓の化学物質管理政策に関する公開セミナーを開催しました。
次回の化学物質政策ダイアローグは、来年、韓国において開催される予定です。
1. これまでの経緯
平成18年12月に開催された第8回日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM8)において「化学物質管理に関する政策や規制に関する情報交換の推進」について合意されたことを受け、化学物質政策ダイアローグが、これまでに6回(平成19年(日本・東京)、平成20年(韓国・ソウル)、平成21年(中国・北京)、平成22年(日本・東京)、平成23年(韓国・済州島)、平成24年(中国・杭州))開催されました。
2. 概要
日時: 11月13日(水)~11月15日(金)
場所: 京都市
出席者:
中国: 環境保護部化学品登記中心Gao課長ほか
韓国: 環境部化学物質管理課Choung課長補佐ほか
日本: 環境省木村化学物質審査室長、国立環境研究所白石環境リスク研究センターフェロー、菅谷環境科学専門員ほか
3. 政策ダイアローグの結果
1日目) 中韓の化学物質管理に関する専門家会合
日時: 11月13日(水)
会場: 京都リサーチパーク
出席者: 18名(日中韓の政府関係者及び専門家等)
内容: 日中韓3カ国の専門家による化学物質に係る生態毒性試験に関する共同研究の進捗の報告、中国のGLP施設への現地調査の結果、定量的構造活性相関(QSAR)等の化学物質のリスク評価手法について意見交換が行なわれました。
今後、甲殻類及び魚類の生態毒性試験に関する共同研究を実施すること、韓国の試験施設への日本及び中国の専門家による訪問を来年上半期に実施するとともに、その際に3カ国の共同研究に関する会合を行うこと等について合意されました。
2日目) 日中韓政府事務レベル会合
日時: 11月14日(木)
会場: 京都リサーチパーク
出席者: 25名(日中韓の政府関係者及び専門家等)
内容: 日中韓の政府関係者により、3カ国の化学物質管理政策の最新動向として、化学物質管理に関する法律等の制定状況及び施行状況、環境リスクの評価方法等について活発な意見交換が行われるとともに、SAICM、POPs、水銀に関する水俣条約等の化学物質管理に関する国際動向への対応等について情報交換がなされました。
次回の会合では、化学物質管理に関する政策の最新の動向、特に、SAICM、水銀、リスク評価等に関する政策の状況について意見交換を行うこと、また、PRTRに関する技術的事項について会期間に情報交換を行い、必要に応じ、次回の専門家会合において議論すること等について合意されました。
3日目) 日中韓の化学物質管理政策に関するセミナー
日時: 11月15日(金)
会場: リーガロイヤルホテル京都
出席者: 約120名(日中韓の政府関係者、専門家及び一般参加者)
内容: 日中韓3カ国から、それぞれの国の化学物質管理制度の最新動向に関する発表がなされました。これらの発表について参加者からの質疑を受け、活発な情報・意見交換がなされました。
4. 次回開催予定
次回の本会合は、来年、韓国において開催される予定です。
2013年11月13日
「特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン及び保護管理の手引き(カワウ編)」について
平成25年11月8日
「特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン及び保護管理の手引き(カワウ編)」について(お知らせ)
平成16年に作成した「特定鳥獣保護管理計画技術マニュアル(カワウ編)」について、その後の状況の変化等を踏まえ、大幅に見直し、「特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン及び保護管理の手引き(カワウ編)」として取りまとめましたのでお知らせいたします。
1.概要
特定鳥獣保護管理計画制度は、地域的に著しく増加または減少している野生鳥獣の個体群の科学的・計画的な保護管理の実施により人と鳥獣との共生を図る目的で、平成11年に創設され、平成25年4月1日現在、46都道府県で6種(カワウ、イノシシ、カモシカ、クマ類、ニホンザル、ニホンジカ)について127計画が作成されています(カワウ作成県:福島県、滋賀県)。
この特定鳥獣保護管理計画を都道府県が作成する際の技術的な参考となる資料が特定鳥獣保護管理計画技術マニュアルです。カワウ以外の5種のマニュアルについては、平成12年に作成し、平成22年に「特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン」として改訂を行っています。カワウのマニュアルについては平成16年に公表しましたが、その後多くの知見が集積されたことから、現行のマニュアルをより具体的かつ実践的な内容とすべく、見直しを行いました。
2.検討経緯
本冊子の取りまとめにあたっては、平成24年度に設置したカワウ保護管理検討会(※以下URLを参照)において検討を行いました。また、関係団体等へのヒアリングや、パブリックコメントを実施し、得られた意見を参考にして「特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン及び保護管理の手引き(カワウ編)」として取りまとめました。
※
カワウ保護管理検討会
http://www.env.go.jp/nature/choju/conf/conf_wp.html#conf01
3.本冊子の内容について
本冊子は、現行のマニュアル作成後に蓄積された生息状況や技術的なノウハウ等を踏まえ、以下のとおり『ガイドライン』と『保護管理の手引き』の2部構成としました(※)。
『ガイドライン』は、生態や行動等、カワウの特性について触れた上で、被害状況に応じた保護管理手法の考え方、関係者や広域的対応を含めた体制整備等の保護管理に必要なエッセンスを簡潔に示しています。
『保護管理の手引き』は、カワウ問題の解決に向けた被害対策の進め方について、フローチャートによって被害地域の状況を大まかに分類した上で、技術編と資料編において、実施すべき方策を事例とともに詳しく紹介しています。
【本冊子の特徴】
○
「ガイドライン」と「保護管理の手引き」の2部構成としたことにより、カワウの保護管理の全体像が掴みやすく、行政担当者だけでなく漁協関係者等、各現場でカワウ問題に取り組む様々な方にも活用できるような内容としました。
○
フローチャートの導入により、地域の状況を分かりやすく診断でき、フェーズごとに今何をすればよいかを詳しく解説しています。
○
現状に即したカワウの保護管理の基本的考え方を整理するとともに、平成16年の技術マニュアル以降に見出された保護管理に関する最新の知見を盛り込み、豊富な成功事例とともに紹介しています。
<成功事例の例>
・
ビニールひも張りによるカワウの分布管理の取組の事例
・
カワウによる漁業被害の把握(算定)方法の詳細な紹介
・
モニタリングや捕獲、植生被害対策など、総合的な取組の事例
・
竹ぶせ・粗朶の設置などによる生息環境管理の取組の事例 など
各現場でカワウ問題に取り組む地方公共団体のご担当者や漁協関係者が活用できるよう、より具体的かつ実践的な内容に見直しを行いましたので、積極的にご活用いただければ幸いです。
なお、本冊子の内容や使い方を分かりやすく説明するため、別添のパンフレットを作成しておりますので、ご参照ください。
※
本冊子の全文(全202頁)は環境省ホームページに準備が整い次第掲載いたします。
(URL)http://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan3-2f/index.html
4 添付資料
パンフレット:「-カワウの被害が減っていく-計画が導く確かな管理へ」
「特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン及び保護管理の手引き(カワウ編)」について(お知らせ)
平成16年に作成した「特定鳥獣保護管理計画技術マニュアル(カワウ編)」について、その後の状況の変化等を踏まえ、大幅に見直し、「特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン及び保護管理の手引き(カワウ編)」として取りまとめましたのでお知らせいたします。
1.概要
特定鳥獣保護管理計画制度は、地域的に著しく増加または減少している野生鳥獣の個体群の科学的・計画的な保護管理の実施により人と鳥獣との共生を図る目的で、平成11年に創設され、平成25年4月1日現在、46都道府県で6種(カワウ、イノシシ、カモシカ、クマ類、ニホンザル、ニホンジカ)について127計画が作成されています(カワウ作成県:福島県、滋賀県)。
この特定鳥獣保護管理計画を都道府県が作成する際の技術的な参考となる資料が特定鳥獣保護管理計画技術マニュアルです。カワウ以外の5種のマニュアルについては、平成12年に作成し、平成22年に「特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン」として改訂を行っています。カワウのマニュアルについては平成16年に公表しましたが、その後多くの知見が集積されたことから、現行のマニュアルをより具体的かつ実践的な内容とすべく、見直しを行いました。
2.検討経緯
本冊子の取りまとめにあたっては、平成24年度に設置したカワウ保護管理検討会(※以下URLを参照)において検討を行いました。また、関係団体等へのヒアリングや、パブリックコメントを実施し、得られた意見を参考にして「特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン及び保護管理の手引き(カワウ編)」として取りまとめました。
※
カワウ保護管理検討会
http://www.env.go.jp/nature/choju/conf/conf_wp.html#conf01
3.本冊子の内容について
本冊子は、現行のマニュアル作成後に蓄積された生息状況や技術的なノウハウ等を踏まえ、以下のとおり『ガイドライン』と『保護管理の手引き』の2部構成としました(※)。
『ガイドライン』は、生態や行動等、カワウの特性について触れた上で、被害状況に応じた保護管理手法の考え方、関係者や広域的対応を含めた体制整備等の保護管理に必要なエッセンスを簡潔に示しています。
『保護管理の手引き』は、カワウ問題の解決に向けた被害対策の進め方について、フローチャートによって被害地域の状況を大まかに分類した上で、技術編と資料編において、実施すべき方策を事例とともに詳しく紹介しています。
【本冊子の特徴】
○
「ガイドライン」と「保護管理の手引き」の2部構成としたことにより、カワウの保護管理の全体像が掴みやすく、行政担当者だけでなく漁協関係者等、各現場でカワウ問題に取り組む様々な方にも活用できるような内容としました。
○
フローチャートの導入により、地域の状況を分かりやすく診断でき、フェーズごとに今何をすればよいかを詳しく解説しています。
○
現状に即したカワウの保護管理の基本的考え方を整理するとともに、平成16年の技術マニュアル以降に見出された保護管理に関する最新の知見を盛り込み、豊富な成功事例とともに紹介しています。
<成功事例の例>
・
ビニールひも張りによるカワウの分布管理の取組の事例
・
カワウによる漁業被害の把握(算定)方法の詳細な紹介
・
モニタリングや捕獲、植生被害対策など、総合的な取組の事例
・
竹ぶせ・粗朶の設置などによる生息環境管理の取組の事例 など
各現場でカワウ問題に取り組む地方公共団体のご担当者や漁協関係者が活用できるよう、より具体的かつ実践的な内容に見直しを行いましたので、積極的にご活用いただければ幸いです。
なお、本冊子の内容や使い方を分かりやすく説明するため、別添のパンフレットを作成しておりますので、ご参照ください。
※
本冊子の全文(全202頁)は環境省ホームページに準備が整い次第掲載いたします。
(URL)http://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan3-2f/index.html
4 添付資料
パンフレット:「-カワウの被害が減っていく-計画が導く確かな管理へ」
2013年11月13日
インベントリータスクフォース(TFI)とその技術支援ユニット(TSU)
1997年12月のUNFCCC COP3(地球温暖化防止京都会議)において先進国の温室効果ガス排出量の削減目標を定めた京都議定書が採択されたことを背景として、IPCCは1998年10月の第14回全体会合において、国別温室効果ガスインベントリーに関するタスクフォース(TFI)を設立することを決定した。同決議と日本政府からの拠出金提供の申し出に従い、1999年9月に、IPCC-TFIのための技術支援ユニット(TSU)が財団法人(現・公益財団法人)地球環境戦略研究機関(IGES)に設置された。以後、今日に至るまで、IPCC-TFIのTSUはIGESにて活動を続けており、日本政府による資金支援を得て、温室効果ガスインベントリーの作成方法に関するガイドラインやそのソフトウェア等の開発・普及活動を行っている。
2013年11月13日
IPCC 気候変動に関する政府間パネル
IPCCは、1988年に世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)により設立された気候変動問題(地球環境問題)に関する世界規模の科学者のネットワークであり、
・ 気候変動の化学、影響、経済的側面、緩和あるいは適応のための方策についての評価
・ 温室効果ガスインベントリーのためのガイドラインなど方法論の評価及び開発
・ 国連気候変動枠組条約(UNFCCC)締約国会議(COP)やその補助機関の要請に応じた科学的・技術的・社会経済的な助言などの活動を行っている。
2013年11月12日
Opening speech by the President of COP19 Mr. Marcin Koro
(ポーランドのMarcin Korolec環境大臣)
2013年11月11日
閣下、 COP18の社長、 - アブドラ·ビン·ハマド·アル·ティーヤ。
気候変動に関する国際連合枠組条約の識別事務局長 - マダムクリスティフィゲラス。
閣下!識別代議員!ご列席の皆様!友人!
私は過去12ヶ月間彼の仕事のためにCOP18の発信社長、ミスターアルティーヤに感謝したいと思いますまず第一にあなたの献身がなければドーハから結果は不可能だったでしょう。ありがとう。
もちろん、私はここに私たちの作業は容易なものであろうとは言わないよ。しかし、これは気候変動交渉の現実であり、私は私たちのすべてが、私より先に何か認識している。ちょっと見我々が対処しなければならないものの両極端。
一部が商業上のスペースに移動する自分自身を準備しながら新しいスマート電話が、より頻繁に充電するために、世界の別の部分を必要とする理由の惑星の一部は不思議、そして13億の人々は、正確には、電気へのアクセスなしで残っている。 、いつ26億周りの便が、まだ調理設備をきれいにするためのアクセスを欠いている。
それが十分に複雑ではなかった場合、我々はすべての。脅かす気候変動を経験して景観を変える、私たちの通常の方法から私たちを強制的に。殺している。
唯一の二日前に、強力な台風が自宅から避難民の数千数百人を残して、数千人の命を主張し、フィリピンを襲った。偉大な人間の悲劇。忘れられない、痛みを伴う、目覚めを。
私はそれはまだ我々は人間と自然の間のこの不平等な闘争を失っていることがもう一つの証拠であるので、それはまだ、再び私たちのより良いを得た。目覚め言う、我々はランクを閉じて打つために一緒に行動していない場合、将来的にそうし続けるバック。
気候変動はグローバルな問題で、同時に世界的な問題とグローバルな機会です。それはまた、我々は協調した方法で行動することができない場合は問題です。我々は一緒に行動する能力を実証したときにそれは機会となります。一つの国、あるいはグループができません違いを生む。しかし、我々はここにいるとして、我々はそれを行うことができます統一、一緒に演技。
あなたは言うかもしれない: "しかし、我々はすべて異なっています"はい、しかし、私たちは有利にこの事実を回すことができるあなたは、誰が私たちのすべては、より良い明日のためにこのクエストでの努力と同じレベルの貢献期待していないことを非常によく知っているが、そこに。 。 。常に各当事者は、テーブルに持って来ることができるものです。私たち一人一人が固有の強さを持っており、我々はすべて私たちの惑星を治すために行うことを医学の1成分を提供することができます。
私はここでワルシャワのあなたを約束することができて、次の12ヶ月間、私はコンセンサスを見つけるために努力を惜しまないでしょう。これは、当事者主導のプロセスですが、それはファシリテーターを必要としています。私はあなたに透明性を約束します私は、包括的なプロセスをお約束します。これらは、私たちは新たな合意のための強固な基盤を築く手助けするための条件を作成するには、私の最優先、私は私の役割を果たす準備ができているように私の国、ポーランドである - 。連帯への献身のために知られています。
私たちは、私は彼らの助けを借りて。我々は非常によく、これはチームの努力でご存知のように。私を助けるためにペルーとフランスからの私の同僚を持っている。これだけではないですが、何よりもまず、あなたの助けを借りて、私たちも、のいずれかを対処するために望むことができる気候変動など人類にとって最も困難な問題は、 。
ご列席の皆様、私はあなたに良いCOPをお祈りしております。
H.E.マルチンKorolec 、 COP19/CMP9の社長
2013年11月11日
閣下、 COP18の社長、 - アブドラ·ビン·ハマド·アル·ティーヤ。
気候変動に関する国際連合枠組条約の識別事務局長 - マダムクリスティフィゲラス。
閣下!識別代議員!ご列席の皆様!友人!
私は過去12ヶ月間彼の仕事のためにCOP18の発信社長、ミスターアルティーヤに感謝したいと思いますまず第一にあなたの献身がなければドーハから結果は不可能だったでしょう。ありがとう。
もちろん、私はここに私たちの作業は容易なものであろうとは言わないよ。しかし、これは気候変動交渉の現実であり、私は私たちのすべてが、私より先に何か認識している。ちょっと見我々が対処しなければならないものの両極端。
一部が商業上のスペースに移動する自分自身を準備しながら新しいスマート電話が、より頻繁に充電するために、世界の別の部分を必要とする理由の惑星の一部は不思議、そして13億の人々は、正確には、電気へのアクセスなしで残っている。 、いつ26億周りの便が、まだ調理設備をきれいにするためのアクセスを欠いている。
それが十分に複雑ではなかった場合、我々はすべての。脅かす気候変動を経験して景観を変える、私たちの通常の方法から私たちを強制的に。殺している。
唯一の二日前に、強力な台風が自宅から避難民の数千数百人を残して、数千人の命を主張し、フィリピンを襲った。偉大な人間の悲劇。忘れられない、痛みを伴う、目覚めを。
私はそれはまだ我々は人間と自然の間のこの不平等な闘争を失っていることがもう一つの証拠であるので、それはまだ、再び私たちのより良いを得た。目覚め言う、我々はランクを閉じて打つために一緒に行動していない場合、将来的にそうし続けるバック。
気候変動はグローバルな問題で、同時に世界的な問題とグローバルな機会です。それはまた、我々は協調した方法で行動することができない場合は問題です。我々は一緒に行動する能力を実証したときにそれは機会となります。一つの国、あるいはグループができません違いを生む。しかし、我々はここにいるとして、我々はそれを行うことができます統一、一緒に演技。
あなたは言うかもしれない: "しかし、我々はすべて異なっています"はい、しかし、私たちは有利にこの事実を回すことができるあなたは、誰が私たちのすべては、より良い明日のためにこのクエストでの努力と同じレベルの貢献期待していないことを非常によく知っているが、そこに。 。 。常に各当事者は、テーブルに持って来ることができるものです。私たち一人一人が固有の強さを持っており、我々はすべて私たちの惑星を治すために行うことを医学の1成分を提供することができます。
私はここでワルシャワのあなたを約束することができて、次の12ヶ月間、私はコンセンサスを見つけるために努力を惜しまないでしょう。これは、当事者主導のプロセスですが、それはファシリテーターを必要としています。私はあなたに透明性を約束します私は、包括的なプロセスをお約束します。これらは、私たちは新たな合意のための強固な基盤を築く手助けするための条件を作成するには、私の最優先、私は私の役割を果たす準備ができているように私の国、ポーランドである - 。連帯への献身のために知られています。
私たちは、私は彼らの助けを借りて。我々は非常によく、これはチームの努力でご存知のように。私を助けるためにペルーとフランスからの私の同僚を持っている。これだけではないですが、何よりもまず、あなたの助けを借りて、私たちも、のいずれかを対処するために望むことができる気候変動など人類にとって最も困難な問題は、 。
ご列席の皆様、私はあなたに良いCOPをお祈りしております。
H.E.マルチンKorolec 、 COP19/CMP9の社長
2013年11月12日
COP19 日本も長期的な地球温暖化対策を示せ
http://blogos.com/article/73397/
記事 木村正人氏 2013年11月11日 08:10
「2005年比3.8%減」
地球温暖化対策を協議する国連気候変動枠組み条約第19回締約国会議(COP19)が11日、ポーランドの首都ワルシャワで開幕、日本は、2020年までの温室効果ガス削減目標として「05年比3.8%減」を新たに表明する見通しだと日本経済新聞などが伝えている。
多国間協調主義を掲げたオバマ米大統領がさっそうと乗り込んだ2009年、コペンハーゲンでのCOP15は先進国と新興国、産油国などの思惑が入り乱れ、事実上決裂した。会議はこれまでに、すべての締約国が参加する新しい削減の枠組みを15年までに採択し、20年に発効させることで合意している。
COP19 では、どこまで合意に向けた議論が進むのかが注目されている。国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)も9月、第5次評価報告書を公表、「人間活動が20世紀半ば以降に観測された温暖化の主な要因であった可能性が極めて高い」と結論づけて、議論を後押しした。
気候変動枠組条約(UNFCCC)のクリスティーナ・フィゲレス事務局長が10月下旬、ロンドンのシンクタンク、英王立国際問題研究所(チャタムハウス)で記者会見した際、筆者は「日本は東日本大震災の福島第1原発事故で原発の再稼働が難しくなっている。再生可能エネルギーはコストが高い。ガス火力発電に頼れば、温暖化対策が後退するが、どう思うか」と質問してみた。
UNFCCC事務局長は日本に配慮
フィゲレス氏は「国連が口出しすることではなく、各国の判断だ。私たちは日本の電気代が上昇する一方で、日本がすでに十分に効率化しているエネルギー効率をさらに上げていることを理解している。日本が大災害で被った深刻な影響を考慮しなければならない。日本がどのように電気代のコスト上昇をやわらげながら、長期的なエネルギーモデルを構築していくのか、国際社会は注視している」と答えた。
短・中期的に日本の温暖化対策が後退するのはやむを得ないが、長期的には温暖化対策と電気代コストのバランスを十分に考慮した日本独自のエネルギー政策の策定が不可欠だとの考えを示したものだ。
09年に民主党の鳩山由紀夫首相(当時)が表明した「2020年までに温室効果ガスの排出量を1990年比で25%削減する」という目標に比べると、「05年比3.8%減」という安倍政権の目標は90年比換算では「約3%増」になるという(産経新聞)。
日本では福島の原発事故で原発再稼働の見通しもつかなくなり、温暖化対策の大幅な見直しを余儀なくされた。一方、他の先進国では、コペンハーゲンのCOP15で見られた温暖化懐疑派の動きがさらに大きくなってきたような印象を受ける。
動き出した温暖化懐疑派
オーストラリアのハワード元首相は11月5日、ロンドンで記者会見し、IPCCの第5次評価報告書が「過去15年の世界平均地上気温の上昇率は1951~2012年の上昇率より小さい」と指摘していることをとらえて、温暖化対策を進めすぎることに異論を唱えた。
ハワード元首相の言い分は次の通りだ。
(1)(地球が温暖化しているという)前提付きの科学を受け入れるな。新たな研究結果にも目を向けろ。
(2)現世代だけではなく、未来世代も公平に温暖化対策の負担を分け合うべきだ。
(3)再生可能エネルギーは採算が合う場合に限り、使用すべきだ。
(4)原子力は長期的に見て重要なエネルギー源だ。
(5)新しい技術でシェールガスの採掘が可能になったように、技術は常に進歩し続ける。
オーストラリアでは、ハワード元首相と同じ自由党のアボット首相率いる保守連合政権が、労働党前政権の導入した炭素税の撤廃に着手している。「シェールガス革命でオバマ大統領の温暖化対策は変わると思うか」という筆者の質問に、ハワード元首相はこう答えた。
「2月の一般教書演説で、オバマ大統領は(温室効果ガスの排出量に制限を設けて取引する)キャップ・アンド・トレードへの強いコミットメントを改めて示したが、野党の共和党だけでなく、与党の民主党にも根強い抵抗がある」
ハワード元首相は、米国の温暖化対策はオバマ大統領が考えているようには進まないとみている。元首相の主張は、IPCCの第5次評価報告書と比べるととても科学的とは言えないが、英国の与党・保守党内にもハワード元首相と同じような考え方を持つ政治家が増え始めている。
一変した環境
09年のCOP15当時と比べて、温暖化対策の議論を取り巻く環境は一変した。
(1)世界金融危機を境に、先進国の「成長の限界」が浮き彫りになってきた。
(2)米国でシェールガスの開発が進んだ。
(3)再生可能エネルギーを促進する欧州でエネルギーコストがかさみ、国際競争力の低下が指摘されるようになった。
(4)風力発電や太陽光発電への投資コストが膨らみ、消費者への電気代が上昇した。
(5)温室効果ガスの排出量削減の数値目標が設定できないため、温暖化対策の切り札とみられてきた排出量取引市場は事実上、崩壊した。
英国のキャメロン首相は野党党首時代、北極にまで出かけて行って温暖化対策を進めるグリーン政策をPRしたが、今や風力発電の建設にブレーキをかけ、シェールガス開発に傾斜する。
労働党のミリバンド党首が電気・ガス料金の据え置き政策を掲げて支持率を上げると、キャメロン首相は電気・ガス料金に含まれるグリーン関係費の見直しを表明した。これは、これまでの英国の温暖化対策を見直すと言っているのに等しい。
労働党のブレア元英首相の経済・財政政策「第三の道」を提唱したロンドン・スクール・オブ・エコノミクスのギデンズ前学長はポピュリズムに走ったミリバンド党首について、「愚かな政策だ。コストがかかっても再生可能エネルギーを促進する必要がある。これでは、欧州がリードしなければならない温暖化対策が後退する恐れがある」と非難した。
政治と科学の闘い
IPCCの第 5 次評価報告書はこう指摘している。
・ 気候システムの温暖化については疑う余地がない。
・ 過去40年間で海洋の上部で水温が上昇していることはほぼ確実である。
・ 過去20年にわたり、グリーンランドや南極の氷床は減少、氷河はほぼ世界中で縮小し続けている。北極の海氷面積も減少し続けている。
・今世紀末における世界平均地上気温の変化は最悪シナリオで摂氏2.6~4.8度上昇する可能性が高い。
ハワード元首相は「気候変動問題では科学が政治家のように振舞っている」と非難したが、筆者には「IPCCの指摘が現実になった時のリスクは未来世代に先送りしてしまえ」と言っているようにしか聞こえなかった。
政治家は現在の有権者の付託を受けている。しかし、政治家は未来世代の声にも耳を澄ますべきだろう。安倍政権が示した「05年比3.8%減」は緊急避難策として仕方がないとしても、長期的なエネルギー政策を国内外に示す必要がある。
石油や天然ガスを輸入に頼る日本にとって当面、原発の安全性を慎重に確認した上で、再稼働させる以外にとるべき道はないと筆者は考える。風力発電や太陽光発電の大規模導入には「地の利」が必要だ。日本近海の地形が、欧州のように洋上風力発電所の建設に適しているとは思えない。
エネルギーの輸入コストがかさみ、日本の貿易収支はすでに赤字に転じている。経常収支が赤字に転落したとき、日本の財政は、経済はどうなるのだろう。地球温暖化は国際社会が1つになって取り組むべき問題だ。日本は原発の安全性を確保し、長期的に持続可能な経済・エネルギーモデルを示すことで温暖化対策の議論をリードする責任を負っているのではないだろうか。
(おわり)
2013年08月12日
平成25年度技術士第ニ次試験問題〔環境部門〕Ⅰ
I-1 2012年6月、ブラジルのリオデジャネイロで開かれた「国際連合持続可能な開発会議」(リオ+20)において採択された成果文章「我々が望む未来」の内容に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
①グリーン経済は、持続可能な開発を達成する上で重要な手段の1つであると認識し、グリーン経済への移行に関する行程表作成に着手する。
②国連環境計画(UNEP)の役割を強化することにコミットする。
③持続可能な開発目標(SDGS)に関する包括的且つ透明な政府間交渉プロセスの立ち上げに合意する。
④多数の先進諸国による、開発途上国向けのODAをGNP比0.7%とする目標を2015年までに達成することが極めて重要であると認める。
⑤環境に配慮した技術の開発、適応、普及及び移転を可能にするように状況を整えることの必要性を強調する。
正解①
○リオプラス20:「グリーン経済」議長案、移行行程表を断念
http://mainichi.jp/feature/news/20120619ddm008040023000c.html
I-2 次のうち、環境と経済は、対立するものではなく両立するという考え方に最も近い内容を表した用語はどれか。
① 調和条項の削除
② 企業の社会的責任(CSR)
③ 汚染者負担原則(PPP)
④ ポーター仮説
⑤ 環境クズネッツ曲線
正解④
I-3 次のうち、環境関連の条約等とその関係国内法の組合せとして、最も不適切なものはどれか。
① バーゼル条約・・・「特定有害廃棄物等の輸出等の規制に関する法律」
② ワシントン条約・・・「絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律」
③ ウィーン条約モントリオール議定書・・・「水質汚濁防止法」
④ 南極条約議定書・・・「南極地域の環境の保護の関する法律」
⑤ MARPOL条約・・・「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」
正解③
ウイーンとモントリオール オゾン。
I-4 我が国を中心とした資源循環に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
① 3Rイニシアティブは、アジアにおいて我が国の経験を生かし3Rを通じて循環型社会の構築を目指すものである。
② パソコンのリサイクルは、「特定家庭用機器再商品化法」等の法に基づくものではなく、業界が自主的に行っている。
③ 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に基づき分別収集したペットボトルは、市町村が自らの判断で売却先を選定できる。
④ ガラスびんは使用済みのびんを砕いたカレットがリサイクルされており、新びんの生産におけるカレットの使用量と利用率は、平成18年から平成23年の期間では、ともに増大している。
⑤ 前世紀末からリサイクルを目的とした再生資源等の国際移動が活発化し、例えば、プラスチックくずの輸出量は、平成10年から平成17年の期間では毎年増加していた。
正解⑤
I-5 地球温暖化対策に関連した次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく特定機器のうち、エアコン、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、蛍光灯器具、テレビ、ストーブ、ガス調理機器、ガス温水器、石油温水機器、電子計算機等は、省エネラベリング制度(省エネ性能表示に関する制度)に関するJIS規格の対象機器である。
② 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」は、再生可能エネルギー源を用いて発電した電気を、国が定める価格で一定期間電気事業者が買い取ることを義務づけている。
③ 「地球温暖化対策の推進に関する法律」では、都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策定するものとしている、
④ 平成25年3月15日に閣議決定された「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」において、「京都議定書目標達成計画」は「地球温暖化対策目標達成計画」に改められている。
⑤ 国連気候変動枠組条約第18回締約国会議(COP18)では、クリーン開発メカニズム(CDM)については、第二約束期間に参加しない国もCDMプロジェクトに参加して2013年以降のCDMクレジット(CER)を原始取得(自国に転送)することが可能であることが確認された。
正解④
I-6 都道府県知事か行う公共用水域の常時監視のための水質調査では、調査項目を回数のほか、調査時期や採水地点について環境省の「水質調査方法」が準拠すべき原則として示されている。次のうち、調査時期や採水地点の選定で最も不適切なものはどれか。
① 河川の調査の時期は、低水量時、水利用が行われている時期を含めるものとする。
② 河川では、土地利用形態での市街地面積比率の増大を考慮して、非特定汚染源(面源負荷)からの流出影響の見られる降雨流出時の調査を含める。
③ 湖沼では、停滞期と循環期の水質が著しく異なるため、その両期の水質を測定するよう配慮する。
④ 湖沼では、河川が流入した後十分混合する地点及び流入河川の流入前の地点を考慮して選定する。
⑤ 海域では、水質が水利用に悪影響を及ぼす時期を含めるものとする。
正解②
I-7 環境騒音の表示・測定方法(JIS Z 8731:1999)における騒音の種類の分類に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① レベル変化が小さく、ほぼ一定とみなされる騒音を定常騒音という。
② レベルが不規則かつ連続的にかなりの範囲にわたって変化する騒音を連続騒音という。
③ 間欠的に発生し、一回の継続時間が数秒以上の騒音を間欠騒音という。
④ 継続時間が極めて短い騒音を衝撃騒音という。
⑤ 個々に分離できる衝撃騒音を分離衝撃騒音という。
正解②
I-8 化学分析方法通則(JIS K 0050:2005)の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① “10~15℃”のように 温度範囲を表す場合は、範囲の最低値は1けた下の目盛りの数値を切り捨てた温度を、最高値は切り上げた温度を意味する。
② 容量分析は、滴定操作により分析種を定量する分析方法である。滴定中に生じる化学反応の種類によって、中和滴定(酸塩基滴定)、酸化還元滴定及び沈殿滴定の3種類に区分される。
③ 化学分析に用いる水は、その温度によって、冷水(15℃以下の水)、温水(40~60℃の水)、熱水(60℃以上の水)に区分する。
④ 質量分率、体積分率及びモル分率を用いて分析結果を記述する場合は、いずれの場合も、容積、容量又は質量を含む表記を用いてはならない。また、体積を用いた記述にはどのような体積であるかを明示する。
⑤ 試験場所における標準温度は、20℃とする。試験場所の温度は、常温(20±5℃)又は室温(20±15℃)のいずれかとする。
正解②
I-9 粒径2.5μm以下の浮遊粒子状物質(PM2.5)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① PM2.5は、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分流装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子としている。
② PM2.5の日平均値として70μg/m3を超えた場合には、不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らすという、注意喚起のための暫定的な指針が示されている。
③ 人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として、年平均値15μg/m3以下かつ日平均値35μg/m3以下と設定されている。
④ 大気汚染防止法に基づく工場・事業場等のばい煙発生施設の規制や自動車排出ガス規制などにより、浮遊粒子状物質(SPM)とPM2.5の国内での発生量は削減されてきたが、北東アジアからの越境大気汚染の影響により、PM2.5の我が国における年間の平均的な濃度は平成13年から平成22年までは増加傾向にあった。
⑤ PM2.5の自動測定機は日平均値については標準的な測定法による濃度と等価であることが認められているものの、1時間値の精度については確認されていない。1時間値を使用するには、複数測定局を対象として1時間値の複数時間の平均値を計算して、それらの中央値を求めるなどにより、1時間値の確からしさを高めるための工夫が必要である。
正解④
I-10 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法に関する次の記述の、( )に入る語句の組合せとして最も適切なものはどれか。
「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年環境庁告示13号)は、廃棄物に起因する( ア )への有害物質の汚染を未然に管理し、( イ )場へ搬入する廃棄物からの有害物質の( ウ )の規制を目的としている。この検定方法は、産業廃棄物を( イ )する際に、陸上・海上埋立及び( エ )における廃棄物からの水溶性有害物質濃度に対して基準値等を設定した検定方法である。
ア イ ウ エ
① 土壌 中間処分 溶出量 焼却
② 土壌 最終処分 含有量 海上投入処分
③ 公共用水域 中間処分 含有量 海上投入処分
④ 公共用水域 最終処分 溶出量 海上投入処分
⑤ 公共用水域 中間処分 溶出量 焼却
正解④
I-11 最も多くの種を保全するための自然保護区のデザイン原則のうち、生物にとって最も不適切なものはどれか。
① 面積に大差ないのであれば、塊上に分散させず、線上に分散させて配置する。
② 小さな数個のまとまりとするより、大きな1つの塊として配置する。
③ 同じ面積であれば、なるべくまとまりのある円に近い形状のものとする。
④ 面積はできるだけ大きく確保する。
⑤ 分断孤立化させないで近接させ、相互に関連づけるように配置する。
正解①
I-12 外来種(移入種)とその外来種による問題の組合せとして、最も適切なものはどれか。
① ジャワマングース・・・大雪山国立公園に生息するナキウナギ等の捕食
② オオクチバス・・・西表石垣国立公園のサンゴ礁に生息する魚類の補食
③ ノヤギ(野生化したヤギ)・・・小笠原国立公園に生息する植物の食害
④ タイリクバラタナゴ ・・・阿寒国立公園の湖沼に生息する魚類の補食
⑤ セイヨウオオマルハナバチ・・・中部山岳国立公園に生育する高山植物の食害
正解③
I-13 我が国で見られる動物及び植物に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① ヒグマは、北海道の森林原野に生息し、夏から秋には中央山地帯では高山植物帯にも出没する。雑食性で、餌となる動植物は150種類以上に達する。12月中旬から4月末まで冬眠する。
② ニホンカモシカとニホンジカはともに草食(植食)動物で、足跡や糞の形が似ているが、分類上の科は異なり、ニホンカモシカはウシ科、ニホンジカはシカ科である。
③ 雑木林の林床や林縁などに生えるカタクリは、春に開花したあと夏までには地上部が消え、次の春までは地下部のみで過ごす。このような植物は「春植物」(スプリング・エフェメラル)と呼ばれている。
④ シラカンバは陽樹で、伐採跡や山火事跡、あるいは湿原の周辺部など日当たりの良い場所に生える。裸地化したところに素早く進出して森林を作ることから、「先駆樹」(パイオニア)と呼ばれることがある。
⑤ 黄色い花が「月」と思わせることから、一般には「月見草」と呼ばれて親しまれているメマツヨイグサやオオマツヨイグサは、我が国固有の植物である。
正解⑤
I-14 自然環境保全に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき国内希少野生動植物を指定し、その個体の繁殖の促進、生息地等の整備等の事業の推進をする必要があると認める場合は、保護増殖事業計画を策定して、保護増殖の事業を行っている。
② 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」では、我が国の在来生物であっても、国内の他地域に移入されることで、生態系、遺伝子資源等に危機を及ぼすおそれのある種を、特定外来生物に指定し移入等を規制している。
③ 「自然環境保全法」に基づく保護地域には、国が指定する原生自然環境保全地域と自然環境保全地域、都道府県が条例により指定する都道府県自然環境保全地域がある。
④ 「鳥獣の保護および狩猟の適正化に関する法律」に基づき、鳥獣の保護を図るため特に必要がある区域を国指定鳥獣保護区に指定している。
⑤ 「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(以下「ラムサール条約」)では、国際的に重要な湿地をラムサール条約湿地として登録している。
正解②
I-15 平成24年度に行われた国のレッドリストの見直しで、カテゴリー(ランク)の変更が行われた生物に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① カテゴリー外のハマグリは、各地で漁獲量が減少していることから、絶滅危惧Ⅱ類(VU)とされた。
② 野生絶滅(EW)のトキは、再導入個体の繁殖が確認されたが、カテゴリーの変更は行われなかった。
③ 絶滅(EX)のクニマスは、山梨県西湖での再発見があり、野生絶滅(EW)とされた。
④ 情報不足(DD)のニホンウナギ(旧和名:ウナギ)は、漁獲量データの減少率から絶滅危惧IB類(EN)とされた。
⑤ 絶滅危惧IA類(CR)のニホンカワウソ(北海道亜種)とニホンカワウソ(本州以南亜種)は、ともに最後の生息確認記録から30年以上が経過しているが、カテゴリーの変更は行われなかった。
正解⑤
I-16 環境影響評価において、騒音・振動の環境保全目標値として環境基準や規制基準等を採用しているが、次のうち、最も不適切なものを選べ。
① 騒音に係る環境基準
② 振動に係る環境基準
③ 航空機騒音に係る環境基準
④ 振動規制法に基づく特定工場等の規制基準
⑤ 在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針
正解②
I-17 環境影響評価において、通常行われている騒音・振動の予測評価手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 1日の離着陸回数が10回以下の小規模飛行場における航空機騒音の予測評価には、時間帯補正等価騒音レベル(Lden)が用いられている。
② 道路交通振動の評価には、振動規制法に基づく要請限度のほか人体感覚の閾値を用いることもある。
③ 道路交通騒音の予測計算には、一般的に日本音響学会の「ASJ CN-Model 2007」が用いられている。
④ 新設の普通鉄道の評価には、等価騒音レベル(LAeq)が用いられている。
⑤ 建設工事騒音の評価には、騒音規制法や地方公共団体によっては条例に基づく規制基準が用いられている。
正解③
CN → Construction Noise
RTN → Road Traffic Noise
I-18 次のうち、「環境影響評価法」の対象事業に該当しないものはどれか。
① 首都高速道路 4車線以上
② 放水路 土地改変面積100ha以上
③ 鉄道 長さ10km以上
④ 風力発電所 出力1万kW以上
⑤ ゴルフ場 すべて
正解⑤
I-19 「環境影響評価法」に基づく環境保全措置に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 環境保全措置の検討に当たっては、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かの検討を行い、講じる環境保全の妥当性を検証するとともに、これらの検討の経緯を明らかにできるようにする。
② 事業者は、改正された「環境影響評価法」(平成23年法律第27号)により、工事中及び供用段階の事後調査や環境保全措置についての報告書の作成を義務付けられる。
③ 配慮書で事業の位置・規模又は配置・構造等の複数案を比較検討した場合には、当該位置等の決定にいたる過程についての環境保全措置の検討内容も明記する。
④ 事後調査の項目や手法及び事後調査の終了判断については、必要に応じて専門家の客観的、科学的根拠に基づく助言を受けることが重要である。
⑤ 報告書の記載事項は、環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度として事後調査により判明した環境の状況に応じて講じたものを含む。また、環境保全措置の効果については、措置後の効果の確認状況を含む。
正解②
I-20 環境影響評価における陸上動植物に関する次の記述の、( )に入る語句の組合せとして最も適切なものはどれか。
各種開発事業による自然環境の改変は、( ア )の中で生物多様性に対する「( イ )の危機」として位置付けられている。例えば、都市近郊の丘陵地には高度経済成長期以降、開発の波が押し寄せ、農業農村の変化とあいまって、現在では里地里山の多くの生きものが絶滅の危機に瀕している。
環境アセスメントにおける「陸上動植物」の評価項目が目的とするところは、事業に先立って動植物の( ウ )を把握し、事業の実施による影響を予測し、必要に応じて各種( エ )を講じることにより、開発事業による影響を回避、低減、代償し、これをもって生物多様性の保全に資することある。
ア イ ウ エ
① SATOYAMAイニシアティブ 存続 状況 環境対策
② 生物多様性国家戦略 多様性 現状 環境保全対策
③ SATOYAMAイニシアティブ 第二 現実 環境保全措置
④ 生物多様性国家戦略 第一 現状 環境保全措置
⑤ SATOYAMAイニシアティブ 生存 現実 環境保全対策
正解④
2013年08月12日
平成25年度技術士第ニ次試験問題〔環境部門〕Ⅱ
19-3自然環境保全【選択科目 II]
II 次の2問題( II-1, II-2)について解答せよ。(問題ごとに答案用紙を替えること。)
II-1 次の4設問(II-1-1~II-1-4)のうち2設問を選び解答せよ。(設問ごとに答案用紙を替えて解答設問番号を明記し,それぞれ1枚以内にまとめよ。)
II-1-1 薪炭林として利用するコナラを主とした二次林を,生物多様性の確保も考慮しながら適切に管理するために必要な作業のうち,重要なものを 5つ挙げ,それぞれの目的と概要を述べよ
II-1 -2 自然公圏内の遊歩道沿いに自然解説標識を設置する場合,標識の計画@設計及び、解説内容について,それぞれ留意すべき点を列挙し?て説明せよ。
II-1-3 我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物種(在来生物)において,近年,生息・生育地域が拡大している,あるいは変化している種が見られる。この傾向が見られる生物種を 1つ取り上げ.変化の状況と考えられる要因について述べよ。
II-1-4 自然再生事業を実施するに当たり留意すべき事項と科学性や計画性を担保するための仕組み・制度であるモニタリング、及び引慎応的管理について述べよ。
II-2 次の2設問(II-2-1,II-2-2)のうち1設問を選び解答せよ。(解答設問番号を明記し,答案用紙2枚以内にまとめよ。)
II -2 -1 都市近郊に残った約5haの里地・皇山環境を基盤とした緑地において,自然環境の保全と育成に関する計画(基本計画)を策定することとなった。この業務を担当者として進めるに当たり,下記の内容について記述せよ。なお,対象とする緑地は農地跡で,ため池,水田放棄地,樹林地(スギ・ヒノキ植林,竹林,落葉広葉樹林)で構成されるものとする。
( 1 )計画策定に当たって調査・検討すべき事項
( 2 )業務を進める手順
( 3 )業務を進めるに当たって留意すべき事項
II-2-2 近年自然とふれあう機会が減る傾向にある中で,林地を自然ふれあいの場とする計画(基本計画)の策定業務を進めるに当たり,下記の内容について記述せよ。
( 1 )計画策定に当たって調査・検討すべき事項
( 2 )業務を進める手順
( 3 )計画する自然ふれあいの場のねらいとソフトを含めた工夫
2013年08月12日
平成25年度技術士第ニ次試験問題〔環境部門〕Ⅲ
19-3自然環境保全【選択科目 Ⅲ]
Ⅲ 次の2問題(ill-1,国一2)のうち1問題を選び解答せよ。(解答問題番号を明記し,答案用紙 3枚以内にまとめよ。)
Ⅲ-1 生物多様性国家戦略では,我が国の生物多様性の 4つの危機を挙げている。自然環境保全の技術士として以下の聞いに答えよ口
( 1 )上記の 4つの危機を挙げそのうちあなたが最も重要と考えるものを 1つ選び,その理由を述べよ。
( 2 )( 1 )で選んだ危機による影響が大きい生物(生物群)を挙げ,その保全に必要な技術的提案を示せ。
( 3 )あなたの技術的提案がもたらす効果を具体的に示すとともに,そこに潜むリスクについて論述せよ。
Ⅲ-2 2011年 3月の東自本大震災における福島第一原子力発電所の事故を教訓とし,我が国で、は再生可能エネルギーへの転換が進められている。自然環境保全の技術士として以下の聞いに答えよ。
( 1 )再生可能エネルギーを 1つ挙げエネルギーを得るための施設整備や施設の稼働等において自然環境に与える影響とその要因について述べよ。
( 2 )( 1 )で挙げた自然環境に与える影響について,あなたが最も大きな技術的課題と考えるものを 1つ挙げ,その技術的課題を解決するための技術的提案を示せ。
( 3 )あなたの技術的提案がもたらす効果を具体的に示すとともに,そこに潜かリスクについて論述せよ。
2013年05月10日
気候変動に関する非公式閣僚級会合
平成25年5月8日
気候変動に関する非公式閣僚級会合 ペータースベルク気候対話IV(結果概要)(お知らせ)
5月6日~5月7日,ドイツ・ベルリンにおいて,気候変動に関する非公式閣僚級会合ペータースベルク気候対話IVが行われ,(1)気候変動に係る行動の促進、(2)長期的なシグナルの提示と民間セクターに対するインセンティブの強化、(3)新たな国際枠組みの設計、(4)COP19で目指すべき成果等の論点について、各国の閣僚レベルの参加の下、率直かつ建設的な議論が行われた。
1.会合
(1)日程・場所
5月6~7日 於:ドイツ・ベルリン
(2)主催
ドイツ及びポーランド政府(共同議長:アルトマイヤー・ドイツ環境・自然保護・核安全大臣、コロレツ・ポーランド環境大臣)
(3)出席者等
ドイツ及びポーランド並びに以下の国・地域・国際機関等が出席した(下線は閣僚級が参加)。
豪州、バングラディシュ、ブラジル、中国、デンマーク、ドミニカ共和国、エジブト、EU(欧州委員会、EU議長国アイルランド)、フィジー、フランス、インド、インドネシア、リトアニア、メキシコ、ナウル、ネパール、ニュージーランド、ノルウェー、ペルー、カタール、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、韓国、スワジランド、スイス、ウクライナ、アラブ首長国連邦(UAE)、英国、米国、ベネズエラ、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局、ADP共同議長
日本からは齋藤環境大臣政務官、鈴木経済産業省産業技術環境局長、吉武外務省気候変動課交渉官、大井環境省国際地球温暖化対策室交渉官他が出席。
2.議論の概要
(1)主な議論
(1)気候変動に係る行動の促進、(2)長期的なシグナルの提示と民間セクターに対するインセンティブの強化、(3)新たな国際枠組みの設計、(4)COP19で目指すべき成果等の論点について、各国の閣僚レベルの参加の下、率直かつ建設的な議論が行われた。
気候変動に係る行動の促進については、各国の先進的な取組が紹介されるとともに、国際的な協力イニシアティブの重要性についても認識が共有された。また、これらの行動に対する国内支持を得るためには、気候変動への取組が低炭素成長につながるというポジティブなメッセージの発信が必要であることが強調された。長期的なシグナルの提示と民間セクターに対するインセンティブの強化については、気候変動対策における民間セクターの取組の重要性について認識が共有されるとともに、政府が民間セクターに対して明確な方向性を示すことの重要性や、努力のインセンティブを与えることの必要性等が確認された。
新たな国際枠組みについては、すべての国の参加のために各国の実情を踏まえ各国が定める貢献が枠組みの基礎となるとの指摘や、この場合にいかに野心を向上させていくかに関する議論が行われた。また、歴史的責任を踏まえ先進国が率先して取組をリードすべきとの意見や、条約の原則は不変であるが状況は変化していくとの指摘があった。
COP19については、国際枠組みの2015年までの合意に向けて同会合において議論を着実に先進させることが重要であるとの認識が共有された。また、資金やロス&ダメージ、野心の引き上げ等も同会合における重要な論点になること、2015年のCOP21までの3回のCOPを一連のものとして捉えて前進していくべき等の指摘がなされた。
議論の結果は、共同議長サマリーとして公表される予定。
(2)メルケル・ドイツ首相の基調講演
会合中、メルケル・ドイツ首相による基調講演が行われ、以下の指摘があった。
・世界の温室効果ガス排出の現状を踏まえると、2℃目標達成のためには先進国のみの努力では十分でないため、全ての国を拘束(binding)する合意を2015年に目指す必要がある。本年のCOP19の議長国であるポーランドのリーダーシップに期待する。
・新たな国際枠組みについて議論を進めるにあたっては正義(justice)や公平(fairness)が重要な視点となる。また、民間に対して行動のインセンティブを与え、また将来の予測可能性を示していくことで明確なメッセージを送ることも政府として重要である。
・EUにおいては、2020年のみならず2030年の目標を検討しているところ。
・また、資金をどのようにスケールアップさせるか、資金についての途上国のガバナンスのどのように向上させるかも重要な問題。
(3)我が国の発言
我が国からは、齋藤環境大臣政務官より、気候変動に係る行動を促進・実行していくためには気候変動が人間の生存基盤に関わる問題であるとのメッセージを発信するとともに、気候変動問題への取組が持続可能な開発やグリーン経済の実現を通じてより良い社会の構築にも資するとのポジティブな側面をアピールしていくことが重要であること、民間セクターによる行動や投資を促進するためには政府がブレのない長期的なビジョンを発信していく必要があること等を説明した。
また、新たな国際枠組みについては、各国の実情を踏まえて条約の原則を捉える必要性、実効的な測定・報告・検証(MRV)の重要性、野心向上のメリットを感じるような制度設計の必要性、既存の枠組みの要素を積極的に活用する必要性等を主張するとともに、COP19に向けては新たな枠組みの要素について建設的な意見交換を続けながら、徐々に議論を深めていき、COP19ではそうした議論を総括して2014年以降の交渉の鍵となる要素を特定することが重要である旨指摘した。また、COP19においては資金やロス&ダメージ、市場メカニズム等も重要な論点になる旨指摘した。
また、二国間オフセット・クレジット制度の構築やフロン類の排出抑制対策の強化、省エネ法に基づくトップランナー制度、低炭素社会創出に向けたファイナンス・イニシアティブ、鉄鋼業界によるCO2排出量算定方法の国際規格化など我が国が進めている取組についても説明した。
(4)その他
上記のほか、会合の合間に英国、米国及びポーランド等の代表者とバイ会談を行ない、気候変動交渉に関する我が国の立場を説明し、意見交換を行った。
(了)
連絡先
環境省地球環境局国際地球温暖化対策室
気候変動に関する非公式閣僚級会合 ペータースベルク気候対話IV(結果概要)(お知らせ)
5月6日~5月7日,ドイツ・ベルリンにおいて,気候変動に関する非公式閣僚級会合ペータースベルク気候対話IVが行われ,(1)気候変動に係る行動の促進、(2)長期的なシグナルの提示と民間セクターに対するインセンティブの強化、(3)新たな国際枠組みの設計、(4)COP19で目指すべき成果等の論点について、各国の閣僚レベルの参加の下、率直かつ建設的な議論が行われた。
1.会合
(1)日程・場所
5月6~7日 於:ドイツ・ベルリン
(2)主催
ドイツ及びポーランド政府(共同議長:アルトマイヤー・ドイツ環境・自然保護・核安全大臣、コロレツ・ポーランド環境大臣)
(3)出席者等
ドイツ及びポーランド並びに以下の国・地域・国際機関等が出席した(下線は閣僚級が参加)。
豪州、バングラディシュ、ブラジル、中国、デンマーク、ドミニカ共和国、エジブト、EU(欧州委員会、EU議長国アイルランド)、フィジー、フランス、インド、インドネシア、リトアニア、メキシコ、ナウル、ネパール、ニュージーランド、ノルウェー、ペルー、カタール、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、韓国、スワジランド、スイス、ウクライナ、アラブ首長国連邦(UAE)、英国、米国、ベネズエラ、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局、ADP共同議長
日本からは齋藤環境大臣政務官、鈴木経済産業省産業技術環境局長、吉武外務省気候変動課交渉官、大井環境省国際地球温暖化対策室交渉官他が出席。
2.議論の概要
(1)主な議論
(1)気候変動に係る行動の促進、(2)長期的なシグナルの提示と民間セクターに対するインセンティブの強化、(3)新たな国際枠組みの設計、(4)COP19で目指すべき成果等の論点について、各国の閣僚レベルの参加の下、率直かつ建設的な議論が行われた。
気候変動に係る行動の促進については、各国の先進的な取組が紹介されるとともに、国際的な協力イニシアティブの重要性についても認識が共有された。また、これらの行動に対する国内支持を得るためには、気候変動への取組が低炭素成長につながるというポジティブなメッセージの発信が必要であることが強調された。長期的なシグナルの提示と民間セクターに対するインセンティブの強化については、気候変動対策における民間セクターの取組の重要性について認識が共有されるとともに、政府が民間セクターに対して明確な方向性を示すことの重要性や、努力のインセンティブを与えることの必要性等が確認された。
新たな国際枠組みについては、すべての国の参加のために各国の実情を踏まえ各国が定める貢献が枠組みの基礎となるとの指摘や、この場合にいかに野心を向上させていくかに関する議論が行われた。また、歴史的責任を踏まえ先進国が率先して取組をリードすべきとの意見や、条約の原則は不変であるが状況は変化していくとの指摘があった。
COP19については、国際枠組みの2015年までの合意に向けて同会合において議論を着実に先進させることが重要であるとの認識が共有された。また、資金やロス&ダメージ、野心の引き上げ等も同会合における重要な論点になること、2015年のCOP21までの3回のCOPを一連のものとして捉えて前進していくべき等の指摘がなされた。
議論の結果は、共同議長サマリーとして公表される予定。
(2)メルケル・ドイツ首相の基調講演
会合中、メルケル・ドイツ首相による基調講演が行われ、以下の指摘があった。
・世界の温室効果ガス排出の現状を踏まえると、2℃目標達成のためには先進国のみの努力では十分でないため、全ての国を拘束(binding)する合意を2015年に目指す必要がある。本年のCOP19の議長国であるポーランドのリーダーシップに期待する。
・新たな国際枠組みについて議論を進めるにあたっては正義(justice)や公平(fairness)が重要な視点となる。また、民間に対して行動のインセンティブを与え、また将来の予測可能性を示していくことで明確なメッセージを送ることも政府として重要である。
・EUにおいては、2020年のみならず2030年の目標を検討しているところ。
・また、資金をどのようにスケールアップさせるか、資金についての途上国のガバナンスのどのように向上させるかも重要な問題。
(3)我が国の発言
我が国からは、齋藤環境大臣政務官より、気候変動に係る行動を促進・実行していくためには気候変動が人間の生存基盤に関わる問題であるとのメッセージを発信するとともに、気候変動問題への取組が持続可能な開発やグリーン経済の実現を通じてより良い社会の構築にも資するとのポジティブな側面をアピールしていくことが重要であること、民間セクターによる行動や投資を促進するためには政府がブレのない長期的なビジョンを発信していく必要があること等を説明した。
また、新たな国際枠組みについては、各国の実情を踏まえて条約の原則を捉える必要性、実効的な測定・報告・検証(MRV)の重要性、野心向上のメリットを感じるような制度設計の必要性、既存の枠組みの要素を積極的に活用する必要性等を主張するとともに、COP19に向けては新たな枠組みの要素について建設的な意見交換を続けながら、徐々に議論を深めていき、COP19ではそうした議論を総括して2014年以降の交渉の鍵となる要素を特定することが重要である旨指摘した。また、COP19においては資金やロス&ダメージ、市場メカニズム等も重要な論点になる旨指摘した。
また、二国間オフセット・クレジット制度の構築やフロン類の排出抑制対策の強化、省エネ法に基づくトップランナー制度、低炭素社会創出に向けたファイナンス・イニシアティブ、鉄鋼業界によるCO2排出量算定方法の国際規格化など我が国が進めている取組についても説明した。
(4)その他
上記のほか、会合の合間に英国、米国及びポーランド等の代表者とバイ会談を行ない、気候変動交渉に関する我が国の立場を説明し、意見交換を行った。
(了)
連絡先
環境省地球環境局国際地球温暖化対策室
2013年05月10日
第15回日中韓三ヵ国環境大臣会合(TEMM15)
平成25年5月7日
第15回日中韓三ヵ国環境大臣会合(TEMM15)の結果について(お知らせ)
第15回日中韓三ヵ国環境大臣会合(TEMM15)を5月5~6 日、福岡県北九州市にて 開催しました。我が国からは石原伸晃環境大臣が出席し、議長を務めました。
会合では、三カ国の国内環境政策の進捗状況の紹介を行うとともに、大気汚染、グ リーン経済、気候変動、生物多様性等について率直な意見交換を行い、共同コミュニ ケを採択しました。
また、日中韓の環境協力に貢献のあった功労者を三大臣が表彰しました。
あわせて、中国、韓国とそれぞれ二国間会談を行いました。
1. 日程
平成25年5月5日(日)~5月6日(月)
2. 開催場所
福岡県北九州市・リーガロイヤルホテル小倉
3. 主な出席者
日本
石原伸晃環境大臣
秋野公造環境大臣政務官
中国
李 幹傑(リ・カンケツ)環境保護部副大臣
韓国
尹成奎(ユン・ソンギュ)環境部大臣
4. 日中韓三カ国環境大臣会合の概要
日本の石原伸晃環境大臣が議長を務め、各国の環境政策の進展、地球規模及び地 域の環境課題及び環境協力に係る三カ国共同行動計画の進捗状況等について意見 交換を行い、共同コミュニケ(別添資料1)が採択された。その主な内容は以下の 通り。
○ 大気汚染については、互いに理解を深め、協力し合うことを通じ、この問題 の解決を図っていくことの重要性について認識が一致し、そのために、新た に三カ国による政策対話を設置することに合意した。また、三カ国は、日中韓のみならずアジア全体の持続的発展に対する大気汚染問題の重要性にかん がみ、既存の地域的取組を更に活用するべく協力を進めることにも合意した。
○黄砂については、発生源対策の重要性を認識し、効果的な対策をとるため、 世界銀行、地球環境ファシリティ(GEF)、モンゴル等のステークホルダーと の調整を行うことに合意した。
○気候変動については、緑の気候基金への協力や、国内排出量取引や二国間オ フセット・メカニズムを含む市場メカニズムの推進等によるグリーン成長と 低炭素開発の達成に向けた取り組みを強化していくこととした。
○水銀に関する水俣条約の合意を歓迎し、本年10月に熊本市・水俣市で開催さ れる外交会議の成功に向けて協力することで一致した。
○生物多様性については、第一回政策対話の成果を歓迎し、さらに強化する必 要性を認識した。
○グリーン経済に関し、これを促進するために、国家の取り組みをさらに推進 していく決意を表明した。
○災害・環境緊急事態対策への協力については、本年1月に福島でセミナーが 開催されたことを歓迎し、今後の三カ国協力について議論する必要性を認識 した。
○次回TEMMは韓国で開催されることが決定した。その際に、2014年以降の優先 協力分野を議論することとなった。
このほか、ビジネスフォーラムでは「環境市場の拡大とグリーン経済の促進に向 けた国際協力」、ユースフォーラムでは「私たちの環境的に持続可能な都市」をそ れぞれテーマに、活発な議論が行われた。また、日中韓の環境協力に功労のあった 者の表彰が行われ、日本からは日本環境衛生センターの秋元肇氏が受賞した。
5.日中及び日韓環境大臣バイ会談の概要(5月6日)
(1)日中環境大臣バイ会談
石原環境大臣と、李副大臣は日中の環境協力は先人らの努力により実り多い成 果があるとの認識を共有した。とりわけ、日中友好環境保全センターを活用し た環境協力をさらに前進させるとの合意をみた。
李副大臣からは、これまでの日本による環境協力を高く評価しており、4月に 開催された日中大気汚染対策セミナーなど、日中間は環境分野で緊密な連携を とっているとの認識が示された。また、今後も優れた経験を持つ日本や北九州 などとの交流への希望が表明された。
さらに、石原大臣から、本年10月に熊本市・水俣市で開催予定の水銀に関す る水俣条約の外交会議への中国政府代表団の派遣を要請した。
(2)日韓環境大臣バイ会談
尹環境大臣からは、日韓は、気候変動、生物多様性保全、大気汚染などの環境分野で緊密な連携をとっていきたいとの認識が示された。
石原環境大臣から、日韓両国は、これらの問題について、アジア地域や世界の 環境保全を牽引していく立場であることを指摘し、この認識で一致した。
大気汚染については、国民の健康にかかわる重要な課題であり、日韓の技術を 活用した協力の枠組みを作ることが重要であると合意した。
6.会合のカーボン・オフセット
なお、今回の大臣会合は、会合の開催に伴って発生する推計約16トンの温室効果 ガス排出量を被災地宮城での温暖化の取組により創出されたオフセット・クレジット J-VER(ジェイバー)を使って、カーボン・オフセットした。
【参考】日中韓三カ国環境大臣会合
日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM= Tripartite Environment Ministers Meeting)は、北東アジアの中核である日本・中国・韓国の三カ国の環境大臣が一堂 に会し、本地域及び地球規模の環境問題に関する対話を行い、協力関係を強化する ことを目的に、1999 年(平成11 年)から毎年各国持ち回りで開催しています。これ までのコミュニケ等については、以下のウェブサイトを御参照ください。
TEMM 公式ウェブサイト http://www.temm.org/
日本語解説サイト
http://www.env.go.jp/earth/coop/temm/introduction_j.html
第15回日中韓三ヵ国環境大臣会合(TEMM15)の結果について(お知らせ)
第15回日中韓三ヵ国環境大臣会合(TEMM15)を5月5~6 日、福岡県北九州市にて 開催しました。我が国からは石原伸晃環境大臣が出席し、議長を務めました。
会合では、三カ国の国内環境政策の進捗状況の紹介を行うとともに、大気汚染、グ リーン経済、気候変動、生物多様性等について率直な意見交換を行い、共同コミュニ ケを採択しました。
また、日中韓の環境協力に貢献のあった功労者を三大臣が表彰しました。
あわせて、中国、韓国とそれぞれ二国間会談を行いました。
1. 日程
平成25年5月5日(日)~5月6日(月)
2. 開催場所
福岡県北九州市・リーガロイヤルホテル小倉
3. 主な出席者
日本
石原伸晃環境大臣
秋野公造環境大臣政務官
中国
李 幹傑(リ・カンケツ)環境保護部副大臣
韓国
尹成奎(ユン・ソンギュ)環境部大臣
4. 日中韓三カ国環境大臣会合の概要
日本の石原伸晃環境大臣が議長を務め、各国の環境政策の進展、地球規模及び地 域の環境課題及び環境協力に係る三カ国共同行動計画の進捗状況等について意見 交換を行い、共同コミュニケ(別添資料1)が採択された。その主な内容は以下の 通り。
○ 大気汚染については、互いに理解を深め、協力し合うことを通じ、この問題 の解決を図っていくことの重要性について認識が一致し、そのために、新た に三カ国による政策対話を設置することに合意した。また、三カ国は、日中韓のみならずアジア全体の持続的発展に対する大気汚染問題の重要性にかん がみ、既存の地域的取組を更に活用するべく協力を進めることにも合意した。
○黄砂については、発生源対策の重要性を認識し、効果的な対策をとるため、 世界銀行、地球環境ファシリティ(GEF)、モンゴル等のステークホルダーと の調整を行うことに合意した。
○気候変動については、緑の気候基金への協力や、国内排出量取引や二国間オ フセット・メカニズムを含む市場メカニズムの推進等によるグリーン成長と 低炭素開発の達成に向けた取り組みを強化していくこととした。
○水銀に関する水俣条約の合意を歓迎し、本年10月に熊本市・水俣市で開催さ れる外交会議の成功に向けて協力することで一致した。
○生物多様性については、第一回政策対話の成果を歓迎し、さらに強化する必 要性を認識した。
○グリーン経済に関し、これを促進するために、国家の取り組みをさらに推進 していく決意を表明した。
○災害・環境緊急事態対策への協力については、本年1月に福島でセミナーが 開催されたことを歓迎し、今後の三カ国協力について議論する必要性を認識 した。
○次回TEMMは韓国で開催されることが決定した。その際に、2014年以降の優先 協力分野を議論することとなった。
このほか、ビジネスフォーラムでは「環境市場の拡大とグリーン経済の促進に向 けた国際協力」、ユースフォーラムでは「私たちの環境的に持続可能な都市」をそ れぞれテーマに、活発な議論が行われた。また、日中韓の環境協力に功労のあった 者の表彰が行われ、日本からは日本環境衛生センターの秋元肇氏が受賞した。
5.日中及び日韓環境大臣バイ会談の概要(5月6日)
(1)日中環境大臣バイ会談
石原環境大臣と、李副大臣は日中の環境協力は先人らの努力により実り多い成 果があるとの認識を共有した。とりわけ、日中友好環境保全センターを活用し た環境協力をさらに前進させるとの合意をみた。
李副大臣からは、これまでの日本による環境協力を高く評価しており、4月に 開催された日中大気汚染対策セミナーなど、日中間は環境分野で緊密な連携を とっているとの認識が示された。また、今後も優れた経験を持つ日本や北九州 などとの交流への希望が表明された。
さらに、石原大臣から、本年10月に熊本市・水俣市で開催予定の水銀に関す る水俣条約の外交会議への中国政府代表団の派遣を要請した。
(2)日韓環境大臣バイ会談
尹環境大臣からは、日韓は、気候変動、生物多様性保全、大気汚染などの環境分野で緊密な連携をとっていきたいとの認識が示された。
石原環境大臣から、日韓両国は、これらの問題について、アジア地域や世界の 環境保全を牽引していく立場であることを指摘し、この認識で一致した。
大気汚染については、国民の健康にかかわる重要な課題であり、日韓の技術を 活用した協力の枠組みを作ることが重要であると合意した。
6.会合のカーボン・オフセット
なお、今回の大臣会合は、会合の開催に伴って発生する推計約16トンの温室効果 ガス排出量を被災地宮城での温暖化の取組により創出されたオフセット・クレジット J-VER(ジェイバー)を使って、カーボン・オフセットした。
【参考】日中韓三カ国環境大臣会合
日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM= Tripartite Environment Ministers Meeting)は、北東アジアの中核である日本・中国・韓国の三カ国の環境大臣が一堂 に会し、本地域及び地球規模の環境問題に関する対話を行い、協力関係を強化する ことを目的に、1999 年(平成11 年)から毎年各国持ち回りで開催しています。これ までのコミュニケ等については、以下のウェブサイトを御参照ください。
TEMM 公式ウェブサイト http://www.temm.org/
日本語解説サイト
http://www.env.go.jp/earth/coop/temm/introduction_j.html
2013年05月08日
「グリーン成長の実現」と「再生可能エネルギーの飛躍的導入」
「グリーン成長の実現」と「再生可能エネルギーの飛躍的導入」に向けたイニシアティブ
はじめに
今般の「日本再生戦略」を受け、国民の関心が高く特に重要と考えられるテーマである「グリーン成長」について、成長を実現するための戦略としての成長エンジンと、革新的エネルギー・環境戦略の策定に向けた最重要事項である再生可能エネルギーの飛躍的導入の実現に向け、来年度概算要求などに盛り込む具体的な取組・施策をとりまとめたイニシアティブを発信するものである。
これにより、グリーンすなわち環境から成長を実現するという新たな挑戦を起こし、大幅な再生可能エネルギー導入に支えられた希望と活力にあふれた日本の実現に貢献するものである。
I.グリーン成長の実現に向けたイニシアティブ
1.今こそ「グリーン成長」
-なぜ今、グリーン成長から日本を考えるべきか-
(1)東日本大震災からの復興エンジンとしてのグリーン成長
大震災からの復興は、ゼロベースからの社会システム構築であり、今後数十年にわたる地域の姿を決定する重要な意義を有する。
環境の世紀に相応しい21世紀型の地域(グリーン・コミュニティ)づくりを復興エンジンとして挑戦する。
豊かな自然環境と共生しながら、低炭素・資源循環型の社会システムを有し、魅力と活力に溢れる「グリーン・コミュニティ」を東北で実現する。
グリーン・コミュニティを実現するための産業・組織・人材の創造と活性化を通じた「グリーン成長」が復興への道筋の鍵となる。
(2)グリーン経済を制することで世界をリード
環境問題をハイライトした「リオ+20(本年6月)」においても、「グリーン経済」が先進国・途上国を問わず中核的なトピックスであった。
資源制約問題、地球環境問題を世界が明確に意識し始めた中、従来の成長モデルを前提とする発展は難しいとの共通認識が醸成されつつある。
このため、世界経済はグリーン経済への移行が新たな潮流になり、グリーン経済を制する国が世界経済をリードするという時代を迎えることになる。
(3)グリーン成長を通じた日本の共創力の発揮
世界的な経済不安、国内における経済不況、雇用不安、少子高齢化などの身近な課題に対処しながら、中長期的には人類の生存基盤を揺るがす地球温暖化問題への対応が求められ、これらを包括する共通の価値観の提示が求められている。
「グリーン成長」は、成長を享受しつつ環境豊かな未来を創るものであり国民の共感が得やすく、共に国を創り上げるモメンタムを醸成できるキー・コンセプトである。
様々な主体の得意分野の力を最大限に発揮しながら、関係各省との連携はもとより、日本の総力を結集してグリーン成長を実現することが日本再生の鍵となる。
2.グリーン成長に向けた基本戦略
-グリーン成長を実現する5つの「成長エンジン」-
【成長エンジンI】
再生可能エネルギー分野と水分野からのイノベーション
原発事故以後、再生可能エネギーの重要性が抜本的に見直され、再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT法)の導入と相まって、今後爆発的な普及展開が期待される。
このような状況を受け、再生可能エネルギーに係る技術を支える様々な産業、運用やメンテナンスを支える幅広いサービス産業などの市場形成と雇用創出による成長を実現する。
水分野(水処理・利用技術、上下水道システム技術等)における技術は日本が世界に誇るグリーン技術である。また、世界的にもこの分野の技術ニーズの高まりは注目に値する状況にある。これらの技術を国内外に市場展開することを通じて成長を実現する。
【成長エンジンII】
地域発の改革力
大震災後は災害にも強い「自立・分散型エネルギーシステム」がハイライトされている。今後は、地産地消型のエネルギーシステムを担う地域の改革力が期待される。
これからの地域は、単にエネルギーを消費する側(コンシューマー)としてだけでなく、自らがエネルギーを創り出す側(プロデューサー)でもある「プロシューマー」として、エネルギーの地域経営によるオーナーシップを発揮し地域主導型の成長を実現する。
地域ぐるみで一体となった大胆な再エネ・省エネ導入を実現することで、地域発の改革力を全国に波及させることを狙う。また、家庭やオフィスなどを含む地域全体のエネルギーネットワークを電力と熱の双方をターゲットに「創り・蓄え・融通し合う」というシステムへの改革に挑戦する。
【成長エンジンIII】
家庭が主役のイノベーション
日本が誇るグリーン技術を、圧倒的な市場ポテンシャルを有する家庭・オフィス分野に導入展開することは今後の成長の鍵を握る。家庭が主役のイノベーションは、人々の意識改革との相乗効果により日本の産業競争力を押し上げるエンジンともなる。
今や避けがたい潮流としての高齢化社会に対応すべく、高齢者にとっての居住性の向上や介護支援の観点からのイノベーションも重要な着目点である。この分野のイノベーションを支えるグリーン技術も成長分野として大きな期待がかかっている。
【成長エンジンIV】
日本発のグリーン技術の国際市場展開
温暖化国際交渉は、2020年以降の新たな国際ルールの策定に向けて今後重要な局面を迎える。他方で目下日本が提案している「二国 間オフセット・クレジット制度」については、日本のグリーン技術で国際市場に展開する絶好の機会でもある。
この制度の創設・活用は、温暖化国際交渉をリードしつつ、途上国等の温暖化対策における国際貢献と日本のグリーン技術の展開の双方を実現する重要な戦略となる。
【成長エンジンV】
グリーン成長を支える基盤創造
【グリーン金融】グリーン技術分野において、新たな資金循環を担う金融メカニズムを活性化することで、様々なグリーン技術市場が活性化され、需要が創り出されるとともに、関連産業への投資促進メカニズムの創造などが期待される。今後は国際的にも金融システムのグリーン化が新たな潮流となることから、日本はこのための先導的・戦略的な対応を展開する。
【グリーン規制】あらゆる市場の飽和が指摘される中、グリーン規制による新たな市場創出は、単に市場創出のみならず市場を豊かなものにするという観点からも今後の国際潮流となり得るものである。このため、グリーン規制をむしろ国内市場の確保や国際市場展開における強みとする戦略を展開し、グリーン規制を成長活力の源泉にしていく。
【グリーン人材】成長を支えるのはまさに人である。今後、新たなグリーン技術の創造、アジアを中心とする国際市場への展開、情報伝達や教育などの分野を担う人材ニーズが急拡大する。これに対応するための人材活用や育成を強力に進める。
3.戦略実現に向けた具体策
-「成長エンジン」を動かす具体的なプロジェクト-
(1)再生可能エネルギーのイノベーション分野
新たな競争力としての浮体式洋上風力発電の市場化へ
(長崎五島列島沖でのパイロットスケールから商用スケールへの拡大、福島沖プロジェクトとの連携、国際市場への展開。)
純国産資源としての地熱開発の戦略的推進
(将来的な地熱開発に大きな弾みをつけるため、地熱資源ポテンシャルについて、従来調査よりも更に詳細・広範なレベルでの調査を実施するとともに、地熱分野における専門家の再結集を図り、 革新的・先導的な地熱開発技術シーズを発掘・活用を推進。)
(自然環境・景観・温泉資源等と高いレベルで調和する地熱開発の優良事例形成プロジェクトの支援、バイナリー発電導入支援。)
様々な省庁との連携プロジェクト
(農山村、港湾、鉄道、物流、データセンター等での各省連携プロジェクトの展開。)
廃棄物・バイオマス発電プロジェクト
(低炭素と資源循環の双方を同時に実現する技術導入への支援。)
再エネ導入拡大を支える系統強化技術
(蓄電池技術を活用した電力系統強化のためのプロジェクト展開。)
海洋国の底力としての海洋エネルギー活用
(波力や潮流を利用する技術分野の研究開発への支援。)
(2)水を媒体とするイノベーション分野
日本が誇る水処理技術を活用したアジア地域へのビジネスの拡大
(日本の水関係企業の海外展開を更に活性化させ、アジアの水ビジネスへの参入機会拡大を図る。)
水システムにおける再エネ・省エネ・未利用エネ技術展開
(各省連携を通じた、水道システムにおける再生可能エネルギー導入や省エネルギー設備の導入、下水道システムにおける未利用エネルギーの活用に向けた先導的プロジェクトの発掘・支援。)
先進的地中熱ヒートポンプ技術による新たな市場創出
(今後の普及の鍵を握る効率的な運転の維持と地中への影響把握に必要となる地下水・地盤温度等の精密モニタリングを支援。)
(3)地域のイノベーション分野
地域が先導役の再エネ等の導入
(FIT制度を活用しつつ、グリーン・ニューディール基金により再生可能エネルギー大幅導入、省エネルギー技術の導入を支援。)
地域が一体となった省エネ実践
(地域における公共施設への省エネルギー技術の大幅導入、「地域まるごとLED」プロジェクトへの発展を狙う。)
地域における自立・分散型エネルギーシステムの構築
(地域における未利用熱の効果的な利用技術の実証、電気・熱の双方を効果的に利用するための管理システムの実証を実施。これにより、未来型モデルとなるグリーン・コミュニティの具体化を目指す。)
(4)家庭のイノベーション分野
「あかり未来計画」の展開
(LED照明の大幅普及のための活動を展開。)
IT技術による革新的省エネ
(家庭やオフィスにおけるHEMSやBEMS技術を活用したライフスタイルに調和する低炭素行動促進のための実証事業、データセンター省エネ化技術の実証事業の実施。)
オフィスのイノベーション
(エネルギーを「創り・蓄え・融通し合う」ことによる、オフィスビルの省エネ化・災害時対応力強化・低炭素化を同時に実現するための技術開発・実証の実施。)
高齢化社会に調和する先進的住宅省エネ技術
(高齢者のヒートショック対策等のための屋内部分断熱技術の低コスト化や施工性の向上を実現する技術等の実証を展開。)
(5)国際市場へのイノベーション展開分野
世界に拡大するグリーン産業分野での日本技術の展開
(経済発展に伴い温室効果ガスの排出増加が見込まれる東南アジア諸国等において、二国間オフセット・クレジット制度を通じて、日本の優れた環境・エネルギー技術の活用による低炭素社会の実現とグリーン成長とを同時に実現。)
(6)グリーン成長基盤分野
グリーン金融
(温暖化対策技術の導入に対する金融支援の事業展開や、投資促進メカニズムの創出に向けたフレームワーク検討。)
グリーン規制
(国として、将来の規制導入を意識した技術開発・実証やモデル事業を展開することで、普及段階で不必要に補助金などに依存しない導入拡大を狙うとともに、それによる新たな市場拡大が期待。効率の悪い旧来製品の製造規制によるグリーン技術の普及加速を検討。)
グリーン人材
(グリーン技術を支える人材活用の促進、来年には順次発行される気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価レポートのポイントを的確に国民に伝え、温暖化影響のリアリティへの認識醸成を支援するための人材育成・基盤整備を展開。)
II.再生可能エネルギーの飛躍的導入に向けた戦略
-野心的ターゲットの実現に向けて-
1.飛躍的導入を実現するアプローチ
再生可能エネルギーの内、太陽光発電、陸上風力発電、水力発電については、これまで様々な施策が幅広く展開されてきたこともあり、今後の導入普及は十分に期待できる分野である。
他方、「洋上風力発電」、「地熱発電」、「バイオマス発電」、「海洋エネルギー」の4分野については、従来の調査から相当な導入ポテンシャルがあることが把握されているにもかかわらず、その掘り起こしに向けた具体的な施策が十分ではない状況にある。
この4つの分野は、短期的には顕著な導入拡大を見込むことは難しいものの、2020年までの間、専門家のノウハウを結集し、R&D、実証事業、モデルプロジェクトなどを強力に推進することにより、2020年以降の加速的導入の起爆剤とすることが可能である。
2.「洋上風力発電」の飛躍的導入に向けた戦略
【現状と方向性】
洋上風力発電については、既に国内外を問わず着床式風力発電が商用段階にあるものの、「着床式」がゆえの立地制約(水深50m以下である必要性)が将来的に顕在化することに鑑みれば、「浮体式」の商用化を実現することが必要不可欠である。
【短中期シナリオ】
<短期:~2020年>・・・3万kW→40万kW
「着床式」風力発電の先導的・モデル的導入による着実な普及拡大を狙う。
「浮体式」風力発電の実証段階から商用段階へのステージアップを実現する。
<中期:~2030年>・・・40万kW→586万kW(→803万kW)
「着床式」風力発電の着実な普及拡大に加えて、「浮体式」風力発電の普及により飛躍的導入拡大を狙う。
【具体的対応策(予算措置など)】
「着床式」風力発電については、既に商用段階にあることから、港湾における風力発電導入に向けたマニュアル(本年6月)の活用により普及拡大を狙う。
「浮体式」風力発電については、本年、我が国初のパイロットスケール(長崎県五島沖100kW)での運転実証を開始したところであり(浮体構造形式としては世界初)、来年度には商用スケール(2MW)での実証を開始する予定である。2015年以降には本格的な商用段階への以降を目指す。(福島県沖においては、大規模な浮体式洋上ウィンドファーム(大規模複数機)実証事業が国主導の事業として準備中。)
環境アセスメントに活用できる環境基礎情報の整備を図ることにより、調査期間の短縮を可能にするとともに、国における審査の迅速化を図ることにより3年程度と想定される環境アセスメントの期間を概ね半減。
系統接続の円滑化のための蓄電池設置支援。
3.「地熱発電」の飛躍導入に向けた戦略
【現状と方向性】
地熱発電については、本年3月に新たな通知(国立・国定公園における地熱開発の取扱いについて、温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)を発出するとともに、戦略的対応に向けた環境省内に副大臣をヘッドとする会議(自然と調和した地熱開発に関する検討会議)を設置し、自然環境保全と地熱開発の調和が十分に図られた優良事例の形成に取り組む。
他方、温泉事業者等との調整や開発リスク等の課題が大きく、専門的・技術的蓄積も国による支援の削減に呼応して弱体化してきた状況にある。今後は、専門的・技術的ノウハウの蓄積や新たな技術活用も念頭に導入の加速化を図ることとする。
【短中期シナリオ】
<短期:~2020年>・・・53万kW→107万kW
既に環境アセスメント手続中の事業に加え、計画中の事業を早期に「優良事例」として形成することにより、地熱開発のモデルを広く共有する。
2020年以降の飛躍的な導入に向けた技術的蓄積や社会環境整備を図る。
<中期:~2030年>・・・107万kW→312万kW(→388万kW)
更なる飛躍的導入拡大に向けた先進的技術(EGS(高温岩体発電等)、高度傾斜掘削技術など)の適用・導入を図る。
【具体的対応策(予算措置など)】
地熱分野に従事する専門家・研究者の再結集による最新技術情報の収集・整備を図る。
地熱開発技術のR&Dや実証を強化・促進する。
環境アセスメントに活用できる環境基礎情報の整備を図ることにより、調査期間の短縮を可能にするとともに、国における審査の迅速化を図ることにより3年程度と想定される環境アセスメントの期間を概ね半減。
地熱開発に際しての合意形成等への支援スキームの充実を図る。
4.「バイオマス発電」の飛躍導入に向けた課題
【現状と方向性】
バイオマス発電については、バイオマス資源の高コスト構造及び供給不安定性、収集・運搬システムの未整備といった課題がある中、関係各省が戦略的に連携し、先導的な事業展開を実施し、更なる事業形成の加速化を図る。
【短中期シナリオ】
<短期:~2020年>・・・240万kW→396万kW
公共の廃棄物焼却施設の更新・改良等を通じ高効率の発電設備を導入するとともに、電力需要に対応した廃棄物発電の実施を図る。
関係各省との連携によりモデルプロジェクトの大幅な展開を図る。
復興関連事業の廃棄物についても燃料としての活用を検討する。
<中期:~2030年>・・・396万kW→522万kW(→600万kW)
2020年までの取組を確実・着実に継続するとともに、公共の廃棄物焼却施設における災害時のエネルギー供給を含めたエネルギーセンター機能の強化を図る。
【具体的対応策(予算措置など)】
「バイオマス事業化戦略(案)」(本年8月)に基づく戦略的施策展開を図る。
交付金等により公共の廃棄物焼却施設におけるエネルギー回収能力を強化するとともに、廃棄物焼却施設の運営の改善を進める。
バイオマス発電をベースとした木質バイオマスのモデル事業を展開する。
5.「海洋(波力・潮力)エネルギー」の飛躍導入に向けた課題
【現状と方向性】
海洋エネルギー(波力・潮力)については、将来的な導入の期待が大きいにもかかわらず、技術として未だ十分に確立されてはいない状況にある(未だR&D段階)。
このため、我が国の特性等を踏まえ、有力技術の洗い出しやR&Dを推進することにより将来の飛躍的導入の基盤づくりを図る。
【短中期シナリオ】
<短期:~2020年>
2015年までにR&Dプロジェクトの対象事業を発掘し、2020年までに有力技術の実証を展開する。
<中期:~2030年>・・・0万kW→100万kW(→150万kW)
2020年までの実証技術をモデル的に導入することを起爆剤に導入普及拡大を狙う。
【具体的対応策(予算措置など)】
技術としては、未だR&D段階にあるものの、日本発の技術としての期待も大きいことから、R&Dスキームの充実・強化を図る。
6.共通的課題への対応
【共通的課題】
系統の容量不足・脆弱性(ハード的課題)
(再エネ大量導入を可能にする送電網、送電可能容量の不足)
(再エネ導入時の電力システムの不安定性(周波数・電圧制御、出力調整)
(電気事業者間の電力融通・調整機能による制約)
系統接続時の手続・運用上の課題(ソフト的課題)
(系統への接続に際しての手続に係る障壁)
(電気事業者が保有する系統接続に必要な情報開示に係る制約)
資金調達に係る課題
(再生可能エネルギー固有の事業リスクに起因する資金面の制約)
【具体的対応策(予算措置など)】
再生可能エネルギーの導入を容易にする「自立・分散型エネルギーシステム」の構築に向け、蓄電池技術の最大限の導入(短期的対応)に加えて、電力系統の大幅な強化(中期的対応)の実現を狙う。
導入促進に向けた実証事業の推進や導入支援スキームの拡充を図る。
はじめに
今般の「日本再生戦略」を受け、国民の関心が高く特に重要と考えられるテーマである「グリーン成長」について、成長を実現するための戦略としての成長エンジンと、革新的エネルギー・環境戦略の策定に向けた最重要事項である再生可能エネルギーの飛躍的導入の実現に向け、来年度概算要求などに盛り込む具体的な取組・施策をとりまとめたイニシアティブを発信するものである。
これにより、グリーンすなわち環境から成長を実現するという新たな挑戦を起こし、大幅な再生可能エネルギー導入に支えられた希望と活力にあふれた日本の実現に貢献するものである。
I.グリーン成長の実現に向けたイニシアティブ
1.今こそ「グリーン成長」
-なぜ今、グリーン成長から日本を考えるべきか-
(1)東日本大震災からの復興エンジンとしてのグリーン成長
大震災からの復興は、ゼロベースからの社会システム構築であり、今後数十年にわたる地域の姿を決定する重要な意義を有する。
環境の世紀に相応しい21世紀型の地域(グリーン・コミュニティ)づくりを復興エンジンとして挑戦する。
豊かな自然環境と共生しながら、低炭素・資源循環型の社会システムを有し、魅力と活力に溢れる「グリーン・コミュニティ」を東北で実現する。
グリーン・コミュニティを実現するための産業・組織・人材の創造と活性化を通じた「グリーン成長」が復興への道筋の鍵となる。
(2)グリーン経済を制することで世界をリード
環境問題をハイライトした「リオ+20(本年6月)」においても、「グリーン経済」が先進国・途上国を問わず中核的なトピックスであった。
資源制約問題、地球環境問題を世界が明確に意識し始めた中、従来の成長モデルを前提とする発展は難しいとの共通認識が醸成されつつある。
このため、世界経済はグリーン経済への移行が新たな潮流になり、グリーン経済を制する国が世界経済をリードするという時代を迎えることになる。
(3)グリーン成長を通じた日本の共創力の発揮
世界的な経済不安、国内における経済不況、雇用不安、少子高齢化などの身近な課題に対処しながら、中長期的には人類の生存基盤を揺るがす地球温暖化問題への対応が求められ、これらを包括する共通の価値観の提示が求められている。
「グリーン成長」は、成長を享受しつつ環境豊かな未来を創るものであり国民の共感が得やすく、共に国を創り上げるモメンタムを醸成できるキー・コンセプトである。
様々な主体の得意分野の力を最大限に発揮しながら、関係各省との連携はもとより、日本の総力を結集してグリーン成長を実現することが日本再生の鍵となる。
2.グリーン成長に向けた基本戦略
-グリーン成長を実現する5つの「成長エンジン」-
【成長エンジンI】
再生可能エネルギー分野と水分野からのイノベーション
原発事故以後、再生可能エネギーの重要性が抜本的に見直され、再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT法)の導入と相まって、今後爆発的な普及展開が期待される。
このような状況を受け、再生可能エネルギーに係る技術を支える様々な産業、運用やメンテナンスを支える幅広いサービス産業などの市場形成と雇用創出による成長を実現する。
水分野(水処理・利用技術、上下水道システム技術等)における技術は日本が世界に誇るグリーン技術である。また、世界的にもこの分野の技術ニーズの高まりは注目に値する状況にある。これらの技術を国内外に市場展開することを通じて成長を実現する。
【成長エンジンII】
地域発の改革力
大震災後は災害にも強い「自立・分散型エネルギーシステム」がハイライトされている。今後は、地産地消型のエネルギーシステムを担う地域の改革力が期待される。
これからの地域は、単にエネルギーを消費する側(コンシューマー)としてだけでなく、自らがエネルギーを創り出す側(プロデューサー)でもある「プロシューマー」として、エネルギーの地域経営によるオーナーシップを発揮し地域主導型の成長を実現する。
地域ぐるみで一体となった大胆な再エネ・省エネ導入を実現することで、地域発の改革力を全国に波及させることを狙う。また、家庭やオフィスなどを含む地域全体のエネルギーネットワークを電力と熱の双方をターゲットに「創り・蓄え・融通し合う」というシステムへの改革に挑戦する。
【成長エンジンIII】
家庭が主役のイノベーション
日本が誇るグリーン技術を、圧倒的な市場ポテンシャルを有する家庭・オフィス分野に導入展開することは今後の成長の鍵を握る。家庭が主役のイノベーションは、人々の意識改革との相乗効果により日本の産業競争力を押し上げるエンジンともなる。
今や避けがたい潮流としての高齢化社会に対応すべく、高齢者にとっての居住性の向上や介護支援の観点からのイノベーションも重要な着目点である。この分野のイノベーションを支えるグリーン技術も成長分野として大きな期待がかかっている。
【成長エンジンIV】
日本発のグリーン技術の国際市場展開
温暖化国際交渉は、2020年以降の新たな国際ルールの策定に向けて今後重要な局面を迎える。他方で目下日本が提案している「二国 間オフセット・クレジット制度」については、日本のグリーン技術で国際市場に展開する絶好の機会でもある。
この制度の創設・活用は、温暖化国際交渉をリードしつつ、途上国等の温暖化対策における国際貢献と日本のグリーン技術の展開の双方を実現する重要な戦略となる。
【成長エンジンV】
グリーン成長を支える基盤創造
【グリーン金融】グリーン技術分野において、新たな資金循環を担う金融メカニズムを活性化することで、様々なグリーン技術市場が活性化され、需要が創り出されるとともに、関連産業への投資促進メカニズムの創造などが期待される。今後は国際的にも金融システムのグリーン化が新たな潮流となることから、日本はこのための先導的・戦略的な対応を展開する。
【グリーン規制】あらゆる市場の飽和が指摘される中、グリーン規制による新たな市場創出は、単に市場創出のみならず市場を豊かなものにするという観点からも今後の国際潮流となり得るものである。このため、グリーン規制をむしろ国内市場の確保や国際市場展開における強みとする戦略を展開し、グリーン規制を成長活力の源泉にしていく。
【グリーン人材】成長を支えるのはまさに人である。今後、新たなグリーン技術の創造、アジアを中心とする国際市場への展開、情報伝達や教育などの分野を担う人材ニーズが急拡大する。これに対応するための人材活用や育成を強力に進める。
3.戦略実現に向けた具体策
-「成長エンジン」を動かす具体的なプロジェクト-
(1)再生可能エネルギーのイノベーション分野
新たな競争力としての浮体式洋上風力発電の市場化へ
(長崎五島列島沖でのパイロットスケールから商用スケールへの拡大、福島沖プロジェクトとの連携、国際市場への展開。)
純国産資源としての地熱開発の戦略的推進
(将来的な地熱開発に大きな弾みをつけるため、地熱資源ポテンシャルについて、従来調査よりも更に詳細・広範なレベルでの調査を実施するとともに、地熱分野における専門家の再結集を図り、 革新的・先導的な地熱開発技術シーズを発掘・活用を推進。)
(自然環境・景観・温泉資源等と高いレベルで調和する地熱開発の優良事例形成プロジェクトの支援、バイナリー発電導入支援。)
様々な省庁との連携プロジェクト
(農山村、港湾、鉄道、物流、データセンター等での各省連携プロジェクトの展開。)
廃棄物・バイオマス発電プロジェクト
(低炭素と資源循環の双方を同時に実現する技術導入への支援。)
再エネ導入拡大を支える系統強化技術
(蓄電池技術を活用した電力系統強化のためのプロジェクト展開。)
海洋国の底力としての海洋エネルギー活用
(波力や潮流を利用する技術分野の研究開発への支援。)
(2)水を媒体とするイノベーション分野
日本が誇る水処理技術を活用したアジア地域へのビジネスの拡大
(日本の水関係企業の海外展開を更に活性化させ、アジアの水ビジネスへの参入機会拡大を図る。)
水システムにおける再エネ・省エネ・未利用エネ技術展開
(各省連携を通じた、水道システムにおける再生可能エネルギー導入や省エネルギー設備の導入、下水道システムにおける未利用エネルギーの活用に向けた先導的プロジェクトの発掘・支援。)
先進的地中熱ヒートポンプ技術による新たな市場創出
(今後の普及の鍵を握る効率的な運転の維持と地中への影響把握に必要となる地下水・地盤温度等の精密モニタリングを支援。)
(3)地域のイノベーション分野
地域が先導役の再エネ等の導入
(FIT制度を活用しつつ、グリーン・ニューディール基金により再生可能エネルギー大幅導入、省エネルギー技術の導入を支援。)
地域が一体となった省エネ実践
(地域における公共施設への省エネルギー技術の大幅導入、「地域まるごとLED」プロジェクトへの発展を狙う。)
地域における自立・分散型エネルギーシステムの構築
(地域における未利用熱の効果的な利用技術の実証、電気・熱の双方を効果的に利用するための管理システムの実証を実施。これにより、未来型モデルとなるグリーン・コミュニティの具体化を目指す。)
(4)家庭のイノベーション分野
「あかり未来計画」の展開
(LED照明の大幅普及のための活動を展開。)
IT技術による革新的省エネ
(家庭やオフィスにおけるHEMSやBEMS技術を活用したライフスタイルに調和する低炭素行動促進のための実証事業、データセンター省エネ化技術の実証事業の実施。)
オフィスのイノベーション
(エネルギーを「創り・蓄え・融通し合う」ことによる、オフィスビルの省エネ化・災害時対応力強化・低炭素化を同時に実現するための技術開発・実証の実施。)
高齢化社会に調和する先進的住宅省エネ技術
(高齢者のヒートショック対策等のための屋内部分断熱技術の低コスト化や施工性の向上を実現する技術等の実証を展開。)
(5)国際市場へのイノベーション展開分野
世界に拡大するグリーン産業分野での日本技術の展開
(経済発展に伴い温室効果ガスの排出増加が見込まれる東南アジア諸国等において、二国間オフセット・クレジット制度を通じて、日本の優れた環境・エネルギー技術の活用による低炭素社会の実現とグリーン成長とを同時に実現。)
(6)グリーン成長基盤分野
グリーン金融
(温暖化対策技術の導入に対する金融支援の事業展開や、投資促進メカニズムの創出に向けたフレームワーク検討。)
グリーン規制
(国として、将来の規制導入を意識した技術開発・実証やモデル事業を展開することで、普及段階で不必要に補助金などに依存しない導入拡大を狙うとともに、それによる新たな市場拡大が期待。効率の悪い旧来製品の製造規制によるグリーン技術の普及加速を検討。)
グリーン人材
(グリーン技術を支える人材活用の促進、来年には順次発行される気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価レポートのポイントを的確に国民に伝え、温暖化影響のリアリティへの認識醸成を支援するための人材育成・基盤整備を展開。)
II.再生可能エネルギーの飛躍的導入に向けた戦略
-野心的ターゲットの実現に向けて-
1.飛躍的導入を実現するアプローチ
再生可能エネルギーの内、太陽光発電、陸上風力発電、水力発電については、これまで様々な施策が幅広く展開されてきたこともあり、今後の導入普及は十分に期待できる分野である。
他方、「洋上風力発電」、「地熱発電」、「バイオマス発電」、「海洋エネルギー」の4分野については、従来の調査から相当な導入ポテンシャルがあることが把握されているにもかかわらず、その掘り起こしに向けた具体的な施策が十分ではない状況にある。
この4つの分野は、短期的には顕著な導入拡大を見込むことは難しいものの、2020年までの間、専門家のノウハウを結集し、R&D、実証事業、モデルプロジェクトなどを強力に推進することにより、2020年以降の加速的導入の起爆剤とすることが可能である。
2.「洋上風力発電」の飛躍的導入に向けた戦略
【現状と方向性】
洋上風力発電については、既に国内外を問わず着床式風力発電が商用段階にあるものの、「着床式」がゆえの立地制約(水深50m以下である必要性)が将来的に顕在化することに鑑みれば、「浮体式」の商用化を実現することが必要不可欠である。
【短中期シナリオ】
<短期:~2020年>・・・3万kW→40万kW
「着床式」風力発電の先導的・モデル的導入による着実な普及拡大を狙う。
「浮体式」風力発電の実証段階から商用段階へのステージアップを実現する。
<中期:~2030年>・・・40万kW→586万kW(→803万kW)
「着床式」風力発電の着実な普及拡大に加えて、「浮体式」風力発電の普及により飛躍的導入拡大を狙う。
【具体的対応策(予算措置など)】
「着床式」風力発電については、既に商用段階にあることから、港湾における風力発電導入に向けたマニュアル(本年6月)の活用により普及拡大を狙う。
「浮体式」風力発電については、本年、我が国初のパイロットスケール(長崎県五島沖100kW)での運転実証を開始したところであり(浮体構造形式としては世界初)、来年度には商用スケール(2MW)での実証を開始する予定である。2015年以降には本格的な商用段階への以降を目指す。(福島県沖においては、大規模な浮体式洋上ウィンドファーム(大規模複数機)実証事業が国主導の事業として準備中。)
環境アセスメントに活用できる環境基礎情報の整備を図ることにより、調査期間の短縮を可能にするとともに、国における審査の迅速化を図ることにより3年程度と想定される環境アセスメントの期間を概ね半減。
系統接続の円滑化のための蓄電池設置支援。
3.「地熱発電」の飛躍導入に向けた戦略
【現状と方向性】
地熱発電については、本年3月に新たな通知(国立・国定公園における地熱開発の取扱いについて、温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)を発出するとともに、戦略的対応に向けた環境省内に副大臣をヘッドとする会議(自然と調和した地熱開発に関する検討会議)を設置し、自然環境保全と地熱開発の調和が十分に図られた優良事例の形成に取り組む。
他方、温泉事業者等との調整や開発リスク等の課題が大きく、専門的・技術的蓄積も国による支援の削減に呼応して弱体化してきた状況にある。今後は、専門的・技術的ノウハウの蓄積や新たな技術活用も念頭に導入の加速化を図ることとする。
【短中期シナリオ】
<短期:~2020年>・・・53万kW→107万kW
既に環境アセスメント手続中の事業に加え、計画中の事業を早期に「優良事例」として形成することにより、地熱開発のモデルを広く共有する。
2020年以降の飛躍的な導入に向けた技術的蓄積や社会環境整備を図る。
<中期:~2030年>・・・107万kW→312万kW(→388万kW)
更なる飛躍的導入拡大に向けた先進的技術(EGS(高温岩体発電等)、高度傾斜掘削技術など)の適用・導入を図る。
【具体的対応策(予算措置など)】
地熱分野に従事する専門家・研究者の再結集による最新技術情報の収集・整備を図る。
地熱開発技術のR&Dや実証を強化・促進する。
環境アセスメントに活用できる環境基礎情報の整備を図ることにより、調査期間の短縮を可能にするとともに、国における審査の迅速化を図ることにより3年程度と想定される環境アセスメントの期間を概ね半減。
地熱開発に際しての合意形成等への支援スキームの充実を図る。
4.「バイオマス発電」の飛躍導入に向けた課題
【現状と方向性】
バイオマス発電については、バイオマス資源の高コスト構造及び供給不安定性、収集・運搬システムの未整備といった課題がある中、関係各省が戦略的に連携し、先導的な事業展開を実施し、更なる事業形成の加速化を図る。
【短中期シナリオ】
<短期:~2020年>・・・240万kW→396万kW
公共の廃棄物焼却施設の更新・改良等を通じ高効率の発電設備を導入するとともに、電力需要に対応した廃棄物発電の実施を図る。
関係各省との連携によりモデルプロジェクトの大幅な展開を図る。
復興関連事業の廃棄物についても燃料としての活用を検討する。
<中期:~2030年>・・・396万kW→522万kW(→600万kW)
2020年までの取組を確実・着実に継続するとともに、公共の廃棄物焼却施設における災害時のエネルギー供給を含めたエネルギーセンター機能の強化を図る。
【具体的対応策(予算措置など)】
「バイオマス事業化戦略(案)」(本年8月)に基づく戦略的施策展開を図る。
交付金等により公共の廃棄物焼却施設におけるエネルギー回収能力を強化するとともに、廃棄物焼却施設の運営の改善を進める。
バイオマス発電をベースとした木質バイオマスのモデル事業を展開する。
5.「海洋(波力・潮力)エネルギー」の飛躍導入に向けた課題
【現状と方向性】
海洋エネルギー(波力・潮力)については、将来的な導入の期待が大きいにもかかわらず、技術として未だ十分に確立されてはいない状況にある(未だR&D段階)。
このため、我が国の特性等を踏まえ、有力技術の洗い出しやR&Dを推進することにより将来の飛躍的導入の基盤づくりを図る。
【短中期シナリオ】
<短期:~2020年>
2015年までにR&Dプロジェクトの対象事業を発掘し、2020年までに有力技術の実証を展開する。
<中期:~2030年>・・・0万kW→100万kW(→150万kW)
2020年までの実証技術をモデル的に導入することを起爆剤に導入普及拡大を狙う。
【具体的対応策(予算措置など)】
技術としては、未だR&D段階にあるものの、日本発の技術としての期待も大きいことから、R&Dスキームの充実・強化を図る。
6.共通的課題への対応
【共通的課題】
系統の容量不足・脆弱性(ハード的課題)
(再エネ大量導入を可能にする送電網、送電可能容量の不足)
(再エネ導入時の電力システムの不安定性(周波数・電圧制御、出力調整)
(電気事業者間の電力融通・調整機能による制約)
系統接続時の手続・運用上の課題(ソフト的課題)
(系統への接続に際しての手続に係る障壁)
(電気事業者が保有する系統接続に必要な情報開示に係る制約)
資金調達に係る課題
(再生可能エネルギー固有の事業リスクに起因する資金面の制約)
【具体的対応策(予算措置など)】
再生可能エネルギーの導入を容易にする「自立・分散型エネルギーシステム」の構築に向け、蓄電池技術の最大限の導入(短期的対応)に加えて、電力系統の大幅な強化(中期的対応)の実現を狙う。
導入促進に向けた実証事業の推進や導入支援スキームの拡充を図る。
2013年05月07日
ADP
平成25年5月7日
強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会第2回会合(ADP2)(結果概要)(お知らせ)
4月29日~5月3日、ドイツ・ボンにおいて、国連気候変動枠組条約の下の「強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会(ADP)」第2回会合第1セッションが行われ、我が国から、外務・経済産業・環境・農林水産・国土交通各省関係者が出席した。
ADPは、2011年末に南アフリカ・ダーバンで開催された第17回気候変動枠組条約締約国会議(COP17)での合意を受け、昨年5月に設置さ れたもの。
[1]全ての国に適用される2020年以降の新しい法的枠組み(以下「2020年枠組み」という。)の2015年までの採択及び
[2]2020 年までの排出削減(緩和)の野心の向上について議論を行う。
本会合は、昨年末にカタール・ドーハで開催されたCOP18で決定されたADP作業計画に基づき、今年3回ないし4回開催されるADP第2回会合の最初 のセッション。上記2つの議題(ワークストリーム)について、各国参加者による議論の場である「ラウンドテーブル」及び有識者、国際機関等も参加する 「ワークショップ」を開催し、各国が自由に意見交換を行った。
我が国は、
(1)今回会合を含む本年のADP会合等の機会を最大限活用して、2020年枠組みの構造(architecture)や含まれるべき主要な 要素について、より具体的なブレーンストーミングを進めながら、共通認識と論点を洗い出し、徐々に議論を深めていくべきであること、
(2)本年後半から 11月のCOP19にかけて、より焦点を絞った議論に移行すべきであること
等を主張しつつ交渉に参加した。
また、交渉と並行して、二国間・多国間の会談等を行い、本年のADPの議論やCOP19で目指すべき成果等について我が国の考えを各国に伝えるとともに、各国の立場について情報収集を行った。
より詳しい会合の概要は以下のとおり。
1.会合の概要
(1) 2020年枠組みのビジョン及び2020年までの緩和の野心向上の2つのワークストリームの 下、2020年枠組みについて「スコープ、構造及びデザイン」、野心向上について「低炭素成長の機会」及び「土地利用関連の緩和及び適応の機会」と題する 3つのワークショップが開催され、有識者や国際機関からのプレゼンテーション、各国交渉官も加わったパネルディスカッション及びそれを受けた意見交換が行 われた。
(2) ワークショップでの議論を受ける形で、2つのワークストリームについて「ラウンドテーブル」の形式で、各国間の自由かつ率直な意見交換が行われた。
2020枠組みのビジョンのワークストリームでは、2020年枠組みのイメージや、全ての国への適用(applicable to all)、各国の事情(national circumstances)、柔軟性(flexibility)といった概念をどのように2020年枠組みに反映させていくかについて意見交換が行われ た。その結果、全ての国が参加するとともに、共通だが差異ある責任(CBDR)や衡平性といった条約の原則に基づく枠組みを構築するためには、各国の事情 に応じた各国の努力を基本としていく必要があること、共通のルールの下で各国の行動の透明性と環境十全性を確保する必要があることについて概ね認識の共有 が見られた。一方で、その詳細については先進国、新興国、開発途上国などのグループごとに考えに違いがあり、とりわけ途上国の側に先進国が率先して緩和を 行うべしとの主張が強く、今後さらに論点を絞って意見交換を進める必要があることが確認された。
2020年までの緩和の野心向上のワークストリームでは、各国の野心向上や低炭素成長に向けた取組の紹介や、国連内外の取組や国際協力イニシアティブの 活用により、排出削減を促進させるための方策について意見交換が行われた。議論の中で、これまでのCOP決定で設置された様々なメカニズムの完全な実施、 技術的な議論の継続及び野心向上に対する政治的なシグナルの重要性、様々な国際協力イニシアティブの推進と情報共有のためのプラットフォームとしての ADPの有用性、各国の開発政策における気候変動の主流化といった点について認識の共有が見られた。また、AOSISからはCOP19に向けて、エネル ギー効率向上と再生可能エネルギーに焦点を絞った作業に関する提案が出された。
(3) 我が国は、2020年枠組みを公平で実効性があり、長続きするものとするために全ての国の参加 の確保が重要であり、そのためには、各国が国内事情を踏まえて自ら決定した削減目標や政策措置を提示・登録し、共通の測定・報告・検証(MRV)制度に よって事前・事後に相互にチェックし合うことで、各国の行動の透明性を高め、緩和野心の向上につなげることが重要との考えを主張した。また、適応、実施の 手段(資金、技術移転、キャパシティビルディング)の重要性については認識しつつも、既存の組織・仕組みとの関係を指摘し、それらとの重複を避けるべき旨 主張した。
(4) 今回の会合は閉会手続きを取らずに中断され、次回6月にボンで開催される補助機関会合(SB)の機会に再開されることとなった。今回のラウンドテーブル及びワークショップの結果は共同議長の責任で取りまとめられ、後日公表される予定。
(5) なお、共同議長から、6月の会合後に共同議長の交代が予定されていることを踏まえ、何らかの中 間成果をとりまとめるための場(コンタクトグループ)を設置してはどうかとの提案があり、設置の是非や数を含めて、6月の会合で引き続き議論されることと なった。また、条約事務局より、次回以降のセッションについては、開催費用の関係から、現時点では9月の開催は困難であり、その場合には6月のSB及び 11月にポーランド・ワルシャワで開催されるCOP19の機会の2回となることが発表された。
2.我が国の立場に関する説明等
(1)二国間・多国間の会談
会合期間中、EU、米国、英国、インド、中国、小島嶼国との二国間会談等を行い、今後のADPプロセスの進め方や我が国が進める二国間オフセット・クレジット制度等について意見交換を行った。
(2)ステークホルダーとの対話
会合期間中、日本のNGO及び国際NGOと意見交換を行った。
(3)プレスへの説明
会合期間中、邦人記者に対するブリーフを行い、交渉の状況や我が国の立場について説明した。
2013年04月19日
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
平成25年4月19日
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」が本日4月19日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第183回国会に提出する予定です。
1.法改正の背景
(1)
生物多様性基本法が平成20年に制定され、さらに、平成22年の生物多様性条約第10回締約国会議において採択された愛知目標の中に、侵略的外来種を制御、根絶するための対策等を講じることが位置付けられるなど、生物の多様性に対する国内外の関心が極めて高まってきており、外来生物対策を一層推進することが求められています。
(2)
一方、特定外来生物が交雑することにより生じた生物による生態系等に係る被害が懸念されるなどの状況にあり、平成24年12月には中央環境審議会から今後講ずべき措置について意見具申がなされました。
(3)
このような状況を踏まえ、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための施策を一層強化するための措置を講じようとするものです。
2.改正の概要
(1)外来生物の定義の改正
外来生物の定義を改正し、これまで法の対象となっていなかった外来生物が交雑することにより生じた生物を、外来生物に含めることとします。
(2)放出等の禁止の例外
現在例外なく禁止されている特定外来生物の放出等について、防除の推進に資する学術研究の目的で主務大臣の許可を受けた場合及び防除の目的で主務大臣の確認又は認定を受けた場合は例外として行えることとします。
(3)措置命令の対象の拡充
主務大臣による措置命令の対象は、これまでは許可を受けて飼養等している者に限られていましたが、許可なく飼養等をしている者等に拡大するとともに、措置命令の内容として、特定外来生物の飼養等の中止、放出等をした特定外来生物の回収等を新たに規定します。
(4)所有者等不明の土地への立入り等の手続の整備
主務大臣等が、防除のために、その職員に所有者等不明の土地への立入り等をさせる場合の手続を新たに規定します。
(5)輸入品等の検査等の創設
特定外来生物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品等の検査及び特定外来生物が付着し、又混入している輸入品等の消毒又は廃棄の命令を新たに規定します。
3.施行期日
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行します。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」が本日4月19日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第183回国会に提出する予定です。
1.法改正の背景
(1)
生物多様性基本法が平成20年に制定され、さらに、平成22年の生物多様性条約第10回締約国会議において採択された愛知目標の中に、侵略的外来種を制御、根絶するための対策等を講じることが位置付けられるなど、生物の多様性に対する国内外の関心が極めて高まってきており、外来生物対策を一層推進することが求められています。
(2)
一方、特定外来生物が交雑することにより生じた生物による生態系等に係る被害が懸念されるなどの状況にあり、平成24年12月には中央環境審議会から今後講ずべき措置について意見具申がなされました。
(3)
このような状況を踏まえ、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための施策を一層強化するための措置を講じようとするものです。
2.改正の概要
(1)外来生物の定義の改正
外来生物の定義を改正し、これまで法の対象となっていなかった外来生物が交雑することにより生じた生物を、外来生物に含めることとします。
(2)放出等の禁止の例外
現在例外なく禁止されている特定外来生物の放出等について、防除の推進に資する学術研究の目的で主務大臣の許可を受けた場合及び防除の目的で主務大臣の確認又は認定を受けた場合は例外として行えることとします。
(3)措置命令の対象の拡充
主務大臣による措置命令の対象は、これまでは許可を受けて飼養等している者に限られていましたが、許可なく飼養等をしている者等に拡大するとともに、措置命令の内容として、特定外来生物の飼養等の中止、放出等をした特定外来生物の回収等を新たに規定します。
(4)所有者等不明の土地への立入り等の手続の整備
主務大臣等が、防除のために、その職員に所有者等不明の土地への立入り等をさせる場合の手続を新たに規定します。
(5)輸入品等の検査等の創設
特定外来生物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品等の検査及び特定外来生物が付着し、又混入している輸入品等の消毒又は廃棄の命令を新たに規定します。
3.施行期日
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行します。
2013年04月19日
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案
平成25年4月19日
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案」が本日4月19日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第183回国会に提出する予定です。
1.法改正の背景
(1)
生物多様性基本法が平成20年に制定され、さらに、平成22年の生物多様性条約第10回締約国会議において採択された愛知目標の中に、「既知の絶滅危惧種の絶滅や減少が防止されること」が位置付けられるなど、生物の多様性に対する国内外の関心が極めて高まってきており、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を一層推進することが求められています。
(2)
これを受けて、環境省では平成23年度に絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する点検を実施し、これまでの我が国の政策の実施状況を把握するとともに、点検会議において今後取り組むべき課題等の提言を得ました。その後、平成25年3月には、中央環境審議会より「絶滅のおそれのある野生生物の保全につき今後講ずべき措置について」答申を得たところです。
(3)
希少野生動植物種はその希少性から高額で取引されるものが多く、違法な譲渡し等の再犯事例も発生しており、悪質な違法取引が後を絶たない状況にあります。こうした状況を踏まえ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存施策を一層強化するため、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」の改正を行うこととしたものです。
2.法律案の概要
(1)罰則の強化
罰則において大幅な強化を図り、希少野生動植物種の個体等の違法な譲渡し等に関する罰則の上限を引き上げます。
(2)広告に関する規制の強化
流通が認められていない希少野生動植物種の個体等に関して、販売又は頒布の目的で広告することを禁止します。
(3)登録関係事務手続の改善
国際希少野生動植物種の個体等の登録に関する事務手続を改善し、個体等の区分又は主な特徴等に変更が生じた場合における変更登録、登録票の書換交付等の手続を新設します。
(4)認定保護増殖事業の特例の追加
国内希少野生動植物種の保護増殖事業の円滑化を図るため、国及び地方公共団体以外の者が、環境大臣の認定を受けた保護増殖事業として行う個体等の譲渡し等について、環境大臣の許可を要しないこととします。
(5)目的規定に「生物の多様性の確保」を加えること等の追加
法の目的において、「生物の多様性の確保」の明記、国の責務規定に「科学的知見の充実」の追加、「教育活動等により国民の理解を深めること」の規定及び施行後3年を経過した場合の法の見直し規定を追加します。
3.施行期日
改正案においては、それぞれ下記の日から施行することとしています。
2(1)公布の日から20日を経過した日。
2(2)、2(3)公布の日から1年以内の政令で定める日。
2(4)、2(5)公布の日。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案」が本日4月19日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第183回国会に提出する予定です。
1.法改正の背景
(1)
生物多様性基本法が平成20年に制定され、さらに、平成22年の生物多様性条約第10回締約国会議において採択された愛知目標の中に、「既知の絶滅危惧種の絶滅や減少が防止されること」が位置付けられるなど、生物の多様性に対する国内外の関心が極めて高まってきており、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を一層推進することが求められています。
(2)
これを受けて、環境省では平成23年度に絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する点検を実施し、これまでの我が国の政策の実施状況を把握するとともに、点検会議において今後取り組むべき課題等の提言を得ました。その後、平成25年3月には、中央環境審議会より「絶滅のおそれのある野生生物の保全につき今後講ずべき措置について」答申を得たところです。
(3)
希少野生動植物種はその希少性から高額で取引されるものが多く、違法な譲渡し等の再犯事例も発生しており、悪質な違法取引が後を絶たない状況にあります。こうした状況を踏まえ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存施策を一層強化するため、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」の改正を行うこととしたものです。
2.法律案の概要
(1)罰則の強化
罰則において大幅な強化を図り、希少野生動植物種の個体等の違法な譲渡し等に関する罰則の上限を引き上げます。
(2)広告に関する規制の強化
流通が認められていない希少野生動植物種の個体等に関して、販売又は頒布の目的で広告することを禁止します。
(3)登録関係事務手続の改善
国際希少野生動植物種の個体等の登録に関する事務手続を改善し、個体等の区分又は主な特徴等に変更が生じた場合における変更登録、登録票の書換交付等の手続を新設します。
(4)認定保護増殖事業の特例の追加
国内希少野生動植物種の保護増殖事業の円滑化を図るため、国及び地方公共団体以外の者が、環境大臣の認定を受けた保護増殖事業として行う個体等の譲渡し等について、環境大臣の許可を要しないこととします。
(5)目的規定に「生物の多様性の確保」を加えること等の追加
法の目的において、「生物の多様性の確保」の明記、国の責務規定に「科学的知見の充実」の追加、「教育活動等により国民の理解を深めること」の規定及び施行後3年を経過した場合の法の見直し規定を追加します。
3.施行期日
改正案においては、それぞれ下記の日から施行することとしています。
2(1)公布の日から20日を経過した日。
2(2)、2(3)公布の日から1年以内の政令で定める日。
2(4)、2(5)公布の日。
2013年04月18日
環境産業市場規模推計、環境成長エンジン報告書等の公表について(お知らせ)
環境省 平成25年4月16日
環境省では、環境産業の市場規模※等について従前より推計を行っているところですが、2011年版の推計についてまとまりましたので公表致します。環境産業の2011年の市場規模は約82兆円(前年比2.3%増)と2年連続の増加となりました。雇用規模についても、約227万人となり2010年(約225万人)から増加しています。
また、昨年度に続きとりまとめた「環境成長エンジン報告書」においては、特徴的な12の環境産業を分析、また、環境ビジネスに取り組む19社の事例調査を実施し、これを踏まえて環境産業の成長要因等を抽出し、今後の更なる拡大のために政府及び企業に求められる対応策等を整理しました。
(※) 「環境産業の市場規模」は「国内にある環境産業にとっての内外市場規模(売上ベース)」の意味
1.趣旨
環境省では、環境と経済がともに向上、発展する社会の構築へ向けた、政策立案の基礎とするため、また、広く環境産業に関わる主体への情報提供を通じて環境保全に資する経済活動を推進するための情報整備を行っています。
今回公表する平成24年度事業では、2011年の環境産業の市場規模及び雇用規模の推計、付加価値額や輸出入額の試算等を行いました。また、国内環境産業の現状・展望をより総合的に整理するため、昨年度に続き「環境成長エンジン報告書」をとりまとめました。
2.公表資料と結果の概要
(1)環境産業市場規模関連
[1] 環境産業の市場規模、雇用規模の推計:「次世代省エネルギー住宅」等9分野を新たな推計対象とした他、必要な推計方法の改善を実施した上で、2000年までの遡及改定を実施しました。その結果、環境産業の市場規模はリーマンショック等の影響により2009年に縮小しましたが、2010年から景気の持ち直し等を受けて増加に転じ、2011年は約82兆円(前年比約2.3%増)と2年連続の増加となりました。また2011年雇用規模は約227万人(前年比1.3%増)となりました。
[2] 推計対象外の環境製品・サービス:継続的な推計に適さない等により今回の推計には含まないが、重要と思われる項目(除染、がれき処理、炭素繊維等)について市場規模の試算を含めて整理を行いました。
[3] 環境産業の付加価値、輸出入の推計:市場規模推計に産業連関表の情報を加味し、2011年環境産業の付加価値額は約35兆円(2011年の名目GDPの約7.5%)、輸出額は約7.7兆円、輸入額は約1.5兆円との試算結果を得ました。
(2) 環境成長エンジン報告書
環境産業・ビジネスが経済成長のエンジン(原動力)とならんとする動きを分析する本報告書では、以下をまとめました。
[1] 東日本大震災によって市場環境に大きな変化が見られる等、特徴的な12の環境産業分野の分析を行いました。そのうち、24年7月の固定価格買取制度導入により注目される再生可能エネルギー発電事業の設備投資や運営段階の資金投入が及ぼす経済波及効果を試算し、いずれも産業平均以上の高い波及効果があることを示しました。
[2] 環境ビジネスを展開する企業19社へのヒアリングにより、参入の経緯、市場における位置づけ、海外市場への展開状況、成功・差別化要因、今後の展望・課題、政策への要望等を整理しました。
[3] 上記を素材として環境ビジネスを分析するに際し、a)政策・制度/事業環境、b)事業のコア(技術・ビジネスモデル等)、c)調達、d)販売市場、という4つの側面から捉えることとし、環境産業のより一層の振興を図るために、政府及び企業それぞれに求められる対応策を提示しました。
いずれも環境経済情報ポータルサイト上、「環境産業情報」において公表いたします。
http://www.env.go.jp/policy/keizai_portal/B_industry/index.html
環境省では、環境産業の市場規模※等について従前より推計を行っているところですが、2011年版の推計についてまとまりましたので公表致します。環境産業の2011年の市場規模は約82兆円(前年比2.3%増)と2年連続の増加となりました。雇用規模についても、約227万人となり2010年(約225万人)から増加しています。
また、昨年度に続きとりまとめた「環境成長エンジン報告書」においては、特徴的な12の環境産業を分析、また、環境ビジネスに取り組む19社の事例調査を実施し、これを踏まえて環境産業の成長要因等を抽出し、今後の更なる拡大のために政府及び企業に求められる対応策等を整理しました。
(※) 「環境産業の市場規模」は「国内にある環境産業にとっての内外市場規模(売上ベース)」の意味
1.趣旨
環境省では、環境と経済がともに向上、発展する社会の構築へ向けた、政策立案の基礎とするため、また、広く環境産業に関わる主体への情報提供を通じて環境保全に資する経済活動を推進するための情報整備を行っています。
今回公表する平成24年度事業では、2011年の環境産業の市場規模及び雇用規模の推計、付加価値額や輸出入額の試算等を行いました。また、国内環境産業の現状・展望をより総合的に整理するため、昨年度に続き「環境成長エンジン報告書」をとりまとめました。
2.公表資料と結果の概要
(1)環境産業市場規模関連
[1] 環境産業の市場規模、雇用規模の推計:「次世代省エネルギー住宅」等9分野を新たな推計対象とした他、必要な推計方法の改善を実施した上で、2000年までの遡及改定を実施しました。その結果、環境産業の市場規模はリーマンショック等の影響により2009年に縮小しましたが、2010年から景気の持ち直し等を受けて増加に転じ、2011年は約82兆円(前年比約2.3%増)と2年連続の増加となりました。また2011年雇用規模は約227万人(前年比1.3%増)となりました。
[2] 推計対象外の環境製品・サービス:継続的な推計に適さない等により今回の推計には含まないが、重要と思われる項目(除染、がれき処理、炭素繊維等)について市場規模の試算を含めて整理を行いました。
[3] 環境産業の付加価値、輸出入の推計:市場規模推計に産業連関表の情報を加味し、2011年環境産業の付加価値額は約35兆円(2011年の名目GDPの約7.5%)、輸出額は約7.7兆円、輸入額は約1.5兆円との試算結果を得ました。
(2) 環境成長エンジン報告書
環境産業・ビジネスが経済成長のエンジン(原動力)とならんとする動きを分析する本報告書では、以下をまとめました。
[1] 東日本大震災によって市場環境に大きな変化が見られる等、特徴的な12の環境産業分野の分析を行いました。そのうち、24年7月の固定価格買取制度導入により注目される再生可能エネルギー発電事業の設備投資や運営段階の資金投入が及ぼす経済波及効果を試算し、いずれも産業平均以上の高い波及効果があることを示しました。
[2] 環境ビジネスを展開する企業19社へのヒアリングにより、参入の経緯、市場における位置づけ、海外市場への展開状況、成功・差別化要因、今後の展望・課題、政策への要望等を整理しました。
[3] 上記を素材として環境ビジネスを分析するに際し、a)政策・制度/事業環境、b)事業のコア(技術・ビジネスモデル等)、c)調達、d)販売市場、という4つの側面から捉えることとし、環境産業のより一層の振興を図るために、政府及び企業それぞれに求められる対応策を提示しました。
いずれも環境経済情報ポータルサイト上、「環境産業情報」において公表いたします。
http://www.env.go.jp/policy/keizai_portal/B_industry/index.html
2013年04月11日
当面の地球温暖化対策に関する方針
当面の地球温暖化対策に関する方針
平成2 5 年3 月1 5 日地球温暖化対策推進本部決定
地球温暖化の進行は、気候変動により人類の生存基盤及び社会経済の存立基盤を揺るがす重大な脅威である。地球温暖化がもたらす脅威に対し、現在及び将来における国民の生命・身体・財産の安全を確保するため、今後とも、環境と経済の両立を図りつつ、切れ目なく地球温暖化対策を推進する必要がある。第四次環境基本計画(平成24 年4月27 日閣議決定)においても、地球温暖化対策の長期的な目標として、2050 年までに80%の温室効果ガスの排出削減を目指すこととしている。
これを踏まえ、地球温暖化対策推進本部は、当面の地球温暖化対策に関する方針について、次のとおり決定する。
Ⅰ.平成25 年度以降の地球温暖化対策に関する基本的方針
これまで我が国は、京都議定書第一約束期間における温室効果ガスの6%削減目標に関し、京都議定書目標達成計画(平成17 年4 月閣議決定、平成20 年3 月全部改定)に基づく取組を進めてきた。引き続き、個別の取組の検証は必要であるものの、6%削減目標は達成可能と見込まれている。
我が国は京都議定書第二約束期間には参加せず、同計画は本年度末を以て終了することとなるが、平成25 年度以降、国連気候変動枠組条約の下のカンクン合意に基づき、平成32 年(2020 年)までの削減目標の登録と、その達成に向けた進捗の国際的な報告・検証を通じて、引き続き地球温暖化対策に積極的に取り組んでいくこととする。
まず、2020 年までの削減目標については、本年11 月の国連気候変動枠組条約第19回締約国会議(COP19)までに、25%削減目標をゼロベースで見直すこととする。
その実現のための地球温暖化対策計画の策定に向けて、中央環境審議会・産業構造審議会の合同会合を中心に、関係審議会において地球温暖化対策計画に位置付ける対策・施策の検討を行う。この検討結果を踏まえて、地球温暖化対策推進本部において地球温暖化対策計画の案を作成し、閣議決定することとする。
また、地球温暖化対策計画の策定の法的根拠となる「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」を今国会に提出し、その成立に万全を期すこととする。
Ⅱ.地球温暖化対策計画の検討方針
地球温暖化対策計画に位置付ける対策・施策については、京都議定書目標達成計画の実施及び進捗点検を通じて得られた知見を十分に活用しながら、エネルギー政策の検討状況を考慮しつつ、我が国の経済活性化にも資するものを目指す。その際、対策ごとの目標(対策評価指標)を設定するとともに、対策ごとの目標を達成するための施策を具体的に示すこととする。
特に、再生可能エネルギーや省エネルギーについては、東日本大震災以降、事業者及び国民による取組が拡大してきたことを踏まえ、これをさらに加速させ、我が国の技術と知恵を活用しながら、低炭素社会の創出にも資するよう、最大限の推進を図るものとする。
エネルギー起源二酸化炭素の各部門の対策については、「低炭素社会実行計画」に基づく事業者による自主的な取組に対する評価・検証等を進めるとともに、排出抑制等指針の策定・公表・運用を始めとする制度的対応や、各種の支援措置等を進めるものとする。
代替フロン等に関する対策を抜本的に強化し、フロン類の製造、製品への使用等を含むライフサイクル全体にわたる排出抑制対策を進める。
国際的に合意された新たなルールに則った森林等の吸収源対策や、バイオマス等の有効活用を積極的に推進する。
新たな削減目標の達成に向けた対策・施策については、定期的かつ定量的な評価を行うことにより厳格に進捗状況を点検するとともに、必要に応じ内容の見直しを行うこととする。
さらに、途上国への温室効果ガス削減技術、製品、システム、サービス、インフラ等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価し、我が国の削減目標の達成に活用するため、二国間オフセット・クレジット制度を構築・実施していく。
併せて、地球温暖化についての観測・監視等の継続、科学的知見の収集、調査の実施及び温暖化問題の解決のための研究・技術開発、低炭素な地域づくりに向けた取組、低炭素社会の創出に向けた国民運動の展開等多様な政策手段を活用することにより、国民の関心と理解の増進や排出削減・吸収の取組の促進に一層努めるものとする。
また、今後避けることのできない地球温暖化の影響への適切な対処(適応)を計画的に進める。
さらに、全ての国が参加する2020 年以降の将来枠組みについて2015 年の合意を目指し、今後の国際的な議論に積極的に参画する。
Ⅲ. 新たな地球温暖化対策計画の策定までの間の取組方針
地球温暖化対策を切れ目なく推進する必要性に鑑み、新たな地球温暖化対策計画の策定に至るまでの間においても、地方公共団体、事業者及び国民には、それぞれの取組状況を踏まえ、京都議定書目標達成計画に掲げられたものと同等以上の取組を推進することを求めることとし、政府は、地方公共団体、事業者及び国民による取組を引き続き支援することで取組の加速を図ることとする。
また、政府は、新たな地球温暖化対策計画に即した新たな政府実行計画の策定に至るまでの間においても、現行の政府実行計画に掲げられたものと同等以上の取組を推進することとする。
2013年04月11日
白書 語句説明 [あ]
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律
愛がん動物用飼料(ペットフード)の製造等に関する規制を行うことにより、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物(ペット)の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする法律。平成21年6月1日施行。
悪臭防止法
工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としたもの。同法では都道府県知事(指定都市、中核市、特例市及び特別区においてはその長)が規制地域の指定及び規制基準の設定を行うこととしている。また、平成12年5月に改正され、臭気測定業務従事者(臭気判定士)制度や事故時の措置について規定された。
アジア森林パートナーシップ
アジアの持続可能な森林経営の促進を目的として、アジア・大洋州諸国や欧米諸国、国際機関、市民社会、民間セクター等の間での自発的な協力を促進するためのパートナーシップ。わが国とインドネシア政府が提唱し、2002年(平成14年)のヨハネスブルグサミットにおいて、タイプ2の取組(各国政府、国際機関、NGO等が自主的に参加する取組)として発足した。
アジア太平洋環境イノベーション戦略プロジェクト
Asia-Pacific Environmental Innovation Strategy Project(アジア太平洋環境イノベーション戦略プロジェクト)。アジア太平洋地域の持続可能な開発に関する政策決定を支援するため、地域内研究機関と共同で、環境モニタリング及びモデリング等の科学的ツール、革新的な政策オプションの開発・提供を目的としている国際共同研究プロジェクト。
アジア太平洋環境会議
アジア太平洋地域各国の環境大臣及び関係国際機関の代表等による自由な意見交換を行う場を提供することにより、この地域における環境分野での協力を推進し、持続可能な開発の実現に資することを目的として、1991年(平成3年)よりほぼ毎年日本で開催している。
アジア太平洋環境開発フォーラム
アジア太平洋環境開発フォーラム。アジア太平洋地域にふさわしいより衡平で持続可能な開発のモデルを提示することを目的に、エコアジア2001において設立された有識者会議。2005年度(平成17年度)より第2段階目の活動(APFEDII)として、2004年(平成16年)12月に取りまとめられた提言を実施すべく取り組んでいる。
アジア太平洋地球変動研究ネットワーク
アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN=Asia-Pacific Network for Global Change Research)は、アジア太平洋地域における地球変動研究を推進し、科学研究と政策決定の連携を促進することを目的として1996年に発足した政府間ネットワークであり、現在21か国が参加している。
アジア水環境パートナーシップ
アジア地域を中心に水環境管理体制の強化を目指して、水環境に関するデータベースの構築や共通課題に関する議論を通じた政府職員の人材育成を行っている環境省の水問題に関する国際協力事業。(関係パートナー国:カンボジア、中国、インドネシア、韓国、ラオス、マレーシア、ミャンマー、ネパール、フィリピン、スリランカ、タイ、ベトナム、日本)
アジェンダ21
21世紀に向け持続可能な開発を実現するために各国及び各国際機関が実行すべき行動計画を具体的に規定するものとして、1992年6月にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された国際会議(通称:地球サミット)で採択。持続可能な開発を実現するための具体的な行動計画である「アジェンダ21」が合意された。大気、水、廃棄物などの具体的な問題についてのプログラムとともに、この行動を実践する主要グループの役割強化、財源などの実施手段のあり方が規定されている。
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律
有明海及び八代海等を豊かな海として再生することを目的として、両海域の再生に関する基本方針を定めるとともに、当該海域の環境の保全及び改善並びに水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画を策定し、その実施を促進するための特別の措置を講ずることを定めている。
2013年04月11日
白書 語句説明 [い]
イタイイタイ病
厚生省(当時)の公式見解によれば、「イタイイタイ病の本態はカドミウムの慢性中毒によりまず腎臓障害を生じ、次いで骨軟化症をきたし、これに妊娠、授乳、内分泌の変調及び栄養としてのカルシウム等の不足などが誘因となって、イタイイタイ病という疾患を形成したものである。骨軟化症のため、容易に骨折がおこったり、そのため激しい痛みを患者が感じ、体型の変型をおこす。三井金属鉱山神岡工業所の事業活動に伴って排出されたカドミウム等の重金属が神通川を汚染し、かつ流域の土壌汚染をひきおこし、食品濃縮の過程を経て人間に多量のカドミウムが摂取された結果、発病したもの」とされている。
一酸化炭素
燃料等の不完全燃焼により生じ、自動車が主な発生源とされている。COは血液中のヘモグロビンと結合して酸素運搬機能を阻害する等の健康への影響のほか、温室効果のあるメタンの寿命を長くする。
一般環境大気測定局
一般環境大気の汚染状況を常時監視する測定局。
一般局
「一般環境大気測定局」参照。
一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物。一般廃棄物はさらに「ごみ」と「し尿」に分類される。また、「ごみ」は商店、オフィス、レストラン等の事業活動によって生じた「事業系ごみ」と一般家庭の日常生活に伴って生じた「家庭ごみ」に分類される。
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
カルタヘナ議定書を国内で担保するために、使用形態に応じた遺伝子組換え生物等の使用等の規制、輸出入に関する手続等について定めた法律。平成15年6月に公布され、平成16年2月に施行。
インターネット自然研究所
国民の自然環境に対する理解と関心を深めるため、親しみやすく、かつ実用的な自然環境情報を提供するホームページ。さまざまなIT(情報技術)を活用することにより、最新の自然情報の提供や環境教育・環境学習に役立つ豊富なコンテンツを分かりやすく提供している。(インターネット自然研究所(別ウィンドウ))
インベントリータスクフォース
温室効果ガスの排出・吸収量の算定の精度を高め、その方法を各国間で統一するため、科学的な立場から検討することを目的に、IPCC内に設置されたタスクフォース。平成11年7月にIGES内に、そのタスクフォースを支える技術支援ユニットが設置されており、わが国はその中核的機能を担っている。
2013年04月11日
白書 語句説明 [う]
ウォーム・ビズ
暖房時のオフィスの室温を20℃にした場合でも、ちょっとした工夫により「暖かく効率的に格好良く働くことができる」というイメージを分かりやすく表現した、秋冬の新しいビジネススタイルの愛称。重ね着をする、温かい食事を摂る、などがその工夫例。
埋立指令
最終処分場の分類(有機物、有害廃棄物、非有害廃棄物、安定廃棄物)、埋立禁止物(液状廃棄物、爆発性・腐食性・酸化性・引火性廃棄物、感染性廃棄物、研究等に使用した環境影響が未知の化学物質、使用済みタイヤ、未処理の廃棄物)、中間処理の義務付け(埋立前の前処理)、生分解性廃棄物の埋立量減少等が定められている。
2013年04月11日
白書 語句説明 [え]
エコアクション21
中小企業等においても容易に環境配慮の取組を進めることができるよう、環境マネジメントシステム、環境パフォーマンス評価及び環境報告を一つに統合した環境配慮のツール。幅広い事業者に対して環境への取組を効果的・効率的に行うシステムを構築するとともに、環境への取組に関する目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価し、報告するための方法を提供している。平成21年11月に、環境問題に関する昨今のさまざまな動きを踏まえ、さらに取り組みやすく、またレベルアップが図れるように、その内容を全面的に改訂した。
エコアジア
「アジア太平洋環境会議」参照。
エコカー減税
一定の排ガス性能、燃費性能を備えた自動車に対する自動車重量税・自動車取得税の時限的免除・軽減措置。減免対象となるのは電気自動車(燃料電池自動車を含む)、一定の環境性能を備えた天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル乗用車、一定の環境性能を備えたハイブリット車、一定の環境性能を備えたガソリン車(乗用車等、中量車)及び一定の環境性能を備えたディーゼル車(中量車、重量車)であり、自動車重量税にあっては平成24年5月1日から平成27年4月30日までの新車に係る新規車検時等、自動車取得税にあっては平成24年4月1日から平成27年3月31日までの新車取得時に納付する税額について、それぞれ免除・軽減される。
エコタウン事業
先進的な環境調和型のまちづくりを推進することを目的として、平成9年度に創設された事業。具体的には、それぞれの地域の特性に応じて、都道府県又は政令指定都市が作成したプランについて環境省と経済産業省の共同承認を受けた場合、当該プランに基づき実施される事業について、総合的・多面的な支援を実施するもの。
エコツーリズム
自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴史文化の保全に責任をもつ観光のあり方。一般には1982年にIUCN(国際自然保護連合)が「第3回世界国立公園会議」で議題としてとりあげたのが始まりとされている。日本においてもエコツアーが数多く企画・実施されており、環境省では持続可能な社会の構築の手段としてエコツーリズムの推進に向けた取組を進めている。
エコツーリズム推進法
エコツーリズムに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、エコツーリズムについての基本理念、政府による基本方針の策定、特定自然観光資源の保護に関する措置等を定める法律。平成20年4月1日施行。
エコファーマー
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)に基づき土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む計画を立て、都道府県知事の認定を受けた農業者の愛称。
エコレールマーク
CO2排出量の少ない、環境にやさしい鉄道貨物輸送を活用して地球環境問題に積極的に取り組んでいる企業や商品であると認定された場合に、その商品や企業の広告等に表示されるマーク。
エコロジカル・ネットワーク
人と自然の共生を確保していくため、原生的な自然地域等の重要地域を核として、生態的なまとまりとを考慮した上で、有機的に繋いだ生態系のネットワーク。ネットワークの形成により、野生生物の生息・生育空間の確保、人と自然とのふれあいの場の提供、地球温暖化防止等多面的な機能が発揮されることが期待される。
エコロジカルフットプリント
人間の生活がどれほど自然環境に依存しているかを分かりやすく示す指標。「人類の地球に対する需要を、資源の供給と廃棄物の吸収に必要な生物学的生産性のある陸地・海洋の面積で表したもの」として計算する。
エネルギーの使用の合理化に関する法律
内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具についてエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律である。平成20年の法改正(平成22年4月より施行)において、工場・事業場単位でのエネルギー管理を義務付け、業務部門における省エネルギー対策を強化した。
エルニーニョ現象
数年に一度、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米のペルー沿岸にかけての広い海域で海面水温が平年に比べて高くなる現象で、日本を含む世界各地の天候に大きな影響を及ぼす。
2013年04月11日
白書 語句説明 [お]
オイルサンド
高粘度の原油を含む砂岩層。
オゾン層
地球を取り巻く大気中のオゾンの大部分は地上から約10~50km上空の成層圏に存在し、オゾン層と呼ばれている。太陽光に含まれる有害紫外線の大部分を吸収し、地球上の生物を保護する役割を果たす。
オゾン層の保護のためのウィーン条約
オゾン層の保護のための国際的な対策の枠組みを定めた条約。国際的に協調して各国が適切な措置を講じ、オゾン層やオゾン層を破壊する物質に関する研究や組織的観測を進めること等を定めている。1985年(昭和60年)に採択され、わが国は1988年(昭和63年)に締結。
オゾン層保護法
「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」参照。
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書
国際的に協調してオゾン層保護対策を推進するため、オゾン層破壊物質の生産削減等の規制措置等を定めたもの。1987年(昭和62年)に採択され、わが国は1988年(昭和63年)に締結した。当初の予想以上にオゾン層破壊が進行していること等を背景として、これまで6度にわたり規制対象物質の追加や規制スケジュールの前倒し等、段階的に規制強化が行われている。
オゾンホール
南極域等の上空でオゾンの量が大きく減少した領域。南極域上空では、冬から春にかけて極めて低温な状態となり、極域成層圏雲と呼ばれる雲が生じる。成層圏に到達したCFC等由来の塩素や臭素は、この雲の粒子表面での反応で活性度の高い状態に変換され、春(9~11月)の太陽の光によってさらに分解された塩素原子や臭素原子が、触媒となって連鎖的にオゾンを破壊する。
オフセット・クレジット制度
国内のプロジェクトによる温室効果ガス排出削減・吸収量について、環境省が運営するオフセット・クレジット(J-VER)認証運営委員会が、排出削減・吸収の信頼性を審査し、カーボン・オフセットに用いることのできる市場流通可能なクレジット(J-VER: Japan Verified Emission Reduction)として認証する制度。
オフロード法
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」参照。
温室効果ガス
大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し再放出する気体。京都議定書では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄の6物質が温室効果ガスとして排出削減対象となっている。
温泉法
「温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もって公共の福祉の増進に寄与すること」を目的とする法律で、昭和23年に制定。これは、貴重な自然資源である温泉の保護等を図るために、温泉を掘削し、ゆう出路を増掘しもしくは動力を装置しようとする場合又は温泉の採取を業として行おうとする場合は都道府県知事の許可を、温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合は都道府県知事又は保健所設置市の市長等の許可を受けなければならないなどの必要な手続を定めるとともに、温泉の公共的利用増進のための地域指定等について規定している。
2013年04月11日
白書 語句説明 [か]
カーボン・オフセット
自らの日常生活や企業活動等による温室効果ガス排出量のうち削減が困難な量の全部又は一部を、ほかの場所で実現した温室効果ガスの排出削減や森林の吸収等をもって埋め合わせる活動。
カーボンフットプリント制度
カーボンフットプリント。商品・サービスの原材料調達から廃棄・リサイクルにいたるライフサイクル全体における温室効果ガス排出量をCO2量に換算し表示する仕組み。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、油、有害液体物質等及び廃棄物を海底下廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制すること等により、海洋汚染等の防止を図るための法律。
海洋汚染防止法
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」参照。
海洋地球研究船「みらい」
海洋研究開発機構が所有する海洋観測船(全長128.6m、総トン数8,687トン)。耐氷性にすぐれ、また、荒天時も安定した観測が可能。気候変動とかかわりがあるとされる、海洋の熱・物質循環の解明などをミッションとする。
外来種
国外や国内の他地域から人為的(意図的又は非意図的)に導入されることにより、本来の分布域を越えて生息又は生育することとなる生物種。外来種のうち、導入先の生態系等に著しい影響を与えるものを特に侵略的な外来種と呼び、これらは自然状態では生じ得なかった影響を人為的にもたらすものとして問題となっている。
科学技術連携施策群
各府省の縦割りの施策に横串を通す観点から、総合科学技術会議が行う、各府省の関連施策の不必要な重複を排除し連携を強化して研究を推進する体制。
化学品の分類及び表示に関する世界調和システム
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals(GHS)。化学品の危険有害性(ハザード)ごとの各国の分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一したルールとして提供するもの。2003年7月に国際連合から勧告がなされ、日本を含め各国はこれを受けて、今後、化学品の分類や表示を適切に行っていくよう努力することが求められている。
化学物質アドバイザー
市民、企業、行政からの要請に応じて、中立的な立場で化学物質や化学物質による環境リスク、PRTR制度の仕組みに関する疑問に答えたり、関連する情報を提供することなどにより、化学物質に関するリスクコミュニケーションを推進するための専門的な能力を有する人材。平成15年4月より派遣を開始している。
化学物質審査規制法
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」参照。
化学物質と環境に関する政策対話
市民、労働者、事業者、行政、学識経験者等の様々な主体により化学物質と環境に関して意見交換を行い、合意形成を目指すとともに、化学物質に関する国民の安全・安心の確保に向けた政策提言を目指す場として、平成23年度に設置されたもの。
化学物質の内分泌かく乱作用
化学物質が、内分泌系に影響を及ぼすことにより、生体に障害や有害な影響を引き起こす外因性の作用。
化学物質の内分泌かく乱作用に関する今後の対応- EXTEND 2010 -
1998年(平成10年)に策定された「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」を改訂し、2005年(平成17年)に化学物質の内分泌かく乱作用に関する新たな取り組み方針としてまとめられた「ExTEND2005」の内容より、重点的に実施すべき課題の抽出を行い、2010年(平成22年)7月、環境省の新たな取り組み方針をまとめたもの。「EXTEND2010」では、ExTEND2005の内容を基本的に踏襲しつつ、化学物質の内分泌かく乱作用に伴う環境リスクを適切に評価し、必要に応じ管理していくことを目標として、評価手法の確立と評価の実施の加速化をねらいとしている。
化学物質排出把握管理促進法
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」参照。
拡大生産者責任
EPR:Extended Producer Responsibility。生産者が、その生産した製品が使用され、廃棄された後においても、当該製品の適正なリサイクルや処分について物理的又は財政的に一定の責任を負うという考え方。具体的には、製品設計の工夫、製品の材質・成分表示、一定製品について廃棄等の後に生産者が引取りやリサイクルを実施すること等が含まれる。OECDでは2000年に加盟国政府に対するガイダンス・マニュアルを策定している。
カスケード利用
リサイクルを行った場合には、通常その度に品質の劣化が起こる。このため、無理に元の製品から同じ製品にリサイクルせずに、品質劣化に応じて、より品質の悪い原材料でも許容できる製品に段階的にリサイクルを進めていくことで効率的なリサイクルを行うことをいう。紙について、コピー用紙、新聞紙、段ボールへと段階的に利用していくことがその例。なお、エネルギーについても、熱エネルギーを温度の高いほうから順に、電気(照明・動力)、次いで蒸気(冷暖房)、さらに温水(給湯)といったかたちで有効利用することをエネルギーのカスケード利用という。
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(家畜排せつ物法)
畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し必要な事項を定めるとともに、家畜排せつ物の処理の高度化を図るための施設の整備を計画的に促進する措置を講ずることにより、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進を図り、もって畜産業の健全な発展に資することを目的とする法律。
家畜排せつ物法
「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」参照。
家電リサイクル法
「特定家庭用機器再商品化法」参照。
花粉観測システム(愛称:はなこさん)
花粉の飛散状況をリアルタイムで情報提供するシステム。(環境省花粉観測システム(はなこさん)(別ウィンドウ))
カリンB号事件
1988年に起きた有害廃棄物の越境移動に伴う国際環境問題を象徴する事件。高度処理とコストが必要な有害廃棄物を規制の緩い開発途上国で投棄する事件が各地で頻発。開発途上国は深刻な環境影響を被るため、有害廃棄物の国境を越える移動等の規制に関するバーゼル条約(1989年)の採択につながった。
カルタヘナ議定書
正式名称「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」。遺伝子組換え生物等の利用等による生物多様性保全等への影響を防止するために、特に国境を越える移動に焦点をあわせた国際的な枠組み。
カルタヘナ法
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」参照。
環境GIS
環境の状況等を地理情報システム(Geographic Information System: GIS)を用いて提供する、国立環境研究所が運営するウェブサイト。
環境JIS
環境・資源保全に関するJIS(日本工業規格)。3R対策、設計・生産段階での環境配慮、地球温暖化対策、有害化学物質対策、環境汚染対策などの推進に利用するJISを指す。
環境影響評価
環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業について、その事業の実施に当たり、あらかじめその事業の環境への影響を調査、予測、評価し、その結果に基づき、その事業について適正な環境配慮を行うこと。わが国においては、環境影響評価法等に基づき、道路やダム、鉄道、発電所などを対象にして、地域住民や専門家や環境担当行政機関が関与しつつ手続が実施されている。
環境会計
企業等が、社会との良好な関係を保ちつつ環境保全への取組を効率的かつ効果的に推進していくことを目的として、事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的(貨幣単位又は物量単位)に測定する仕組み。この中でも、企業の廃棄物削減と生産性向上に着目したものをマテリアルフローコスト会計という。
環境カウンセラー
環境保全に関する専門的知識や豊富な経験を有し、環境省の実施する審査に合格し、その知識や経験をもとに市民や事業者等の環境保全活動に対して助言等を行うことのできる人材。
環境関連税
OECD統計上、強制的、一方的な政府への支払いであって、特定の環境関連と考えられる課税対象に課せられるものと定義されている。環境に関連した課税対象には、エネルギー製品、自動車、輸送機関、廃棄物管理、オゾン層破壊物質等が含まれる。(「OECD環境データ集」(2006年、2007年版))
環境技術実証事業
すでに適用可能な段階にありながら、普及が進んでいない先進的環境技術の環境保全効果等を、第三者が客観的に実証する事業。
環境基準
環境基本法第16条の規定に基づき、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として国が定めるもの。
環境基本計画
環境基本法第15条に基づき、政府全体の環境保全施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、総合的かつ長期的な施策の大綱などを定める計画である。平成6年に第1次計画、平成12年に第2次計画、平成18年に第3次計画、平成24年に第4次計画が閣議決定された。
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
持続可能な社会を構築する上で国民、民間団体等が行う環境保全活動並びにその促進のための環境保全の意欲の増進及び環境教育が重要であることに加え、これらの取組を効果的に進める上で協働取組が重要であることに鑑み、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組について、基本理念を定め、並びに国民、民間団体等、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に必要な事項を定める法律。
環境研究総合推進費
環境問題が人類の生存基盤に深刻かつ重大な影響を及ぼすことにかんがみ、さまざまな分野における研究者の総力を結集して学際的、国際的な観点から総合的に調査研究及び技術開発を推進し、もって持続可能な社会構築のための環境保全に資することを目的とした政策指向型の競争的研究資金。平成22年度より、地球環境研究総合推進費と環境研究・技術開発推進費を統合。また、平成23年度より循環型社会形成推進科学研究費補助金を統合。
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律
事業者の自主的な環境配慮の取組を促進することをねらいとして、環境報告書の普及促進と信頼性向上のための制度的枠組みの整備や一定の公的法人(特定事業者)に対する環境報告書の作成・公表の義務付け等について規定。平成17年4月1日より施行。
環境と開発に関する国連会議
1992年(平成4年)開催。地球温暖化、酸性雨等顕在化する地球環境問題を人類共通の課題と位置付け、「持続可能な開発」という理念の下に環境と開発の両立を目指した。各国や国際機関が遵守すべき原則である環境と開発に関するリオ宣言、同宣言を達成するための行動原則であるアジェンダ21などを採択するとともに、気候変動枠組条約・生物多様性条約の署名が開始され、砂漠化対処条約策定について基本合意された。
環境配慮契約
「グリーン契約」参照。
環境配慮契約法
「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」参照。
環境配慮設計
DfE:Design for Environment。分解が容易である、リサイクルしやすいよう単一素材を使用するなど製品等の設計段階において環境配慮を行うための手法のこと。環境適合設計や、エコ・デザインともいう。
環境配慮促進法
「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」参照。
環境報告ガイドライン
環境報告書に係る国内外の最新の動向を踏まえ、その望ましいと思われる方向及び内容を取りまとめ、環境報告書を作成・公表しようと考える事業者、すでに環境報告書を作成・公表している事業者に対し、実務的な手引きとなるよう環境省が作成したもの。
環境報告書
名称の如何を問わず、事業者が、事業活動に係る環境配慮の方針、計画、取組の体制、状況や製品等に係る環境配慮の状況等の事業活動に係る環境配慮等の状況を記載した文書。
環境放射線等モニタリングデータ公開システム
放射性物質などのデータを専用のホームページで情報提供するシステム。(環境放射線等モニタリングデータ公開システム(別ウィンドウ))
環境保護に関する南極条約議定書
国際的に高い価値が認められている南極地域(南緯60度以南の地域)の環境及びそれに依存する生態系の保護を目的としている議定書。議定書は、本文及び5つの附属書で構成されており、各附属書において、環境影響評価の実施、動植物相の保護、廃棄物の処分及び管理、海洋汚染の防止並びに特定別保護地区の保護及び管理が規定されている。1991年(平成3年)に採択、1997年(平成9年)に受諾。議定書本文及び附属書I~IVについては1998年(平成10年)に、附属書Vについては2002年(平成14年)に発効。
環境マネジメント
事業者が自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標等を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくこと。
環境ラベリング
「環境ラベル」参照。
環境ラベル
製品の環境側面に関する情報を提供するものであり、
1)「エコマーク」など第三者が一定の基準に基づいて環境保全に資する製品を認定するもの、
2)事業者が自らの製品の環境情報を自己主張するもの、
3)ライフサイクルアセスメント(LCA)を基礎に製品の環境情報を定量的に表示するもの等がある。
環境リスク
人の活動によって環境に加えられる負荷が環境中の経路を通じ、環境の保全上の支障を生じさせるおそれ(人の健康や生態系に影響を及ぼす可能性)。
環境リスク評価
環境リスクの大きさを判定すること。化学物質であれば、人の健康及び生態系に対する有害性を特定し、用量(濃度)-反応(影響)関係を整理する(有害性評価)とともに、人及び生態系に対する化学物質の環境経由のばく露量を見積もり(ばく露評価)、両者の結果を比較考慮することによってリスクの程度を判定する。これには、まず多数の化学物質の中から相対的に環境リスクが高そうな物質をスクリーニングするための「初期評価」と、次の段階で化学物質の有害性及びばく露に関する知見を充実させて評価を行い、環境リスクの管理方策などを検討するための「詳細評価」がある。
環境ロードプライシング
有料道路の料金に格差を設け、住宅地域に集中した交通を環境影響の少ない地域に誘導することを目的とした施策。
官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム
産業界と国が連携して、既存化学物質の安全性情報(物理化学的性状、人への毒性、生態毒性等)の収集を加速化し、化学物質の安全性について広く国民に情報発信することを目的に、平成17年6月から開始したプログラム。
2013年04月11日
白書 語句説明 [き]
企業の社会的責任(CSR)
Corporate Social Responsibility。企業は社会的な存在であり、自社の利益、経済合理性を追求するだけではなく、ステークホルダー(利害関係者)全体の利益を考えて行動するべきであるとの考え方であり、行動法令の遵守、環境保護、人権擁護、消費者保護などの社会的側面にも責任を有するという考え方。
気候変動に関する国際連合枠組条約
一般的に気候変動枠組条約と呼ばれる。地球温暖化対策に関する取組を国際的に協調して行っていくため1992年(平成4年)5月に採択され、1994年(平成6年)3月に発効した。本条約は、気候系に対して危険な人為的影響を及ぼすこととならない水準において、大気中の温室効果ガス濃度を安定化することをその究極的な目的とし、締約国に温室効果ガスの排出・吸収目録の作成、地球温暖化対策のための国家計画の策定とその実施等の各種の義務を課している。
気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書
一般的に京都議定書と呼ばれる。1997 年12 月に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)において採択された。先進各国の温室効果ガスの排出量について法的拘束力のある数値目標が決定されるとともに、排出量取引、共同実施、クリーン開発メカニズムなどの新たな仕組みが合意された。2005年2月に発効。米国は批准していない。
気候変動に関する政府間パネル
1988年(昭和63年)に、国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)により設立。地球温暖化に関する科学的・技術的・社会経済的な評価を行い、得られた知見を政策決定者をはじめ広く一般に利用してもらうことを任務とする。5~6年ごとに地球温暖化について網羅的に評価した評価報告書を発表するとともに、適宜、特別報告書や技術報告書、方法論報告書を発表している。
揮発性有機化合物
トルエン、キシレン等の揮発性を有する有機化合物の総称であり、塗料、インキ、溶剤(シンナー等)などに含まれるほかガソリンなどの成分になっているものもある。
キャップ・アンド・トレード方式
政府が、排出枠(温室効果ガスを排出することのできる上限量)の交付総量を設定し、個々の事業者に排出枠を割り当てる制度。同時に、各主体間での排出枠の取引等を通じて、自らの排出量と同量の排出枠を確保することにより、削減義務を達成したとみなす制度。域内・国内制度としてEUや米国等で導入・検討されており、わが国でも、地球温暖化対策基本法案において、本方式による国内排出量取引制度の創設が盛り込まれた。
共通だが差異のある責任及び各国の能力の原則
地球環境問題の解決における基本原則の一つとして用いられる考え方。各国は、地球環境問題に対して共通責任があるが、その責任の程度の差異や、各国の資金や技術等の負担能力の違いを背景として、地球環境問題解決において果たすべき役割が異なってくるという考え方。
共同実施
Joint Implementation(JI)。京都議定書による京都メカニズムの一種類(第6条)。先進国同士が温室効果ガスの排出削減・吸収増進事業を共同で行い、その結果生じた削減量・吸収量を投資国が自国の削減目標達成のために利用できる制度。
京都議定書
「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」を参照。
京都議定書目標達成計画
地球温暖化対策の推進に関する法律第8条に基づき、平成17年4月に閣議決定され、平成20年3月に改定された、京都議定書によるわが国の6%削減約束を達成するために必要な対策・施策を盛り込んだ計画。
京都メカニズム
京都議定書において導入された、国際的に協調して数値目標を達成するための制度。
1)国際排出量取引(International Emissions Trading)、
2)共同実施(JI:Joint Implementation)、
3)クリーン開発メカニズム(CDM:Clean Development Mechanism)の3種類がある。
業務用冷凍空調機器
業務用のエアコンディショナー並びに冷蔵機器及び冷凍機器(自動販売機を含む)。多くの場合、冷媒としてフロン類が充てんされているため、オゾン層保護及び地球温暖化防止の観点から、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」により、機器の整備時及び廃棄時に、当該機器に充てんされているフロン類を適切に回収し、破壊処理すること等が義務付けられている。
2013年04月10日
白書 語句説明 [く]
クール・ビズ
冷房時のオフィスの室温を28℃にした場合でも、「涼しく効率的に格好良く働くことができる」というイメージを分かりやすく表現した、夏の新しいビジネススタイルの愛称。「ノーネクタイ・ノー上着」スタイルがその代表。
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律
環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築するため、国等の公的部門が契約をする際に、価格だけでなく、温室効果ガス等の排出等、環境への負荷をも考慮すること等を目的としている。平成19年11月22日施行。
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
国等の公的機関が率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り,持続的発展が可能な社会を構築を推進することを目的としている。平成13年4月1日施行。
グリーン・イノベーション
平成21年10月8日総合科学技術会議の「平成22年度の科学技術に関する予算等の資源配分の方針」によれば、革新的な環境・エネルギー技術の研究開発の加速化・新技術の創出を行い、その研究開発成果の実利用・普及を強力に推進するために社会システムの転換を図り、これを通じて産業・社会活動の効率化、新産業の創造や国民生活の向上に資するものであり、わが国のみならず世界規模での環境と経済が両立した低炭素社会の構築に貢献するものとされている。
グリーン・ツーリズム
農山漁村地域において自然・文化、農林漁業とのふれ合いや人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。
グリーン・ニューディール
厳密な定義はないが、一般的には、環境分野への投資を通じた景気浮揚策を指すことが多い。
クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ
2005年7月にアジア太平洋を中心に、クリーンで効率的な技術の開発・普及・移転を通じ、増大するエネルギー需要、エネルギー安全保障、気候変動問題などに対処するために設立された。参加国は、米国、カナダ、オーストラリア、中国、インド、日本、韓国の7か国。参加国間のボランタリーな官民パートナーシップを基本とし、気候変動枠組条約に整合的であり、また京都議定書を代替するものではなく、これを補完するものである。
クリーン開発メカニズム
Clean Development Mechanism(CDM)。京都議定書第12条に規定する京都メカニズムの一種類。議定書の削減約束を達成するに当たって、先進国と途上国が共同で排出削減・植林事業を行い、その結果生じた削減量・吸収量を「認証された排出削減量(クレジット)」として事業に貢献した先進国等が獲得できる制度。途上国にとっては投資と技術移転がなされるメリットがある。
グリーン契約(環境配慮契約)
製品やサービスを調達する際に、環境への負荷ができるだけ少なくなるような工夫をした契約。
グリーン購入
製品やサービスを購入する際に、その必要性を十分に考慮し、購入が必要な場合には、できる限り環境への負荷が少ないものを優先的に購入すること。
グリーン購入法
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」参照。
クリーンな環境のための北九州イニシアティブ
2000年(平成12年)9月の国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)環境大臣会議において採択された「クリーンな環境のための北九州イニシアティブ」等の効果的な実施に向けて2001年(平成13年)11月に発足したアジア太平洋地域の都市間ネットワーク。
グリーン物流パートナーシップ会議
物流部門でのCO2の一層の削減を図るため、荷主企業と物流事業者の連携・協働(パートナーシップ)により、物流システムの改善に向けた施策の幅を広げ、中小企業を含めた裾野の広い取組拡大を図るため、平成17年4月に正式発足した会議体。荷主企業、物流事業者、地方公共団体、シンクタンク、有識者など3,200を越える会員登録がある(平成23年3月現在)。
2013年04月10日
白書 語句説明 [け]
景観法
都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制等所要の措置を講ずる日本で初めての景観についての総合的な法律。
経済協力開発機構(OECD)
世界経済の発展、途上国経済の健全な拡大、多角的かつ無差別な世界貿易の拡大のための政策の推進を目的とした国際機関であり、現在34か国(2010年にチリ、スロベニア、イスラエル、エストニアの4か国が新規加盟)が加盟している。
京阪神圏ゴミゼロ型都市推進協議会
都市再生本部で決定されたプロジェクトである「大都市圏におけるゴミゼロ型都市への再構築」を実現するため、平成14年7月に、都市再生本部事務局を事務局とし、京阪神圏の9府県市(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、大阪市、神戸市)及び関係各省(農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)により設置された協議会。
限界集落
集落人口の過疎化や高齢化により、社会的共同生活の維持が困難な状態にある集落のこと。
健康項目
原則的に全公共用水域及び地下水につき一律に定められている、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
一定規模以上の建設工事について、その受注者に対し、コンクリートや木材等の特定建設資材を分別解体等により現場で分別し、再資源化等を行うことを義務付けるとともに、制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、発注者による工事の事前届出制度、解体工事業者の登録制度などを設けている。
建設リサイクル推進計画2008
国土交通省における建設リサイクルの推進に向けた基本的考え方、目標、具体的施策を内容とする計画として策定。目標年度は平成24年度。
建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)
産学官共同で開発された、住宅・建築物の居住性(室内環境)の向上と地球環境への負荷の低減等を、総合的な環境性能として一体的に評価を行い、評価結果を分かり易い指標として示す評価システム。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律
地盤沈下の防止を図るため、特定の地域における、井戸による建築物用地下水の採取についての規制を定めたもの。平成21年3月現在、4都府県4地域が政令により指定されている。
2013年04月10日
白書 語句説明 [こ]
広域臨海環境整備センター法
昭和56年法律第76号。廃棄物の広域的処理が必要な区域において、海面埋立てによる広域処理場の建設、管理等の業務を行う法人の設立手続等を定める。本法に基づき、現在、近畿圏の2府4県を処理対象区域とする「大阪湾フェニックス計画」が推進されている。
公園管理団体
民間団体や市民による自発的な自然風景地の保護及び管理の一層の推進を図る観点から、一定の能力を有する一般社団法人又は一般財団法人、NPO法人であって、国立公園にあっては環境大臣が、国定公園にあっては都道府県知事が指定する団体。風景地保護協定に基づく風景地の管理や公園内の利用に供する施設の管理等を行う。
公園計画
自然公園の保護と利用を適正に行うために、公園ごとに定める計画。「規制計画」と「事業計画」に大別され、この計画に基づき、公園内の規制の強弱、施設の種類や配置、生態系の維持又は回復のための事業の実施方針等が定められる。
公害健康被害の補償等に関する法律
公害健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るため、公害健康被害補償法が昭和49年9月1日から施行された。本制度は、民事上の損害賠償責任を踏まえ、汚染物質の排出原因者の費用負担により、公害健康被害者に対する補償給付等を行うもの。制度の対象となる疾病は、気管支ぜんそく等のような原因物質と疾病との間に特異的な関係のない疾病(大気汚染が著しく、その影響による気管支ぜんそく等の疾病が多発している地域を第一種地域として指定)並びに水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症のような原因物質と疾病との間に特異的な関係がある疾病(環境汚染が著しく、その影響による特異的疾患が多発している地域を第二種地域として指定)の2種類がある。このうち第一種地域については、大気汚染の態様の変化を踏まえて見直しが行われ、昭和61年10月に出された中央公害対策審議会答申「公害健康被害補償法第一種地域のあり方等について」に基づき、1)第一種地域の指定解除、2)既被認定者に関する補償給付等の継続、3)大気汚染の影響による健康被害を予防するための事業の実施、4)「公害健康被害の補償等に関する法律(公健法)」への法律名の改正等を内容とする制度改正が行われ、昭和63年3月から施行されている。
公害健康被害予防事業
昭和63年3月の公害健康被害補償法の改正法の施行により、新たに大気汚染の影響による健康被害を予防するため、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に置かれた公害健康被害予防基金の運用益により、機構が直接行う事業(1)調査研究、2)知識の普及、3)研修)と、機構の助成を受けて地方公共団体等が旧第一種地域等を対象として行う事業(1)計画作成、2)健康相談、3)健康診査、4)機能訓練、5)施設等整備、6)施設等整備助成)。
公害防止計画
環境基本法第17条の規定に基づく法定計画で、現に公害が著しい地域等において、環境大臣の策定指示により関係都道府県知事が作成し、環境大臣により同意される公害の防止を目的とした地域計画。
公害防止事業費事業者負担法
公害防止事業に要する費用の事業者負担に関し、公害防止事業の範囲、事業者の負担の対象となる費用の範囲、各事業者に負担させる額の算定その他必要な事項を定めたもの。
光化学オキシダント
工場・事業場や自動車から排出される窒素酸化物(NOx)や揮発性有機化合物(VOC)などが太陽光線を受けて光化学反応を起こすことにより生成されるオゾンなどの総称で、いわゆる光化学スモッグの原因となっている物質。強い酸化力を持ち、高濃度では眼やのどへの刺激や呼吸器に影響を及ぼすおそれがあり、農作物などにも影響を与える。
公共車両優先システム
PTPS(Public Transportation Priority Systems)。バス専用・優先レーンの設定等の交通規制を行うとともに、バスがなるべく停止しないように進行方向の信号を優先的に青にすること等により、バスの定時運行と利便性向上を図るシステム。
工業用水法
工業の健全な発達と地盤沈下防止を図るため、特定の地域における、井戸による工業用地下水の採取についての規制を定めたもの。平成24年3月現在、10都府県17地域が政令により指定されている。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
国土交通大臣が設置する公共用飛行場のうち騒音等による障害が著しいと認めて指定した特定飛行場及び成田国際空港について、騒音の程度に応じて区域指定を行い、区域ごとに行う対策を定めている。また、周辺が市街化しているため、計画的な整備が必要な空港については周辺整備空港と指定し、空港周辺整備機構が当該空港に係る騒音対策事業の実施主体となることを規定している。最近では、平成14年に一部改正を行い、平成15年10月より空港周辺整備機構を独立行政法人化した。
航空機騒音・新幹線鉄道騒音に係る環境基準
航空機騒音に係る環境基準は、告示により、WECPNL(加重等価平均感覚騒音レベル Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level )の値をもっぱら住居の用に供される地域については70以下、それ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域については75以下にすることとされている。新幹線騒音に係る環境基準は、主として住居の用に供される地域は70デシベル以下、商工業の用に供される地域等は75デシベル以下とすることとされている。
公健法
「公害健康被害の補償等に関する法律」参照。
交通公害低減システム
EPMS(Environmental Protection Management System)。大気汚染や騒音等の状況を考慮した交通情報提供や信号制御を行うことにより、排気ガス等道路交通に起因する公害を低減するとともに、自動車からの二酸化炭素排出を抑制することにより、地球温暖化を防止し、もって環境の保護を図るシステム。
交通需要マネジメント
TDM(Transportation Demand Management)。都市又は地域レベルの交通需要の時間的・空間的集中を緩和するため、時間の変更、経路の変更、手段の変更、自動車の効率的利用、発生源の調整等により、交通需要量を調整(=交通行動の調整)する手法。
高度道路交通システム
ITS(Intelligent Transport Systems)。道路交通の安全性、輸送効率、快適性の向上等を目的に、最先端の情報通信技術等を用いて、人と道路と車両とを一体のシステムとして構築する道路交通システムの総称。
神戸3R行動計画
2008年5月に神戸で開催されたG8環境大臣会合で合意された、今後G8各国が3Rの一層の推進にむけて取り組む具体的な行動が列挙された計画。(1)3R関連政策の優先的実行及び資源生産性の向上(2)国際的な循環型社会の構築(3)開発途上国の能力開発に向けた連携、を掲げている。
合流式下水道
汚水及び雨水を同一の管きょで排除し処理する方式。分流式下水道に比べ管路施設の建設が容易でコストも安い。古くから下水道が普及してきた大都市等において多く採用されているが、雨天時に公共用水域に流出する未処理下水により、水質汚濁上、公衆衛生上の問題が発生している。
国際海事機関
国際海事機関(IMO)は船舶の安全及び船舶からの海洋汚染の防止等、海事問題に関する国際協力を促進するための国連の専門機関として、1958年に設立(設立当時は「政府間海事協議機関(IMCO)」。1982年に国際海事機関(IMO)に改称。)。わが国は設立当初に加盟国となり、理事国の地位を保持している。2012年4月現在、170の国・地域が正式に加盟、3地域が準加盟国となっている。現事務局長は、関水康司氏(2012年1月~)。
国際協力機構
Japan International Cooperation Agency。開発途上地域等の経済及び社会の発展に寄与し、国際協力の促進に資することを目的とし、政府開発援助(ODA;技術協力、有償及び無償の資金協力)等を行う。有償資金協力(海外経済協力業務)は、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(行政改革推進法)に基づき、国際協力銀行から2008年10月1日に承継したもの。同時に、無償資金協力についても外務省が実施する一部のもの以外は原則として国際協力機構が実施することとなった。
国際協力銀行
JBIC(Japan Bank for International Cooperation)。平成11年10月1日に日本輸出入銀行(JEXIM)と海外経済協力基金(OECF)が統合して発足。業務はJEXIMが行っていた輸出金融・輸入金融・投資金融・アンタイドローン等と、OECFが行っていた政府開発援助(ODA)としての円借款等を、それぞれ「国際金融等業務」「海外経済協力業務」として継承。なお、平成18年5月26日付けで成立した「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(行政改革推進法)に基づき、国際協力銀行は2008年10月1日に、国際金融等業務が株式会社日本政策金融公庫の国際金融部門として承継され、海外経済協力業務が独立行政法人国際協力機構(JICA)に承継された。
国際サンゴ礁イニシアティブ
日米が中心となり、平成7年に開始されたサンゴ礁保全と持続可能な利用に関する包括的な国際的な枠組み。地球規模でのサンゴ礁モニタリングの推進及び途上国の能力開発等を実施。わが国は、地域会合及びワークショップ等を開催することにより、その活動を推進している。
国際自然保護連合(IUCN)
IUCNは、International Union for Conservation of Nature and Natural Resourcesの略。IUCNは、1948年(昭和23年)に国家、政府機関、非政府機関という独特の世界的な協力関係の下で設立された。2008年4月現在、84か国から、111の政府機関、874の非政府機関、35の団体が会員となり、181か国からの約10,000人の科学者、専門家が参画する世界最大の国際的な自然保護機関。本部は、スイスのグラン。
国際生物多様性年国内委員会
2010年は国連が定めた「国際生物多様性年」であり、すべての国連加盟国に対し、経済界、学術会等多様な分野の代表者を含む国家的な委員会を設置し、国際年を記念する行事等を行うことが奨励されている。こうした点を踏まえ、生物多様性に対する社会の認識を高めるとともに、生物多様性の保全と持続可能な利用に資する活動の実施及び促進を行う組織(平成22年1月25日設立)。
国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ
化学物質管理について、関連する国際機関や諸外国が連携・協力して取り組むための中長期的な行動計画。2006年(平成18年)2月の第1回国際化学物質管理会議で承認された。
国際熱帯木材機関(ITTO)
International Tropical Timber Organization。「1983年国際熱帯木材協定(ITTA 1983)」に基づき1986年(昭和61年)に設立された国際機関。本部は横浜市に置かれており、61か国とEUが加盟している。熱帯木材の貿易と有効利用や熱帯林の持続可能な経営に関する議論及び国際協力の推進を目的に活動をしており、これまで「熱帯生産林の持続可能な経営のためのガイドライン」等技術的なガイドラインの策定のほか、違法伐採対策、熱帯木材貿易の統計情報能力の向上、環境配慮型伐採方法の普及・訓練、熱帯木材の利用効率の向上等のプロジェクトを実施している。
国際排出量取引
京都議定書による京都メカニズムの一種類(第17条)。議定書の削減約束を達成するに当たって、先進国同士が、温室効果ガスの排出枠の一部を取引することができる制度。
国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約
人の健康及び環境を保護し、当該化学物質の環境上適正な使用を促進するために、化学物質の輸入に関する事前同意(PIC:Prior Informed Consent)手続や輸入国に対して有害情報の送付を行う制度等を定めた条約。1998年(平成10年)9月にロッテルダムにおいて採択され、2004年(平成16年)2月に発効した。日本は2004年(平成16年)6月に受諾。
国際民間航空機関
国際民間航空条約(シカゴ条約)が発行した1947年(昭和22年)に正式に設立された国連の専門機関の一つである。国際民間航空の安全かつ秩序ある発展及び国際航空運送業務の健全かつ経済的な運営を図ることを目的とし、技術的問題、法律的問題等に関する各種の活動のほか、最近では経済的問題に関する活動も行っている。本部はモントリオールにあり、平成22年4月現在、190か国が加盟している(日本は昭和28年10月に加盟)。
国土利用計画
国土利用計画法第4条の規定に基づき、第2条に示された国土利用の基本理念に則して、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、長期にわたって安定した均衡ある国土の利用を確保することを目的として策定されるものであり、国土の利用に関する行政上の諸計画の基本となるもの。
国立水俣病総合研究センター
水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報収集、整備及び提供をつかさどることを目的に熊本県水俣市に設置。
国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)
国連経済社会理事会の下部機構の地域委員会の1つとして、1947年(昭和22年)に前身の国連アジア極東経済委員会(ECAFE)が設立され、1974年(昭和49年)に現在の名称に改称し、アジア太平洋地域の経済・社会開発にかかわる地域協力プロジェクト等を実施している。ESCAPアジア太平洋環境と開発に関する閣僚会議(MCED)は、ESCAP各国の環境大臣が一堂に会し、アジア太平洋地域の持続可能な開発の実現に向け意見交換を行う会議であり、5年に1回開催されている。
国連環境開発会議
昭和47年(1972年)6月にストックホルムで開催された国連人間環境会議の20周年を機に、平成4年(1992年)6月にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された首脳レベルでの国際会議。地球サミットとも呼ばれる。人類共通の課題である地球環境の保全と持続可能な開発の実現のための具体的な方策が話し合われた。「環境と開発に関するリオデジャネイロ宣言(リオ宣言)」や宣言の諸原則を実施するための「アジェンダ21」そして「森林原則声明」が合意された。
国連環境計画
1972年(昭和47年)にストックホルムで開催された国連人間環境会議の結果として設立された国連機関であり、本部はケニアのナイロビに置かれている。国連諸機関が行っている環境に関する諸活動の総合的調整管理及び環境分野における国際協力の推進を目的としている。
国連持続可能な開発委員会
1992年(平成4年)6月にブラジルのリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国連会議」(地球サミット)において設置が決まった国連組織。環境と経済の統合のための国際的な政策決定能力の促進やアジェンダ21の実施の進捗状況の審査を行うことを主な目的として、国連の経済社会理事会の下に設置されている。
国連持続可能な開発のための教育の10年
[1]2005年1月からの10年間を「国連持続可能な開発のための教育の10年」とし、[2]ユネスコにその国際実施計画を作成するよう要請し、[3]各国政府がその実施のための措置を国内の教育戦略及び行動計画に盛り込むよう呼びかけた第57回国連総会決議に基づく取組。2005年9月にユネスコ執行委員会において国際実施計画が承認され、日本では、同年12月、関係省庁連絡会議を内閣官房の下に設置し、各方面から寄せられた意見等にも十分に配慮しつつ検討を進め、2006年3月、関係省庁連絡会議において、わが国における「国連持続可能な開発のための教育の10年」実施計画を定めた。
国連食糧農業機関
世界の人々の栄養及び生活水準の向上、食料及び農産物の生産、流通の改善、並びに農村住民の生活条件の改善を通じた世界経済の発展及び人類の飢餓からの解放を目的として、1945年(昭和20年)に設立された国連の専門機関。2007年現在で、191か国及びECが加盟している。森林分野では、世界の森林の現況を取りまとめた「世界森林資源評価」の発刊や森林・林業関係フィールド・プロジェクトの実施、森林に関する情報の収集、分析、普及などの活動を行っている。
国連森林フォーラム
地球サミット以降、世界の持続可能な森林経営の推進を協議する場として国連に設置された、森林に関する政府間パネル(IPF)、森林に関する政府間フォーラム(IFF)を受けて、2001年に国連経済社会理事会(ECOSOC)の下に設置された機関。2007年の第7回会合では、2015年までに持続可能な森林経営と4つの世界目標を達成するための方策等を盛り込んだ文書が採択された。
国連生物多様性の10年日本委員会
国連が定めた「国連生物多様性の10年」(2011~2020年)に対応するため、国内のあらゆる主体が、それぞれの立場で連携をとりつつ、生物多様性の保全とその持続可能な利用の確保に取り組むことを促進し、愛知目標の達成に貢献することを目的として、2011年(平成23年)9月1日に「地球生きもの委員会(国際生物多様性年国内委員会)」を改組して設立された。
国連人間環境会議
1972年(昭和47年)の開催。「ストックホルム会議」と呼ばれる。国際社会が初めて環境問題を取り上げ、環境問題が国際問題であるとの認識を国際社会が初めて示した。
国連水と衛生に関する諮問委員会
2004年(平成16年)3月、アナン国連事務総長が世界水の日のメッセージにおいて設置を発表した諮問組織。世界の水問題解決策の検討を目的としており、世界中のさまざまな分野から、閣僚経験者や国際機関の長を務めた有識者やNGOの代表など約20名の委員で構成されている。
国連ミレニアム開発目標
MDGs(Millennium Development Goals)。2000年(平成12年)9月に採択された国連ミレニアム宣言と、1990年代に開催された主要な国際会議やサミットで採択された国際開発目標とを統合し、一つの共通の枠組みとしてまとめたもの。2015年(平成27年)までに達成すべき8つの目標を掲げている。
湖沼水質保全計画
湖沼水質保全特別措置法に基づき、特に緊要な対策が必要として環境大臣が指定した指定湖沼(現在、琵琶湖、霞ヶ浦等11湖沼)ごとに、関係都道府県知事が環境大臣との協議を経て策定する。COD(化学的酸素要求量)、総りん及び総窒素(排水規制対象湖沼のみ)について水質改善目標値を設定し、湖沼の水質保全に資する事業に関する方針、水質保全に資する事業に関すること、規制その他の措置に関すること等を定める。
湖沼水質保全特別措置法
湖沼は閉鎖性の水域であり、汚濁物質が蓄積しやすいため、水質汚濁防止法に基づく諸対策のみでは環境基準の達成がむずかしいことから、湖沼の水質保全を総合的に推進するために制定された。
国家ハロンマネジメント戦略
モントリオール議定書締約国会合の決定に基づき、日本におけるハロンの管理についての考え方、取組を取りまとめたもの。2000年(平成12年)7月に国連環境計画のオゾン事務局に提出した。
固定価格買取制度
固定価格買取制度(フィード・イン・タリフ制度)とは、再生可能エネルギーにより発電された電気の買取価格(タリフ)を法令で定める制度で、主に再生可能エネルギーの普及拡大を目的としている。再生可能エネルギー発電事業者は、発電した電気を電力会社などに、一定の価格で、一定の期間にわたり売電できる。ドイツ、スペインなどでの導入の結果、風力や太陽光発電が大幅に増加した実績などが評価され、採用する国が増加している。一方で、国民負担の観点にも配慮が必要である。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
日本固有の文化的資産として、今後も継承していくべき古都における歴史的風土を保存するため制定された。平成18年度末現在、本法が適用されている市町村は、京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村、逗子市及び大津市である。(よみ修正)
コベネフィット・アプローチ
開発途上国の課題である大気汚染や水質汚濁などの環境汚染対策と、地球規模の課題である温室効果ガスの削減を同時に実現する取組。急速に発展しつつある開発途上国の温暖化対策への取組を促す上で有効と考えられている。
コペンハーゲン合意
平成21年12月に開催されたCOP15において首脳級での協議等を経て、米中等の主要国を含む形で取りまとめられた合意。世界全体の気温の上昇が2℃以内にとどまるべきであるとの科学的見解を認識し、長期の協力行動を強化すること、先進国や途上国の削減目標・行動の登録、気候変動対策に取り組む途上国に対する短期資金や長期資金の支援の実施などが合意された。
ごみ発電
ごみ焼却時に発生する熱エネルギーをボイラーで回収し、蒸気を発生させてタービンを回して発電を行うもの。化石燃料の使用削減につながることから温暖化対策としても注目されている。
2013年04月10日
白書 語句説明 [さ]
サーマルリサイクル
「熱回収」参照。
再資源化施設
リユース・リサイクルを進めるための施設の総称。
最終処分場
廃棄物は、資源化または再利用される場合を除き、最終的には埋立処分又は海洋投入処分される。最終処分は埋立てが原則とされており、大部分が埋立てにより処分されている。最終処分を行う施設が最終処分場であり、ガラスくず等の安定型産業廃棄物のみを埋め立てることができる「安定型最終処分場」、有害な産業廃棄物を埋め立てるための「遮断型最終処分場」、前述の産業廃棄物以外の産業廃棄物を埋め立てる「管理型最終処分場」及び一般廃棄物最終処分場(「管理型最終処分場」と同様の構造)とに分類される。これらは埋め立てる廃棄物の性状によって異なる構造基準及び維持管理基準が定められている。
再使用(リユース)
いったん使用された製品や部品、容器等を再使用すること。具体的には、(1)あるユーザーから回収された使用済み機器等をそのまま、もしくは修理などを施した上で再び別のユーザーが利用する「製品リユース」、(2)製品を提供するための容器等を繰り返し使用する「リターナブル」、(3)ユーザーから回収された機器などから再使用可能な部品を選別し、そのまま、もしくは修理等を施した上で再度使用する「部品リユース」などがある。
再飼養支援データベース・ネットワークシステム
都道府県等によって引取り又は収容された犬ねこ等について、飼い主及び譲渡を希望する者への返還・譲渡を推進するための広域的なデータベース・ネットワークシステム。インターネットを活用したシステムで、「収容動物データ検索サイト(http://jawn.env.go.jp/(別ウィンドウ))」から都道府県等の収容動物情報が検索できる。
再生可能エネルギー
エネルギー源として永続的に利用することができる再生可能エネルギー源を利用することにより生じるエネルギーの総称。具体的には、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマスなどをエネルギー源として利用することを指す。
再生利用
廃棄物等を原材料として再利用すること。効率的な再生利用のためには、同じ材質のものを大量に集める必要があり、特に自動車や家電製品といった多数の部品からなる複雑な製品では、材質の均一化や材質表示などの工夫が求められる。なお、再生利用のうち、廃棄物等を製品の材料としてそのまま利用することをマテリアルリサイクル(例:びんを砕いてカレットにした上で再度びんを製造する等)、化学的に処理して利用することをケミカルリサイクルという(例:ペットボトルを化学分解して再度ペットボトルにする等)。
里海
豊かな海の恵みを利用しながら生活してきている人の暮らしと強いつながりのある地域で、自然生態系と調和しつつ人手を加えることにより、高い生物生産性と生物多様性の保全が図られている海域概念。
里地里山
奥山自然地域と都市地域の中間に位置し、さまざまな人間の働きかけを通じて環境が形成されてきた地域であり、集落を取り巻く二次林と人工林、農地、ため池、草原などで構成される地域概念。
里地里山保全活用行動計画
里地里山に対する国民の関心及び理解を促し、多様な主体による保全活用の取組を全国各地で国民的運動として展開する計画。
砂漠化対処条約
正式名称は「深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約」。1994年(平成6年)に採択され、1996年(平成8年)に発効した。わが国は、同条約を1998年(平成10年)に受諾した。砂漠化の影響を受ける締約国は砂漠化に対処するための行動計画を策定し実施すること、また、先進締約国は開発途上締約国のそのような取組を支援すること等が規定されている。約190か国が加盟している。
産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックなど20種類の廃棄物をいう。大量に排出され、また、処理に特別な技術を要するものが多く、廃棄物処理法の排出者責任に基づきその適正な処理が図られる必要がある。
酸性雨
二酸化硫黄、窒素酸化物等の大気汚染物質は、大気中で硫酸、硝酸等に変化し、再び地上に戻ってくる(沈着)。それには2種類あり、一つは、雲を作っている水滴に溶け込んで雨や雪などの形で沈着する場合(「湿性沈着」と呼ばれる。)であり、ほかの一つは、ガスや粒子の形で沈着する場合(「乾性沈着」と呼ばれる。)である。当初はもっぱら酸性の強い(pHの低い)雨のことのみに関心が寄せられていた。しかし、現在ではより幅広く、「酸性雨」は湿性沈着及び乾性沈着を併せたものとしてとらえられている。(したがって、より科学的には「酸性沈着」という用語が使用される。)
残留性有機汚染物質
毒性、難分解性、生物蓄積性及び長距離移動性を有する物質で、POPs(Persistent Organic Pollutants)と呼ばれる。
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
POPs(「残留性有機汚染物質」参照)の廃絶、削減等に国際的に取り組むため、2001年(平成13年)5月に採択され、2004年(平成16年)5月に発効。POPsの製造、使用の原則禁止及び原則制限、非意図的生成物質の排出削減、POPsを含む在庫・廃棄物の適正管理及び処理、これらの対策に関する国内実施計画の策定等を締約国に義務付けている。現在PCB,DDT,ダイオキシン類など12物質群が対象とされており、第4回締約国会議(2009年5月)において新たに9物質群を対象とすることが決定された。日本は、2002年(平成14年)8月に締結。
2013年04月10日
白書 語句説明 [し]
ジェニュイン・セービング
世界銀行によって開発された指標。国民総貯蓄から固定資本の消費を控除し、教育への支出を人的資本への投資額と考えて加えるとともに、天然資源の枯渇・減少分及び二酸化炭素排出等による損害額を控除して計算する。
ジオパーク
「大地の公園」ともいわれるもので、地形の成立ちと仕組み、地形と生態系や人間生活との関わりを考える公園。日本国内では日本ジオパーク委員会が,国際的な活動としてはユネスコが支援するNGO「世界ジオパークネットワーク」が認定を行っている。
資源生産性
投入された資源をいかに効率的に使用して経済的付加価値を生み出しているかを測る指標で、循環型社会基本計画では、GDP(国内総生産)を天然資源等投入量(国内・輸入天然資源及び輸入製品の総量)で割ることによって算出している。天然資源等はその有限性や採取に伴う環境負荷が生じること、また、それらが最終的には廃棄物等となることから、より少ない投入量で効率的にGDPを生み出すよう、資源生産性の増加が望まれる。
資源動員戦略
生物多様性条約COP9において、条約の3つの目的と2010年目標の効果的な実施を支援するために、現在の資金のギャップを解消し国際的な資金の流れと国内の基金の強化を図ることを目的として「資源動員戦略」が策定された。COP10では、戦略に具体的な金額目標の明記を求める途上国と、しっかりとした指標なしにそのような目標を設定する議論に応じられないとする先進国との間で交渉が難航したが、最終的にはこうした指標ができる条件でCOP11において目標を採択することなどが決定された。COP11では「資源動員戦略」の目標設定が最も重要な課題となる。
資源の有効な利用の促進に関する法律
平成3年に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律」の改正法として、平成12年に制定されたもの。[1]製品の環境配慮設計(軽量化等、解体の容易化等に配慮した設計)、[2]使用済製品の自主回収・リサイクル、[3]製造工程で生じる副産物のリデュース・リサイクル(事業所のゼロ・エミッション)といった3Rに関するさまざまな取組を促進することにより、循環経済システムの構築を目的とする。
資源保全再生法
有害廃棄物の削減、処理・処分における環境影響の最小化などを目的とするアメリカの有害廃棄物規制に関する法律(1976年制定)。有害廃棄物の定義、各主体の義務(発生者のマニフェスト交付義務、輸送者のアメリカ環境保護庁登録義務、処理・貯蔵・処分施設の所有者・管理者の施設操業許可取得と技術的要件遵守義務)を定めている。
資源有効利用促進法
「資源の有効な利用の促進に関する法律」参照。
資産除去債務
有形固定資産(不動産)を除去する際の将来費用をあらかじめ負債として計上するもの。建築等のライフサイクルコストの明確化につながり、投資情報として有用との判断から会計基準化されたもの。
指針値(環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値)
指針値は、環境基本法第16条に基づき定められる環境基準とは性格及び位置付けは異なるものの、人の健康に係る被害を未然に防止する観点から科学的知見を集積し、有害性評価に係るデータの科学的信頼性において制約がある場合も含めて、評価した結果として設定されたものであり、現に行われている大気モニタリングの評価に当たっての指標や事業者による排出抑制努力の指標としての機能を果たすことも期待されている。
自然環境保全基礎調査
全国的な観点からわが国における自然環境の現況及び改変状況を把握し、自然環境保全の施策を推進するための基礎資料を整備するために、環境省が昭和48年度より自然環境保全法第4条の規定に基づきおおむね5年ごとに実施している調査。一般に、「緑の国勢調査」と呼ばれ、陸域、陸水域、海域の各々の領域について調査項目を分類し国土全体の状況を調査している。調査結果は報告書及び地図等に取りまとめられた上公表されており、これらの報告書等は、自然環境の基礎資料として、自然公園等の指定・計画をはじめとする自然保護行政のほか、環境影響評価等の各方面において活用されている。
自然環境保全法
自然環境を保全することが特に必要な区域等の適正な保全を総合的に推進することを目的とする法律。自然環境保全基本方針の策定、自然環境保全基礎調査の実施、すぐれた自然環境を有する地域を原生自然環境保全地域等として保全することなどを規定している。
自然公園法
すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする法律。
自然再生推進法
自然再生に関する施策を総合的に推進するための法律。自然再生についての基本理念、実施者等の責務及び自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な事項を定めている。
1 制定の趣旨
自然再生を総合的に推進し、生物多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的とするもの。
自然再生事業を、NPOや専門家を始めとする地域の多様な主体の参画と創意により、地域主導のボトムアップ型で進める新たな事業として位置付け、その基本理念、具体的手順等を明らかにするもの。
2 制定の経緯(議員立法)
平成14年5月28日:
政策責任者会議において与党案了承。
平成14年7月24日:
与党及び民主党関係議員により154回国会提出(継続審議)。
平成14年11月19日:
衆議院環境委員会で一部修正の上可決。同日、衆・本会議で成立。
平成14年12月3日:
参議院環境委員会で可決(付帯決議あり)。
4日:
参議院本会議で成立。
3 法律の概要
【定義】
自然再生:過去に損なわれた自然環境を取り戻すため、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、NPO、専門家等の地域の多様な主体が参加して、自然環境の保全、再生、創出等を行うこと。
【基本理念】
地域における自然環境の特性、自然の復元力及び生態系の微妙な均衡を踏まえて、科学的知見に基づいて実施。
事業の着手後においても自然再生の状況を監視し、その結果に科学的な評価を加え、これを事業に反映。
地域の多様な主体の参加
政府は、自然再生に関する施策を総合的に推進するための基本方針を閣議決定。基本方針の案は、環境大臣が農林水産大臣、国土交通大臣と協議して作成。
自然再生事業の実施者が、地域住民、NPO、専門家、関係行政機関等とともに協議会を組織。
実施者は、自然再生基本方針及び協議会での協議結果に基づき、自然再生事業実施計画を作成。
NPO等への支援
主務大臣は、実施者の相談に応じる体制を整備。
国及び地方公共団体は、自然再生を推進するために必要な財政上の措置その他の措置に努力。
関係省庁の連携
環境省、国土交通省、農林水産省その他の関係行政機関で構成する自然再生推進会議を設置。
3省は自然再生専門家会議を設置し、意見聴取。
4 その他
施行期日は、平成15年1月1日。自然再生基本方針の策定は年度内を目途として行うため、本格運用は平成15年4月以降の予定。
施行5年後に見直しを予定。
持続可能性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)
持続性の高い農業生産方式の導入を促進するための措置を講ずることにより、環境と調和のとれた農業生産の確保を図り、もって農業の健全な発展に寄与することを目的とする法律
持続可能な開発に関する世界サミット(WSSD)2020年(平成32年)目標
2002年(平成14年)9月に開催された持続可能な開発に関する世界サミット(WSSD)において合意された、化学物質管理に関する世界共通の中長期目標。予防的取組方法に留意しつつ、透明性のある科学的根拠に基づくリスク評価・管理手順を用いて、化学物質が、人の健康と環境への著しい影響を最小化する方法で生産・利用されることを、2020年までに達成する。
持続可能な開発に向けた開発途上国の研究能力開発・向上プログラム
Scientific Capacity Building and Enhancement for Sustainable Development in Developing Countries(持続可能な開発に向けた開発途上国の研究能力開発・向上プログラム)。アジア太平洋地域の途上国を対象に、地球温暖化に関する科学的能力の向上を目指す研究プログラム。APNの活動の一環として実施される。
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
自動車交通の集中等により、大気汚染防止法等の既存の施策のみによっては大気環境基準の確保が困難となっている地域において、自動車から排出されるNOx及びPMの総量を削減し、大気環境の改善を図ることを目的とした法律。現在、この法律に基づき、関東、関西及び中部の約250市区町村が対策地域として指定され、ほかの地域よりも厳しい特別の排出ガス規制(車種規制)が適用されている。
自動車税のグリーン化
排出ガス及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さい一定の自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置。
自動車排出ガス測定局
自動車走行による排出物質に起因する大気汚染の考えられる交差点、道路及び道路端付近の大気を対象にした汚染状況を常時監視する測定局。
自動車リサイクル法
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」参照。
自排局
「自動車排出ガス測定局」参照。
社会的責任投資(SRI)
SRI(Socially Responsible Investment)。従来からの株式投資の尺度である企業の収益力、成長性等の判断に加え、各企業の人的資源への配慮、環境への配慮、利害関係者への配慮などの取組を評価し、投資選定を行う投資行動。
臭化メチル
主に土壌くん蒸や農産物の検疫くん蒸に使用される。オゾン層破壊物質でありモントリオール議定書の削減規制対象物質である。
臭化メチルの不可欠用途を全廃するための国家管理戦略
モントリオール議定書締約国会合の決定に基づき、日本における不可欠用途臭化メチルの削減に向けた考え方、取組を取りまとめたもの。2006年(平成18年)1月に国連環境計画にオゾン事務局に提出した。
重要生態系監視地域モニタリング推進事業
全国にモニタリングサイト(調査地点)を設定し、さまざまなタイプの生態系を長期的にモニタリングする調査事業。定量的・継続的にデータを収集することにより、各生物種の増減、変化等を把握し、生物多様性保全のための適切な対策につなげていくことを目的としている。NPO・ボランティア・研究者等の多様な主体との連携により調査を実施している。
首都圏ゴミゼロ型都市推進協議会
都市再生本部で決定されたプロジェクトである「大都市圏におけるゴミゼロ型都市への再構築」を実現するため、平成13年7月に、都市再生本部事務局を事務局とし、首都圏の8都県市(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市(平成15年4月に加入))及び関係各省(農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)により設置された協議会。
種の保存法
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」参照。
シュレッダーダスト
廃自動車、廃家電製品等を破砕した後、比重の大きい鉄スクラップと非鉄金属スクラップを選別回収した後の、プラスチックやガラス、ゴムなど比重の小さいものからなる廃棄物。年間発生量は約100万t前後で推移している。深刻化する埋立処分場不足、有害物質の混入のほか、鉄スクラップ相場などの経済影響を受けやすく、不法投棄や不適正処理につながりやすい。香川県豊島の不適正処理はその代表的なもの。
循環型社会
大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念。循環型社会基本法では、第一に製品等が廃棄物等となることを抑制し、第二に排出された廃棄物等についてはできるだけ資源として適正に利用し、最後にどうしても利用できないものは適正に処分することが徹底されることにより実現される、「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された社会」としている。また、循環型社会基本計画では、このアンケート結果を踏まえ、具体的な循環型社会のイメージを提示している。
循環型社会形成推進基本計画
循環型社会形成推進基本法に基づき、政府全体の循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環型社会の形成に関する施策についての基本的な方針などを定める計画である。平成15年に第1次計画、平成20年に第2次計画が閣議決定・国会報告された。同計画は、循環型社会のイメージを明らかにするとともに、経済社会におけるものの流れ全体を把握する「物質フロー指標」等についての数値目標、国の取組、各主体の役割等を定めている。
循環型社会形成推進基本法
循環型社会の形成について基本原則、関係主体の責務を定めるとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項などを規定した法律。
循環資源
循環型社会基本法で定義されたものであり、廃棄物等(無価物である廃棄物及び使用済製品等や副産物等で有価のもの)のうち有用なものを指す。実態的には「廃棄物等」はすべて有用なものとしての可能性を持っていることから、廃棄物等と同等であるといえる。有価・無価という違いを越えて廃棄物等を一体的にとらえ、その発生抑制と循環的利用(再使用、再生利用、熱回収)を推進するために考案された概念である。
循環利用率
循環型社会基本計画で採用した指標。同計画では循環利用率=循環利用量/(循環利用量+天然資源等投入量)(=総物質投入量)としている。ここで、循環利用量とはリユース又はリサイクルされた量を指す。最終処分量を減らすために適正な循環利用が進むよう、原則的には増加が望まれる。
準絶滅危惧
レッドリストのカテゴリーの1つ。存続基盤が脆弱な種。現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する要素を有するもの。
小水力発電
水力発電のうち、ダム等に設置された大規模な水力発電ではなく、河川や水路に設置した水車などを用いてタービンを回し発電する小規模な水力発電のこと。
使用済自動車の再資源化等に関する法律
自動車製造業者等を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けることにより、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るための法律。自動車製造業者・輸入業者に、自らが製造・輸入した自動車が使用済みになった場合に生じるシュレッダーダスト(破砕された後の最終残さ)等を引き取ってリサイクルする等の義務を課し、そのために必要な費用はリサイクル料金(再資源化預託金等)として自動車の所有者が原則新車販売時に負担する制度。解体業者などの関係事業者はすべて都道府県知事等の登録・許可を受けることが必要であり、各事業者間の使用済自動車の流通は一元的に情報管理される仕組みとなっている。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生抑制及び減量に関する基本的事項を定めるとともに、登録再生利用事業者制度等の食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効利用及び食品廃棄物の排出抑制を図ること等を目的として制定された。
新交通管理システム
UTMS(Universal Traffic Management Systems)。 光ビーコンを用いた個々の車両と交通管制システムとの双方向通信により、ドライバーに対してリアルタイムの交通情報を提供するとともに、交通の流れを積極的に管理し、「安全・快適にして環境にやさしい交通社会」の実現を目指すシステム。
新・ゴミゼロ国際化行動計画
2008年5月に神戸で開催されたG8環境大臣会合の際に、日本として、アジア等における循環型社会の構築に向けて進めていく国際的取組を列挙した行動計画。(1)各国のニーズに応じた廃棄物の適正処理と3Rの統合的推進(2)廃棄物の適正管理・3Rを通じた温暖化対策への貢献(3)有害廃棄物の不法な越境移動の防止(4)アジア全体の循環型社会の構築に向けた取組(5)世界的な循環型社会の構築に向けた連携、を掲げている。
新成長戦略
平成22年6月18日に閣議決定された経済成長戦略。強みを活かす成長分野として、グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦略及びライフ・イノベーションによる健康大国戦略を掲げるとともに、これらのほかアジア経済戦略、観光立国・地域活性化戦略、科学・技術・情報通信立国戦略、雇用・人材戦略及び金融戦略の7つの戦略分野について基本方針と目標を定めている。
振動規制法
工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行なうとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としたもの。
森林原則声明
正式名称は「全てのタイプの森林の経営、保全及び持続可能な開発に関する世界的合意のための法的拘束力のない権威ある原則声明」。1992年(平成4年)の地球サミットで採択された森林に関する初めての世界的な合意文書。
森林認証制度
独立した第三者機関が一定の基準等を基に、適切な森林経営や持続可能な森林経営が行われている森林又は経営組織などを認証し、それらの森林から生産された木材・木材製品へラベルを貼り付けることにより、消費者の選択的な購買を通じて、持続可能な森林経営を支援する取り組み。