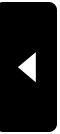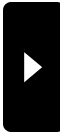2013年04月10日
白書 語句説明 [す]
水質汚濁に係る環境基準
水質保全行政の目標として、公共用水域及び地下水の水質について達成し維持することが望ましい基準を定めたもので、人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)と生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)の二つからなっている。
水質汚濁防止法
公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止し、国民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図るため、事業場からの排出水の規制・生活排水対策の推進・有害物質の地下浸透規制等が盛り込まれている。また、同法においては、閉鎖性水域に対して、汚濁負荷量を全体的に削減しようとする水質総量規制が導入されている。
ストックホルム宣言
人間環境宣言。1972年、スウェーデンのストックホルムで開催された人間環境会議において採択された環境問題に取り組む際の原則を明らかにした宣言。環境問題を人類に対する脅威と捉え、国際的に取り組むべきことを明らかにしている。
スマートウェイ
交通安全、渋滞対策、環境対策などを目的とし、人と車と道路とを情報で結ぶITS技術を活用した次世代の道路。
2013年04月10日
白書 語句説明 [せ]
生活環境項目
河川、湖沼、海域ごとに利用目的に応じた水域類型を設けてそれぞれ生活環境を保全する等の上で維持されることが望ましい基準値を定めている。
税制のグリーン化
環境への負荷の低減に資するための税制の見直し。
生態系価値評価パートナーシップ
生態系サービスの価値を評価し、国家勘定に組み入れることなどにより、生態系サービスの価値が各国の経済・開発政策の立案上、主要な考慮事項とされることを目指した、世界銀行が進める国際的な枠組。
生態系サービス
人々が生態系から得ることのできる便益のことで、食料、水、木材、繊維、燃料などの「供給サービス」、気候の安定や水質の浄化などの「調整サービス」、レクリエーションや精神的な恩恵を与える「文化的サービス」、栄養塩の循環や土壌形成、光合成などの「基盤サービス」などがある。
生態系サービスへの支払い制度
生態系サービスの恩恵を受けている人々(受益者)に対して、サービスの内容や規模に応じた対価を支払ってもらう仕組みのこと。例えば、上流部の森林に水源かん養や水質浄化という生態系サービスを提供してもらっている人々がこれを維持するための管理費用を管理者に支払う場合などがこれに当たる。
生態系と生物多様性の経済学
The Economics of Ecosystems and Biodiversity(TEEB)。生態系と生物多様性のもたらす経済的価値への理解を深め、価値を適切に計算するための経済的ツールの提供を目指した研究。国連環境計画の主導のもと、ドイツ銀行のエコノミスト スクデフ氏を研究リーダーとしてドイツ政府が中心となり実施。2010年の生物多様性条約COP10において最終報告書が発表された。
生態系ネットワーク
エコロジカル・ネットワークともいう。保全すべき自然環境やすぐれた自然条件を有している地域を核として、生息・生育空間のつながりや適切な配置を考慮した上で、これらを有機的につないだネットワークのこと。ネットワークの形成により、野生生物の生息・生育空間の確保のほか、人と自然とのふれあいの場の提供、地球温暖化への適応策等多面的な機能が発揮されることが期待される。
政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画(政府の実行計画)
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、平成14年7月19日に閣議決定し、17年4月28日に改訂。平成19年3月30日に新たな計画を閣議決定。庁舎等からの温室効果ガスの総排出量を平成13年度比で平成22年度から平成24年度までの総排出量の平均を少なくとも8%削減することを目標とすること等を定めている。
生物多様性基本法
平成20年法律第58号。生物多様性の保全及び持続可能な利用について基本原則を定め、国、地方公共団体、事業者、国民及び民間の団体の責務を明らかにするとともに、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策の基本となる事項を規定した法律。生物多様性に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、生物多様性から得られる恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的とする。
生物多様性国家戦略
生物多様性条約第6条に基づき、条約締約国が作成する生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する国の基本的な計画。わが国は平成7年、平成14年、平成19年の3回、国家戦略を策定した。平成20年に施行された生物多様性基本法第11条で、国家戦略の策定が規定されたことから、平成22年3月に、同法に基づく初めての国家戦略となる「生物多様性国家戦略2010」を閣議決定した。
生物多様性自治体ネットワーク
生物多様性の保全や回復を進めるには、地域に根付いた現場での活動を、自ら実施し、また住民や関係団体の活動を支援する地方自治体の役割は極めて重要なため、14の発起自治体を核として、環境省が設立準備事務局を務め、「生物多様性自治体ネットワーク」の設立を呼びかけたところ、99の自治体より参画に賛同を得て、113の自治体から成る「生物多様性自治体ネットワーク」が2011年10月7日に設立された。
生物多様性情報システム(J-IBIS)
自然環境保全基礎調査などにより集積した成果をはじめ、日本の自然環境、生物多様性に関する情報を総合的に収集・管理し、インターネットにより情報提供するシステム。生物多様性情報システム(別ウィンドウ)
生物多様性条約
「生物の多様性に関する条約」参照。
生物多様性条約戦略計画
生物多様性条約第6回締約国会議(COP6(2002 年)、オランダ・ハーグ)にて採択された。戦略計画の「使命」として「2010 年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少させる」といういわゆる「2010年目標」を掲げている。
生物多様性条約第10回締約国会議
生物多様性条約の締約国(193の国と地域)が集まる最高意思決定機関であり、2年に一度開催されている。その第10回の会議が、平成22年10月に愛知県名古屋市で、わが国が議長国となり開催される。2010年目標の評価と2010年以降の新しい目標の採択、遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)に関する国際的枠組の検討などが主要な議題となる。
生物多様性総合評価
1950年代後半から現在までの評価期間における、日本全国の生物多様性の損失の要因と状態等を総合的に評価。平成22年5月に公表。JBOは生物多様性総合評価(Japan Biodiversity Outlook)の略称。
生物多様性地域連携促進法
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)(生物多様性地域連携促進法)。地域における生物多様性の保全の必要性にかんがみ、地域における多様な主体が連携して行う生物多様性保全活動を促進することによって、豊かな生物多様性を保全することを目的として、平成22年12月10日に制定され、平成23年10月1日に施行された。
生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム
Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)。科学と政策のインターフェイスの強化を図るための組織として、気候変動枠組条約のIPCCのような、生物多様性の動向評価等を行う政府間プラットフォームの創設が提案されており、現在、国連環境計画(UNEP)の下で検討プロセスが進められている。
生物多様性民間参画イニシアティブ
平成22年10月に、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する民間の参画を推進するため、日本経済団体連合会、日本商工会議所及び経済同友会等、経済界が中心となって設立した自発的なプログラム。
生物の多様性に関する条約
生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的とした条約。1992年(平成4年)に採択され、1993年(平成5年)12月に発効した。日本は1993年(平成5年)5月に締結した。条約に基づき生物多様性国家戦略を策定し、これに基づく各種施策を実施している。
世界気象機関
世界の気象事業の調和的発展を目標とした国際計画の推進・調整を行うため、世界気象機関条約(1950年発効)に基づき設立されたもので、国連の専門機関の一つである。わが国は1953年に加盟。
世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約
世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(平成4年条約第7号)。文化遺産及び自然遺産を人類全体のための世界の遺産として損傷、破壊等の脅威から保護し、保存するための国際的な協力及び援助の体制を確立することを目的とする。1972年(昭和47年)に採択され、1975年(昭和50年)に発効した。わが国においては1992年(平成4年)に発効し、平成24年3月現在、12の文化遺産及び43つの自然遺産が登録されている。
セクター別アプローチ
温室効果ガスの削減量を決めるために、産業、運輸、業務、家庭等の部門(セクター)ごとに対策など実施する手法。各セクターごとにエネルギー効率やCO2原単位、省エネ技術の普及状況などから、最も高効率の技術を導入した場合の温室効果ガス削減可能量を算出し、その量を合計して一国の排出削減目標可能性とするほか、最良の技術の普及やベストプラクティスの共有等を通じ、途上国の削減行動を加速する有効なツール。
絶滅危惧IA類
ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの。
絶滅危惧IB類
IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの。
絶滅危惧II類
絶滅の危険が増大している種。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧I類」のランクに移行することが確実と考えられるもの。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全することを目的とした法律。
瀬戸内海環境保全特別措置法
瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的として、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海環境保全基本計画の策定、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全、埋立ての基本方針等に関することを定めている。
ゼロ・エミッション
ある産業の製造工程から出る廃棄物を別の産業の原料として利用することにより、廃棄物の排出(エミッション)をゼロにする循環型産業システムの構築を目指すもの。国連大学が提唱し、企業や自治体で取組が進んでいる。
全球大気監視(GAW)計画
温室効果ガス、オゾン層、エーロゾル、酸性雨など地球環境にかかわる大気成分について、地球規模で高精度に観測し、科学的な情報を提供することを目的に、世界気象機関(WMO)が1989年(平成元年)に開始した国際観測計画。
全球地球観測システム(GEOSS)10年実施計画
国際的な連携によって、衛星、地上、海洋観測等の地球観測システムを統合し、地球全体を対象とした包括的かつ持続的な地球観測システムを10年間で整備し、政策決定に必要な情報を創出することを目指す計画。2005年2月の第3回地球観測サミットにおいて策定。
全国海の再生プロジェクト
海上保安庁及び国土交通省を中心とする関係省庁及び自治体が連携して、汚濁負荷削減対策、海域の環境改善対策、環境モニタリング等の各種施策を推進するプロジェクト。全国4カ所(東京湾、大阪湾、伊勢湾、広島湾)で行われている。
戦略的環境アセスメント
個別の事業の計画、実施に枠組みを与えることになる政策や計画、事業の位置、規模又は施設の配置、構造等の検討段階に環境配慮を組み込むため、これらの策定等の段階において、環境への影響を把握・評価し、環境への配慮が十分に行われることを確保するための手続。
2013年04月10日
白書 語句説明 [そ]
騒音規制措置
在日米軍の航空機騒音による住民の負担を軽減するため、厚木、横田、嘉手納及び普天間の各飛行場に関する騒音規制について日米間で合意している。具体的には、
[1]22時から翌朝6時までの間の飛行等の活動は、運用上の必要性から緊要と認められたものに制限され、又は禁止されること、
[2]夜間訓練飛行は、任務達成、練度維持のために必要な最小限に制限されること(厚木飛行場は記載無し)、
[3]日曜の訓練飛行は最小限に抑えること、
[4]18時から翌朝8時までの間は、原則としてジェット・エンジンのテストは実施しないこと(横田飛行場は、翌朝7時まで)、
[5]人口稠密地域上空をできる限り避けること等の規制措置が定められている。
騒音規制法
工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としたもの。
騒音に係る環境基準
騒音に係る環境上の条件について、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準で、地域の類型及び時間の区分ごとに指定される。航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音を除く一般騒音に適用される。
第1 環境基準
1 環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が指定する。
地域の類型 基準値昼間 夜間
AA 50デシベル以下 40デシベル以下
A及びB 55デシベル以下 45デシベル以下
C 60デシベル以下 50デシベル以下
(注)1 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
2 AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
3 Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
4 Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
5 Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。
総合静脈物流拠点港
広域的なリサイクル施設の立地に対応し、循環資源の収集・輸送・処理の総合的な静脈物流拠点として、港湾管理者からの申請により国土交通省港湾局に指定された港湾。このリサイクルポートを核として、低廉で環境にやさしい海上輸送により、そのネットワーク化を図り、総合的な静脈物流システムを構築する。
2013年04月09日
白書 語句説明 [た]
ダイオキシン対策推進基本指針
平成11年3月に「ダイオキシン対策関係閣僚会議」において策定された国の総合的かつ計画的なダイオキシン対策の具体的な方向を取りまとめたもの(ダイオキシン類対策特別措置法の制定に伴い、11年9月改定)。この基本指針では、「今後4年以内に全国のダイオキシン類の排出総量を平成9年に比べ約9割削減する」との政策目標を導入するとともに、排出インベントリーの作成や測定分析体制の整備、廃棄物処理及びリサイクル対策の推進を定めている。
ダイオキシン法
「ダイオキシン類対策特別措置法」参照。
ダイオキシン類
ダイオキシン類対策特別措置法では、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)に加え、同様の毒性を示すコプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)と定義している。生殖、脳、免疫系などに対して生じ得る影響が懸念されており、研究が進められているが、日本において日常の生活の中で摂取する量では、急性毒性や発がんのリスクが生じるレベルではないと考えられている。なお、これらの物質は炭素・水素・塩素を含むものが燃焼する工程などで意図せざるものとして生成される。
ダイオキシン類対策特別措置法
平成11年7月に議員立法により制定されたダイオキシン類対策に係る法律。ダイオキシン類による環境汚染の防止や、その除去などを図り、国民の健康を保護することを目的に、施策の基本とすべき基準(耐容一日摂取量及び環境基準)の設定、排出ガス及び排出水に関する規制、廃棄物処理に関する規制、汚染状況の調査、汚染土壌に係る措置、国の削減計画の策定などが定められている。
大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)
窒素酸化物や浮遊粒子状物質などの大気環境データをリアルタイムで収集・配信するシステム。(大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)(別ウィンドウ))
大気汚染防止法
工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに健康被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的としたもの。
耐容一日摂取量
Tolerable Daily Intake。生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない1日当たりの摂取量。
脱温暖化社会に向けた中長期的政策オプションの多面的かつ総合的な評価・予測・立案手法の確立に関する総合研究プロジェクト(2050年脱温暖化社会プロジェクト)
(独)国立環境研究所等が参加し、環境省の競争的研究資金である地球環境研究総合推進費により、平成16~20年に実施された研究プロジェクト。日本における中長期脱温暖化対策シナリオの構築に向け、技術・社会イノベーション統合研究を行い、 2050年までを見越した日本の温室効果ガス削減のシナリオとそれにいたる環境政策の方向性を提示すること等を目的として行われた。
2013年04月09日
白書 語句説明 [ち]
地域循環圏
地域の特性や循環資源の性質に応じて、最適な規模の循環を形成することが重要であり、地域で循環可能な資源はなるべく地域で循環させ、地域での循環が困難なものについては循環の環を広域化させていくという考え方。
チーム・マイナス6%
京都議定書によるわが国の温室効果ガス6%削減約束の達成に向けて、国民一人ひとりがチームのように一丸となって地球温暖化防止に立ち向かうことをコンセプトに、平成17年4月から政府が推進している国民運動。
地球温暖化対策の推進に関する法律
地球温暖化対策を推進するための法律。京都議定書目標達成計画の策定や、地域協議会の設置等の国民の取組を強化するための措置、温室効果ガスを一定量以上排出する者に温室効果ガスの排出量を算定して国に報告することを義務づけ、国が報告されたデータを集計・公表する「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」等について定めたもの。
地球温暖化対策のための税
地球規模の重要かつ喫緊の課題である地球温暖化対策を進める観点から、平成24 年度税制改正において実現した税。広範な分野にわたりエネルギー起源CO2排出抑制を図るため、全化石燃料を課税ベースとする現行の石油石炭税にCO2 排出量に応じた税率を上乗せする「地球温暖化対策のための課税の特例」を設ける。
地球環境研究総合推進費
地球環境保全のための政策を科学的側面から支援することを目的として、研究課題を公募、審査により採択する競争的研究資金。地球温暖化研究をはじめ、オゾン層の破壊、越境汚染、広域的な生態系保全・再生、持続可能な社会・政策研究等、総合的に地球環境研究を推進している。
地球環境戦略研究機関
持続可能な開発のための革新的な政策手法の開発、環境対策の戦略を作成するための政策的・実践的研究を行っている。1998年(平成10年)に設立された。
地球環境ファシリティ
開発途上国等における地球環境保全への取組を促進するための主要な資金メカニズムの一つとして世界銀行、UNDP及びUNEPの協力により1991年(平成3年)に発足。
地球観測に関する政府間会合
「全球地球観測システム(GEOSS)10年実施計画」の推進のための国際的な組織。2005年(平成17年)2月の第3回地球観測サミットにおいて設置が決まったもの。本部はスイス(ジュネーブ)。日米欧を含む77か国及び欧州委員会並びに56機関が参加。(平成21年4月現在)
地球規模生物多様性概況
GBO(Global Biodiversity Outlook)。生物多様性条約事務局が地球規模の生物多様性の状況を評価した報告書。条約の実施状況を把握するために2001年に第1版が、2010年目標の達成状況を評価するために第2版(2006年)及び第3版(2010年)が公表されている。
地球サミット
「国連環境開発会議」参照。
地方公共団体実行計画
地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3第1項に基づき、都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策定することとされている。また、同法第20条の3第3項に基づき、都道府県並びに政令市、中核市及び特例市は、区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策を策定することとされている。
チャレンジ25キャンペーン
温室効果ガス排出量を、すべての主要国による公平かつ実効性のある国際枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を前提に、2020年までに1990年比で言えば25%削減という目標を実現させるために、2010年1月14日よりスタートした地球温暖化防止のための国民的運動。
チャレンジ25宣言
「チャレンジ25キャンペーン」の趣旨に賛同している個人、企業・団体が同キャンペーンに参加の意思を表す宣言。
中間処理
収集したごみの焼却、下水汚泥の脱水、不燃ごみの破砕、選別などにより、できるだけごみの体積と重量を減らし、最終処分場に埋立て後も環境に悪影響を与えないように処理すること。さらに、鉄やアルミ、ガラスなど再資源として利用できるものを選別回収し、有効利用する役割もある。
中部圏ゴミゼロ型都市推進協議会
都市再生本部で決定されたプロジェクトである「大都市圏におけるゴミゼロ型都市への再構築」を実現するため、平成17年9月に、都市再生本部事務局を事務局とし、中部圏の7県市(長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、静岡市、名古屋市)及び関係各省(農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)により設置された協議会。
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による被害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護と狩猟の適正化を図ることを目的とした法律。
鳥獣保護法
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」参照。
鳥類観測ステーション
鳥類標識調査を重点的に実施するために設定してきた調査地点で、現在、全国各地に計60か所が設定されている。
鳥類標識調査
かすみ網などの捕獲用具を使って鳥類を捕獲し、足環などによって個体識別することで、渡り鳥の渡り経路や生態を解明するための調査。鳥類の識別について十分な知識を持ち、鳥を安全に捕獲して放鳥する技術を身に付けた調査員によって調査が実施されている。
2013年04月09日
白書 語句説明 [て]
テレワーク
情報通信技術を活用した、時間と場所にとらわれない柔軟な働き方であり、企業等に勤務する被雇用者が行う雇用型テレワーク(例:在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィスでの勤務)と、個人事業者・小規模事業者等が行う自営型テレワーク(例:SOHO、在宅ワーク)に大別される。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
エネルギー源としての再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関し、その価格、期間等について特別の措置を講ずることにより、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進し、もって我が国の国際競争力の強化及び我が国産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律。2012年(平成24年)7月1日施行予定。
2013年04月09日
白書 語句説明 [と]
動物の愛護及び管理に関する法律
動物の虐待防止、適正な取扱について定め、動物愛護の気風の招来、生命尊重、友愛等の情操のかん養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて、動物による人の生命、身体及び財産への侵害を防止することを目的とするもの。
道路交通情報通信システム
VICS(Vehicle Information and Communication System)。ドライバーの利便性の向上、渋滞の解消・緩和等を図るため、渋滞状況、所要時間、工事・交通規制等に関する道路交通情報を、道路上に設置したビーコンやFM多重放送により、ナビゲーションシステム等の車載機へリアルタイムに提供するシステム。光ビーコン、電波ビーコン(ITSスポットを含む)、FM多重放送の3種類のメディアにより情報提供される。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止するため、特定外来生物として指定した生物の飼養、栽培、保管又は運搬、輸入、譲渡し等及び野外に放つこと等を規制し、防除等を行うことを定めた法律。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境保全上の支障の未然防止を図ることを目的としている。環境への排出量の把握等を行うPRTR制度及び事業者が化学物質の性状及び取扱に関する情報(MSDS)を提供するMSDS制度等が定められている。
特定家庭用機器再商品化法
エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫及び冷凍庫について、小売業者に消費者からの引取り及び引き取った廃家電の製造者等への引渡しを義務付けるとともに、製造業者等に対し引き取った廃家電の一定水準以上のリサイクルの実施を義務付けたもの。
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法
平成15年法律第98号。平成10年6月以前に不適正処分された産業廃棄物に起因する生活環境保全上の支障の除去等を自ら行う都道府県等に対し、それに要する経費に国が財政支援等を行うための枠組みを規定している。
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
オゾン層を破壊したり地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊を実施するための措置等を定めた法律。平成18年6月に改正され、機器の廃棄時にフロン類の回収行程を管理する制度が導入されたほか、整備時の回収義務の明確化等が盛り込まれ、平成19年10月1日に施行された。
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
特殊自動車の使用による大気の汚染の防止を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、これまで未規制であった公道を走行しない特殊自動車(オフロード特殊自動車)に対する排出ガス規制を行う法律。
特定農薬
その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬(農薬取締法第2条第1項)。平成24年3月現在、重曹、食酢及び使用場所周辺にもともといた天敵が指定されている。
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
国際的に協力してオゾン層の保護を図ることを目的として、オゾン層の保護のためのウィーン条約及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書を的確かつ円滑に実施するための特定物質の製造の規制並びに排出の抑制及び使用の合理化に関する措置等を定めた法律。
特定物質の排出抑制・使用合理化指針
昭和64年環境庁・通商産業省告示第2号。オゾン層保護法第20条に基づき、使用事業者による特定物質の排出の抑制対策として、密閉、吸着、凝縮等を通じ、特定物質の大気中への放出の抑制を図ること、また、特定物質の使用の合理化対策として、代替品の導入、回収再利用、省フロン型設備の導入等を通じ、日本全体としての特定物質の有効利用を図ること等を定めている。
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
バーゼル条約を担保する国内法であり、特定有害廃棄物等の定義のほか、基本的事項の公表、輸出入の承認、移動書類の交付、措置命令等を規定している。
特別管理廃棄物
廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性があるなど人の健康又は生活環境に被害を及ぼすおそれがある性状を有するもの。ほかの廃棄物と区別しての収集運搬や、特定の方法による処理を義務付けるなど、特別な処理基準が適用される。特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物に分けて政令で指定することとされており、特定の施設から生ずるばいじん、病院等から生ずる感染性廃棄物、廃PCB、廃石綿などが指定されている。
土壌汚染対策法
土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的として、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めたもの。平成21年4月の改正により、一定規模(3000㎡)以上の土地の形質変更時の調査の実施、自主的な調査の活用、汚染土壌の適正な処理の義務付けなどが規定された。
途上国における森林減少・劣化に由来する排出の削減等(REDD+)
REDDとは、開発途上国における森林減少・劣化に由来する温室効果ガスの排出削減に関し、過去の推移などをもとに将来の排出量の参照レベルを設定し、資金などインセンティブを付与することにより、参照レベルからの削減を達成しようとする考え方。森林保全、持続可能な森林経営、森林炭素蓄積の増加に係る取組を含む場合には、「REDD+」と呼ばれる。
2013年04月09日
白書 語句説明 [な]
名古屋・クアラルンプール補足議定書
正式名称は「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」。カルタヘナ議定書第27条に基づき、平成23年10月に名古屋で開催され、日本が議長を務めた第5回締約国会議において採択されたが、平成24年3月現在で未発行。日本は平成24年3月署名。遺伝子組換え生物の国境を越える移動により生物多様性の保全及び持続可能な利用に損害が生じた場合の責任と救済に関して、締約国が講ずるべき措置を規定している。
名古屋議定書
2010年(平成22年)に採択、未発効。生物の多様性に関する条約の3つ目の目的である遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(ABS: Access and Benefit Sharing)を達成するため、各締約国が具体的に実施すべき措置を規定している。正式名称は「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」。
ナショナル・トラスト活動
寄附を募って土地や建造物等を取得したり、所有者と保全契約を結んで開発を防ぐなどの方法により、国民自らが自然環境や歴史的価値を有する文化遺産等の景観を保全、管理し、それらの財産を広く一般に公開する市民運動。この活動は19世紀末のイギリスで始まり、現在、日本各地でも広く行われている。
ナノテクノロジー
ナノ(10億分の1)メートルの精度を扱う技術の総称。マイクロ-マシンなどの加工・計測技術だけでなく、新素材の開発なども含めていう。
南極地域の環境の保護に関する法律
国際的な協力の下に、南極地域の環境の包括的な保護を図り、「環境保護に関する南極条約議定書」の的確かつ円滑な実施を確保するため、南極地域活動計画の確認制度を設けるとともに、環境影響評価の実施、南極動植物の保護、廃棄物の処分及び管理、海洋汚染の防止並びに特別保護地区における活動の制限などを規定し、南極地域における行為の制限に関する所要の措置等を講じているもの。また、同法第5条第1項に基づき、南極地域で観光、冒険旅行、取材等のあらゆる活動(ただし、海域における漁業活動等は除く)を行う場合は、当該活動について環境大臣へ申請し、南極地域に与える影響に係る基準を満たしている旨の確認を受ける必要がある。また、日本以外の議定書締約国において、確認に類する許可等の行政処分を受けた場合には、同法第5条第3項に基づき環境大臣への届出が必要となる。詳細については、「南極地域の環境保護」ホームページ(http://www.env.go.jp/nature/nankyoku/kankyohogo/(別ウィンドウ))参照。
2013年04月09日
白書 語句説明 [に]
二国間渡り鳥条約・協定
「日米渡り鳥等保護条約」、1972年(昭和47年)に採択、1974年(昭和49年)に発効。「日豪渡り鳥等保護協定」、1974年(昭和49年)に採択、1981年(昭和56年)に発効。「日中渡り鳥保護協定」、1981年(昭和56年)に採択、1981年(昭和56年)に発効。「日ソ渡り鳥等保護条約」(日本とロシア連邦との間で承継)、1973年(昭和48年)に署名、1988年(昭和63年)に発効。これらは、渡り鳥の捕獲等の規制、絶滅のおそれのある鳥類の保護(日中を除く。)及びそれらの鳥類の生息環境の保護等を目的としている。条約等に基づく会議は、それぞれおおむね2年ごとに日本、相手国交互に開催されているほか、韓国との間でも渡り鳥保護協力会合の開催等を行っている。
二酸化硫黄
硫黄分を含む石油や石炭の燃焼により生じ、かつての四日市ぜんそくなどの公害病や酸性雨の原因となっている。
二酸化炭素排出原単位
一単位当たりの生産(活動)量に伴う二酸化炭素の排出量(例)電気の1kWh当たりの生産に伴い排出されるkgで表した二酸化炭素の量(kg-CO2/kWh)
日中韓三カ国環境大臣会合
北東アジアの中核である日本・中国・韓国の3か国の環境大臣が一堂に会し、地域及び地球規模の環境問題に関する対話や協力関係を強化するため、1999年(平成11年)より毎年開催。
日中水環境パートナーシップ
中国における水質汚濁防止に関する協力として、排水処理対策の遅れている中国の農村地域に日本の排水処理技術を移転するための、日中両環境省による共同事業。
日本版バイオセーフティクリアリングハウス
カルタヘナ議定書事務局が運営しているバイオセーフティに関する情報交換センター(バイオセーフティクリアリングハウス:BCH)と連携して環境省が運営しているホームページ。
人間と生物圏計画
生物多様性の保全、持続可能な開発、学術研究支援を目的としてユネスコが1971年(昭和46年)に開始したプログラム。同プログラムに基づき、1976年(昭和51年)には生態系の保全と持続可能な利活用の調和(自然と人間社会の共生)を目的とする「生物圏保存地域」(ユネスコエコパーク)制度が開始され、我が国では平成24年3月現在、「屋久島」「大台ヶ原・大峰山」「白山」「志賀高原」の4件つの生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)が登録されている。
2013年04月09日
白書 語句説明 [ね]
熱回収
廃棄物等から熱エネルギーを回収すること。廃棄物の焼却に伴い発生する熱を回収し、廃棄物発電をはじめ、施設内の暖房・給湯、温水プール、地域暖房等に利用している例がある。リユース、マテリアルリサイクルを繰り返した後でも熱回収は可能であることから、循環型社会基本法では、原則としてリユース、マテリアルリサイクルが熱回収に優先することとされている。なお、熱回収はサーマルリカバリーともいう。
2013年04月09日
白書 語句説明 [の]
農薬登録保留基準
農薬取締法に基づき登録の申請のあった農薬について、登録を認めるかどうかの判断基準。環境省では、1)作物残留、2)土壌残留、3)水産動植物の被害防止及び4)水質汚濁の観点からそれぞれ基準を定めている。
農薬取締法
昭和23年法律第82号。農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することが目的。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
農用地のカドミウム等による土壌汚染防止及び対策についての国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物や飼料用植物の生育が阻害されることを防止することが目的。鉱山の廃水等に由来した重金属類による農用地汚染等が原因と考えられる健康被害(イタイイタイ病)や農作物等の生育阻害が大きな問題となったことから制定された。
2013年04月05日
白書 語句説明 [は]
バーゼル条約
正式名称は「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」。1989年(平成元年)に採択、1992年(平成4年)に発効し、日本は1993年(平成5年)に加入。有害廃棄物の輸出に際しての許可制や事前通告制、不適正な輸出、処分行為が行われた場合の再輸入の義務等を規定している。
バーゼル法
正式名称は「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」。平成4年12月16日法律第108号。バーゼル条約を担保する国内法であり、特定有害廃棄物等の定義のほか、基本的事項の公表、輸出入の承認、移動書類の交付、措置命令等を規定している。
バイオエタノール
植物等のバイオマスを原料として製造される燃料。燃焼しても大気中のCO2を増加させない特性を持っており、ガソリンと混合して利用することにより、ガソリンの燃焼時に発生するCO2の排出を減少させる効果を有する。
バイオディーゼル
油糧作物(なたね、ひまわり、パーム)や廃食用油といった油脂を原料として製造する軽油代替燃料。B化石燃料由来の燃料に比べ、大気中のCO2を増加させないカーボンュートラルの特性持った燃料。
バイオマス
再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。廃棄物系バイオマスとしては、廃棄される紙、家畜排せつ物、食品廃棄物、建設発生木材、黒液、下水汚泥などがある。主な活用方法としては、農業分野における飼肥料としての利用や汚泥のレンガ原料としての利用があるほか、燃焼して発電を行ったり、アルコール発酵、メタン発酵などによる燃料化などのエネルギー利用などもある。
バイオマス・ニッポン総合戦略
バイオマスの積極的な利活用に向けて平成14年12月に閣議決定した総合戦略(平成18年3月改訂)。農林水産省/バイオマス・ニッポン(別ウィンドウ)で入手可能。
バイオマス活用推進基本計画
バイオマス活用推進基本法に基づき、バイオマスの活用促進に関する施策についての基本的な方針、国が達成すべき目標、技術の研究開発に関する事項等について定める計画。
バイオマス活用推進基本法
バイオマスの活用の推進に関する基本理念、施策の基本となる事項を定めること等により、バイオマスの活用に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として制定された法律。
バイオマスタウン
域内において、広く地域の関係者の連携の下、バイオマスの発生から利用までが効率的なプロセスで結ばれた総合的利活用システムが構築され、安定的かつ適正なバイオマス利活用が行われているか、あるいは今後行われることが見込まれる地域。平成23年3月末現在、全国303地区がバイオマスタウン構想を策定・公表し、取組を進めている。
バイオレメディエーション
微生物等の働きを利用して汚染物質を分解等することによって、土壌、地下水等の環境汚染の浄化を図る技術のこと。
廃棄物処理法
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」参照。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律で、廃棄物処理施設の設置規制、廃棄物処理業者に対する規制、廃棄物処理に係る基準等を内容とする。
廃棄物枠組み指令
廃棄物やリサイクル、リカバリーの定義、廃棄物の処分方法、廃棄物管理の優先順位、汚染者負担原則(PPP)等が明記されている。EU加盟国は、新たなリサイクル目標の設定や廃棄物発生抑制プログラム策定が義務付けられている。欧州委員会にも、発生抑制に関する報告及び目標設定の責務があり、発生抑制が強化されている。
排出者責任
廃棄物等を排出する者が、その適正なリサイクル等の処理に関する責任を負うべきとの考え方。廃棄物処理に伴う環境負荷の原因者はその廃棄物の排出者であることから、排出者が廃棄物処理に伴う環境負荷低減の責任を負うという考え方は合理的であると考えられ、その考え方の根本は汚染者負担の原則にある。
ばいじん
工場・事業場から発生する粒子状物質のうち、燃料その他の物の燃焼等に伴い発生する物質。
発生抑制(リデュース)
廃棄物の発生自体を抑制すること。リユース、リサイクルに優先される。リデュースのためには、事業者には原材料の効率的利用、使い捨て製品の製造・販売等の自粛、製品の長寿命化など製品の設計から販売にいたるすべての段階での取組が求められる。また、消費者は、使い捨て製品や不要物を購入しない、過剰包装の拒否、良い品を長く使う、食べ残しを出さないなどライフスタイル全般にわたる取組が必要。
バリ行動計画
2007年12月にインドネシアのバリ島で開催された気候変動に関する国際連合枠組条約第13回締約国会議において採択された計画。2013年以降の地球温暖化対策に関して、2009年の第15回締約国会議で合意を得られるように作業を進めるという計画。
ハロン
主に消火剤として使用される。オゾン層破壊物質でありモントリオール議定書の削減規制対象物質である。温室効果ガスでもある。
2013年04月05日
白書 語句説明 [ひ]
ヒートアイランド対策大綱
ヒートアイランド対策に関する国、地方公共団体、事業者、住民等の取組を適切に推進するため、基本方針を示すとともに、実施すべき具体的な対策を体系的に取りまとめたもの。2004年(平成16年)3月、ヒートアイランド対策関係府省連絡会議において策定された。
ヒートアイランド現象
都市域において、人工物の増加、地表面のコンクリートやアスファルトによる被覆の増加、それに伴う自然的な土地の被覆の減少、さらに冷暖房などの人工排熱の増加により、地表面の熱収支バランスが変化し、都心域の気温が郊外に比べて高くなる現象をヒートアイランド現象という。この現象は、都市及びその周辺の地上気温分布において、等温線が都心部を中心として島状に市街地を取り巻いている状態により把握することができるため、ヒートアイランド(熱の島)といわれる。
ヒートアイランド対策関係府省連絡会議
ヒートアイランド対策に関係する行政機関が相互に密接な連携と協力を図り、ヒートアイランド対策を総合的に推進するため、平成14年9月に設置された。内閣官房、警察庁、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省で構成される。
東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ
東アジア・オーストラリア地域において、渡り性水鳥及びその生息地の保全に関する国際協力の推進を図ることを目的とした、政府機関、国際機関、国際NGO等のためのパートナーシップ。1996年(平成8年)から実施されたアジア太平洋地域渡り性水鳥保全戦略の成果を踏まえ、その解消とともに、わが国及び豪州環境省が主導し、2006年(平成18年)11月に発足した。渡り性水鳥の重要生息地ネットワークの構築、その普及啓発及び保全活動の促進等を行っている。
東アジア酸性雨モニタリングネットワーク
東アジア地域における酸性雨の現状やその影響を解明するとともに、この問題に対する地域協力体制の確立を目的として、各国の自主的な参加、貢献の下で設立されているネットワーク。参加国は共通の手法を用いて酸性雨のモニタリング(湿性沈着、乾性沈着、土壌・植生、陸水の4分野)を行っており、得られたデータはネットワークセンターに集積され、解析、評価及び提供がなされている。また、データの質の向上のため、精度保証・精度管理活動等も推進している。事務局は国連環境計画(UNEP)が指定されており、アジア太平洋地域資源センター(バンコク)においてその活動を行っている。また、ネットワークセンターには、(財)日本環境衛生センター・アジア大気汚染研究センター(新潟県)が指定されている。現在の参加国は、カンボジア、中国、インドネシア、日本、韓国、ラオス、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、フィリピン、ロシア、タイ及びベトナムの13か国。
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法
平成23年法律第99号。東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理が喫緊の課題となっていることに鑑み、国が被害を受けた市町村に代わって災害廃棄物を処理するための特例を定め、あわせて、国が講ずべきその他の措置について定める法律。2011年(平成23年)8月18日公布、同日施行。
干潟
干出と水没を繰り返す平坦な砂泥底の地形で、内湾や河口域に発達する。浅海域生態系の一つであり、多様な海洋生物や水鳥等の生息場所となるなど重要な役割を果たしている。
光害
良好な「光環境」の形成が、人工光の不適切あるいは配慮に欠けた使用や運用、漏れ光によって阻害されている状況、又はそれによる悪影響。
光ビーコン
ビーコン(路側に設置し、アンテナ部を通じ、車両の位置座標や道路交通情報等を送受信する装置)の一種。通過車両を感知して交通量等を測定するとともに、車載のカーナビゲーション装置等と交通管制センターの間の情報のやり取りを媒介する路上設置型の赤外線通信装置である。赤外線の代わりに準マイクロ波を使用する電波ビーコンも実用化されている。
微小粒子状物質
浮遊粒子状物質のうち、粒径2.5μm(マイクロメートル:μm=100万分の1m)以下の小さなもの。健康への影響が懸念されている。
非特定汚染源
工場・事業場や家庭からの排水などと異なり、汚濁物質の排出ポイントが特定しにくく、面的な広がりをもつ市街地、農地、山林等の地域を発生源とする負荷や降雨等に伴って大気中から降下してくる負荷のこと。
非メタン炭化水素
Non-methane Hydrocarbons。全炭化水素(メタンを含むすべての炭化水素。)からメタンを除いたもの。
琵琶湖いきものイニシアティブ
平成21年4月に、滋賀経済同友会が公表した、企業活動を通じた生物多様性保全のモデル構築を目指すこと等を謳った宣言文。「最低1種類、もしくは1か所の生息地の保全に責任を持ちます。」などの10 項目からなる。
貧酸素水塊
溶存酸素濃度が極度に低下した水塊のこと。水域の底層においては、微生物などが富栄養化によって増殖したプランクトンの死骸や水域に流入する有機物を分解するため、酸素を消費し、溶存酸素濃度が極度に低下する。貧酸素水塊が水の表層に上昇すると青潮を引き起こす。水生生物が貧酸素水塊に長時間接することで死滅する等の被害が出ることがある。
2013年04月05日
白書 語句説明 [ふ]
フィード・イン・タリフ制度
「固定価格買取制度」参照。
風景地保護協定
自然公園内の里山や二次草原などの良好な自然の風景地の保護を図るため、土地所有者と公園管理団体等との間で協定を締結し、公園管理団体等により、草原の火入れ、刈払いなどの自然の風景地の管理を行う制度。
富栄養化
湖沼や内湾が水中に窒素、りん等の栄養塩が多い状態に遷移すること。藻類の異常繁殖により、アオコ、赤潮等の原因となる。湖沼や東京湾等の内湾で生活排水等の人為的な原因で急速に進行していることが問題になっている。
覆砂
ヘドロや底泥の堆積した水底を砂等により覆うこと。ヘドロや底泥からの栄養塩や有害物質の溶出の防止、漁場環境の改善を目的に行うものである。
物質フロー会計
MFA: Material Flow Accounts。区域及び期間を区切って、当該区域への物質の総投入量、区域内での物質の流れ、区域外への物質の総排出量等を集計したもの。資源生産性などの指標を算定する基礎となる。循環型社会白書では、日本という単位で集計しているが、地方公共団体、企業、事業場などを単位としても集計することが可能。また、物質フロー会計を用いて資源利用の効率性を分析することを「物質フロー分析」という。物質フロー分析は、通常の経済統計では分からない、経済における天然資源その他の資源の浪費を見出すのに役立つ。
浮遊粒子状物質
大気中に浮遊する粒子状の物質(浮遊粉じん、エアロゾルなど)のうち粒径が10μm(マイクロメートル:μm=100万分の1m)以下のものをいう。
フロン回収・破壊法
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」参照。
粉じん
物の破砕、選別その他の機械的処理等に伴い発生、飛散する物質。
2013年04月05日
白書 語句説明 [へ]
平均生物種豊富度(MSA)
Mean Species Abundance。代表的な生物種の母集団の大きさについて平均的な傾向を表した指標。平均生物種豊富度は、ある特定の地域に住む固有種のみを対象として計算されるため、固有種の減少を分かりにくくする日和見種の増加は除外される。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
平成23年法律第110号。平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質による環境の汚染が生じていることに鑑み、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置について定めること等により、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的とする法律。2011年(平成23年)8月30日公布、2012年(平成24年)1月1日完全施行。
2013年04月04日
白書 語句説明 [ほ]
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律
自衛隊等の行為又は防衛施設の設置もしくは運用により生ずる障害の防止等のため防衛施設周辺地域の生活環境等の整備について必要な措置を講ずるとともに、自衛隊の特定の行為により生ずる損失を補償することにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的とし、騒音防止工事の助成(学校、病院等の防音工事)、住宅防音工事の助成、移転等の補償、移転先地の公共施設整備の助成、土地の買い入れ、買い入れた土地の無償使用、緑地帯の整備等の各種施策を定めたもの。
ポートステートコントロール
Port State Control(PSC)。船舶の登録国である旗国政府が本来果たすべき役割を補完するため、寄港国の政府が、入港する外国船舶に対して立入検査を行い、船舶の構造設備・船員の資格証明等について、国際条約に定められている基準への適合を監督する制度。
北西太平洋地域海行動計画
海洋環境の保全のため国連環境計画(UNEP)が進めている地域海計画の一つ。日本海及び黄海を対象とし、1994年(平成6年)に日本、中国、韓国及びロシアの4か国により採択された。その事務局機能を果たすRCU(地域調整ユニット)が、日本(富山)及び韓国(釜山)に2004年(平成16年)に設置された。
北東アジア準地域環境協力プログラム(NEASPEC)
1993年に「北東アジア環境協力高級事務レベル会合」で決定した地域の環境協力の取組を具体化するための包括的な協力メカニズム。これまでに、大気汚染対策のためのトレーニングやデータ収集、大型哺乳類や渡り鳥の保全計画づくりを行っている。
ポツダム・イニシアティブ
2007年(平成19年)にドイツのポツダムで開催されたG8環境大臣会合で、まとめられた付属文書。生物多様性の地球規模の損失における経済的重要性(生物多様性の地球規模の経済的価値、生物多様性の損失に伴うコスト等の分析に着手する)、科学(科学と政策の間の接点向上に取り組む)、生産と消費のパターン(政府、産業界、消費者などを巻き込む政策の統合強化など)、侵略的外来種(種の特定、阻止及び統制管理における取組の拡大)などが盛り込まれた。
ホムンクルス
ホムンクルス(Homunculus)とは、ヨーロッパの錬金術師が作り出す人工生命体、または、フラスコの中の小人と言う意味でラスト、グラトニー、エンヴィー、グリード、スロウス、プライド、ラースの7体。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)
PCBは昭和4年に初めて工業製品化されて以来、その安全性、耐熱性、絶縁性を利用して電気絶縁油、感圧紙等、さまざまな用途に用いられてきたが、環境中で難分解性であり、生物に蓄積しやすくかつ慢性毒性がある物質であることが明らかになり、生産・使用の中止等の行政指導を経て、昭和49年に化学物質審査規制法に基づき製造及び輸入が原則禁止された。しかし、PCB廃棄物については、処理施設の整備が進まなかったことなどから事業者が長期間保管し続けてきており、平成13年にPCB廃棄物処理特別措置法が制定され、処理体制の整備を図った上で平成28年までに処理を終えることとしている。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
ポリ塩化ビフェニル廃棄物について、処理体制の速やかな整備と確実かつ適正な処理を推進し、国民の健康の保護と生活環境の保全を図ることを目的として定められたもの。処分そのものを一定期間内に確実に行う点に重きを置いて立法措置がとられた。
ボン・ガイドライン
「遺伝資源へのアクセスとその利用から生じる利益配分の公正かつ衡平な配分を確保するため、法令、行政措置や契約作成の参考となる任意のガイドライン。平成14年にオランダのハーグで開催されたCOP6で採択された。
2013年04月04日
白書 語句説明 [ま]
マテリアルフローコスト会計
企業の生産プロセスにおいて、原材料などのマテリアルのフローとストックを数量と金額で測定することで「ロスの見える化」を可能にするシステムであり、生産性の向上によるコスト削減と環境負荷低減を同時に実現することができる。
慢性砒素中毒症
砒素中毒症には急性型と慢性型がある。慢性中毒症は長期にわたって砒素が摂取される場合にみられ、多彩な症状を呈する。すなわち、皮膚には初期に皮膚炎、後には摩搾部を中心として色素沈着、色素脱失が認められ、足蹠、手掌などを中心として角化症がみられるようになる。一方、神経系に対する障害も知られている。
2013年04月04日
白書 語句説明 [み]
緑の回廊
森林生態系保護地域を中心にほかの保護林とのネットワークの形成を図るため、これらの保護林間を連結する野生動植物の移動経路のこと。野生動植物の移動経路を確保し、生息・生育地の拡大と相互交流に資することを目的として管理を行うことにより、分断化された個体群の保全と個体群の遺伝的多様性の確保、生物多様性の保全を期待している。
緑の国勢調査
「自然環境保全基礎調査」参照。
ミレニアム生態系評価
国連の主唱により2001年(平成13年)から2005年(平成17年度)にかけて行われた、地球規模の生態系に関する総合的評価。95か国から1,360人の専門家が参加。生態系が提供するサービスに着目して、それが人間の豊かな暮らし(human well-being)にどのように関係しているか、生物多様性の損失がどのような影響を及ぼすかを明らかにした。これにより、これまであまり関連が明確でなかった生物多様性と人間生活との関係が分かりやすく示されている。生物多様性に関連する国際条約、各国政府、NGO、一般市民等に対し、政策・意志決定に役立つ総合的な情報を提供するとともに、生態系サービスの価値の考慮、保護区設定の強化、横断的取組や普及広報活動の充実、損なわれた生態系の回復などによる思い切った政策の転換を促している。
2013年04月04日
白書 語句説明 [む]
ムーブメント信号制御方式
交通需要の少ない方向の青信号を削減し、交通需要の多い方向の青信号に割り当てる信号制御方式である。流入方向ごとの交通需要に応じた最適な信号制御が可能となる。
2013年04月04日
白書 語句説明 [め]
メタン発酵
嫌気性細菌の作用により汚水や汚泥に含まれる生物分解性有機物(BOD成分)をメタンや二酸化炭素に還元分解する方法である。還元したメタンは回収され、さまざまな用途に用いられる。
2013年04月04日
白書 語句説明 [も]
モーダルシフト
トラック等による幹線貨物物流を、環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨物輸送・内航海運に転換すること。
モニタリングサイト1000
「重要生態系監視地域モニタリング推進事業」参照。
藻場
大型底生植物(海藻・海草)の群落を中心とする浅海域生態系の一つであり、海洋動物の産卵場や餌場となるなど重要な役割を果たしている。
モントリオール・プロセス
地球サミットでの森林に関する合意を受け、欧州以外の温帯林・北方林を対象とした、森林経営の持続可能性を把握・分析・評価するための基準・指標の策定・運用に向けた取組。1993年(平成5年)に開始された。1995年(平成7年)には「サンティアゴ宣言」が採択され、持続可能な森林経営のための7基準67指標が合意された。なお、世界的には9つの同様な取組が進められており、FAOによれば2000年の時点で149か国がこれら9つの取組のうち少なくとも1つに参加している。
モントリオール議定書
「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」参照。
2013年04月04日
白書 語句説明 [ゆ]
有害大気汚染物質
大気中から低濃度ではあるが検出され、長期間に渡ってばく露することにより健康影響が生ずるおそれのある物質。
有害廃棄物指令
廃棄物枠組み指令を補足するため、1991年に策定された指令で、乾電池・容器包装・PCB等の特定廃棄物に係る要求事項を規定したもの。その後、EUの第6次環境行動計画において、廃棄物・再利用・処分の定義の明確化、製品のライフサイクルにおける廃棄物抑制、廃棄物規定の標準化を盛り込む必要が出てきたため、2007年に廃棄物枠組み指令改正で統合され、廃油指令とともに廃止された。
有害廃棄物の不法輸出入防止に関するアジアネットワーク
わが国の提案により、有害廃棄物の不法輸出入防止を目的として、平成15年に開始された政府間ネットワーク。各国のバーゼル条約担当官による日常的な情報交換やワークショップの開催、ウェブサイトの運用等により、アジア各国のバーゼル条約実施能力の向上及び情報交換体制の整備等を行っている。
2013年04月04日
白書 語句説明 [よ]
要監視項目
平成5年3月に人の健康の保護に関する環境基準項目の追加等が行われた際に、人の健康の保護に関連する物質ではあるが公共用水域等における検出状況等から見て、現時点では直ちに環境基準健康項目とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断されるクロロホルム等の25物質について「要監視項目」と位置付け、継続して公共用水域等の水質の推移を把握することとした。その後、平成11年2月の見直しにより3項目を環境基準健康項目に移行し、16年3月には、新たに5項目を追加し、21年11月には、公共用水域については1項目、地下水については3項目を環境基準健康項目に移行して、現在では、公共用水域26項目、地下水24項目を設定している。
公共用水域
項目 指針値
クロロホルム 0.06 mg/l以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/l以下
1,2-ジクロロプロパン 0.06 mg/l以下
p-ジクロロベンゼン 0.2 mg/l以下
イソキサチオン 0.008 mg/l以下
ダイアジノン 0.005 mg/l以下
フェニトロチオン(MEP) 0.003 mg/l以下
イソプロチオラン 0.04 mg/l以下
オキシン銅(有機銅) 0.04 mg/l以下
クロロタロニル(TPN) 0.05 mg/l以下
プロピザミド 0.008 mg/l以下
EPN 0.006 mg/l以下
ジクロルボス(DDVP) 0.008 mg/l以下
フェノブカルブ(BPMC) 0.03 mg/l以下
イプロベンホス(IBP) 0.008 mg/l以下
クロルニトロフェン(CNP) -
トルエン 0.6 mg/l以下
キシレン 0.4 mg/l以下
フタル酸ジエチルヘキシル 0.06 mg/l以下
ニッケル -
モリブデン 0.07 mg/l以下
アンチモン 0.02 mg/l以下
塩化ビニルモノマー 0.002 mg/l以下
エピクロロヒドリン 0.0004 mg/l以下
全マンガン 0.2 mg/l以下
ウラン 0.002 mg/l以下
地下水
項目 指針値
クロロホルム 0.06 mg/l以下
1,2-ジクロロプロパン 0.06 mg/l以下
p-ジクロロベンゼン 0.2 mg/l以下
イソキサチオン 0.008 mg/l以下
ダイアジノン 0.005 mg/l以下
フェニトロチオン(MEP) 0.003 mg/l以下
イソプロチオラン 0.04 mg/l以下
オキシン銅(有機銅) 0.04 mg/l以下
クロロタロニル(TPN) 0.05 mg/l以下
プロピザミド 0.008 mg/l以下
EPN 0.006 mg/l以下
ジクロルボス(DDVP) 0.008 mg/l以下
フェノブカルブ(BPMC) 0.03 mg/l以下
イプロベンホス(IBP) 0.008 mg/l以下
クロルニトロフェン(CNP) -
トルエン 0.6 mg/l以下
キシレン 0.4 mg/l以下
フタル酸ジエチルヘキシル 0.06 mg/l以下
ニッケル -
モリブデン 0.07 mg/l以下
アンチモン 0.02 mg/l以下
エピクロロヒドリン 0.0004 mg/l以下
全マンガン 0.2 mg/l以下
ウラン 0.002 mg/l以下
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)
平成7年法律第112号。一般廃棄物の減量及び再生資源の利用を図るため、家庭ごみの大きな割合を占める容器包装廃棄物について、消費者は分別して排出する、市町村は分別収集する、容器を製造する又は販売する商品に容器包装を用いる事業者は再商品化を実施するという新たな役割分担を定めたもの。
容器包装リサイクル法
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」参照。
2013年04月04日
白書 語句説明 [ら]
ライダー装置
レーザー光線を発射し、返ってくる光を測定・解析することにより、上空の黄砂・エーロゾル・オゾンなどの鉛直方向の濃度分布をリアルタイムで把握する装置。
ライフサイクル・アセスメント
原材料採取から製造、流通、使用、廃棄にいたるまでの製品の一生涯(ライフサイクル)で、環境に与える影響を分析し、総合評価する手法。製品の環境分析を定量的・総合的に行う点に特徴がある。
ラブ・カナル事件
アメリカ・ナイアガラ滝近くのラブ・カナル運河に猛毒物質を含む廃棄物が合法的に投棄され、埋立後に小学校や住宅などが建設された。1978年に化学物質等の漏出で地下水や土壌汚染、地域住民への健康影響が判明し、これを契機に包括的環境対処補償責任法(スーパーファンド法)が制定された。
ラムサール条約
正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」。1971年(昭和46年)に採択、1975年(昭和50年)に発効し、日本は1980年(昭和55年)に加入。国際的に重要な湿地及びそこに生息、生育する動植物の保全と賢明な利用を推進することを目的としている。平成24年3月現在、わが国では37か所の湿地が登録されている。
2013年04月04日
白書 語句説明 [り]
リ・スタイル(Re-Style)
リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)の3つのリ(Re)を推進する、循環型社会におけるライフスタイル、ビジネススタイルを「リスタイル」として平成14年版循環型社会白書で提唱。
リサイクル
廃棄物等を再利用すること。原材料として再利用する再生利用(再資源化)、焼却して熱エネルギーを回収するサーマル・リサイクル(熱回収)がある。
リサイクルポート
「総合静脈物流拠点港」参照。
リデュース
「発生抑制」参照。
硫酸ピッチ
強酸性で油分を有する泥状の廃棄物。雨水等と接触して亜硫酸ガスを発生させ、周辺の生活環境保全上の支障を生じる可能性がある。近年不法投棄等が問題となっており、不正軽油(軽油引取税の脱税を目的として製造される軽油)を密造する際に不正軽油の原料であるA重油や灯油に濃硫酸処理を施すことにより副産物として発生することが多い。
リユース
「再使用」参照。
2013年04月04日
白書 語句説明 [れ]
レアアース
31鉱種あるレアメタルの1種。17種類の元素(希土類)の総称。
21 Sc スカンジウム、39 Y イットリウム、 57 La ランタン、 58 Ce セリウム、 59 Pr プラセオジム
60 Nd ネオジム、 61 Pm プロメチウム、 62 Sm サマリウム、 63 Eu ユウロピウム、 64 Gd ガドリニウム
65 Tb テルビウム、 66 Dy ジスプロシウム、 67 Ho ホルミウム、 68 Er エルビウム、 69 Tm ツリウム
70 Yb イッテルビウム、 71 Lu ルテチウム
レアメタル
レアメタルの定義については、国際的に一意的に定まったものはないが、一般的には地球上の存在量が稀であるか、技術的・経済的な理由で抽出困難である鉱種等を指すものと考えられる。鉱業審議会においては、現在工業用需要があり、今後も需要があるものと、今後の技術革新に伴い新たな工業用需要が予測されるもの31鉱種についてレアメタルと定義。
レッドデータブック
レッドリストに掲載されている種について生息状況や減少要因等を取りまとめた本。
レッドリスト
日本の絶滅のおそれのある野生生物種のリスト。日本に生息又は生育する野生生物について、生物学的観点から個々の種の絶滅の危険度を評価し、絶滅のおそれのある種を選定してリストにまとめたもの。
レッドリストインデックス
生物の分類群ごとの絶滅のおそれのある状況を示す指標。この値が1に近い場合はその分類群のすべての種が近い将来に絶滅の危機に瀕していないことを表し、値が0の場合はその分類群のすべての種がすでに絶滅したことを表す。
2013年04月04日
白書 語句説明 [ろ]
ローマクラブ
1970年3月民間組織の法人としてスイスに設置され,政治に関与しない各国の科学者,経済学者,プランナー,教育者などで構成されるシンクタンク。
ロンドン条約1996年議定書
正式名称は「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書」。1996年(平成8年)に採択、2006年(平成18年)に発効、2007年(平成19年)10月締結。ロンドン条約の内容を改正・強化した議定書であり、廃棄物の海洋投棄及び海底下廃棄を原則禁止とするとともに、投棄可能な廃棄物についても、その環境影響についての事前の検討等を求めている。
2013年04月04日
白書 語句説明 [わ]
ワシントン条約
正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」。1973年(昭和48年)に採択、1975年(昭和50年)に発効し、日本は1980年(昭和55年)に加入。野生動植物の国際取引の規制を輸入国と輸出国が協力して実施することにより、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保護を図ることを目的としている。条約の附属書に掲載された野生動植物の国際取引は禁止又は制限され、輸出入の許可書等が必要となっている。
2013年04月04日
白書 語句説明 [A]
AFP
「アジア森林パートナーシップ」参照。
APFED
「アジア太平洋環境開発フォーラム」参照。
APN
「アジア太平洋地球変動研究ネットワーク」参照。
APP
「クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ」参照。
Argo計画
地球全体の海洋変動をリアルタイムにとらえることを目指す国際的な研究計画。水深2,000mまでの水温や塩分のデータを、世界の海に展開されたアルゴフロートと呼ばれる観測機器によって取得し、人工衛星を介して各国に配信する。気候変動のメカニズム解明や予測精度の向上につながることが期待されている。
2013年04月04日
白書 語句説明 [B]
BOD
Biochemical Oxygen Demand 生物化学的酸素要求量。水中の有機汚濁物質を分解するために微生物が必要とする酸素の量。値が大きいほど水質汚濁は著しい。
BRT
Bus Rapid Transit 輸送力の大きなノンステップバスの投入、バス専用レーン、公共車両優先システム等を組み合わせた高次の機能を備えたバスシステム。
BRZ
最近出たスバルの2ドア