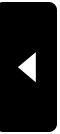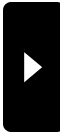2013年04月02日
生物多様性条約第11回締約国会議(COP11)
「COP11」
インドのハイデラバードで開催されていた生物多様性条約第11回締約国会議(COP11)が、10月20日に閉幕した。前回(2010年)のCOP10は愛知県名古屋市で開催されており、そこでは「名古屋議定書」と「愛知ターゲット」が採択された。COP10の内容については以前のエコマガでも触れているので、そちらを参照していただきたい。
昨年のエコマガでも説明したが、「COP」とは「Conference of the Parties」の略であり、締約国会議(※条約を結んだ国家間の会議)のことを意味する。そして、いわゆるCOP11とは国際連合が1992年に定めた生物多様性条約を締結した国家間の“11回目の会議”なのである。締約国会議では、絶滅の危機にある生物を保護する法律の成立や、途上国への資金援助などについて話し合われる。なお、地球温暖化に関する会議(気候変動枠組条約締約国会議)も「COP」と呼ばれており、ややこしいので注意しよう。
名古屋議定書とは、途上国に存在する動植物や微生物などから医薬品をつくって利益を得た際に、それを先進国と途上国でいかに公平に分けるかというルールを定めたものだ。そして、愛知ターゲットとは、生物の絶滅を避けるために、2020年までに「絶滅危惧種の絶滅や減少を防止する」や、「陸地では少なくとも17%、海域については10%を保全する」など、国際社会が実現すべき目標を定めたものだ。
あれ? 確か、COP11は同じインドでもニューデリーで開催されると述べていたような気が……。それはさておき、COP11ではどのようなことが決まったのだろうか。
COP11の重要なテーマのひとつとなったのが「資源動員戦略」だ。これは、途上国における生物多様性を保護するために、先進国から“資源=資金や技術”をどの程度投入すべきかの目標値を決めることだ。この点、経済状況の厳しい先進国側と、多くの資金援助を受けたい途上国側の意見が対立していた。日本は最大の資金拠出国(※)であるが、経済状況が厳しいのは周知の通り。今回、途上国側の要求に難色を示したことで、会議の足を引っ張ったという非難まで浴びている。成果があったと評価された前回のCOP10とは大きな違いだ。
※2006年から2010年における日本の年間平均支援額は、11億ドル以上(約870億円)にもなるとされている(参照:産経ニュース記事)。
さて、COP11で決まった内容を簡単に言うと、さまざまな生物が生息する環境を保護するために、途上国への資金援助を2015年までに2006年から2010年の平均値の2倍に拡大し、2020年まで少なくともその水準を維持するという文書を採択したことだ。この点、先進国が資金援助をするという点の明示を避けており、中国・インド・ブラジルといった新興国も資金援助倍増の対象に含まれる。ただし、これは努力目標にとどまるという点には注意。もちろん、途上国側では生物多様性を優先した開発が期待される。また、名古屋議定書や愛知ターゲットの今後の方策についても話し合われた。
最後に、2年後の2014年には韓国でCOP12が開催されることが決定した。
インドのハイデラバードで開催されていた生物多様性条約第11回締約国会議(COP11)が、10月20日に閉幕した。前回(2010年)のCOP10は愛知県名古屋市で開催されており、そこでは「名古屋議定書」と「愛知ターゲット」が採択された。COP10の内容については以前のエコマガでも触れているので、そちらを参照していただきたい。
昨年のエコマガでも説明したが、「COP」とは「Conference of the Parties」の略であり、締約国会議(※条約を結んだ国家間の会議)のことを意味する。そして、いわゆるCOP11とは国際連合が1992年に定めた生物多様性条約を締結した国家間の“11回目の会議”なのである。締約国会議では、絶滅の危機にある生物を保護する法律の成立や、途上国への資金援助などについて話し合われる。なお、地球温暖化に関する会議(気候変動枠組条約締約国会議)も「COP」と呼ばれており、ややこしいので注意しよう。
名古屋議定書とは、途上国に存在する動植物や微生物などから医薬品をつくって利益を得た際に、それを先進国と途上国でいかに公平に分けるかというルールを定めたものだ。そして、愛知ターゲットとは、生物の絶滅を避けるために、2020年までに「絶滅危惧種の絶滅や減少を防止する」や、「陸地では少なくとも17%、海域については10%を保全する」など、国際社会が実現すべき目標を定めたものだ。
あれ? 確か、COP11は同じインドでもニューデリーで開催されると述べていたような気が……。それはさておき、COP11ではどのようなことが決まったのだろうか。
COP11の重要なテーマのひとつとなったのが「資源動員戦略」だ。これは、途上国における生物多様性を保護するために、先進国から“資源=資金や技術”をどの程度投入すべきかの目標値を決めることだ。この点、経済状況の厳しい先進国側と、多くの資金援助を受けたい途上国側の意見が対立していた。日本は最大の資金拠出国(※)であるが、経済状況が厳しいのは周知の通り。今回、途上国側の要求に難色を示したことで、会議の足を引っ張ったという非難まで浴びている。成果があったと評価された前回のCOP10とは大きな違いだ。
※2006年から2010年における日本の年間平均支援額は、11億ドル以上(約870億円)にもなるとされている(参照:産経ニュース記事)。
さて、COP11で決まった内容を簡単に言うと、さまざまな生物が生息する環境を保護するために、途上国への資金援助を2015年までに2006年から2010年の平均値の2倍に拡大し、2020年まで少なくともその水準を維持するという文書を採択したことだ。この点、先進国が資金援助をするという点の明示を避けており、中国・インド・ブラジルといった新興国も資金援助倍増の対象に含まれる。ただし、これは努力目標にとどまるという点には注意。もちろん、途上国側では生物多様性を優先した開発が期待される。また、名古屋議定書や愛知ターゲットの今後の方策についても話し合われた。
最後に、2年後の2014年には韓国でCOP12が開催されることが決定した。
Posted by 春 ヲ 呼 プ at 11:36│Comments(0)
│自然環境・生物多様性