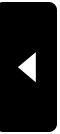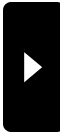2013年04月02日
日本国インプット 持続可能な開発に向けた9つの提案
出典:国連持続可能な開発会議(リオ+20)
①防災
ポスト「兵庫行動枠組」を策定し、 防災を開発政策へと統合。東日本大震災等の災害で得られた知見・教訓を国際社会で共有する。
②エネルギー
大胆なエネルギーシフトに向けて省エネルギー、再生可能エネルギー、クリーンエネルギーを推進する。
③食料安全保障
食料増産に向けた農業分野への投資拡大、責任ある農業投資の前進、集約化・効率化など、持続可能な農業を通じた食料安全保障を実現する。
④水
「橋本行動計画II」に代わる総合的な水資源管理に関する目標について検討を開始する。
⑤環境未来都市
経済・社会・環境価値を創造し続ける「環境未来都市」のモデルを世界に提供する。
⑥持続可能な開発のための教育
持続可能な開発のための教育に係る取組の促進・共有を行い、持続可能な市民の育成に取り組む。
⑦地球観測システム(GEOSS)
地球規模課題に適切に対処するために、GEOSSを通じた地球観測体制ネットワークを一層強化する。
⑧技術革新とグリーン・イノベーション
技術革新とグリーン・イノベーションの重要性を再認識し、成長段階に応じた取組を開始する。
⑨生物多様性
愛知目標の重要性を再確認し、そのための国際的取組への参加を促進し、愛知目標の実現に向けた取組を強化する。
***************************************************************************************
※兵庫行動枠組 「災害に強い国・コミュニティづくり」をテーマとする、2005 年から2010 年までの10 年の国際社会における防災活動の基本的指針である。2005 年1 月18 日から22 日にかけて、兵庫県神戸市において開催された「国連防災世界会議」において採択された。
I.序文
○ この会議において、自然の脅威に対する脆弱性を軽減する戦略的、体系的な手法により、災害に強い国・コミュニティを構築する具体的な方法を特定した。
○ 災害による損失は増大し、開発利益を奪い、地球規模の問題となっている。無計画な都市化、環境の悪化、気候変動等により脆弱性が増し、災害は世界の人々や途上国の持続可能な開発をますます脅かしかねない。過去20年間、災害により毎年平均2億人以上が被害を受けている。防災を持続可能な開発や貧困削減の取組みに体系的に取り込む必要性は、今や国際的な認識を得ている。
○ 横浜戦略の点検作業において、防災を持続可能な開発と関連づけ、より体系的に展開し、各国や地方の防災能力の強化を通じて災害に強い国・コミュニティを構築することが主要な課題として浮き彫りとなった。
○ 特定された具体的な課題は次の5分野。
a) 防災のための統治力(組織的、法的、政策的な枠組)、
b) 災害リスクの特定、評価、観測、早期警報、
c) 災害知識の普及、防災教育、
d) 災害リスク要因の削減、
e) 効果的な応急・復旧への備え
II.期待される成果及び戦略目標
○ 本行動枠組の実施により今後10年で期待される成果は、災害による人的被害、社会・経済・環境資源の損失が実質的に削減されること。この実現のため、次の3つの戦略目標を設定する。
a)持続可能な開発の取組みに減災の観点をより効果的に取り入れる。
b)全てのレベル、特に、コミュニティレベルで防災体制を整備し、能力を向上する。
c)緊急対応や復旧・復興段階においてリスク軽減の手法を体系的に取り入れる。
III.2005-2015の優先行動
○ 全ての国がそれぞれの持続可能な開発と自国内の人々の生命と財産を守るための一義的な責任を有する、コミュニティの防災対応能力を高める、といった一般的配慮事項を定めた上で、5つの分野ごとに、次の具体的優先行動を設定。
1.防災を国、地方の優先課題に位置づけ、実行のための強力な制度基盤を確保する。
○ 国レベルの制度的、法的枠組の整備(多部門間の防災行動の調整を図る国レベルのプラットフォームの設立・強化等)
○ 資源の確保(防災に関わる人材、資金の確保等)
○ コミュニティの参画(コミュニティレベルの具体的な防災政策の策定、ボランティア資源の戦略的活用等)
2.災害リスクを特定、評価、観測し、早期警報を向上する。
○ 国及び地方レベルの災害リスク評価(リスクマップの整備・普及、災害リスクや脆弱性の評価指標の体系整備等)
○ 早期警報(住民本位の早期警報体制の整備等)
○ 防災能力(災害の研究・観測・予測のための科学技術の振興、組織の整備等)
○ 地域レベルの顕在化するリスク(地域レベルの災害リスク・損失に関する統計データの整備、地域レベルの災害リスクの評価・観測・情報交換・早期警報の提供等)
3.全てのレベルで防災文化を構築するため、知識、技術、教育を活用する。
○ 情報交換(災害に脆弱な地域の住民に対するわかりやすい災害情報の伝達、防災に関わる多様な関係者間の情報交換等)
○ 研究(全てのレベルでの防災行動の社会経済的コスト便益評価手法の確立、気候関連災害リスクに関する脆弱性や影響の評価手法の開発能力の強化等)
○ 意識啓発(防災文化の普及のためのメディアの取組み促進)
4.潜在的なリスク要因を軽減する。
○ 環境資源の管理(ハード・ソフト両面からの総合的な水資源の管理等)
○ 社会的・経済的開発実践(災害に脆弱な地域の食糧の安全確保、保健分野への防災計画の統合、重要な公共施設・インフラの耐震性の向上等)
○ 土地利用計画その他の技術的措置(都市計画、開発プロジェクトの計画過程への防災の取り入れ)
5.効果的な応急対応のための事前準備を強化する。
○ 防災トレーニングによる人材育成、全てのレベルにおける緊急事態対応計画の準備、防災訓練、ボランティア精神に根ざしたコミュニティの多様な関係者の積極的関与
IV.実施とフォローアップ
○防災に関わる多様な分野の関係者による多部門間調整の促進、コミュニティに根ざした組織やボランティア等の民間主体、研究機関の関与、国境を越えた災害への対応体制の支援といった、といった一般的配慮事項を定めた上で、関係主体ごとの取組方針を設定。
1.国
○各国は、強い自助の精神の下、市民社会その他の関係主体と連携しつつ、各国の実情に即して、自らの防災能力を評価し、本行動枠組に関わる防災プログラムの概要を公表する等の取組みを実施する。
2.地域機関
○地域機関は、本行動枠組に掲げた目的を地域レベルで達成するための域内各国の防災能力の向上、災害の監視手法の開発等の地域プログラムを推進する、地域レベルでの達成状況や障害を検証し、要請に基づき各国の支援を行う、津波等の早期警報体制の整備を支援する等の取組みを実施することが求められる。
3.国際機関
○国連機関をはじめとする国際機関は、本行動枠組に位置づけられた人道分野及び開発分野に防災の観点を取り入れるための総合的な取組みにより、国際防災戦略を推進する、復興過程における将来のリスクの削減の支援、優良事例や知識の共有等により被災国の復興を支援する国際的な仕組みを強化する等の取組みを実施することが求められる。
4.国際防災戦略(ISDR)
○ISDRのパートナーは、本行動枠組のフォローアップを支援するため、関係主体の役割と取組みを整理する、国連機関等関係主体の防災行動について、実施のための課題の特定やガイドライン、政策ツールの整備を通じ、効果的な調整を図る、防災に関する優良事例や教訓、技術、行動についての情報交換を促進するための情報集(ポートフォリオ)を整備する等の取組みを実施することが求められる。
5.資金供与
○本行動枠組の実施の支援に必要な資源を動員するため、各国、地域・国際機関は、多面的な仕組みを通じ、防災のための資金を適切に動員する。
○災害が多発する途上国に対する財政的、技術的支援や南北、南南協力を促進する。
○貧困削減や都市開発、気候変動への適用に関わる開発援助プログラムの中に防災措置を適切に取り入れる。
※「橋本行動計画」国連「水と衛生に関する諮問委員会」(議長:橋本元総理)は、第4回世界水フォーラム(2006年3月、メキシコ)において、水と衛生問題解決に向けた「行動計画(Your Action、Our Action)」を発表。同行動計画は、以下の通り、水と衛星分野において、6分野で各国政府や国際機関がとるべき具体的な行動を提案し、その行動実現に向けた諮問委員会自身の活動内容を明らかにしたもの。
1.資金調達:地域機関は、ガバナンスと透明性を確保するためのプログラムを設定すべき。地域金融機関と世銀は、地方の事業体及び地方資金市場を開発するプログラムを設定する。また、援助機関は、これらの分野に資金を提供する。
2.水事業体パートナーシップ:国連水関連機関調整委員会は、水事業体パートナーシップに対する国連関係機関からの支援を要請する。諮問委員会は行動プログラムを作り、その実現のため公共機関と国際社会に呼びかける。
3.衛生:2008年(平成20年)を「国際衛生年」とする。同年に国連地域事務所が各地域でハイレベルな会議を開催する。国連開発の10年の総括として、進捗状況を確認するために国連が「国際衛生会議」を開催する。諮問委員会は援助機関や関係機関、政府と共に衛生の優先度の向上を目指す。
※「橋本アクションプラン」の提案通り、2006年(平成18年)12月の国連総会において、2008年(平成20年)を国際衛生年とする決議が採択。
4.モニタリング:国連事務総長は、国連機関の幹部と共同して、ジョイント・モニタリング・プログラムにふさわしい予算や人員の配分についての優先度を高め、統合水資源管理の目標に関して、2008(H20)年の国連持続可能な開発委員会に進捗状況を報告するよう各国に求める。各国政府水と衛生へアクセスできる人数を毎年計測・報告するよう求める。OECDは資金調達などの目標を踏まえ向上させる。諮問委員会は財政機関等に働きかける。
5.統合水資源管理:国連事務総長は国連加盟国に進捗状況を調査し、2008(H20)年の国連持続可能な開発委員会第16会期(CSD16)に報告するよう要請するよう求める。国連経済社会局にデータベースの構築を求める。
6.水と災害:国際社会が、世界的に統一された政治的な意思に基づき、水の災害に起因する生命・生活の損失削減に向けた世界行動の指針を表明した明確な目標を設定する必要がある。国と地方の政府は、災害発生中あるいは発生後の安全な飲料水と衛生の即時の提供を確保すべき。諮問委員会はそのような努力を支持し、国際社会による共通の目標の実現に向けて関係者と協力する。
※GEOSS:全球地球観測システム(GEOSS:Global Earth Observation System of Systems)。幅広いユーザーに対して、地球観測のデータ・情報を活用した意志決定支援ツールを提供するものであり、インターネット等を通じて、意思決定者が必要な情報にアクセスすることを可能とする。
GEOSS10年実施計画の概要
全球地球観測システム(GEOSS)の構築方針
世界全域を対象とし、既存及び将来の人工衛星や地上観測など多様な観測システムが連携した、包括的なシステムを今後10年間(2005-2015年)で構築します。
意志決定者や公衆など、利用者が必要とする情報を重点的に提供します。
地球観測システムによる達成目標の明確化
災害 自然及び人為起源の災害による、人命及び財産の損失の軽減
健康 人間の健康と福祉に影響を与える環境要因の理解
エネルギー エネルギー資源管理の改善
気候 気候変動と変化の理解、評価、予測、軽減及び適応
水 水循環のより良い理解を通じた、水資源管理の向上
気象 気象情報、予報及び警報の向上
生態系 陸域、沿岸及び海洋生態系の管理及び保護の向上
農業 持続可能な農業及び砂漠化との闘いの支援
生物多様性 生物多様性の理解、監視、保全
具体的な手法の明確化
上記の目標を達成するため、以下のような手法を推進。
地球上の観測点数の不十分さや、観測頻度の少なさを補完するため、既存の観測システムの充実・連携と新たな観測手段を導入。その際、データ保管・流通や観測継続性の確保、など
最小時間及び最低限の費用による適切なデータ及び情報提供
複数の観測システムを連結させるための相互運用性基準の確立
研究開発の促進
開発途上国の積極的関与と能力開発
GEOSSデータ共有原則
関連する国際文書や国家のデータポリシー及び法律の存在を認識しつつ、GEOSS内で共有データ、メタデータ及びプロダクトは完全かつオープンに交換される
全ての共有データ、メタデータ及びプロダクトは、最小限の時間遅延かつ最低限の費用で提供される
全ての共有データ、メタデータ及びプロダクトは、研究及び教育目的については、無料もしくは複製にかかる費用を超えない費用であることが奨励される
地球観測に関する政府間会合(GEO)の設立
「10年実施計画」を実際に推進するための国際調整メカニズム(言わば事実上の小規模な国際機関)として、新たに、参加各国政府を中心とする地球観測に関する政府間会合(GEO)(事務局をジュネーブに設置)を2005年2月に設立。
※ 愛知目標:正式名称は「生物多様性新戦略計画」。2010年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択されたのにちなんで「愛知目標」(ポスト2010年目標(2011-2020年))と呼ばれる。
「愛知目標」は、2050年までに「自然と共生する」世界を実現するというビジョン(中長期目標)を持って、2020年までにミッション(短期目標)及び20の個別目標の達成を目指すもの。中長期目標については、「2050年までに、生態系サービスを維持し、健全な地球を維持し全ての人に必要な利益を提供しつつ、生物多様性が評価され、保全され、回復され、賢明に利用される」ことが合意されている。
個別目標は、数値目標を含むより具体的なものとすることを目指している。そのうち、生物多様性保全のため地球上のどの程度の面積を保護地域とすべきかという目標11に関しては、最終的には「少なくとも陸域17%、海域10%」が保護地域などにより保全されるとの目標が決められた。その他「森林を含む自然生息地の損失速度が少なくとも半減、可能な場所ではゼロに近づける」といった目標(目標5)が採択されている。
①防災
ポスト「兵庫行動枠組」を策定し、 防災を開発政策へと統合。東日本大震災等の災害で得られた知見・教訓を国際社会で共有する。
②エネルギー
大胆なエネルギーシフトに向けて省エネルギー、再生可能エネルギー、クリーンエネルギーを推進する。
③食料安全保障
食料増産に向けた農業分野への投資拡大、責任ある農業投資の前進、集約化・効率化など、持続可能な農業を通じた食料安全保障を実現する。
④水
「橋本行動計画II」に代わる総合的な水資源管理に関する目標について検討を開始する。
⑤環境未来都市
経済・社会・環境価値を創造し続ける「環境未来都市」のモデルを世界に提供する。
⑥持続可能な開発のための教育
持続可能な開発のための教育に係る取組の促進・共有を行い、持続可能な市民の育成に取り組む。
⑦地球観測システム(GEOSS)
地球規模課題に適切に対処するために、GEOSSを通じた地球観測体制ネットワークを一層強化する。
⑧技術革新とグリーン・イノベーション
技術革新とグリーン・イノベーションの重要性を再認識し、成長段階に応じた取組を開始する。
⑨生物多様性
愛知目標の重要性を再確認し、そのための国際的取組への参加を促進し、愛知目標の実現に向けた取組を強化する。
***************************************************************************************
※兵庫行動枠組 「災害に強い国・コミュニティづくり」をテーマとする、2005 年から2010 年までの10 年の国際社会における防災活動の基本的指針である。2005 年1 月18 日から22 日にかけて、兵庫県神戸市において開催された「国連防災世界会議」において採択された。
I.序文
○ この会議において、自然の脅威に対する脆弱性を軽減する戦略的、体系的な手法により、災害に強い国・コミュニティを構築する具体的な方法を特定した。
○ 災害による損失は増大し、開発利益を奪い、地球規模の問題となっている。無計画な都市化、環境の悪化、気候変動等により脆弱性が増し、災害は世界の人々や途上国の持続可能な開発をますます脅かしかねない。過去20年間、災害により毎年平均2億人以上が被害を受けている。防災を持続可能な開発や貧困削減の取組みに体系的に取り込む必要性は、今や国際的な認識を得ている。
○ 横浜戦略の点検作業において、防災を持続可能な開発と関連づけ、より体系的に展開し、各国や地方の防災能力の強化を通じて災害に強い国・コミュニティを構築することが主要な課題として浮き彫りとなった。
○ 特定された具体的な課題は次の5分野。
a) 防災のための統治力(組織的、法的、政策的な枠組)、
b) 災害リスクの特定、評価、観測、早期警報、
c) 災害知識の普及、防災教育、
d) 災害リスク要因の削減、
e) 効果的な応急・復旧への備え
II.期待される成果及び戦略目標
○ 本行動枠組の実施により今後10年で期待される成果は、災害による人的被害、社会・経済・環境資源の損失が実質的に削減されること。この実現のため、次の3つの戦略目標を設定する。
a)持続可能な開発の取組みに減災の観点をより効果的に取り入れる。
b)全てのレベル、特に、コミュニティレベルで防災体制を整備し、能力を向上する。
c)緊急対応や復旧・復興段階においてリスク軽減の手法を体系的に取り入れる。
III.2005-2015の優先行動
○ 全ての国がそれぞれの持続可能な開発と自国内の人々の生命と財産を守るための一義的な責任を有する、コミュニティの防災対応能力を高める、といった一般的配慮事項を定めた上で、5つの分野ごとに、次の具体的優先行動を設定。
1.防災を国、地方の優先課題に位置づけ、実行のための強力な制度基盤を確保する。
○ 国レベルの制度的、法的枠組の整備(多部門間の防災行動の調整を図る国レベルのプラットフォームの設立・強化等)
○ 資源の確保(防災に関わる人材、資金の確保等)
○ コミュニティの参画(コミュニティレベルの具体的な防災政策の策定、ボランティア資源の戦略的活用等)
2.災害リスクを特定、評価、観測し、早期警報を向上する。
○ 国及び地方レベルの災害リスク評価(リスクマップの整備・普及、災害リスクや脆弱性の評価指標の体系整備等)
○ 早期警報(住民本位の早期警報体制の整備等)
○ 防災能力(災害の研究・観測・予測のための科学技術の振興、組織の整備等)
○ 地域レベルの顕在化するリスク(地域レベルの災害リスク・損失に関する統計データの整備、地域レベルの災害リスクの評価・観測・情報交換・早期警報の提供等)
3.全てのレベルで防災文化を構築するため、知識、技術、教育を活用する。
○ 情報交換(災害に脆弱な地域の住民に対するわかりやすい災害情報の伝達、防災に関わる多様な関係者間の情報交換等)
○ 研究(全てのレベルでの防災行動の社会経済的コスト便益評価手法の確立、気候関連災害リスクに関する脆弱性や影響の評価手法の開発能力の強化等)
○ 意識啓発(防災文化の普及のためのメディアの取組み促進)
4.潜在的なリスク要因を軽減する。
○ 環境資源の管理(ハード・ソフト両面からの総合的な水資源の管理等)
○ 社会的・経済的開発実践(災害に脆弱な地域の食糧の安全確保、保健分野への防災計画の統合、重要な公共施設・インフラの耐震性の向上等)
○ 土地利用計画その他の技術的措置(都市計画、開発プロジェクトの計画過程への防災の取り入れ)
5.効果的な応急対応のための事前準備を強化する。
○ 防災トレーニングによる人材育成、全てのレベルにおける緊急事態対応計画の準備、防災訓練、ボランティア精神に根ざしたコミュニティの多様な関係者の積極的関与
IV.実施とフォローアップ
○防災に関わる多様な分野の関係者による多部門間調整の促進、コミュニティに根ざした組織やボランティア等の民間主体、研究機関の関与、国境を越えた災害への対応体制の支援といった、といった一般的配慮事項を定めた上で、関係主体ごとの取組方針を設定。
1.国
○各国は、強い自助の精神の下、市民社会その他の関係主体と連携しつつ、各国の実情に即して、自らの防災能力を評価し、本行動枠組に関わる防災プログラムの概要を公表する等の取組みを実施する。
2.地域機関
○地域機関は、本行動枠組に掲げた目的を地域レベルで達成するための域内各国の防災能力の向上、災害の監視手法の開発等の地域プログラムを推進する、地域レベルでの達成状況や障害を検証し、要請に基づき各国の支援を行う、津波等の早期警報体制の整備を支援する等の取組みを実施することが求められる。
3.国際機関
○国連機関をはじめとする国際機関は、本行動枠組に位置づけられた人道分野及び開発分野に防災の観点を取り入れるための総合的な取組みにより、国際防災戦略を推進する、復興過程における将来のリスクの削減の支援、優良事例や知識の共有等により被災国の復興を支援する国際的な仕組みを強化する等の取組みを実施することが求められる。
4.国際防災戦略(ISDR)
○ISDRのパートナーは、本行動枠組のフォローアップを支援するため、関係主体の役割と取組みを整理する、国連機関等関係主体の防災行動について、実施のための課題の特定やガイドライン、政策ツールの整備を通じ、効果的な調整を図る、防災に関する優良事例や教訓、技術、行動についての情報交換を促進するための情報集(ポートフォリオ)を整備する等の取組みを実施することが求められる。
5.資金供与
○本行動枠組の実施の支援に必要な資源を動員するため、各国、地域・国際機関は、多面的な仕組みを通じ、防災のための資金を適切に動員する。
○災害が多発する途上国に対する財政的、技術的支援や南北、南南協力を促進する。
○貧困削減や都市開発、気候変動への適用に関わる開発援助プログラムの中に防災措置を適切に取り入れる。
※「橋本行動計画」国連「水と衛生に関する諮問委員会」(議長:橋本元総理)は、第4回世界水フォーラム(2006年3月、メキシコ)において、水と衛生問題解決に向けた「行動計画(Your Action、Our Action)」を発表。同行動計画は、以下の通り、水と衛星分野において、6分野で各国政府や国際機関がとるべき具体的な行動を提案し、その行動実現に向けた諮問委員会自身の活動内容を明らかにしたもの。
1.資金調達:地域機関は、ガバナンスと透明性を確保するためのプログラムを設定すべき。地域金融機関と世銀は、地方の事業体及び地方資金市場を開発するプログラムを設定する。また、援助機関は、これらの分野に資金を提供する。
2.水事業体パートナーシップ:国連水関連機関調整委員会は、水事業体パートナーシップに対する国連関係機関からの支援を要請する。諮問委員会は行動プログラムを作り、その実現のため公共機関と国際社会に呼びかける。
3.衛生:2008年(平成20年)を「国際衛生年」とする。同年に国連地域事務所が各地域でハイレベルな会議を開催する。国連開発の10年の総括として、進捗状況を確認するために国連が「国際衛生会議」を開催する。諮問委員会は援助機関や関係機関、政府と共に衛生の優先度の向上を目指す。
※「橋本アクションプラン」の提案通り、2006年(平成18年)12月の国連総会において、2008年(平成20年)を国際衛生年とする決議が採択。
4.モニタリング:国連事務総長は、国連機関の幹部と共同して、ジョイント・モニタリング・プログラムにふさわしい予算や人員の配分についての優先度を高め、統合水資源管理の目標に関して、2008(H20)年の国連持続可能な開発委員会に進捗状況を報告するよう各国に求める。各国政府水と衛生へアクセスできる人数を毎年計測・報告するよう求める。OECDは資金調達などの目標を踏まえ向上させる。諮問委員会は財政機関等に働きかける。
5.統合水資源管理:国連事務総長は国連加盟国に進捗状況を調査し、2008(H20)年の国連持続可能な開発委員会第16会期(CSD16)に報告するよう要請するよう求める。国連経済社会局にデータベースの構築を求める。
6.水と災害:国際社会が、世界的に統一された政治的な意思に基づき、水の災害に起因する生命・生活の損失削減に向けた世界行動の指針を表明した明確な目標を設定する必要がある。国と地方の政府は、災害発生中あるいは発生後の安全な飲料水と衛生の即時の提供を確保すべき。諮問委員会はそのような努力を支持し、国際社会による共通の目標の実現に向けて関係者と協力する。
※GEOSS:全球地球観測システム(GEOSS:Global Earth Observation System of Systems)。幅広いユーザーに対して、地球観測のデータ・情報を活用した意志決定支援ツールを提供するものであり、インターネット等を通じて、意思決定者が必要な情報にアクセスすることを可能とする。
GEOSS10年実施計画の概要
全球地球観測システム(GEOSS)の構築方針
世界全域を対象とし、既存及び将来の人工衛星や地上観測など多様な観測システムが連携した、包括的なシステムを今後10年間(2005-2015年)で構築します。
意志決定者や公衆など、利用者が必要とする情報を重点的に提供します。
地球観測システムによる達成目標の明確化
災害 自然及び人為起源の災害による、人命及び財産の損失の軽減
健康 人間の健康と福祉に影響を与える環境要因の理解
エネルギー エネルギー資源管理の改善
気候 気候変動と変化の理解、評価、予測、軽減及び適応
水 水循環のより良い理解を通じた、水資源管理の向上
気象 気象情報、予報及び警報の向上
生態系 陸域、沿岸及び海洋生態系の管理及び保護の向上
農業 持続可能な農業及び砂漠化との闘いの支援
生物多様性 生物多様性の理解、監視、保全
具体的な手法の明確化
上記の目標を達成するため、以下のような手法を推進。
地球上の観測点数の不十分さや、観測頻度の少なさを補完するため、既存の観測システムの充実・連携と新たな観測手段を導入。その際、データ保管・流通や観測継続性の確保、など
最小時間及び最低限の費用による適切なデータ及び情報提供
複数の観測システムを連結させるための相互運用性基準の確立
研究開発の促進
開発途上国の積極的関与と能力開発
GEOSSデータ共有原則
関連する国際文書や国家のデータポリシー及び法律の存在を認識しつつ、GEOSS内で共有データ、メタデータ及びプロダクトは完全かつオープンに交換される
全ての共有データ、メタデータ及びプロダクトは、最小限の時間遅延かつ最低限の費用で提供される
全ての共有データ、メタデータ及びプロダクトは、研究及び教育目的については、無料もしくは複製にかかる費用を超えない費用であることが奨励される
地球観測に関する政府間会合(GEO)の設立
「10年実施計画」を実際に推進するための国際調整メカニズム(言わば事実上の小規模な国際機関)として、新たに、参加各国政府を中心とする地球観測に関する政府間会合(GEO)(事務局をジュネーブに設置)を2005年2月に設立。
※ 愛知目標:正式名称は「生物多様性新戦略計画」。2010年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択されたのにちなんで「愛知目標」(ポスト2010年目標(2011-2020年))と呼ばれる。
「愛知目標」は、2050年までに「自然と共生する」世界を実現するというビジョン(中長期目標)を持って、2020年までにミッション(短期目標)及び20の個別目標の達成を目指すもの。中長期目標については、「2050年までに、生態系サービスを維持し、健全な地球を維持し全ての人に必要な利益を提供しつつ、生物多様性が評価され、保全され、回復され、賢明に利用される」ことが合意されている。
個別目標は、数値目標を含むより具体的なものとすることを目指している。そのうち、生物多様性保全のため地球上のどの程度の面積を保護地域とすべきかという目標11に関しては、最終的には「少なくとも陸域17%、海域10%」が保護地域などにより保全されるとの目標が決められた。その他「森林を含む自然生息地の損失速度が少なくとも半減、可能な場所ではゼロに近づける」といった目標(目標5)が採択されている。
Posted by 春 ヲ 呼 プ at 15:25│Comments(0)
│環境白書